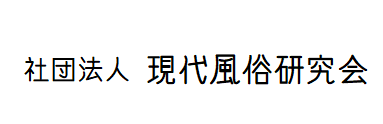| 第10回『“戦争はうんざり”の時代』 |
地下に潜む怪物が唸り声を上げてのたうつように、地面は不気味に波打つ。歩けば足を取られる。やっと裏庭によろけ出た祖母と私は、直径30センチほどの檜に抱きついたが、檜は大揺れに揺れ、祖母を振り飛ばそうとする。私は祖母の背中に手を回し、必死に抱きとめる。接触して隣り合う家屋の棟が大きく離れてはぶつかり合い、土ぼこりを高く吹き上げる。
1944年12月7日の昼過ぎ、遠州灘を震源として起きた東南海地震はM8。生まれて初めての大地震だった。被害状況はその日のうちに、清洲の町外れに住む私たちへも、近所の通勤者や通過者によって恐ろしげに伝えられた。「勤労動員の学徒が、建物の下敷きになってたくさん死んだ」「多くの工場がペシャンコになって、航空機の生産がだめになった」などなど。
こうして、軍需工場が密集する名古屋市南部から知多半島にかけての一帯に、甚大な地震被害の出ていることがわかった。しかし翌日の新聞は、「たいした被害もなく」と小さく伝えたのみ。この報道は、動員先でも話題になり、「知れて具合の悪い、どえらい被害が出たのと違うか」と勘ぐらせた。仲間内で「日本が負ける前兆では」と、不安をなったり打ち消したりで侃々諤々。
そして12月13日の昼食後、警戒警報に続いて、ついに空襲警報のサイレンが鳴り響いた。
すでに東京方面では、マリアナ諸島を基地とするB29の空襲が始まっていたが、いつも「我方、損害軽微」といった新聞報道にだまされて、私たちにはまだ空襲の怖さがわからず、思わぬ休憩ができるぐらいに思っていた。工場内の片隅に自分たちで作った防空壕に入り、ワイワイ騒いでいると、溜め池に貯留した材木に乗って遊んでいた連中が、突如「空襲だ!」と叫びながら、担任ともども膝の上になだれ込んできた。中の私たちは冗談だと思い、担任に上着をかぶせ、ボンボン叩いて日頃のうっぷん晴らし。担任は上着を振り払って立ち上がったが、犯人を追及できる雰囲気ではなかった。「ものすごい爆風だった」「池の中へ吹き飛ばされそうになった」と、壕内は興奮ぎみの体験談で充満した。
この日の空襲は、70機のB29。私たちの工場をねらった爆弾は、すべてはずれて田圃に落ちたが、市内の工場や民家にかなりの被害があり、死傷者も何百人と出た。
この空襲を幕開けにして、日本屈指の軍需都市・名古屋は、敗戦に向けて幾たびとなくB29の大規模空襲を受け、その怖さをじっくりと味合わされることになる。
1945年1月3日には、早くも3回目の大空襲を受け、名古屋市全域で被害が出た。
そして3月24日の夜から25日かけて、不気味な空襲を体験することになる。
名古屋が空襲されているということで東裏に出てみると、名古屋方面の中空に、強烈に輝く数個の発光体が浮かんでいる。10kmも離れた私たちまで、月夜のように青白く照らし出された。私たちは「あれじゃ、上から何もかも丸見えだがや」と、逃げまどう人たちに思いを馳せながら、絶え間なくひびく爆発音に耳をそばだて、広範囲に立ち上る炎や黒煙を見守るばかり。
初めて照明弾を使い、170機のB29が爆弾や焼夷弾で無差別爆撃をしたのだった。
そんな頃、私は中年の工員さんから、工場の片隅に誘い込まれ、「学生さん、私は日本が負ける方に500円賭けたけど、どう思われますか」と聞かれた。日本が負ける方に賭けたのも驚きだったが、その額の大きさにも驚かされた。4年前に、叔父が大卒で中学の教師になったときの月給は70円だったからだ。一人前と思って聞かれたのに、私はなにも答えられなかった。
4月。引き続く勤労動員の惰性で、2年生になったことを気にも止めていなかったが、町役場は待っていたように、「息子さんは頭も体格もいいから、町の名誉のため陸軍少年航空兵に応募してもらえないか」と頼みに来たという。いやだと言えば非国民とされる。うろたえる母に、「上級生になったら陸軍士官学校を志願するつもりだから」と、断りの文句を教えておいた。私の留守に来た役場の吏員は、「それならば」とあっさり引き下がり、母は胸を撫でおろしたとのこと。
しかし、私にとって運命の日は刻々と近づきつつあった。
⇒ 目次にもどる
| 第11回「“目からうろこが落ちた日”のこと」 |
1945年5月14日。早朝から快晴。空襲日和だ。このところ、アメリカの超重爆撃機・B29の大挙来襲が遠のいている。「今日あたり来そうだな」と予感がした。国鉄東海道線清洲駅から名古屋駅に着くや、案の定警戒警報発令。より安全な田舎のわが家に引き返そうとする心とは裏腹に、足は市電の停留所へと勝手に急ぐ。
7時半過ぎ、名古屋北部の街はずれにある工場に着くと同時に、空襲警報。それまでは、自分たちで造った構内の防空壕へ避難していたのに、その日は、動員学徒は全員工場外へ避難せよとのこと。私たち明倫中学2年生も、裏門から近くの矢田川堤防へと避難した。矢田川は当時の名古屋市北部の市境。堤防や河川敷は、上流に向けて一面に人の群れ。上部からの通達でもあったのか、矢田川沿いに並ぶ大小の軍需工場に動員された学徒が、全員避難してきた感じだった。堤防には何の防護設備もなく、河川敷にタコツボが掘ってあるだけ。タコツボとは、戦場に掘る1人用の壕のこと。と言っても単なる穴だから、空からの攻撃には全く心細い。
「こんな何もない堤防に落とすもんか」と、無防備の不安を打ち消す間もなく、金属音の混じった独特の爆音とともに、B29の10数機編隊が北よりのコースで、西方から接近してきた。それまでは、大工場が集中する港湾部や市街地南部と、それに続く中心部を狙ってきたが、この日は北部を狙う気配だ。北部も大工場が集中していたが、工場以外の市街地は比較的無傷だった。
堤防からは、南方に広がる市街地が遠くまで一望できる。3、4km先には、住宅街をへだてて、金の鯱が輝く名古屋城の天守閣がそびえていた。
最初の編隊が通過した下の市街地から、爆発音もなく、広範囲に煙が立ち上った。爆弾でなく、焼夷弾爆撃をしかけたのだ。最初の編隊が通過すると、すぐに次の編隊が西の空に現れる。5分ほどの間隔で波状攻撃をかけるB29の編隊は、微妙にコースを変えながら、被災地を広げていった。次々と編隊が通過するにつれて、煙は市街地一帯を空高くまで包み込み、煙の間から見え隠れしていた名古屋城天守閣も、ついには見えなくなってしまった。
「名古屋城もこれまでか」と、目を凝らしていると、突然エンジンの大きな異常音。見上げると、高度を下げてきた1機のB29が、翼と胴体に分解。同時に5つの落下傘が空中で開いた。それぞれの落下傘には、乗員がぶら下がっていることがわかる。「やったやった」と、みんなは手を叩いた。軍事教練と、あるクラスの担任を兼ねた予備役将校が、軍刀を抜いて、「斬れえ!斬れえ!」と、何度も空に振りかざす。落下傘はどんどん風に流されて、煙の中に消えていく。
「あいつら降りたら、きっと殺されてまうぜ」「あんな奴ら、生かしておけるか」
落下傘に気をとられていると、新しい爆音が聞こえる。振り向くと、B29が真上に向かってくる。「わー」と、私たちは河川敷に駆け下り、先客のいないタコツボを探して飛び込む。多くは中に身を隠したが、横着な連中は私にように立ち上がって、B29を見守った。すると、前方斜め上空まで来たとき、B29の編隊は胴体下部を開いて、バラバラと何かを落とした。それが細かく分解して、ごま粒の広がりとなる。「当たるなら当たってみろ」と、私は目を凝らした。ごま粒の広がりは、瞬く間にふくれ上がってスズメの大群となり、ムクドリの巨大群となり、ザアーと大地を圧する大音響を立てて、視界一面に広がり、投網をかぶせるように降りかかってきた。逃げ場はない。思わずタコツボの中に身を伏せた。ポンポンと破裂音が聞こえると、人の騒ぎが起こった。
穴から立ち上がって見ると、周りは、あちこちで、多いところでは3.3㎡に1、2発の焼夷弾が突き刺さったり、倒れたりして黒煙と火を噴いていた。川に落ちた焼夷弾は、金魚花火のように水面を漂い、至るところで黒煙と火を噴いている。その間を、大勢の男たちに混じって、同じ工場へ動員されていた女子学徒たちが、腰まで水につかり、対岸へと逃げていた。
堤防に駆け上がって状況を見ようとしたが、それどころではない。焼夷弾を束ねていたテープ状の鋼帯が、空一面にひらひらと舞い降りてくる。付属品らしい直径30㎝ほどの鉄の円盤も、大きな木の葉のように舞っている。どこへ落ちてくるかわからない。右往左往していると、近くでボッタン!と大きな音。見ると、漬け物石のような鉄塊が堤防にめり込んでいた。
次の編隊も再度私たちを襲ったが、それを最後に、間もなく空襲警報は解除。私たちは犠牲者が沢山出たのではないかと見に回ったが、うつぶせになって胴体が飛び散っている一人の遺体が、橋の上から見えただけだった。「あれだけ落ちたのに、案外当たらないものだなあ」と、私は不思議に思い、爆発力のない焼夷弾爆撃に対する怖さが薄れていった。
空襲の興奮が冷めやらず、工場へ戻る気もせず、時間がたつのを忘れて、堤防から市街一帯が燃え続けるのを眺めていた。やがて、昼もとっくに過ぎたことに気づき、この場から帰ろうとなった。どうせ市内は交通が途絶えているはずからと、歩いて帰ることにし、私と同方向のものは集団になって歩き出した。すると、行く手の彼方に1条の煙が立ち上っている。
「爆撃されたのは西枇杷島か」「いや、新川の豊和重工かも」
私たちが近づくつれて、煙の位置は西へ西へとずれていく。名古屋の西隣の西枇杷島町も、その西隣の新川町もやられていなかった。友達たちは喜び勇んで別れていき、清洲町からただ一人通う私だけが残った。まさかと思いながらも、小走りに田畑を横切り、よその屋敷を突っ切り、小川を飛び越えた。しかし煙は、目指す行く手にどんどん近づいてくる。そして、私が住む字の入り口ともいえる新国道の清洲橋に立ったとき、戦災は一目瞭然だった。旧国道に沿った家並みは燃え落ち、一面に薄青い煙を上げていた。
家並みと平行して走る新国道は、見物の人だかり。わが家の近くは、掻き分けなければ通れないほど。家に通ずる農道までくると、祖母が「通してちょうだい、通してちょう」と声を上げて、水の入ったバケツを両手に提げながら、人混みの国道を横切り、自宅に向かおうとしていた。燃え切らずにあちこちで立ち上る炎が、夜の空襲の目標になって、焼け残った家が狙われては気の毒だから、夜までに田圃の水を運んで消し止めておこうというわけだ。
「何回運んだか、わかれせん。くったくただわ」「誰も手伝ってくれせなんだ?」「ああやって突っ立っているだけだわさ。せめて通る道だけでも、空けといてくれたらええのにな」
「次はお前らの番だぞ」と心の中で叫んで、私は怒りを抑えた。
1500㎡ほどのわが屋敷は、すっかり灰に覆われ、1軒置いた北隣からは焼け残っている。
この日、字の大半の150軒、良いといわれる人も、悪いといわれる人も、一緒に焼かれた。
「神も仏もないわ」と、自他共に認める信心家の祖母が、焼け跡に立ってつぶやいた。
「これが最後の編隊ですから頑張ってくださいと、ラジオが放送すると同時だったわ、空襲されたのは。あんな放送、何の役にもなれせん」と、母は悔しそうに言い、何か焼け残ったものはないかと、あちこちの灰の中を棒で掻き回し続けた。
夕方近く、「これからどうしよう」と隣り合った親戚同士が立ち話する中で、突然“よねさま”が拳骨で天を突き上げ、大声でののしった。
「ド天皇タとド東条タが戦争始めなんだら、わしら、こんな目に遭えせなんだのに!」
表の道を調査や監視の巡査が行き交っている。彼らの耳に入ったらどんな目に遭うか。みんなは「そんなことを言うもんでない」と、あわててヨネサマの口をふさぎ、なだめた。
その夜、祖母と母は焼け残ったAさんの家へ泊めてもらいに行ったが、私は同情されることが嫌で行かなかった。焼けぼっくいや焼けトタンを集めて、見舞いに来た伯父と作った小屋で寝ていると、夜中、顔が冷や冷やする。目を覚ますと、外は豪雨。顔には雨が跳ねかかり、下に敷いた戸板の横を、雨水が滝のように流れている。恨めしくも、Aさんから無理矢理差し入れられた新品の掛け蒲団に、焼けトタンの屋根から漏れる黒い雨だれが、ぽたぽたと垂れている。
小学校へもろくすっぽ行っていない中年女性・ヨネサマの口から出た衝撃的な言葉を反芻していると、戦争、天皇、神仏、軍人など、いろいろな面で“目からうろこが落ちる”思いがした。
(この日、名古屋城も焼亡。来襲したB29は、資料で480機。今回念のため資料に当たり、ムクドリの大群を連想させた焼夷弾の数を割り出してみると、答えは1.1~1.4万発と出た。)
⇒ 目次にもどる
| 第12回「“負~けた、負けた”の時代」 |
字(あざ)の大半、ほぼ150軒がB29の空襲でやられた1945年5月14日の翌朝。何かおかしい。瞼の裏が真っ赤だ。驚いて目を開ける。集めた焼けトタンで、どうにか格好をつけた仮小屋の出入り口から、初夏の陽光がまっすぐ顔を射していた。
焼け跡に立つと、「これで燃えて惜しいものは何もない。もう空襲はこわくない」と気が軽くなった。すべてが無くなってみると、それまで広いと思っていた屋敷は意外に狭く、数百年続いていると繰り返し言われてきた先祖の重みからも解放されるような気がした。
しかし本が燃えてしまったのは、何としても惜しかった。本箱のあった辺りに灰がうずたかく積もっている。空襲の恐れが多い名古屋の親戚を「これは大切な本だから、ぜひ安全な田舎へ」と説き伏せ、衣服や夜具とともに大八車に乗せてわが家へ疎開させた平凡社の『大百科事典』28巻の灰だ。表面の灰を掻き分けると、奥の方は蒸し焼きになって本の形を保っている。壊さないように引き出してみるが、紙がくっついて1ページごとには開けない。1㎝ほどの厚さで割るように開くと、中身がはっきり読める。半年ほどの期間であったが、“処女膜”や“あぶな絵”など、たやすく人には聞けないような知識をいろいろ教えてくれた。このまま置いておきたい。しかし、両手で挟みつけると簡単につぶれ、揉むと完全な灰の粉に化してしまう。「これからは、もう読めないのだ」と悲哀を感じながら1冊ずつ揉んで風に散らしていると、無性に腹が立ってきた。
「工場へは行かなくてもええの?」と不安がる母や祖母に、「後は焼け残った連中で戦ったらええのだ」と、無断で勤労動員をさぼり、率先して焼け跡の整理に取りかかった。中国へ出征するとき「お祖母さんや母ちゃんを守るんだぞ」と言い置いた叔父(家の跡取り・母の弟)の願いを果たすのはこんな時だと、心を高ぶらせてもいたのだ。
早く暮らしの場を確保したいと、まず寝場所を兼ねた防空壕のために広さ4m×2m弱、深さ1.5mほどの穴を夢中で掘った。材料を調達してきた伯父の差配で、防空壕に隣接して地上に炊事と居間用のトタン小屋がつくられている間に、私は、別の大きな穴を堀りはじめた。今度はマイペース。疲れると穴底に寝ころび、背中の汗を冷やしながら空を見上げた。穴の縁で区切られた空は平和そのもの。戦争を忘れて心は静まりかえる。穴が掘れると、祖母や母は割れた瓦や陶器、崩れた壁土、大量の灰を懸命に放り込み、新たな土を撒いて整地していった。
3、4日でトタン小屋ながらもわが家ができ、親戚知人の差し入れなどで日常生活はなんとか出来るようになったが、本好きに本がないのは辛かった。そんな気持ちを察したかのように、従兄が「本好きのお前さんが困っとらぇすだろうと思って」と、長く貸し忘れていた『古事記全釋』を持って訪ねてきた。「選りに選って、この本だけが残ったとは」と、手に持って感無量。この運命的な再会は、全身をほのぼのとさせた。小学5年のとき、この本に書かれてあるエロチックな神々の行為を読んで、秘かに天皇崇拝から脱落したのである。
毎日続く焼け跡の整理は大変だったが、天皇のために動員先の鋳物工場で煤にまみれるよりはましだった。その間に、焼け跡から拾い出したり、掘り出した焼夷弾の焼け殻や不発弾は、合わせて約130本。屋敷の隅へ山のように積み上げていると、煙を噴く1本の発煙筒めがけてバケツの水をかけるような、それまでの防空演習があほらしく思えた。
6月に入ったころ、「あまり休んでいると、憲兵や特高(特別高等警察)が調べにくるらしいぞ」と友人が知らせにきた。すでに同盟国ドイツは降伏。沖縄では米軍と苦戦続き。天皇の宮城は空爆で炎上。国の焦りは見え見え。ここで逆らったら何をされるか判らない。「そんな怖い目にあったらどもならん」と、不安になった祖母や母は、後は自分たちでやれると、私を工場へ通わせることにした。
工場に通い出してみると、交通事情、食糧事情は一段と切迫していた。爆撃によって国鉄列車や市電の数が減り、いつも超満員の乗客。機関車の前部や炭水車の上、無蓋貨車に乗れたら上々。しばしば片手片足でデッキにぶら下がる破目になる。
また工場の昼食で、ご飯に混じる大豆の割合が増したのは目をつぶるとして、おかずに、丼いっぱいに盛ったイナゴの塩ゆでがたびたび出るようになったのには閉口した。捕ったばかりのイナゴを糞も出させないで茹でるのか、とにかく糞まみれなのだ。ときどき足元にぶっちゃけて、逃げるところを教師に見つかって叱られる者が出た。
ある日、いつも閉まっている来賓用食堂のカーテンが開いていた。気づいた数人で覗いてみると、パリッとした軍装で粋に闊歩している海軍監督官や軍需省の出向役人をまじえて工場幹部が食事する食卓には、真っ白なテーブルクロスが掛けられ、洋皿にナイフとフォークが燦然と並べられていた。「何を食ってやがるだろう」と、私たちは当然疑心暗鬼になった。
そして6月9日。始業間もなく空襲警報。近くの堤防に避難したが、すぐに空襲警報も警戒警報も解除。安心して工場へ戻ろうとしたら、突然B29の編隊が前方に現れた。
「警報の出し間違いか?」と、あっけにとられて機影を追っていると、大きな爆裂音が何度も轟いてきた。名古屋市南部の愛知時計電気(当時軍用機製作)や愛知航空機が爆撃され、沢山の被害者が出たことが終業までに伝わってきて、軍部の間抜けぶりを呪った。
6月下旬、新聞で沖縄の地上部隊全滅が報じられ、本土決戦への兆しが高まった。私は危機に備え、焼け跡から折れ曲がって出てきた刀を叩きのばし、木の柄をつけたり、割った竹を合わせて鞘をつくったり、腰に差して使えるようにした。しかし、敵に首を切られたり、銃殺されたり、腹を刺される夢を立て続けに3回見たら、死が怖くなくなった。「こんな刀で戦えるもんか」と、馬鹿にして木を割ったら良く割れるので、戦後斧が買えるまで重宝した。
この頃になると、B29がばらまく宣伝ビラが話題になった。官憲はデマに迷わされるなと警戒したが、人々の間では密かに、「宣伝ビラによると、日本軍はどこでも負けているそうだ」「日本は間もなく降伏すると、宣伝ビラに書いてあったそうだ」などと取りざたされた。
また、私が住む清洲界隈では、「ある人が某神社の近くを夕方歩いとると、白装束のお爺さんからすれ違いざまに、もうじき戦争は終わるぞよと言葉をかけられ、ふと振り返ると姿が消えてまってたので、あれはきっと、あの神社の神様が姿を現して教えてくれやぁたんでぜ」と言った話が、人から聞いたこととして、こそこそと囁かれた。
7月の半ば、動員をさぼっていると、動員先の愛知時計で6月9日の爆撃にあった従姉が、頭に包帯を巻いた痛々しい姿で祖母を訪ねてきた。誤った警報解除で工場に復帰したところへ、いきなり空襲。慌てて工場内の地下防空壕に避難したとたんに被爆。壊れた壕から救助されたとき、ガラスの破片が30数個刺さっていたという。そんなことを防空壕の中で話し合っていると空襲警報が出た。やがて遠くでバリバリと機銃掃射の音。「ここなら、爆弾の直撃以外は安全だ」と言いながら外の様子を窺っていると、突然近くで大きな銃撃音。従姉は悲鳴を上げて体を伏せて震えた。雨防ぎのために防空壕を覆ったトタン屋根にカラカラと何か落ちた音。「ここにいたら機銃掃射くらい心配ないよ」と従姉を慰めながら外に出てみると、機関砲の薬莢が数個転がっていた。近づく爆音に振り返ると、艦載機が梢すれすれに旋回してきた。操縦士が乗り出すようにして見下ろしていく。その若い顔。目が合ったような気がしたが、憎めなかった。こちらから挑んだ戦いだ。相手が敵になって攻めてくるのは当然だと思ったからだ。
8月、広島に新型爆弾投下。新聞報道からは事情がよくわからず、ピンとこない。続いて『ソ聯、對日宣戦布告』の報。これで日本は、いずれにしても負けると実感した。日本軍がソ連軍に大敗北したノモンハン事件の噂や、軍事冒険小説家・山中峯太郎の書いた『敵中横断三百里』などで、ソ連の怖さを心に刻みつけられてきたからだ。
そしてある日の帰り際、教師から「明日は、昼のラジオで重大発表があるそうだから、工場に来なくてもよい」と言われて、私は臨時休暇が出たように思い、喜々として帰宅した。
(文部省は、私が焼け跡整理で工場を休んでいる間に、決戦体制に備えて、動員学徒の勤労意欲を高めるための戦時教育令を出していたのである。)
⇒ 目次にもどる
| 第13回「“敗戦か終戦か?”の時代」 |
アジア・太平洋戦争が末期的症状を見せていた8月のある日。朝食を終えるや、近くの小川へ泳ぎと魚取りに飛び出す。「明日は、昼のラジオで重大発表があるそうだから、工場に来なくてもよい」と前日に教師から言われて、その日は久しぶりの休日だった。
当時は、刻々と本土に迫ってくる米軍を前に、「決戦に備えよ」「国を守れ」と国からけしかけられ、休日を返上して鋳造工場で働いていた。
「昼の重大放送が聞けるように帰ってこないかんぜ」
「わかっとる、わかっとる」と、祖母の注意もそこそこに、川へ急いだ。
どうせ、国が言うことは決まっている。「国を守れ」とけしかけられたって、戦災によって無一物になってみれば、無理して守るべきものは何もない。それに、小学5年の春古事記や万葉集を読んで、天皇が神でないことに感づいて以来、忠義を尽くす気持ちはうすれている。今日を逃したら、いつまた休日があるかわからない。空は快晴。重大放送より、羽をのばすことが肝心だ。
昔から夏になれば、毎日早朝から賑わった小川の水浴び場に来てみると、人っ子一人いない。重大放送を聞くため、子どもたちまで外出を止められているか。水に潜って魚を掴み取りするには絶好の条件だ。フリチンで、ひとしきり魚取りに興じたあと、暖をとるため草むらに寝ころんだ。陽光がさんさんと降りそそぎ、空はどこまでも青い。自然の恩寵に包まれた感じ。空に向かい、久しぶりに元気を噴射して解放感に浸ったが、何か変だ。辺りが、あまりにも、静かで爽やかだった。(この感じは、昭和天皇が亡くなった朝にも感じたが、この件については、いつか書く機会もあるだろう)
10時過ぎだったかと思うが、聞き慣れた爆音が聞こえ、B29が1機、名古屋方面に向かっていた。警報も出ず、対空射撃もない。いつもだったらブーブーパンパンと騒ぎ立てられるのに、B29も何か間の抜けた感じに見える。不思議な気持ちで水に戻り、フナやナマズが生姜醤油で煮れば当分のおかずになるほど取れたので、家に帰った。すでに祖母と母は食事をすませ、防空壕の中で昼寝していた。中を覗くと、祖母が、「帰ったかよ」と気づいた。祖母は入り口に足を向け、空襲が始まってから殆ど脱いだことのなかった上着とモンペを脱ぎ捨て、腰巻き1枚の立て膝で寝ころんでいた。
「お祖母さん、丸見えだぜ」「そうかよ、お前ぁさんに見られたぐらいどうもあれせん。それより、負けたぞよ」「何が?」「戦争にきまっとるぎゃあ。今夜からは安心して寝られるわ」
私は戦争がストップしたことを聞いて、強い不公平感に襲われた。焼け出された者と焼け残った者が、このままの状況で固定されては、あまりにも違いが大きすぎた。やがては、みんなが焼け出されると思っていたのだ。
その夜、気兼ねなく明るくし、焼け残った唯一の本・『古事記全釈』を開いていると、戦勝気分に浮かれていた開戦当初に、材木屋の小父さんが「勝てもせんのに、馬鹿な戦争をはじめやがって」と呟いたこと、親戚のヨネサマが戦災にあった日、「ド天皇タと、ド東条タが戦争始めなんだら、わしら、こんな目に遭えせなんだのに!」と罵ったことなどが、改めて心に響いてきた。結局私の周辺では、まともな人より、小ずるいと陰口をたたかれたり、学問や教養のない人が真実を語っていたのだ。
そして、『あなた様の白い御手で、私の柔らかな肌を素肌のままに抱いて、互いに手足をさしちがえ、まとわりつきながら、足をさし伸べてゆるゆると寝ましょう』と、女神が夜這いに来た男神に応えた古事記の中の歌の情景が、平和のイメージとしてよみがえってきた。そして何よりも印象的なことは、天皇は神でなかったことがはっきりして、長年の疑問から解放されたことだった。
この日、1945年8月15日は、忘れられない日として心に刻みつけられることになった。
翌朝、動員工場に集合すると、直ちに学校へ引き上げた。そして、その日だったか、配属将校・陸軍中佐の離任式があった。白い口髭をたくわえ、いつも温厚な風貌を漂わせていた老中佐が、珍しく気色張った顔つきで講壇に立った。何を聞いたためか忘れたが、私が苦笑していると、中佐は軍服の袖で涙をぬぐい、「私たち軍人が、こんな状況に導いてまことに申し訳ない」と謝り、「ただ最後に、何よりも心配なことは、君たちのお母さんやお姉さんのことだ。今後敵軍が占領にやって来ると、どんなひどいことをするかわからない。どうか、遠くの田舎か山奥に隠れように伝えてもらいたい」と注意を促した。
ところで、中佐の話に苦笑したことはよく記憶しているが、なぜ苦笑したかは、これまで思い出せなかった。今回この文を書くに当たり、2、3の同窓生に尋ねて、60年ぶりに氷解した。
講壇に立った中佐は軍刀を抜いて、「この軍刀に敵の血を吸わせてやりたかったが、その機会が無くて残念だった」というようなことを、激して口走ったのだそうだ。私は、温厚ぶった中佐の豹変と負け惜しみを滑稽に感じたのかも知れなかった。小学校入学時に、私が戸主になっている戸籍謄本を見せられ、「お前は後見人から離れて戸主になったのだから、これからはお前が私を守っていかないかんぜ」と言い聞かされて以来、母のことが気になっていたので、中佐が最後に言い残した女性向きの心配事に気をとられ、抜刀の件は忘れてしまったに違いない。因みに同窓生は両人とも、女性向きの心配事に関しては記憶があいまいだった。
学校から帰って中佐の話を伝えると、母や祖母は「そんなこと言われても、わたしらのような力のない者はどうともしようがないぎゃあ、無責任な」と、軍人を呪った。
その後、米軍が姿を見せるまで、近所でも、あちこちで戦地体験のある軍人を囲み、強姦される、略奪されるなどと占領下の不安を予測する話が飛び交った。特に南京攻略に参加した傷痍軍人の話は強烈だった。彼が兵役を解かれた当時は、婦女殺人・暴行を自分の手柄話のように喋っていたのが、今度は自分を隠し、負けた側がどんな目に遭うかということのみを解説した。
いろんな話を聞いているうちに、戦地体験者は老中佐を始め、自分のしてきた影におびえているような気がした。
学校は残り少ない8月を夏休みに当てた。
しかし、家にはまだ焼け跡の整理が残っていた。遊んでいるばかりいられない。整理できた所から畑にしていこうというわけだ。母はトタン小屋で、現金稼ぎの和裁に励んでいたから、私と祖母が焼け跡整理に当たった。暑い真昼の祖母や母が昼寝する間は、おかずにするための魚取りを兼ねて泳ぎに行き、朝のうちや日が陰った午後の涼しさを見計らって畑づくりに精を出した。
そのうちに、母に和裁を頼みに来たり、祖母を慕って来る老若男女の話を聞いていて、戦争に負けたという敗戦派と、アメリカの物量には負けたが精神では勝っていて、天皇陛下が詔勅を出して命令されたから矛を収めたという終戦派がいることがわかってきた。焼け出されたり、家族が戦死したり、戦地に家族を送り出しているなど戦争に深手を負っている人たちに敗戦派が多く、戦争でうまい汁を吸ったり、戦災を逃れたりして、戦争による痛手の軽い人たちに終戦派が多いことがわかってきた。近郷近在で焼け出されたのは私の字(あざ)の約150軒だけ。圧倒的多数が無傷のまま。そんな人たちには、まだ戦う余裕はたっぷりあると、敗戦が納得できないようであった。
8月15日を敗戦の日とするか、終戦の日とするか。この認識の違いは根が深くて、戦後の歴史をややこしくし、未だに国の進路をあやふやにしている。
私は言うまでも無き敗戦派。小学生低学年までとは言え、中国を分捕ろうとして軍人になりたがったり、南京攻略の体験談から、敵国の女性を暴行してみたいと興奮したのは事実だ。だから私は、明らかに戦争に加担した。そして敗れたのだ。
私の戦後は、戦争加害者としての後ろめたさを引きずって始まった。
⇒ 目次にもどる
| 第14回「“戦後の空は青空”の時代」 |
戦争は終わったが、便所も風呂もない、防空壕と、それに連なるトタン小屋で不自由な暮らしはつづいた。祖母や母のように、もらい風呂や便所を借りることはプライドが許さず、私は小川の水浴び場で体を洗い、雨の日も風の日も、人目を忍びながら小径をへだてた裏の竹藪で大の用を足した。ときには元気の噴射でもと、改めて辺りをうかがえば、いつものフクロウが見下ろしていて、止めざるを得ないこともあった。いかに鳥だとはいえ、元気の噴射を見られるのは、なんとも気恥ずかしい。
トタン小屋の中では、母が反物をひろげて和裁をしていたので、外光のある間は、防空壕の入り口へ降りる階段が本や新聞を読む場所になった。その防空壕から3メートルと離れていないところを、街道から畑へ向かう農道が通じている。地元の人に見られるのは何でもなかったが、他村の人が、国鉄東海道線清洲駅への近道としては大した差もないのに、農道をわざとがましく行き来して、それとなく投げかけていく視線には強い屈辱と怒りを覚えた。
しかし、こうした不自由な暮らしを続けていても、「天皇は、神か人間か?」という長年の疑いが晴れて、心の中にはいつも青空が広がっていた。ただ1冊焼け残った『古事記全釈』を繰り返し読み、そして考えた。
「おれは古事記を読んで、日本は神の国でもなけりゃ、天皇は神でもないとわかったのに、勉強呆けしたのか利口馬鹿だったのか、偉い学者や大人は、どうして同じものから皇国思想や天皇崇拝ちゅう好い加減な理屈をひねくりだしたのか?」
敗戦のどさくさに紛れて、近所でもいろんなことが起こった。最大手軍需工場の幹部が、清洲公園に備蓄されていた軍の建築資材を出入り業者に大量に運び込ませ、それが窃盗になると指摘されて、あわてて返しにいったり、名古屋の輜重隊に入っていた兵隊が、馬に引かせた運搬車で山のように軍の毛布や衣類などを運んできて、横領になるからと返しに戻ったり、鋳掛け屋から下請けの軍需工場に転業して羽振りの良かった親爺さんが、ヒトラーや東条大将のように生やした口ひげを急いで剃ったりした。こんなことを見聞きしていると、大人たちの化けの皮がはがれた感じがした。半月ほどの夏休みはアッという間に過ぎ去った。
8月末には連合国最高司令官マッカーサー元帥が厚木飛行場に到着。9月2日ミズーリ艦上で降伏文書調印式。いよいよ占領軍がやってくるという慌ただしさと不安に包まれて、中学2年の2学期が始まった。
多くの学校は、食糧不足の折から弁当を持ってこなくてもすむように、午前と午後の2部授業を実施したそうだが、わが明倫中学は愛知一中をライバルとする進学校。「勤労動員による遅れを取り戻せ」「食えるものは何でもいいから持ってこい」とハッパをかけ、全日授業を強行した。しかし私が学用品として持っているのは、勤労動員のために母が帯芯で作ってくれた雑嚢と、その中にどうして入っていたのかわからない一対の大きな三角定規だけ。学校が配給してくれたのか、闇で手に入れたのかは思い出せないが、削りにくくて芯の折れやすい粗雑な鉛筆や、ノート代わりのわら半紙を用意した。
秋口には学年ごとに記録を争う催しが、運動会代わりに行われた。学年優勝者には、わら半紙を二つ折りにして綴じただけの粗末なノート1冊が与えられた。私は100m、200m、円盤投げ、砲丸投げ、幅跳び、走り幅跳び、高跳び、走り高跳びに学年優勝し、各教科に対してノートが調った。しかし参考書類のないのには閉口した。
母からもらったわずかな金を持って、名古屋中心街の焼け跡にぼつぼつと小規模ながらも出始めた古本屋を渡り歩いた。しかし、ほとんどの本が高くて手に負えなかった。そうした或る日、『数学大全』という分厚い本に出合った。値段も手頃だ。明治時代の発行となっているが、パラパラとめくってみると、数学のことがすべて解りそうだった。あわてて買って家に帰り、見直してみてガックリ。大半が算術で占められ、中学で習うべき代数幾何は初歩の部分がわずかに出ているだけだった。翌日急いで返しに行ったが、鶴亀算や旅人算、植木算などに混じって、糞尿算のあったことが後々まで印象に残った。
糞尿算とは、成分になっている物質の単価から、人糞1貫目(3.75㎏)、尿1升(1.8リットル)の値段を割り出す計算法であった。糞尿算の存在理由は、後年助監督として映画撮影所に就職し、時代劇の風俗考証を手がけるうちに類推できた。糞尿を肥料として盛んに使った江戸時代や明治の庶民とって、糞尿の扱いや貨幣価値を知っておくことは、生きる上で大切な知識だった。糞は主に根肥に、尿は掛け肥にと、それぞれ使い方が違うので、糞尿が混ざると貨幣価値は下がる。古くから1940年代まで、普通に見られた女性の立ち小便は、糞尿を仕分ける重要な風俗でもあったのだ。
名古屋でも、進駐した米軍の姿が目立つようになった。そのスマートなこと。上官に対する挙手の礼は、挨拶程度の軽快な動作。街を連れ立って歩くときの伸び伸びした身のこなし。暴力と罵声で鍛え、鍛えられ、上官に欠礼して殴れれてはかなわないと、どこにいてもおどおどと気を配り、こちこちになっていた日本軍とは格段の違いだった。
「あの調子でも戦争に勝てたんだ。日本軍は何しとったんだ」
清洲の町にも進駐軍がジープで現れた。トラブるわけでもなく、祖母や母は安心した。
「それ見やぁ、日本の軍隊とはえらぇ違ぇだげぁ」
進駐軍は近くの子どもたちにチョコレートやチューインガムをばらまいたこともあった。親たちは「みっともなぇことするもんだなぇ」と叱りながら、陰では「ちびっとだけ、ちびっとだけ」と子どもから分けてもらい、「ヤンキーはうまぇもの食ってやがるなぁ。これじゃ負けるのも無理なぇわなあ」と納得する人も多かった。
寒くなる前に、「お祖母さんに、いつまでも防空壕生活をさせてはおけん」と、母の姉婿が材木を調達し、町役場の便宜を頼りに一間の家を建てることになった。しかし町役場の便宜と言っても、当時不足していた大工や左官、瓦葺き職人の手配だけだった。助手の仕事は、学校を休みがちにして私が一手に引き受けたが、60代半ばの祖母も脇からよく手伝ってくれた。土台を築いたり、建て前や瓦葺きを手伝ったり、竹を割ったり細縄をなって壁を塗るための木舞を組んだり、わらを切り込んだ泥と水を足でこねて壁土を作ったり、荒壁を塗るなどして、冬の初めに、押し入れや床の間付きの6畳間の家と、便所や板の間、台所、土間などを含んだトタン葺きの差しかけを組み合わせた住まいが完成した。罹災後6ヶ月、やっと地上の暮らしに戻ることが出来た。あたかも巷には、「赤いリンゴに唇寄せて、黙ってみている青い空・・・」と、松竹映画『そよ風』の主題歌、並木路子が歌う『リンゴの歌』が流行り始めていた。そして祖母が、罹災以来絶っていた神信心を、いつの間にか始めていることに気づいた。
「ついこないだまで、神も仏もないと言ってらぇたのに」
「そんなこと言ってたかよ、そんなことは言うもんかよ」
祖母は肩をすぼめ、飼い猫のミケにつきまとわれながら、夕闇せまる裏の氏神さんへお参りに行った。やがて、私が、戦災まで家にあった木造の小さな“立ちダルマ”を思い出して彫った、下手くそな立ちダルマを床の間に飾って拝みだした。中国戦線に派遣されたままの一人息子、私が兄貴代わりにしている叔父のことが心配でたまらなかったのだ。
1945年は、敗戦後の混乱のうちに慌ただしく過ぎていった。
そして1946年の元旦、新聞は、天皇が詔書を発布し、自分は現人神でないと宣言したことを伝えた。「こんなことは、とっくにわかっとるわ」とつぶやくと、祖母がたしなめた。
「そんな、もったぇなぇことを言うもんでなぇ!」
祖母は戦災に遭う前の自分を取り戻していたのだった。
⇒ 目次にもどる
| 第15回「“やみくもに生きた”時代」 |
1946年1月、中学2年の3学期が始まった。しかし、国鉄は汽車通学を全面禁止していたので、名古屋へ出るのに、清洲駅から東海道線を利用できなくなった。
敗戦を境に、炭坑へ強制動員されていた朝鮮人、中国人、俘虜などの解放や、劣悪な労働条件による炭坑労働者の激減で、石炭が極度に不足したからだそうだ。石炭を焚かなければ、蒸気機関車は走れない。国鉄は前年暮れから旅客を5割削減。通勤は仕方ないとして、通学には私鉄の郊外電車を使えというわけだ。
ところで私の家から私鉄の駅まではかなり遠く、電車通学に気乗りがしなかった。祖母や母から「無茶だ」と言われたが若気の至り、裏の新国道を名古屋の市電が通る所まで歩くことにした。道程およそ7キロ。通学時間はそれまでの倍、3時間近くかかることになった。
気がせく登校時には、しばしばトラックの後ろにぶら下がり、一挙に時間・距離を稼ぎ、下校時には、空の運送馬車に頼んで荷台に寝ころび、のんびり帰ったりした。朝6時に家を出て、夕方7時前後に帰る通学は、黄だん発病のため、2ヶ月ばかりでダウン。やはり若気の至りだった。
心配した祖母は、農家の“こひょうさ”と呼ばれる人に切符の手配を頼んでくれた。
「お前ぇさんとこのことなら、心配ぇせんで任せといてちょう」
こひょうさは、“屁こひょう”とも言われ、呼ぶと「ぷっ」と屁で応えるひょうきんな人。当時は食糧・生活用品など全てが不足していた時代。そこを見込んで、こひょうさは、米や農産物、鶏肉、闇物資などを融通して、駅員をはじめ、必要な人たちを秘かに手なづけるのが上手だった。その後は、朝駅長の官舎を訪れると、名古屋までの往復切符を売ってくれるようになった。
この年、テンペツと呼ぶ小さな竹かごをいつも腰に吊っている“テンペツ乞食”、体にぶら下げた沢山の空き缶をガラガラいわせて歩く“がんがん乞食”、1本づつ抜いた頭髪の根本を舐めては「がぇっ、がぇっ」と唾を吐く“稲葉のがぇがぇ”、妻らしき女性をいつも背負って物乞いに出る
“父ちゃん母ちゃん”など、もの覚えがついた頃から親しんできた乞食が、栄養失調で皆死んだ。世間では畑泥棒、家泥棒が横行していたのに、なぜ盗み食いをしなかったろう。横山大観に似た風貌のてんぺつ乞食は、裏の鎮守の拝殿で死んだ。彼らは潔癖孤高の人として私の記憶に残っている。
私は暇のある限り、栄養補給のための魚を捕りに川へ出かけた。川魚の好きな祖母に見習い、フナ、モロコ、ナマズなどが美味しく食べられるようになった。小骨の多い川魚を上手に食べるコツは、煮付けた味がなくならないうちに、小骨を肉に包むようにして喉元を通すことだ。小骨を気にして噛みすぎると、生臭いだけになってしまう。このことから人(特に女性?)とのつきあい方を学んだような気がする。個性はその人の小骨、上手に飲み込むに限る。とはいうものの、なかなか骨の折れることで、修行は未だに続いている。
4月、3年に進級した。
剣道、柔道など武道を除いて、部活動が復活した。かつての軍国主義への反発から、武張ったことを嫌ってテニス部に入ろうとしたが、上級生は、学年一と目される私の腕力を見逃さなかった。集団制裁まがいに、むりやり相撲部へ入れられた。現在は知らないが、当時の中学相撲はぶつかり相撲、押し相撲、立ち上がりの瞬発力で勝負を決めるのを良しとした。四つに組み、技で駆け引きするのはプロのやることで、中学生の相撲らしくないとされた。だから、力さえあれば上級生とも対等。上級生の制裁が黙認された敗戦前とは違うんだ。私は言葉や態度で、秘かに部活動の民主化をねらった。野球部、テニス部など他の部は戦前の名残で、先輩後輩の秩序を保ち、しごきに近いことをやっていたようだが、相撲部は肉弾をぶつけ合う猛者の集まりにもかかわらず、雰囲気は和やかだった。皆楽しんで相撲を取った。私は今も、先輩後輩のけじめがうるさい部活や体育界は大嫌いだ。
5、6月頃だったと思う。戦後初めて映画を見た。アメリカ映画で、グレゴリー・ペック主演『王国の鍵』だ。筋は忘れたが、ペックの実直そうな青年牧師の姿だけが瞼の裏に焼き付いている。しかし、それよりも印象的に覚えているのは、その頃、本編の前に上映するニュース映画が映し出した昭和天皇の地方巡幸する姿だ。当時天皇は、敗戦後の国民を慰め、元気づける名目で方々の地方を巡幸していた。よたよたとした歩き方、ぎこちない物腰、住民との対話で、間の手に「あっそう、あっそう」と連発する調子はずれのかん高い声。侍従武官を引き連れ、軍服で東京空襲の被災地を巡幸する戦争末期の報道写真の颯爽とした姿とは格段の違いだった。どちらが本当の姿か。両方とも演技だったのか。突き詰める気はないが、今に残る疑問だ。
そして、その秋のことだった。天皇が裏の国道を名古屋から岐阜へ向かうという。ヨネサマが「見に行こまぇか」と和裁をしている母や祖母をしきりに誘った。ヨネサマは空襲で焼け出されたとき「ド天皇タとド東条タが戦争始めなんだら、わしら、こんな目に遭えせなんだのに!」と叫んだ親戚の小母さんだ。母たちは興味を示さなかった。やがてヨネサマが帰ってきた。
「いま通らっせたわ、すぐ近くをよう。それに窓開けて」
「そんなら、よう見えただろうがぇ」
「それがあかんがぇ。ありがた涙に目がかすんでまって、よう見えなんだわ」
私たちは罹災時のヨネサマと比較して大笑いした。その後いつだったか、再びニュース映画で地方巡幸する天皇を見たとき、懸命にぎこちなく手を振るその姿に、思わずこみ上げてくるものがあって愕然とした。戦時中、頭の方は天皇崇拝から脱落していたはずなのに、意識の奥底には崇拝感情が消えずに潜んでいたのだ。自分に裏切られることがあることを知り、改めて人の不思議さを感じた。自分探しの始まりかも知れない。
2学期中間試験の1日が雨にたたられた。わが家は母子家庭として戦後復興が遅れ、おんぼろの番傘1本しかなかった。母は「近所から借りて来ようか」と気をつかったが、私は他人の世話になるのはプライドが許さず、強く断った。試験をさぼることに決めたのだ。そのため2学期の成績表には、何科目かに落第点を示す赤座布団(赤い線)が敷かれ、成績順位は250余人中のビリ近くに下がった。母は父兄会で担任にこっぴどく叱られてきた。私は悩んだ末、母に頼んで英文の毎日新聞を取ってもらい、editorial(社説)の翻訳に取り組んだ。文法も単語もほとんどわからない。単語の意味がわかれば文の意味もわかるだろう。片っ端から単語の意味を調べた。毎日毎晩何百回となく字引を引いた。必修単語は毎回のように繰り返し出てくるので、単語帳を作って暗記する必要はなく、自然に覚えられていった。語彙が増えると、文も訳しやすくなる。1947年の正月を過ぎて2月半ばになると、10回ほど字引を引けば、専門分野以外を扱うeditorialは大体読み切れた。英語の教科書が、驚くほどやさしく思えるようになった。3学期の席次は、250番台から40番台に上昇した。後年、娘たちが大学受験に備え、面白くなさそうに単語帳で単語を暗記してるので、自分の経験を奨めたら、「時代が違う」と一蹴された。
学年末のことだったと思うが、名古屋宝塚劇場で額縁ショーが上演されることになった。女性の裸が見られると、東京で話題になったものだ。どのようにして入場料を都合したのか覚えがない。中学生と怪しまれずに入場できた。放出品の軍服に老けた顔。中学生とは思えなかったのだろう。大劇場の広い客席は満員。幕が上がると、大きな額縁の中で、裸の女性が腰に布を巻いてポーズをとっていた。思わず魅せられて目を凝らす。照明に輝く白い肌。じばらくして、パッと暗転。次の照明が当たると、パラソルで腰を隠した女性が別のポーズを作っている。じっとしているだけとは言え、その日のヌード鑑賞は、私にとって戦後の象徴的な出来事となった。
⇒ 目次にもどる
| 第16回「“民主的混乱”の時代」 |
1946年11月、新しく成立した日本国憲法が公布された。政府はその普及に乗り出し、私の中学校にも新憲法の産婆役を果たしたとされる金森徳治郎国務相が、「世界に自慢できる素晴らしい憲法だ」と講演にきた。巷には、「民主憲法」「平和憲法」とともに、「主権在民」「戦争放棄」「自由平等」「男女平等」「基本的人権の尊重」「民主主義」「自由主義」などの言葉があふれ出した。しかし私には、「見たいものは見たい」「したいことはしたい」と、小学校の頃から新憲法の幾らかを先取りしている感があった。
小学6年生の級長をしているときだ。親戚の農家から盗んだ婦人雑誌の付録で女性の生理を知ると、むしょうに女性器が見たくなり、幼女を誘って“お医者ごっこ”をした。それが、小学校もろくに行っていないと無学を自認する母親のヨネサマに知れ、「いつも級長するようなおまぇさんでも、そんなことをしやぇすのか」と、悲痛な表情を向けられたときの屈辱感。ヨネサマは、その場限りとして一生胸の内にしまい込んでくれたが、それ以来私は、見たいものは堂々と見せてもらおうと努めるようにしてきたのだ。
敗戦以来私は、片意地張った軍国主義が崩壊して、人の欲望が噴き出す戦後の街の状況に強く興味を引かれていた。学校が退けると、ほとんど毎日のように中心繁華街の栄町・広小路へ迂回し、戦災後の焼け跡に闇市が広がる盛り場をぶらついた。そして、婆さんが見たとたんに小便をもらしてしゃがみ込んだと吹聴する大蛇をいつ見せてくれるかと、傷薬を売る香具師の巧妙なタンカバイ(口上販売)に心をわくわくさせながらだまされたり…、華麗な看板の絵につられて入ったムシロ小屋の中の、みすぼらしいサーカスにがっかりしたり…、ゴザの上に並べられた『猟奇』『りべらる』など、カストリ雑誌のエロチックな表紙の絵に引かれ、買わずに開いてばかりいて露天商にいやがられたり…。時には金を無理して、半裸の女性が演ずる『額縁ショー』なるものを見るなど、当時の私は、一見真面目そうだが、叩きようによっては埃の出る体だった。
そして翌1947年、3年3学期末のある朝。
「ツジミツ・アキラ君はおらんかね!ツジミツ・アキラ君はおらんかね!」と、校長が興奮気味に声を張り上げがら、廊下を近づいてきた。
「おい、君のことと違うか」と、周りの級友たちがささやく。席について、「何か悪いことでもばれたのかなあ」と思い返しているうちに、校長が飛び込んできた。
「ツジミツ・アキラ君はどこかね」と、校長は顔を赤らめ、目を光らせて、教壇の上から睨みつけるように見回した。すでに級友たちは私に顔を向けている。切羽詰まった気持ち。
「ツジ・ミツアキでしたら、ぼくですが」と、私は恐る恐る立ち上がった。
「君が、そうか」と、校長は、穴のあくほど私を見つめた。叩かれたら埃が出るかもしれない。覚悟を決めていると、校長はわめくように言った。
「君はね、今度の成績で、席次が一度に150番も上がった。本校始まって以来の上昇ぶりだよ。それが言いたくて来たんだ!」
校長は余ほど驚いたともの見える。2学期の成績があまりにも悪かったので、冬休みから英文毎日新聞の社説の翻訳に取り組んだ結果が、功を奏したのだ。しかし、150番上がったところで、250人中の40番台になっただけのことではないかと、私は照れくさいばかりだった。
4月から新憲法の理念を受けて成立した教育基本法、学校教育法に基づく新学制、いわゆる6・3・3・4制がスタートした。
私たち中学3年生は、4年生になるところを、新学制の高等学校1年生となった。わが明倫中学校は、明倫高等学校と改称された。格が上がった気になったのか、帽子を目深にかぶったり、破いたり、汚れた手ぬぐいを尻に長く垂らすなど、弊衣破帽を誇った旧制高校の風俗を真似る者が多く出てきた。物は大切にと、貧しく育った私には無用のこと。ただし靴がなかなか買えないので、高校卒業するまで、旧制高校生が愛用したホオ歯の高下駄でほとんど過ごした。
そして5月3日、新憲法施行。農家の多い私の住む地域でも、「これからはよう、自由で平等な民主主義の世の中だぜぇも」と、合い言葉のように交わされた。すでに公布されている労働基準法に従って、農業協同組合では、8時間労働制や週48時間制などは無理としても、週休制の規則を決めた。最初は新時代を迎えた気になって、活き活きと週休を楽しんでいたが、2、3ヶ月もすると様子がおかしくなった。時はゴボウの収穫期。出荷すれば金になる。じっとしておれない。お互いに人目を忍んで、早朝や夕暮れの暗い間に取り込み、戸を閉め切った土間で秘かに出荷の準備する人たちが増えた。規則破りは罰金だと決めたものの馬鹿らしくなり、「欲がふけぁと、民主主義は難しいもんだなも」と、週休制はうやむやに終わった。
それでも「2、3ヶ月に1回ぐらぇは平等に」と、組合員男女連れだって名古屋へ慰安に出かけた。後日、私の家へ来て祖母や母に報告する女性たちの喧しいこと。男連中の口車に乗せられて、ストリップ劇場へ誘い込まれたそうだ。
「今はやりだと上手いこと言って、ベベダスショーとやらを見せさっせるもん。あんな、とろくっさぇ人らあとは、2度とよう行かんわ」というわけで、その後慰安には、男女別々で行くことになった。
東京では5月半ばにストリップが始まったとされてるが、名古屋市内でも、秋には何軒かのストリップ劇場が出来ていた気がする。私はその一つに何度か入った。咎められることを恐れて、友人たちは脇の下に学帽を隠したが、「ヌード鑑賞の自由も、民主憲法の内だ」とばかり、私はかぶったまま入場した。当時は真剣のつもりだが、つまらない若気の至りに過ぎなかっただろう。
ところで当時の明倫高校には、がっちりと背の高い、目立って暴力を振るう体育の教師がいた。ある日、自習をしていると、大して騒いでいないのに、「お前ら喧しいぞ。しゃべっていた奴は出てこい!」と、隣の教室から腕をさすりながら入ってきて怒鳴った。教室は静まりかえった。彼の体躯に威圧されて誰も出て行かなかった。そのうちに、「委員長、出てこい!」となり、委員長がおずおず教壇に近づくと、いきなり往復ビンタを食らわした。
瞬間、私はかっときて、「しゃべっていました」と立ち上がった。
「今気づいたか」「はい、ようやく気づきました」「誰としゃべっていた」「独りでしゃべっていました」「相手がいるだろう」「いえ、独りで」「お前は独りしゃべりが趣味か」「はい」「履歴書の趣味欄に独りしゃべりが趣味だと書くか」「書きます」と、切りがない。おどおどとした教師の眼が座った瞬間、「みんな立て」ということになり、全員50人ほどが往復ビンタを食わされた。
この暴力事件は、数日生徒会を開いて「生徒に体罰を加えることは、法が禁じている」と抗議した結果、講堂に集まった全校生徒に、彼が謝罪することで収まった。元海軍将校で、みんなが格好いいと感じていた英語の担任教師は、「君たちの行動は、民主的で立派だった」と賞賛した。しかし直後に控えていた学期試験で、私の組から大量カンニング発生。私のようなものの答案用紙さへ誰から誰に渡ったのか、提出時には行方不明で大あわて。暴力事件に気を奪われ、まともに勉強できなかったことを理由に再試験。英語教師は私たちに失望して東京へ去ったと聞いた。 民主主義は、至らぬ者にとっては一筋縄で行かない。それだけに一層魅力的な主義だと感ずるようになった。
⇒ 目次にもどる
| 第17回「“可能性?”の時代」 |
戦後の憲法に基づいた学制改革により、1947年(昭和22年)4月にスタートした新制明倫高等学校の第1学年は、私にとって、人生の精神面を少なからず決定する画期的な学年となった。教科書から離れて新しい授業を模索する2人の国語教師のおかげで、『平家物語』と『奥の細道』に出会えたことである。2人はそれぞれガマ、ダルマとあだ名が付いていた。張り出した顎いっぱいに広がるガマさんの口。太い眉毛で赤ら顔のダルマさん。あだ名を聞けば、一目で察しがついた。
ガマさんは自分のあだ名が不満なのか、新任の教師がくると、それとなくあだ名の付け方を暗示した。ある坊さんが他の坊さんを見て“しろうるり”と名付けたので、「しろうるりとは何ぞや」と別の坊さんが尋ねたら、「自分も知らないが、もしあるとすればあの坊さんの顔に似ている」と答えたという。この『徒然草』の話を例に引いて、あだ名を付けるにも、知性と感性をもっと働かせろというわけだ。当時の職員室は明倫動物園と呼ばれ、タヌキ、トンボ、フクロウ、チャボ、ニャンデブなどと、即物的なあだ名が氾濫。繊細なガマさんには我慢できなかったに違いない。
そのガマさんが『平家物語』の巻2あたりまでを、自分でしたのか業者に頼んだのか、ガリ版刷りにし、1学期間の教材として配布した。授業で興に乗ると、教壇で能の『船弁慶』などを舞った。颯爽として格好良かった。興味を掻きたてられて、学期終了後には残った分の方が多かったが、プリント最後まで読み終えた。興味はいっそう高まり、ついには『平家物語』全文を読み通すことになった。
『祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる者久しからず、ただ春の夜の夢の如し。猛けき人もついには滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。』
この冒頭の一節は、敗戦体験を味わった心に深く刻まれ、つねに口ずさむ教訓となった。
ダルマさんは『奥の細道』の注釈本1冊を、学期の教材として買わせた。授業の進め方は、一区切りずつ読んでは解釈していくとのこと。1ページ目を開かせ、「月日は百代の過客にして行きかふ年も又旅人也。」と最初の一区切りを読み上げたので、顔を上げて解釈を待った。するとダルマさん、おもむろに本を教卓に伏せ、「オダサクさんは……」と、小説『夫婦善哉』の作者・織田作之助について熱っぽく語りはじめた。この1月に30歳半ばで死去した織田作之助は、絶筆となった『可能性の文学』で、志賀直哉流の私小説を鋭く批判し、無限の可能性を含んだ文学創造の必要性を強く論じているというのだ。最初の授業はオダサクさんの話で終わった。
「次からは芭蕉さんを」と繰り返しながら、結局最後の授業までオダサクさんに終始。『奥の細道』の方は、2ページ目の終わりだったと思うが、親しい人たちに見送られて江戸を出立する辺りで時間切れになってしまった。その間私は、ダルマさんの「可能性」連呼を耳にタコができるほど聞きながら、見開きにしたままの1ページ、2ページに目を注いだ。
その頃の私は、戦争を欲望しながら、そのことを戦後けろっと忘れた大人たちに囲まれていることに嫌気がさし、年老いたら自転車に乗って朝鮮半島から中国大陸を横断し、ゴビ砂漠の青空の下にしゃれこうべを曝せたらと、無謀にも願っていた。
『…古人も多く旅に死せるあり。余もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて漂泊の思いやまず』『そぞろ神の物につきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず』といった言葉が、自分の人生イメージをふくらませた。ダルマさんは、あまりにのろい授業の進め方に気づいた振りをして、最後の授業を締めくくった。
「芭蕉さんも奥の細道をゆっくり歩いたんだから、まあ良いでしょ」
この年から、わが清洲町の農村部でも農地改革が実施されはじめた。農地改革とは、アメリカの民主的な占領政策の1つによるもので、不在地主の全土地と、在村大地主の所有地から規定を超える分を国が強制買収し、小作農に売り渡して、その自作農化を進めることであった。
私たち母子が居候している母の実家は、後継者の叔父が東京の大学に進学する際、祖母は畑を他村の親戚に売って学資にあてた。そして、空襲による家屋全焼のために下りた火災保険金で、その畑をただちに買い戻し登記変更を名古屋の登記所に申請した。しかし、登記所内の整理が済まないうちに空襲で書類いっさい焼失。敗戦後、祖母が登記の復活を努力している間に、改革の実施を進める農地委員のボスは、強引にその畑を不在地主の所有とし、自分の所有にしてしまった。抗議する祖母に、字で指折りの良畑を手に入れたそのボスは、薄笑いを浮かべて言ったそうだ。
「お上さまがくだえたもん、仕方がなぇがぇ」
私は自分なりに農地改革を理解していたつもりだったが、そのやり方、「お上さま」といった言葉づかいには腹が立った。そのボスは良い田畑ばかりを手に入れ、同じ小作農の人たちからも陰口をたたかれた。そのボスは間もなく料理屋のような豪邸を建て、名古屋に青果問屋を出して、しゃあしゃあと戦後の混乱を乗り切った。
農地改革は、民主主義的、社会主義的な施策のはずだが、結局、地主が小作農と入れかわっただけ、昔ながらの保守主義者を増やしただけのことではないかと、当時の私は考えた。
ところで、名古屋の第3師団から中国戦線に送られていた叔父は、中国戦線からの復員がほとんど終わっても帰ってこなかった。心配した祖母は方々を訪ね歩き、叔父の消息を探っていると生死不明の公報が届いた。叔父は戦争末期に内地転属となって部隊を離れたので、その後のことはどうなったか、調べようがないとのことだった。祖母は戦災にあったとき「神も仏もあるもんか」と、一時は捨てた神信心をいやが上にもつのらせているうちに、シベリアから叔父の葉書が舞い込んだ。さっそく祖母は、息子がいつ帰っても良いように、材木屋の親戚に協力を求め、突貫工事で1間と風呂、台所を増築することにした。当然私は学校をさぼり勝ちにして、土台を突いたり、壁土をこねたりして職人さんの下働きをした。しかし、間もなく冬が迫ると、シベリアからの引き上げは、海が氷結するために来年春まで中断することになった。
「厳しいシベリアの冬を無事に越せるだろうか」と案ずる母を、「夢にも、そんな心配するもんでなぇ。あの子はきっと帰ってくる」とたしなめる祖母。私たち家族は叔父の帰還を信じて、1948年(昭和23年)を迎えた。
戦後もこの頃になると、戦時中から続いたモンペ姿が減り、スカートが増えて、女性が活き活きと美しくなってきた。
私たちの学年でも、色気づいた連中の間で女子高生とのナンパがすでにはじまっていた。ところで私は、同級生の中でもダントツの老け顔、いかつい体躯。もてるわけがないと、相撲をとるときとはうって変わって自粛気味。新しい時代に、これではだめだ。勇気をふるって女子高生に話しかけてみた。色魔を見る目で睨まれ、一度で懲りた。
そして学年末、登校時のことだった。名古屋駅で同じ列車から降りる大勢の乗客に混じって、彼女がいた。体に衝撃が走った。小学校時代に憧れていた1学年下の女の子だ。歌が上手で、学芸会ではいつも歌った。毎年、彼女の出番を逃さないようにして聞き惚れたものだった。
どのようにして呼び止めたらいいのか。絶対に失敗してはいけない。もたもたしているうちに彼女は人の流れの中に空しく消えていった。
「明日も会えたら」
しかし翌日から、学校は春休み。それに彼女の名前も住所もわからない。再会できる可能性に賭けて、4月の新学年開始を待つほかはなかった。
⇒ 目次にもどる
| 第18回「“無恋に悩む”時代」 |
1948年(昭和23年)4月、高校2年1学期がスタートした。春休み直前に、通学時の名古屋駅構内で目撃した憧れの彼女に再会できる、と私は燃える。小学校時代、学芸会の歌で私を魅了した彼女は、名前も住所もわからない“幻のマドンナ”として、卒業以来私の脳裏に刻み込まれたままだった。通学の途上、駅や列車内に目を光らせたが、いっこうに姿を見せなかった。やはり、彼女は幻だったのか? 半信半疑ながらに希望をつないだ。
その頃学校では、“学校統合”の話が持ち上がっていた。戦後の新学制による男女共学への足がかりとして、まず男子校と女子校を1校ずつ一緒にしようというものだ。わが校の合併相手は名古屋市立第一女子高等学校だとの噂が流れた。戦争末期の勤労動員で、わが校の生徒が市電の運転手、市一の生徒が車掌とコンビになったため、市一には全校的に親しみを感じていた。ガールフレンドに恵まれない級友たちは、2学期からの統合に期待した。すでにクラスでは、自力で他校の女子高生と交際を始めていた連中が幅をきかせつつあったのだ。
ところで5月、昨年の冬からソ連領内海の氷結を理由に中断していたシベリヤ抑留者の帰国再開。6月、叔父が帰ることになった。名古屋駅到着は深夜になるとのこと。祖母や母とともに駅付近の引揚げ者用宿舎で待機していると、上陸した舞鶴港で支給された毛布や衣類などを背負いきれないほど背負う大勢の引揚げ者の中から、叔父は、軍服の胸ポケットに手製らしい大振りのアルミ箸を2本差し込み、小さな風呂敷包みをぶら下げ、ちょっと出先から帰った感じで現れた。重くて持ち帰るのが面倒だからと、支給品は全部人に呉れてしまったという。自宅が空襲で焼失したことは知らないにしても、敗戦国の現状を把握できていなかったらしい。大正生まれの叔父は、斜陽の小地主でも羽振りが利いた頃の坊ちゃん育ちを引きずったままだった。
叔父は忽ち着る物に困った。空襲の焼け跡から無一物で出発した男手無しの女所帯は、周りに比べて戦後の回復が大きく遅れていたのである。叔父は嘆いた。
「こんなことなら、シベリヤにいた方がよかった」
中国中部の戦線にいた叔父は、敗戦間際に内地転属となり、陸づたいに帰国の途上、中国に進出していた日本人事業主から「ここでは使い道がない。旅費の足しにでも」と予想外の金をもらった。そのため天津、北京などを見て回り、時間をかけながら朝鮮半島へ抜ける途中の奉天(今の瀋陽)で敗戦。すぐに帰れば内地へたどり着けていたのに、ソ連軍の捕虜となり、シベリヤへ抑留。当初は将校も兵隊と一緒に収容され、少しでも早く帰してもらおうと、ソ連のご機嫌取りに走る人たちに煽られて過酷な労働に駆りたてられたが、ドイツの捕虜たちがジュネーブ捕虜条約を盾に誇り高く、ゆったりと収容所生活を送っていることに見習い、叔父たち将校は結束して待遇改善を要求したので、兵隊と分けて収容されることになった。その後は、労働も比較的楽になり、捕虜たち各人は多様なキャリアを生かし、道具を工夫して麻雀や将棋に興じたり、味噌醤油の製法を教え合ったり、演芸会を催すなどして帰国を待ったという。叔父の体験談は、それまでに聞いていたシベリア抑留中の悲惨な話と食いちがっていて、非常に驚かされた。
ある夕暮れ、叔父に誘われて散歩に出たときのことだった。叔父は一言漏らした。
「兵隊に行かな、男は一人前になれぇせん」
私は内心反発した。兵隊だけが戦ったのと違う。祖母も母も俺も、みんな銃後で戦ったんだ。人の苦労も察しられなくて、何が一人前だ。以後私の心は叔父と断絶する。戦地に向かうとき、軍人に憧れた小学生の私に「軍人にはなるな」と諭した叔父ではなくなっていたのだ。
私は、相変わらず憧れの彼女には出会えなかった。学校では往年の猛者と交代するかのように勃興してきた軟派のチンピラ連中が「○○校のスケにナンパされた」「××校のマブを引っかけた」などと、これ見よがしにひけらかしてくる。往年の猛者はナンパが苦手。そんな猛者の1人、私は幻のマドンナに憧れを募らせるほかはなかった。
夏休みが近づいた頃から、統合の相手は市一でなく、愛知県立第一女子高等学校らしいとの噂が立ち始めた。「えっ、バンケンか」と失望の声がみなぎった。どうして県一にバンケンと異名が付いたか知らないが、生徒たちは、自分の学校も田舎モンが多いくせに、市内の女子が集まる市一はスマートで、田舎モンが多く混じる県一は泥臭いと思いこんでいたのだ。
1学期の終りに教頭が全校生徒に、「学校としては、諸君の意を察して市一と統合できるように努力してきたが力及ばず、県一に統合することになってしまった」と弁解し、2学期からは県一に移って授業を始めることを伝えた。
叔父は、遠縁の県会議員を介して、郡部に新設された県立高校の国語教師に就職が決まった。次は結婚ということで、結婚後の叔父が暮らす玄関付きの一間を旧家屋につないで新築することになった。夏休み中の私は叔父と共同して、戦災後の自宅建築で知った要領を内心得意げに教えながら、土台固めや木舞掻き、荒壁塗り、瓦葺きの手伝いなどで明け暮れた。
9月早々、母校から2キロほど離れた県一へ、椅子を組み込んだ木製の重い机を各自で運んだ。県一の生徒たちも教師に引率されて、書類や手持ちできる備品を運んでくれた。華やいだ雰囲気がみなぎり、級友たちは統合後に備えて、県一との統合に一度でも失望したことがあったのかと言った顔を並べ、彼女たちに品定めの目を注ぐ。派手な花柄のワンピースをまとった美貌の女教師に、私たちは思わず歓声を送る。かくして、両校の同窓会である明倫会と和楽会の頭文字をいただいた愛知県立明和高等学校の2学期は始まった。
1組から4組までは男組、5組から8組までは女組の男女併学制で高校2年2学期がスタート。当初、男たちは興奮気味。一緒になって女生徒に見とれる教師も出る始末。部活動が始まると、テニスやバレーなど男女混合の運動部は大人気。男女で楽しく放課後を過ごしている。
それに比べてわが相撲部は、時代から取り残された感じ。土俵づくりを認められた場所は、ゴミ捨て場の入口。回しを締めたお尻丸出しの格好のさえないこと。ゴミ捨てに行く女生徒たちは、チラチラッと横目で見ながらクスクス笑いを押さえて通り過ぎる。時には近道だとばかり、土俵の上を踏み越えていく。見つけると、私たちは腹いせ混じりに怒鳴る。
「こらっ、神聖な土俵に土足で上がるな!」
しかし女生徒たちに猛者の威厳は伝わらない。当座は嬌声を上げて逃げ去るが、元の木阿弥。相撲が馬鹿らしくなり、クリスチャンの級友に誘われて哲学研究会に顔を出す。彼は戦前の旧制高校生から青春の必読書とされた『愛と認識との出発』の著者倉田百三に傾倒。男女の愛より、隣人愛が上だと主張。幻のマドンナを求め続けている私は、男女の愛が全うされてこそ隣人愛は成立すると反論。求道故に妻子を捨てる『布施太子の入山』など、以ての外だった。
当時は自由平等をうたう新憲法が新鮮な時代。ヒューマニティ、ヒューマニズムと言った言葉や思想が大流行。小学校時代から自分なりの独断と偏見を育ててきた当時の私は、ヒューマニティとは人間の生物性に他ならず、ヒューマニズムとは人間の生物性を認識・理解・尊重し、世界中の人間が自由平等の立場で通婚できる社会の実現に努力することだと考えていた。
そして、ついに天が味方した。
昼休みに教室の窓から中庭を見下ろしていると、憧れの彼女が仲間たちと朗らかに笑いながら走っていくではないか。それから間もなく、通学時に清洲駅でも見かけるようになった。“無恋の悩み”は解決しそうな気がしてきた。
⇒ 目次にもどる
| 第19回「“手さぐりで青春を”の時代」 |
ある時から耳にこびりついた言葉がある。
“デス・バイ・ハンギング”
言うまでもなく、death by hanging、絞首刑を意味する言葉だ。
ある時とは、年表で調べてみると、1948年11月12日の夜。高校2年の私は、極東軍事裁判(東京裁判)判決の模様を報道するラジオに耳をそばだてた。
「なんとかかんとか・センテンス・なんとかかんとか・デス・バイ・ハンギング。なんとかかんとか・センテンス・なんとかかんとか・デス・バイ・ハンギング。なんとかかんとか・・・・・・・・」
英文は何とか訳せるが、ヒアリングの全くダメな私にも、「デス・バイ・ハンギング」と何回も繰り返されて、絞首刑が宣告されているのだと察しがついた。大東亜戦争開戦時の首相・東条英機たち7人が絞首刑を言い渡されたのだ。初めて直に聞く死刑宣告の冷酷な響き。憎い戦争指導者たちではあるが、天皇の戦争加害責任をかぶったその境遇に悲哀と同情を感じた。
何となれば、南京攻略に参加した復員軍人から、中国人女性に対する性的残虐行為を手柄話のように聞かされ、幼心にも興味を抱いて「おれもやってみたい」と出征を待ち望んだり、大東亜戦争初頭の戦勝気運にのぼせ上がった大人たちに、「お前たちは幸せだ。大きくなったらニューヨークでアメリカの女が抱けるぞ」とそそのかされて、軍人になることを夢見たりしたこともあったが、戦争に行くことは、あくまで天皇の命令に従うことであり、天皇に忠義を尽くすためであって、東条たちの命令で戦争に行くとは少しも考えたことはなかったからだ。そのため、「天皇陛下万歳!」と叫んで戦死する予行演習を、戦争ごっこで何回となく繰り返したのだ。
「天皇さんは戦争責任とらんでもええのか」と、戦争加害責任を自分にも問いながらぶつぶつ言っていたら、祖母がたしなめた。
「そんなこと、口が裂けても言うもんでなぇ」
東京裁判によって、天皇と多くの日本人は戦争の加害責任を免責されたことにし、以来被害意識ばかりを肥大させてきた感じがする。往生際の悪い卑屈な歴史だ。
その頃、叔父(母の弟)は知人の仲介で縁談を進めつつあった。6月にシベリアから帰り、9月より高校の国語教師として就職できたので、次は結婚というわけだ。叔父はもとより祖母も母も、シベリヤ抑留による人生の遅れを取り戻そうと、結婚を急いでいる気配だった。
そして、見合いをして結婚に進もうとした矢先のことだ。縁の近い親戚からクレーム。結婚相手の家は、何代か前にライ病(ハンセン病)患者を出した“水が悪い家系”だから、もし結婚されたら親戚付き合いを断るとのこと。当時ハンセン病は、遺伝病ではなくて感染の起こりにくい伝染病だということが、まだ一般化しておらず、私の周辺では結婚差別の強い対象だった。
叔父はどんな理由をつけて断ったか知らないが、間もなく縁談相手の女性が解消の理由を聞かせてほしいと訪れてきた。あいまいな言い訳を並べて「とにかく無かったことにしてちょうだぇ」とひたすら断る祖母の言葉に、しょんぼりと立ち去った女性の悲しげな後姿を今だに印象深く覚えている。
引き続くようにして、叔父に次の縁談があった。直ぐに見合いをし、結婚へとなった。私は内心、叔父は女性だったら誰でもええのかといぶかったほどだ。案の定、叔父は私に耳打ちした。
「1回合っただけではよう判らんから、お前も見てきてちょー」
叔父は、わが家が斜陽になりかかった頃の坊ちゃん育ち。軍隊に入るまでは使いにも行けなかった人だ。私が育ったのは、はっきりと貧乏時代。どこへでものこのこ入っていく性格を身につけて生きてきた。
ある日曜日、縁談相手の家を尋ねると、どうも様子が変だ。縁談相手らしき女性と母親が、ばたばたと入れかわり立ちかわり出たり入ったり。座敷に上げてもらい、どうしゃべったか、私のことだから図々しく訪問の理由を話したことだろう。相手の人たちの顔が弾けてほっとした。相手の女性母子も叔父の印象をうろ覚えで、私と叔父の判別がつかなかったのだ。
「美人とはよう言わんけど、かわいくて、ええ人だと思うよ」
私の感想が功を奏したかどうかわからないが、やがて縁談相手の女性は叔母となる。
ところで、私の方は高校2年でありながら、一回り年長、12歳も年上の叔父と見まちがえられるとは、何ともガッカリした。それにしても、それにしてもだった。折角見つけた歌の上手なマドンナの前にどの面下げて出られようか。さすがの猛者も、通学で出合う彼女を遠くから目を注ぐ心境に落ち込んでしまった。
しかし間もなく、マドンナに悩んでいる場合ではない状況になってきた。母が、「今度の冬休みはアルバイトに行っとくれ」と言い出したのだ。アルバイト先は親戚の製材所。夏休みをごろごろ過ごしていた私を見て叔父が何か言ったのを気兼ねし、親戚に頼んだらしい。
「私たちの食い扶持やお前の学資以上のものを家計に入れているのに、厄介になっている手前そうも言っておれない。頼むからそうしてとくれ」
シベリヤ抑留で人生に出遅れた叔父は、安心できる家庭を持つために、貯金を殖やそうと努力していたに違いない。母は叔父から一定の額を渡され、足らない分を一生懸命裁縫で補っていたのだ。小学校入学以来私を立てて、自由にさせてくれている母に頼まれては断るわけにいかなかった。
名古屋市街の外れにある製材所は、交通の便が悪く、通学より30、40分も余計にかかった。当時は戦後の復興期。製材所がある新開地では、あちこちで家が建ち始め建築業は忙しくなっていた。仕事は機械による板削りと、建築現場への運搬。横に片輪の荷台をつけた自転車で、1キロ、2キロと運んだ。慣れるまではハンドルを取られ、人や車をよけて運ぶのに骨が折れた。それでも一緒に働いている人たちから一人前扱いされ、仕事が終わると近所の風呂屋へ行って疲れた体をやすめ、夕飯を食べさせてもらい、「ご苦労様」とねぎらわれれば、8時、9時と帰宅が遅くなっても気持ちは快適だった。仕事休みの正月3ヶ日は、「文句言われる筋合いはない」と、大手を振ってごろごろ暮らした。
冬休みが終わって、3学期が始まった。再びマドンナを意識し始めたが、家は叔父の結婚準備でごたごたし、彼女に言い寄る心の体勢は整わなかった。1月の終わりに叔父たちは目出度く結婚。家は他人を家族に加えた新しい時代に入った。
学校にも新しい時代が訪れようとしていた。地域制の導入により、新学期から地域の高校へ通うことになったのだ。地域に寄留して、このまま明和高校に残るかどうかで、級友たちは動揺した。「お前はどうする?」とよく相談がけられたが、私は「こそこそと手を使うのは性に合わん。新しい環境へ行くのもええがや」と、のっけから名古屋西高校へ転校することに決めていた。しかし私には、転校の前にどうしても確かめておきたいことがあった。マドンナの動向である。
3学期が押し詰まったある朝、通学列車の中で遂にマドンナに話しかけた。何を話し合ったか思い出せない。顔がほてったことと、舌が乾いて口がもつれたことはよく覚えている。それでも彼女の名前と、彼女も名古屋西高校へ転校する意向は聞き出せた。おまけに、初めての学校は地理がわからなくて不安だからと、一緒に初登校する約束まで出来てしまった。彼女に不安を抱かせることのないように、私は喜び勇んで名古屋西高校の下見に出かけた。
(2003年12月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ