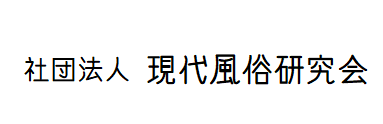| 第20回「“我が道を往く(Going My Way)”の時代」 |
1949年、高2修了後の春休みも、親戚の製材所でアルバイトを始める。憧れのマドンナに心を奪われていたのか、相次いで思わぬ事故を起こした。一度は木端を薪に切る作業中、回転する丸鋸で人差指の先を切り落としそうになった。二度目は漏電が原因だとは知らず、煙を噴いたモーターの焼け具合を確かめようと足で触ったとたん、はじき飛ばされてひっくり返った。指先が落ちそうに開いた傷口を見て一瞬青ざめたが、慌てて傷口を合わせると、奇跡的にもくっついた。はじき飛ばされた方の脚は、1日中軽快に動いて疲れない。どちらも自分の不注意から生じたことだが、Going My Way!。自分の生命力が強いと証明された、電気ショックの効能実験をしたまでだなどと楽天的に気分転換して、いつも窮地を切り抜けた。
1946年の秋に封切られたアメリカ映画『我が道を往く』の原題名が“Going My Way”。名歌手ビング・クロスビーが、衰微した教会の老牧師を助ける副牧師に扮し、歌を生かして苦労を乗り越え、火災にもめげずに教会を再建していく。敗戦後の復興に励む日本人にぴったりの話だった。封切り当時、歴史教師が「君たちは“I Go My Way” を観たかね。良い映画だぞ」と、原題名の間違いに気づかず、生徒の嘲笑を浴びながら感動的に推奨したほどで、題名は流行語となり、言葉の端々に使われた。
その後、指の傷跡は冷えると痛んだりしびれたりした。今だに跡は残っていて、映画の題名とともに気強く生きた当時を思い出させてくれる。
4月、地域の県立普通科高校に指定された名古屋西高校に、3年生として初登校する日が来た。一緒の登校を約束したマドンナとは国鉄東海道線清洲駅で待ち合わせ、名古屋駅前から市電を経由して登校したはずだが、歓喜のあまりか緊張のあまりか、その間の記憶はとんと無い。ただ、校門を入って各々の教室へと別れる寂しさと、走り去る彼女の後姿だけはその日のこととして覚えているから、知る限りの範囲で、私たちがアベック登校第1号だった。その後2人は毎朝のようにアベック登校を続けた。
私たち3学年は3組で構成され、明和高校からの目立った連中が1組に集まった感があった。旧県立高等女学校を前身とする名西高校は、この年から初めて男生徒を扱うようになったので、女生徒しか教えたことのない大半の教師は困ったようだ。特に1組は、旧明和連中のやんちゃな雰囲気が反映したのか、おとなしい雰囲気の2組、3組に比べてだけでなく、学校中で最もやりにくい組とされた。
まず備え付けの掃除道具を窓の外へ投げ出した。担任が叱ると「ぼくたちは、汚くても勉強できます」と反抗し、大きいゴミを拾うだけで掃除当番を済ませてしまう。女性教師の授業では、オモチャの自動車を走らせ、叱って取り上げると「先生の泥棒」と囃したてる。東大生を兄に持つ東大志望生が、回答困難な数学問題を仕入れてきて教師を立ち往生させ、他校から来た本物に近い不良が図に乗って「先生、出直してきてください」と授業をダメにしてしまう。戦争中に前の学校で農業指導員として採用され、今回生物教科担任として転任してきた教師の場合は、確かに教科書を読み上げるだけの退屈な授業であったが、「先生の授業面白くありませんから失礼させていただきます」と、多くが教室を出て行ってしまう。
こうなってくると、私のやんちゃとは方向が違ってくる。私は敗戦以来教師を聖職としてでなく、労働者として見るようになり、教師の生活権を脅かすようなことはしたくなかった。教室が喧しく我慢できなくなると「うるさい、授業が嫌だったら黙って寝とれ!」と怒鳴った。
しかし揚げ足を取られる場合もあった。女性教師による幾何の授業のときだ。
「先生、辻君よう、英語の勉強しとるぜえ!」
「騒ぐよりええわい」
彼女は旧奈良女子高等師範学校の出身。“ミス・ライオン”とあだ名がついていたが、教え方はそれまでの教師に比べて抜群。数学の苦手な私が最も敬愛する先生で、私にはライオンどころか、世界的名女優、イングリット・バーグマンのイメージが重なって見えてしまい、彼女の授業だけは何としても守らねばと秘かに思っていた。
ところで高3は、大学進学に備える学年だ。学校は受験指導の資料を求めて、学期が始まると早々に進学者の実力テストを行った。掲示板に発表された私の成績順位はベストテンに入っている。その上、成績点数は自分が予想したものとほとんど変わらない。何時からか、試験の成績は他者につけてもらうものではなく、自分でつけるものだとしてきた。判ることは書くし、判らないことは書かない。自分の判らないことが判れば良いんだ。何とか白紙を埋めて点数稼ぎしようと、ごちゃごちゃ答案を書くようなことは意に反した。他者と比較する必要はないし、裁いてもらう必要もない。私は実力テストの結果に納得し、以後実力テストは受けないことにした。
実力テストで好成績をあげると、アベック登校に対して教師側に或る変化が現れた。それまでは、登校の途中で出合うと咎めるように目を向けたが、テスト後は顔を伏せたり、見て見ぬふりをするようになった。
また登校の列車内で座れずに立っているとき、いつもの教師がいないことを見とどけてタバコに火をつけ、一服吸ってふと下を見たら、その教師が席に座って懸命に顔を伏せていた。こんなことが何度もあり、卒業式後の謝恩会で「どうして叱らなかったのですか」と尋ねると、「そんなこと、君には怖くてできなったよ」と苦笑された。叔母から12歳年長の結婚相手だった叔父と間違われるほどの小父さんだったから、校外では高3生がタバコを吸っているとは思われず、教師も大目に見ていたのかも知れない。
一学期末、7月に入ると、国鉄の人員整理にからんだとされる大事件発生。下山国鉄総裁が轢死体で発見され、10日後には、三鷹駅で無人電車が暴走して6人の死者が出た。いずれも共産党や労働組合の弾圧に利用されそうな事件だ。敗戦で晴れ渡った自由の空が、1947年のマッカーサーによる2・1ゼネスト中止命令を契機に曇り始め、それがますます曇ってきたと感じた。とは言っても、小学生時代から独自の考えで生きてきた私には、共産党や労組に100%の賛成はできなかった。
一方、2大事件に続いて民主主義を賛美する東宝の青春映画、石坂洋次郎原作の『青い山脈』が主題歌とともに大ヒット。朝日新聞連載中に原作を読んでいた私としては、マドンナとの関係もあって、この映画は観るべきだと駆りたてられた。しかし金がなくては、おいそれと映画館へ走り込めない。父代わりの叔父からいつも言われていた。
「お前ぇさんなぁ、奨学資金がもらえなんだら、大学へは行けんと思っとけよ」
夏休みにはいると、すぐに製材所でアルバイト。金の都合をつけて映画館へ急いだ。
映画の舞台は、青い山脈が遠くに見える東北の港町にある旧制の高等女学校。そこの女生徒と旧制高校生との交際を巡って、町の人々や女学校の教師たちの間に対立が生まれる。封建的な考えにこだわって男女交際に反対する側、新たな考えで賛成する側。両者が激突する中で、新しい民主的な暮らしや社会を追求していくのが話の筋。私の住む清洲の町からも青い山脈が遠くに見える。私は女生徒と高校生の清新な交際に共感した。
Going My Way!
或る午後、私は朴(ほお)歯の下駄をカランコロンと響かせて、コンクリートの国道をマドンナの家に向かった。
(2004年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第21回「“若気と、ごり押し”の時代 」 |
1949年、高校3年の夏休みも終わりに近いある日の午後、私は意を決して憧れのマドンナ宅を訪れた。いきなりの訪問にもかかわらず、彼女は快く私を応接間へ通してくれた。彼女の家でもボーイフレンドの訪れは初めてのことだった。両親や姉が代わる代わる入ってきて、挨拶がてらに好奇心をにじませた。ひとしきり、そんな通過儀礼があって一応面接に合格したのか、私たちだけにしてくれた。後は談論風発。何を話し合ったか記憶にないが、彼女の朗らかな笑い声だけが今も耳にこびりついている。
夕陽を顔に浴びて帰る私の心は、貧しさを忘れ、生きる自信に包まれて意気揚々。小学5年頃から、『古事記』や西鶴の『好色一代男』、婦人雑誌の付録『母・妻・娘の生理衛生』、平凡社の『大百科事典』、戦後になってアメリカ文化センターから借り出した『The Expektant Mo-
therhood』、戦後日本の性解放に大きな役割を果たしたヴァン・デ・ヴェルデの『完全なる結婚~生理とその技巧』などで蓄積し、逆に悩みの種となっていた性知識は吹っ飛び、改めて清新な男女交際への意欲を高めた。
9月から担任が研修で不在になるため、2学期は、教頭の老国語教師を臨時担任として始まった。彼は戦前、伊勢神宮付属の官立神宮皇学館大学(現・私立皇学館大学)を首席で卒業し、皇族の館長から恩賜の銀時計をもらったことを自慢した。絶対天皇制の時代、神宮皇学館大学は皇学研究の中心として、戦争とファシズムを進める国策の一翼を担い、高等神職、国語・漢文・歴史の中等学校教師を養成する権威の高い大学だったようだ。国語教師を希望した叔父も神宮皇学館大学を受験した口だが、不合格。あわてて早稲田大学の高等師範部へ走ったことを幼心に覚えている。戦後は、占領軍の命令で廃校になっていた。
(註)皇学=古代の天皇中心の体制を理想として、これを明らかにするために文献や歴史・国文学を研究する学問(広辞苑)
戦前戦中は勇ましかったであろう老教頭も、戦後は好々爺の体。それまで女子校の教師だったためか、男子生徒の扱いに手を焼いている感があった。彼は国語の授業で、当時の流行作家・田村泰次郎の文学を下劣な肉体文学とけなし、『源氏物語』のような高級な文学を読めと奨めた。田村が「肉体の解放こそ人間の解放」だと主張し、敗戦直後の焼け跡ビルで共同生活する少女たちの売春を描いた『肉体の門』は、爆発的な人気を呼び、演劇化されるとロングランを記録し、映画化されるほどだった。田村の主張に共感していた私はカチンと来た。
「源氏物語も肉体文学ではないですか。田村の文学と、どう違うか教えてください」
教頭があわてて始めた解説はしどろもどろ。彼がたいして読んでいないと察しがついた。戦災に遭う前の叔父の本棚に、重要古典を1、2節ずつ抜粋して解説を加えた国語教師養成用の分厚い本があったことを覚えていたからだ。
「先生は源氏をどこまで読んだのですか」「桐壺の巻だけだ」「僕は明石まで読んでいます。ちょっと齧っただけで、いい加減なことは言わないでください」
私は夏休みの間に、図書室で借りた源氏の注釈本を、明石の巻まで読み終えていた。
また朝礼でも、教頭の訓示にカチンと来た。「本校の生徒にあるまじき格好で来る者がいる。もっと服装を正せ」というのだ。朝礼後、すぐに教員室へ押しかけた。
「先生、あれは僕のことと違いますか」「いや、決して君のことではない」「帽子はかむらず、髪はぼうぼう、いつまで経っても兵隊の服に履き物はゴロンタ(朴歯の下駄のこと)。こんな格好している者は僕しかいないじゃないですか。家庭の事情も知らないで、勝手なことを言わないでください」
教頭はとどめを刺されたように黙った。空襲で焼け出された後、母子家庭の私は復興がままならず、鶏が土を蹴って座り心地をよくするように、精神衛生のため、いつも心の地ならしをして生きてきた気がする。
さて、2学期からは交通費を節約するため、国鉄で名古屋駅まで出て市電を利用する方法を止め、名古屋駅の手前の枇杷島駅で降りて学校までの約3キロを歩くことにした。駅のある西枇杷島町周辺の生徒は、ほとんど徒歩通学していたので、旧制明倫中学からの級友数人が仲間になってくれた。学校までの中程に名古屋市の境を流れる庄内川の堤防道があるが、その河川敷にとぐろを巻いて喫煙することが、行き帰りの楽しい習いとなった。
そしてある日の午後、通学仲間と体育の時間をさぼり、例の河川敷でタバコを吸っていると、小学生らしい1団が水際の細道を騒ぎながら下ってくる。ふと見ると、雨後の増水で広がった幅5、60mの濁流の真ん中当たりを、子どもが口を大きく開いて泳いでいる様子。応援しているのかと思ったら、溺れているとのこと。えっと、私たちは立ち上がってみたものの、どうして助けたらよいのかわからない。みんな顔を見合わせて、もじもじ。「えいっ、くそ!」と、私は裸になって飛び込んだ。流れを横切り、泳ぎ着いて子どもを抱きとめると、子どもは私の首に手を回してしがみついた。泳ぐに泳げない。流れは速い。水は深い。あわてて引き離そうとしたが離れない。一瞬恐怖に襲われたが、水の深さを探ってみると、立って頭が沈むくらいの深さ。流れに乗り、水底を蹴って浮いたり沈んだりしながらやっとの思いで岸に戻った。しかし、戻ってみると、さあ大変。ぐずぐずしていては大ごとになり、授業をさぼって喫煙していたことがばれてしまう。私たちは急いで逃げ去った。その後仲間内で話題に上がったこともなく、70年の人生で、ただ1度の人命救助はかくして終わっていたのである。
今回この文を書くに当たり、飛び込んだときパンツをはいていたのか、脱いでいたのか思い出せない。幸い仲間だった1人が、その時のことをうっすら覚えているというので聞いてみた。
「パンツ?そんなこと覚えとるもんか。それより、お前さんが助けて上がってきたとき、待っとった子どもたちがいっせいに見せた嬉しそうな顔は、よう覚えているがや」
と、友は淡々と答えてくれたが、55年ぶりに初めて子どもたちの笑顔について聞かされ、私の方はびっくりした。助けた後のことは、逃げることばかりを考え、あわてて服を着た記憶しかない。よくぞ覚えていてくれた、持つべきものは親友だと、つくづく思った。
12月に入って間もない午後、仲間の1人が空気銃を持ってきたが、鳥を撃つ気はないので国鉄枇杷島駅構内に入り、危害を生じないよう、石炭の山に囲まれた一角で50銭玉を的にして撃っていた。すると、突然警官が現れ「お前ら、狩猟法違反だ。ちょっと来い」というわけで、西枇杷島町の自治体警察署に連行された。まさか、近くに警察署が潜んでいたとは…。
戦後の一時期、従来の中央集権的国家警察を改革し、民主化・分権化を進めるため、国家地方警察の他に、人口5千人以上の市町村には自治体警察が置かれていたのだ。
取調室に入ると、「親切に、優しく、丁寧に」と書いた標語を額に入れて掲げてある。しかし隣では窃盗犯の妻らしい中年女性がぼろくそに怒鳴られていた。
私たちは鳥を撃つ気は無かったと主張しても通じず、おまけに「50銭玉には菊の御紋章がついているのがわからんのか」と、とんでもない言いがかりをつける。「ええっ!不敬罪は戦後廃止されたはずなのに」と私。「逆らったら大学へ行けないようになるぞ」と机を叩いて脅迫。取られた調書には「鳥が見つかるまで50銭玉を撃っていた」と、あくまで狩猟法違反にこじつけ、さも大悪を犯したような思いもよらない文面。逮捕されたら黙秘権行使に限ると、いい勉強になった。
空気銃の持ち主が市会議員に話を通したので、翌日口惜しそうに調書を破り、空気銃を返した。市会議員によると、年末にありがちの点数稼ぎということだった。警官は隣村の住人で、その後列車でよく乗り合わせるようになる。にらみつけると、私服で通勤の彼は気弱そうに顔を背けたものだった。
(2004年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第22回「“進学ゲリラ”の時代」 |
1949年の暮れ。国鉄東海道線の上り列車から名古屋駅の一つ手前・枇杷島駅で降りる私をいつも待って、いっしょに名古屋市内の高校へ徒歩通学してくれる星好き、鳥好きの友だち2人との間で、冬休みになったらマージャンを始めようということになった。目的は、大学入試に先立って行われる進学適性検査にそなえて、勘をきたえること。
進学適性検査=進適は、戦後日本の教育制度改革を行った連合国最高司令部民間情報教育局(CIE)の奨めによって、文部省が大学・専門学校の進学に適当な資質・能力を調べるため、1947年度から全国一斉に実施したものだ。一般系・文化系・理科系の3分野から各50問出題し、計150問を2時間で解答させる検査だったと記憶している。問題をびっしり書き並べた3枚の問題用紙を、模擬試験で初めて見たとき、私たちはビックリした。
「なんだこれ。問題読むだけで、時間が経っちまうがや。アメリカは無茶しやがる」
「いちいち考えとったらどうにもならんぞ。答えは勘だ。勘をきたえようや、勘を」
教師はあらかじめ、進適の成績は入試の成績には組み込まれない、使われるとしても、その大学の入試倍率が5倍をこえた場合に足切りの材料にされることもあるといった程度だから気にするなと説明した。だが、試される身としては少しでも好成績を取りたいのが人情だ。
かくして、私たちの3人マージャンは始まった。場所は枇杷島駅の前にある星好きの家。星好きは、進適対策を理由にして、母から自宅をマージャン宿にする許しを得たとのことだった。星好きの母は、旧制高女をトップで卒業したことを誇らかに息子の尻を叩く教育ママだった。
私たちは毎日のように、夕食までの午後をマージャンに当てた。「がんばりなさいよ」と、星好きの母はお茶やおやつを用意して、せっせとサービスしてくれた。
年改まって1950年に入ると正月気分に浮かれ、進適は入試成績に関係ないからと、早くも勘をきたえる切迫さはうすらいで、マージャンはもっぱら大学入試を控えて緊張する心のガス抜きになっていった。マージャンは3学期の授業が始まっても、時間の許す限り続いた。私たちの変心を知らない星好きの母のサービスも続いた。
進適は1月下旬に行われたが、「勘は入試にも必要だ」と、その後もマージャンは続いた。そうなると、教育ママも私たちの魂胆を見抜いたとみえて、息子のマージャンを禁止した。しかし星好きは、母に内緒でジャン牌を持ち出すからと、彼の家から2キロ半も南にある鳥好きの家に場所替えしてマージャンを再開した。星好きは、3人が鳥好きの家で集まるのは入試の勉強をするためだと母に言って、遅い帰宅を認めてもらっているとのこと。教育ママは、自由にのんびりしながら成績を上げているように見える鳥好きや私に比べて、説得を繰り返さなければ成績が上がらないとわが子を劣等視している気配で、最後まで息子の行動を見抜けなかったらしい。
マージャンでの話題はガールフレンドに関することは当然として、2月に入り大学入試の出願日が近くと、進路問題に集中してくる。私と鳥好きは名古屋大学の文学部、星好きは理学部を志望していたが、それぞれ問題を抱えていた。
鳥好きは生物クラブを取りまとめたり、フクロウが吐き出す不消化物・ペリットを竹栽培を業とする父の大藪から拾い集め、それを洗浄して得た鼠や蛙の白骨を大きなガラス容器に山積みしていた。当然理学部志望かと思っていたら、文学部志望。しかし後年、文学部の途中から農学部に移った。当時から何か悩みごとを抱えていたはずだが定かでない。
私は3学年の初めに、親代わりの叔父(母の弟)から「奨学資金がもらえなかったら大学へは行けないぞ」とか、「文学部では飯が食えない。法科か経済でなかったら許さんぞ」と強く言われた。奨学資金に関しては納得できたが、学部志望の強要には承服できず、「文学部でなかったら、大学に行かない」と抵抗し、それ以後叔父との確執が続いていた。
父が大手銀行の幹部だった星好きも悩んでいた。
「法科か経済へ入って銀行員になれと言われてるんだが、お前さんはどう思う?」
「好きな道を進んだらええがや。それが男だ」
このようなことを即座に答えたことを、今もはっきり覚えている。
出願日が迫った頃、担任にこっそり呼ばれた。
「君は名古屋大学を受験しないそうだが、君には受けてほしいんだ。初めて男子の卒業生を出す本校としては、今後のために少しでも多く名大合格者を出したいんだ。君は必ず合格する。大学へ行く行かないは別として、受けるだけは受けてくれ」
「それじゃ、まだ収めていない3学期の授業料を免除してください。受験料にしますから」
「わかった」
私の話を聞いて母は、「長い間あんたらを見ていて、どうなることやらと心配していたが…。あんたの好きなようにしたらええ」と、裁縫の手を止め、ほっとした表情を浮かべた。私は叔父に内緒で受験の手続きを取った。
当時、名古屋の国公立大学では1期校に名古屋大学、2期校に名古屋工業大学、3期校として愛知学芸大学や市立、県立の大学などがランキングされていた。だから、1次志望を名大の法学部か経済学部、2次志望に名工大、3次志望に教員養成の学大などに出願して、「一体何になろうとしてるんだ」「入れたらどの大学でもええがや」と言った会話がよく聞かれた。
星好きは私に励まされたのか、ついに地球物理を専攻するため理学部に出願。父の怒りに振れて必要経費以外の小遣いを止められたと、私たちのタバコをせびるようになった。
叔父と意見が合わずに先行き不明の私は、研究社の『英語青年』『時事英語研究』を拾い読みしたり、注釈頼りに英和辞典を引きながら『種の起源』や『スケッチブック』『宝島』などの和訳でお茶を濁していたが、入試が迫ると、受験勉強の追い込みに入っている友人たちのオーラが伝わってくるのか、やはり心が鬱屈。誰か忘れたが数人と語らって、ある日曜日、日直の女性音楽教師を急襲、社交ダンスを手ほどきしてくれとせがんだ。彼女は最初戸惑っていたが、メンバーは一応勉強家ばかり。意を決し、私たちを抱擁するようにして、ブルースやワルツ、タンゴなどの簡単なものを教えてくれた。翌日校長から小言を言われたそうだが、ダンスを習ったのは人生でこれ1回切り。今頃彼女はどうしているんだろうなあ。有り難く懐かしい思い出にしている。
3月名大入試を5日後に控えて、叔父は言った。
「文学部でもええから行け。ただし専攻は英文科だぞ」
望むところだ。受験科目に語学は英語、社会は世界史、数学は幾何、理科は生物を選ぶつもり。英語は自信があったので、他課目の教科書に一通り目を注いで入試に望んだ。高校では私の答案早出しは仲間内でも有名だった。各科目の持ち時間は2時間だったが、苦手の数学以外は20分前後で解答。「おい、もうあいつ出来たぞ」と友だち同士の私語が聞こえる。しめしめ戦略は当たっているぞと、残り時間は近くの喫茶店へ行って英気を養った。対抗意識からか、星好きも遅れを取らないように別の受験場から駆けつけた。0点だけを警戒していた苦手の数学は、山勘が当たって半分は確答。お手の物の自己採点で合格間違いなし。
翌日、「奨学資金をもらう手続きにきましたが」と文学部の教務を訪れたら、「あんたは誰です?」と疑惑の眼。「今度入試を受けた者ですが」「それだったらね、入学してからのことにして下さいよ。あんたのような人は本学始まって以来ですわ」
私は顔を赤らめて、すごすごと引き揚げた。
(2004年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第23回「“破れかぶれで順風満帆”の時代」 |
「もうお昼だぜ。起きなあかんがぇ。はよ見にいけって、兄さま(母の弟)が怒ってらぇすぜ」
と、母にゆり起こされた。1950年度名古屋大学入試合格発表の日のことだ。つねに自己採点で試験にのぞんできた私には、入試結果に自信があった。
「待っとたら、そのうちに合格通知の郵便がくるわ」
私は午後から魚取りに行くつもりだったが、家族にせき立てられて仕方なく家を出た。名古屋駅前で市電を待っていると、反対方向を通過していく市電の窓から、友人が「おーい、お前受かっとるぞ」と大声で知らせてくれた。それなら、次はどうすべきか。服や靴を調える力はない。今のままの兵隊服とゴロンタ(朴歯の高下駄)で通えと言うのか。混乱した頭で焼け跡をぶらついた先は、繁華街の2本立て映画館。そのため帰宅は夕食時。叔父が怒鳴った。
「遅いだなぇか。こんな時間まで何しとったんだ。不合格で自殺でもしとれせんかと、お祖母さんが心配してばっかりしてらぇたぞ」
「これまで何度も死に目にあってきた。そんなことで自殺なんかせぇせんわ」と言い返したが、和裁で生計を立てる母に代わって、幼児から面倒を見てくれた祖母には弱い。
「警察から何かあったり、3日以上も音信不通だったら仕方なぇが、わしも大学生になったし男だしよう、ちっとは破目外すかもしれんけど、取り越し苦労だけはせんどいてちょう。頼むわ」
「そうかよ。そうかよ」と、祖母は私を頼もしそうに見上げて願いを聞いてくれた。翌日祖母は、両手で抱いた学生服に角帽を乗せて帰ってきた。懇意にしてる近所の薬屋から、子息が使い終えたものを頂いてきたのだ。また、祖母が古くから親しくしている被差別部落の小父さんは、お祝いにと、旧海軍から放出された中古の黒靴を真新しく修繕して届けてくれた。
当時の名古屋大学は“蛸の足大学”とも言われ、文学部、医学部、工学部、経済学部などが名古屋市中に分散。とくに教養部は名古屋と、60キロも離れた豊川に分かれ、文系志望の最初の1年は豊川分校で講義を受けることになっていた。豊川分校は陸の孤島のような交通の不便なところにあり、名古屋からでも片道3時間、清洲の町外れにある私の家からは4時間近くかかる。学生のほとんどが寮に入った。経済的に入寮できない私は通わざるを得なかった。
また、講義は午前中に2時限、午後に3時限。「本学は、教員養成所ではない」と、教員資格を取るための講義はすべて、通学生に不利な、午後6時近くまで続く5時限目に当てられている。私は1年間の長時間通学に備えて、1時限目、5時限目の講義を放棄した。
時代に有利だからと法・経学部を強いる叔父を説得し、英文科を専攻する条件で文学部にすすんだ私にとって、教職課目の放棄は現実的な選択肢をせばめる恐れもあったが、意識や感覚の自由を広げることにもなった。
朝6時に家を出て、夜9時に帰る通学はかなりの負担。間もなく急性肺炎にかかったが、戦後の新薬・ペニシリンにより、半月ほどで快癒した。私が生まれて3月目に急性肺炎にかかり、10日ほどで21年の生涯を閉じた父を感無量に思い出し、改めて自分の生き方を考えた。
信仰心の厚い父は今際の際に、私の行く末を心配する母から言い残すことはないかと尋ねられると、「この子には光明という良い名前をつけておいたから心配することはない。きっと良い子に育つから言い残すことはない。後はお題目を唱えてくれ」と答え、母や祖母、幼い叔父が一心に唱える「南無妙法蓮華経」に包まれて息を引き取ったそうだ。
しかし私は、涅槃の境地で逝った父と違い、戦争体験によって神仏を捨てている。また前年の秋、東大生が高利のヤミ金融会社「光クラブ」を経営し、金繰りに行き詰まって自殺した、いわゆる「光クラブ」事件に関して、著名な漢学者のコラムの中に、「光」と言う文字は「……し尽くす」と言った激しい意味を持ち、皇帝や皇后など位の高い人の名には釣り合うが、何でもない人に使うと位負けして不吉を招くとあった。日中戦争時代に日本軍が中国で行った作戦を、中国では三光政策と呼び、焼光〈焼きつくす〉、殺光〈殺しつくす〉、搶光〈奪いつくす〉の三つを指していることを後に知ったが、私も小学5年に古事記、万葉集を読んで天皇崇拝から脱落するまでは、三光政策に加担してきた覚えがある。
考えていると、一筋縄ではいかない前途が待っているよう気がしてきた。
6月25日朝鮮戦争勃発。
新聞では北朝鮮軍が韓国へ侵入してきたように報道されていたが、私にはマッカーサーの(公式的には連合軍総司令部だが)米軍司令部が共産主義国家・北朝鮮攻撃のチャンスを掴むために誘い込んだように思われた。1947年の2・1ゼネスト中止命令を出して以来、米軍司令部は、日本の保守政府と結託して共産党や革新勢力、革新運動を弾圧してきたからだ。
また大学には民間情報教育局顧問イールズを送り込んで、教授から共産主義者を排除せよと押しつけたので、かなりの学生が反政府的、反権力的気分をみなぎらせていた。権力をむさぼる国家や資本家からはむしり取るにかぎるという理屈をつけて、週末に名古屋周辺の実家へ帰りたがる入寮者は、私のような通学者の定期券を利用してキセル乗車をよくやった。ある時などは、10人近くが私の定期券を使い回して名鉄名古屋駅の改札口を出た。そのとき浮いた金でみんなと観た映画が、戦前から有名な『モロッコ』。砂漠へ出発する外人部隊。その中のプレーボーイ(ゲーリー・クーパー)に惹かれた酒場の女(マレーネ・ディトリッヒ)がハイヒールを脱ぎ捨てながら追いかけていくラストカットは、太鼓の音ともに、強烈な記憶となった。
大学授業料は年3600円だが、奨学金は月1800円。それに夏休みは、例の薬屋でアルバイトが出来ることになったので、高校時代より懐事情がやや好転し、通学を続けられる目途がついた。仕事は、自転車であちこちの病院や医院へ医薬品を配達したり、ロウを溶かし込んだ塗り薬や、薬草を煎じた咳止めの水薬などを作業場でつくることだった。
ある朝店番をしていると、表の国道でトラックを止めた若い運転手が飛び込んできて、顔を赤らめ口早に注文した。「ハ…ゴニョゴニョ…ビン下さい」「はあ?何ですか」「ハ…ゴニョゴニョ…ビン」「ああ、蠅取りビンですね。ここは薬局ですから置いてませんが」
若者はますます顔赤らめて用件を述べるが、聞き取れない。すると、身を隠すようにして出てきた薬屋の娘さんが、小声で「辻さん」と、笑いをこらえて指差している。私は「ええっ?」と唸った。それは、「ハート美人」と名づけられた衛生サックだった。若者は女性を意識していっそう顔を赤らめ、金を払ういなや飛び出していった。
「悪いことしちゃいましたね」
「いいのよ。私だって、ナイトキャップ下さいと入ってこられて困ったことがあったもん」
ところで、運搬用自転車の荷台に満載し、ハンドルを取られないように田舎の凸凹道を走る医薬品の配達は、炎天下の大変な仕事でもあった。古い店なので商圏が広く、病院や医院、受注先の薬局を地図で探しながら、汗を拭き拭き1日20キロ、30キロと走った。疲れたが辛くはなかった。私には希望があったのだ。自然に鼻歌が出、口笛が鳴った。
配達の途中、たまたま長い木橋を渡っているときのことだ。「行ってらっしゃーい! 気いつけるんだよ!」と女性の叫び声。自転車を止めて斜め下を眺めると、私に靴を贈ってくれた小父さんの住む被差別部落から、母らしき人に見送られて、角帽を被った大学生が大きなトランクを下げて去るところだった。幼いとき祖母に連れられてよく通ったその部落は、水はけの悪い道に軒の低い家が連なり、じめじめとした暗い感じだった。2人の情景に目を注いでいると、部落の未来が明るく開けていくような気がして、言いしれぬ感動に包まれた。
(2004年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第24回「“自由を求めてジグザグ”の時代」 |
1950年、名古屋大学に入って最初の夏休みが終わった。アルバイト代を手にして、真っ先に買ったのは近眼鏡だった。
視力1.5だった私の眼は、戦災後半年もつづいた暗い地下防空壕の生活や栄養不足が祟ったのか、高校前ごろから近視がすすんだ。黒板の字や、外国映画の字幕が読みづらくなった。しかし、眼鏡を買う経済的余裕はない。友人がオモチャにしていた父親の眼鏡レンズをもらい、支えやすいように割り箸にはさんで片めがねを作った。社交場や舞踏会などで、西欧の貴婦人が柄付きの片眼鏡を目に当てて男の品定めする場面にヒントを得たわけだ。自作の片眼鏡を教室で使うのは気が引けたが、映画鑑賞には利用した。高3からは、たまたま叔父が作りかえて不要になった眼鏡をかけることにした。ところが私には度が強く、道の前方は下がりぎみに見え、足元は実際より低く見えるので、足がもつれたり、階段でつまずいたりした。新しい眼鏡はこれまでのトラブルをすべて解消し、自分の眼に合った眼鏡はなんといいものだろうかと実感した。
9月の末、前期の講義が終わって秋休みに入った。その頃になると稲田に水は要らなくなる。用水の流れは止まり、小川にはあちこち水溜まりができる。その水を掻い出して閉じこめられていたフナやナマズなどの魚を捕るのを掻い掘りといい、秋の楽しみの一つだ。泥んこになりながら水をバケツで掻い出していると、背中に声が響いた。
「お前は大学に入って、まだこんなことやっとるのか!」
東京の大学に進学した友人が、呆れたと言わんばかりの表情で立っていた。
「おれは30までに金を貯め、後は芸者遊びで暮らすんだ」
友人と2人で1人の女郎と遊んだことを面白そうに打ち明け、将来の夢を意気揚々と語った。
高校を離れて、それぞれの人生が始まっていた。
これも、秋休み中のことだったと思う。高校の数学女教師、親愛なるイングリット・バーグマン先生を訪れたとき、私たちの学年が卒業するのを待っていたかのように生徒補導委員会が設置されたと聞いた。
「授業がやりやすくなったわ。でも、面白い生徒がいなくなったみたい」
教師たちの戦争協力ぶりを知っている私たちの世代に突っ込まれるのを恐れたのか、ほとんどの教師が戦争中の話題を避けた。そのため私たちには遠慮気味で、生徒補導は不可能だった。 「2度と生徒になめられてたまるか」
こんなところに、教師たちが管理体制を整える原因があったのではないだろか。
9月15日、米軍主体の国連軍が朝鮮戦争に出動。仁川に上陸。北朝鮮に半島全域が占領されるかどうかの危機に迫られていた韓国軍も反撃に転じ、38度線突破して北進。国連軍、北朝鮮首都平壌を占領。しかし10月末、中国人民義勇軍の出動を得て北朝鮮軍の総反撃開始。12月始めには平壌奪回。
一方国内では、朝鮮戦争と並行するかのようにマッカーサーの指示による警察予備隊の創設、公務員やマスコミ関係者のレッドパージ、戦争責任を問われた旧政府要人・旧軍人の追放解除、対日講和問題などが目白押し。政府の右傾化・逆コースがはっきりしてきた。私たち学生や周りの人たちの会話は、再軍備に賛成、反対などと自然に政治がらみとなった。
こうした中で、再軍備まっぴらごめんの私は「喉元過ぎれば熱さを忘れる」のことわざどおり、敗戦で晴れ渡った日本の空を曇らす連中が増えつつあることを実感した。戦争中から団体行動が嫌いになった私は、再軍備反対の運動に参加する気にはなれなかったが、軍備に頼らない世界平和への道を探るようになって今に至る。
1951年は、北朝鮮軍・中国軍が38度線を突破して南下、ソウルに入城するという緊迫した状況で明けた。韓国政府の釜山移転。国連軍の反撃でソウル再奪回。38度線を再突破して北進。
私の大学1年目は朝鮮戦争を背景に終わった感じで、豊川分校への長時間通学を解かれた。
4月、名古屋分校で講義を受けることになり、通学時間は半減した。嬉しいことに、高校を卒業して洋裁学校に通いはじめた憧れのマドンナとも、いっしょに通学できる機会がふえた。時には遅刻覚悟で喫茶店に入り、朝の一時を楽しんだ。
しかし困ったことに、大学2年になっても講義の聞き書きが不得手なことは相変わらずだった。私は生来の左利き。右利きに矯正したものの、指先は脳とうまく回路がつながっていないのか、急がされると字がグニャグニャになってしまう。努力が足らないと言われればそれまでだが、左利きを不利とする世間に反抗心をかき立てながら、講義に臨んだ。
私の心は当然のように、発行されたばかりのカミュ作『異邦人』に惹かれた。そこには「不条理」の哲学なるものが書き表されているというのだ。理性で割り切れない世界と人生、それを明晰に理解しようとする人間の欲望、その対立が不条理というものらしいが、底の浅い私にはよくわからず、ただ「不条理」の字面・語感に酔っただけのことだろう。心がもやもやしていると靴を爪先で放り、靴先の向いた方に歩く方向を変えながら市街を回り、いっぱしの哲学者気取りで心を晴らした。
夏休みになると近所の薬屋でアルバイト。休みの午後は、国道のコンクリートで朴歯の高下駄を鳴らしながら、その薬屋の前を通ってマドンナ宅を訪れた。薬屋の人たちは、マドンナ宅へ行き来する私の姿を見て、「それ、また石中先生のお出ましだぜ」と笑い合ったという。当時小説新潮に連載されたり単行本になった石坂洋次郎の『石中先生行状記』が評判だった。作者の分身と思われる、やや好色傾向のある石中先生が疎開先の郷里津軽で体験したり見聞したことを読み切り風に綴ったものだ。
しかし、私はぼやぼやと日を送っていたわけではない。祖母といっしょに2アールほどの畑と五アールほどの水田を耕していたのだ。夏休みには田の草取り、里芋の水かけに精を出した。
9月に入ると、アメリカ主導で対日講和条約、日米安全保障条約が調印された。全面講和か単独講和か、再軍備に賛成か反対かのもめごとは不消化のまま、否応なく時代がすすんだ感じで、曖昧な日本の出発に思えた。
10月、大学では後期になると、教養部に加えて、文学部でも専攻科を登録して講義を受けることになっている。文学部は名古屋城に近く、旧第3師団歩兵第6連隊の旧兵舎を利用していた。
英文学科の講義に出ると、教養部で、近づく気になれないような常識的に思える人ばかり。語学単位取得の関係で、今さら仏文学科には変われない。私は教務へ急いだ。
「誰も行かない専攻科は、哲学科の美学・美術史ですね」
美学・美術史なんて、それまでに思いも寄らなかった専攻科だったが、幼児から女体に憧れてきた私には新鮮に響いた。そんなものがあったのか!
美学の研究室へ出向くと、持ち込んだベッドで寝込んでいる男がいる。彼が専任講師だった。
「なんですか」と寝ぼけ声。「美学に入れてほしいのですが」「ああ、いいですよ」「あまり外国語出来ないんですが」「ああ、いいですよ。日本語がわかれば、ホッホッホ」
私は美学専攻を即決した。
また自由を求めて、現実的な選択肢を減らすことになった。
(’04年10月記)
⇒ 目次にもどる
| 第25回「“逆コースの憂さはパイプの煙で”の時代」 |
1951年、大学2回生の秋は、サンフランシスコで調印された対日講和条約・日米安全保障条約の批准に向け、国会承認の賛成・反対で社会が揺れ動いた。
日本社会党は衆議院での承認を前に、講和賛成・安保反対の右派と両条約反対の左派に分裂する騒ぎもあったが、参議院でも両条約は承認され、翌年の発効を待つばかりとなった。
講和への過程で、私は中国に対する戦争責任・賠償責任が棚上げされているように思えて不満だった。小学校時代の一時期にせよ、忠勇無双の日本軍が犯した婦女暴行・略奪の話を南京攻略戦で負傷した軍人から聞いて、そんな忠義があったら、自分も早く立派な軍人になって忠義がしてみたいと思った、中国人に対する加害意識を明確に記憶しているからだ。かといって、講和条約・安保条約反対の学生運動に参加する気にはなれなかった。その原因の一つが、学生自治会と日中友好協会が催した中共映画『白毛女』の上映会にあった。
『白毛女』は、地主に犯されて山中に逃げ込み苦しさのあまり白髪と化した貧農の娘が、八路軍に救出され、兵士となって地主打倒の先頭に立ち、やがて黒髪を取り戻すという、抗日戦争中に華北の農村で広く伝承されていた物語を歌舞劇化し、それを映画化したものだ。
いかにも憎々しげな日本軍が八路軍に追われて退却する画面に、大勢の学生たちが盛大な拍手を送ったことに、私は疑問を抱いたのだ。こんな仲間には入れない。
「あの悪い日本軍は、よその人ではなく、自分たちの父や兄でもある。筋書きの上で、悪がやっつけられるのを痛快と感じるのは仕方がないにしても、拍手まですることはないだろう。あの日本軍は、みんな自分にも関係しているんだぞ」
ところで、その頃の私はタバコの吸い殻を撒き散らしていた。思えば恥ずかしいことだ。
朝、起き抜けに吸う。朝食後に吸う。駅に着くまでに吸う。列車待ちに吸う。列車内で吸う。駅降りて市電の停留所までに吸う。市電待ちに吸う。電車内で吸う。市電を降りて学校までに吸う。教室で講義待ちに吸う。清洲の自宅から名古屋の大学で講義が始まるまでの1時間半に消費するタバコは約10本。1日の喫煙量は推して知るべし。環境を汚すことはさておいて、経済的に何とかしなければと思っているときに助っ人が現れた。近所に住む20歳近く年長の“ユーコーさん”と呼ばれている人だ。
ユーコーさんは近所の寺の息子で、東京にある仏教系の大学卒と言われ、理科系の才能や音感にもすぐれていた。時々父を手伝う僧衣姿を見せることもあったが、自分の部屋に組み立てた精度の高い大型の電蓄(電気蓄音機=レコードプレイヤー)から、寺の裏に広がる田畑地帯に大音量で西欧の名曲を鳴り響かせては、洋楽に無関心な農家の人たちの顰蹙を買っていた。戦争たけなわの頃は東京帝大卒と称し、名古屋帝大の施設を利用して軍関係の研究をしているとかで見知らぬ学生が大勢出入りするので、何をしているのかわからないと怪しまれたりした。
また、私の家と同時に焼夷弾爆撃を受けたとき、消火は不可能なので記録しておけば何かの役に立つと、燃える本堂を何枚も写真撮影。そのことが、たとえ消火不可能でも最後まで水をかけるのが住職になる人の勤めではないかと、檀家の怒りを買った。将来住職を継げなくなった彼は、父住職に免じて借りられた参道脇の寺地に小屋のような住宅を建て、戦後は名古屋の中心街・栄町の広小路に面した雑居ビルの2階に“高周波研究所”なるものを開いて通勤していた。その行き帰りの列車で出合っているうちに私は親しくなり、パイプを貰い、吸い方を伝授されたのだ。
当時はピース10本入り50円、10本入りの憩やハッピーなどは20円か30円。国産のパイプタバコには、50グラム入りの桃山と日光があり、それぞれ100円、50円だったと記憶している。買うのは日光に限った。最初の1服はうまいが、さすがに安タバコ、吸い続けているうちに吐き気を催す。口内を荒らしたり、喉を痛めたり。詰めたタバコが残らず灰になるまで吸えるようになるまでには時間がかかった。しかし、50グラム50円で1週間から10日は保つ。私の経済的負担と環境汚染度は格段に減った。
今に続くパイプタバコは、かくして始まった。
祖母は、ユーコーさんの母親から「近所で息子と分け隔て無く付き合ってもらえるのは、お前ぇ様とこの光っつあまだけだ」とお礼を言われたそうだ。父親の住職は温厚な人だが、母親は手癖が悪いとか、兄は「こそ泥やって、また刑務所に入ってとるげな」と、近所の噂は絶えなかった。
確かにユーコーさんは、油断のならない人ではあった。英会話の出来る彼は、戦後いち早くコネをつけた米軍の誰かを通して、当時珍しかったスリースピード・レコードプレイヤーの部品をアメリカから取り寄せ、組み立てては10万円から20万円で注文主に売っていた(因みに当時の総理大臣の給料は、記録によると8万円)。しかし注文主がときどき「品物は何時渡してくれるんだ」と抗議に来ることから、詐欺まがいのこともしている気配を感じた。安月給であえいでいた叔父は、乗り合わせた列車の中でユーコーさんから「金は天下の回りもの」と、内ポケットに入れた分厚い札束をひそかに見せられ、「何やって暮らしてるんだろう」と驚いていた。
高周波研究所は、繁華街に便利な場所だったので、やがて私の大学仲間の溜まり場になった。劇の演出と小説家を志望している仏文の利ちゃん、日曜学校の先生をしている心理学の似非牧師、賭けマージャンで学費を稼いでいると噂のある社会学のパクサンなど、私の入れ知恵で所長に油断しないよう、楽しく研究所を利用した。とにかくユーコーさんは親切にしてくれ、青春を楽しませてくれた懐かしい人の1人になった。
ユーコーさんは今年の1月、89歳で亡くなった。
私が清洲へ帰り、何十年ぶりかで彼の自宅を訪れたときは83歳。奥さんは6人目か7人目だった。彼のもの静かさ優しさは徹底的で、荒々しい声は聞いたことがなかった。デパートの販売員、カメラ屋の店員、研究所の事務員など女性友達が次々に出来、妻の地位を求める人は、喧嘩したり話し合ったりして入れ替わっていった。
ユーコーさんは、400ギガのハードデスク装置を組立中だった。諏訪の工場から頼まれたもので、完成したらマイカーで運ぶために、運転免許状を更新したばかりとのこと。
「この免許証で、86まで仕事ができるよ」
驚いていると、彼は淡々と語った。
「おい辻よ。おれが坊主にならなかったのは、親爺やその周りの人たちを見ていて、坊主が詐欺師に思えたからだ。おれは坊主にはならなかったが、一度たりとも仏教を捨てたことははなかったぞ。これを見てくれ」
彼は技術関係の本の間から、大型の分厚い仏教辞典を取り出した。真新しいものだが、開いてみるとアンダーラインが盛んに引いてあった。この間ユーコーさんは、部屋いっぱいに仕組んだ音響装置から、素晴らしい音色で器楽曲を聞かせてくれた。
そして1952年が、再軍備を匂わせる逆コースの足音をあるいは高く、あるいは低く響かせ、日本防衛の義務を負わない形で米軍の駐留を押しつける日米安保条約を引きずりながら、曖昧な独立に向けて明けていった。
私のパイプタバコを吸う量は、お尻の穴から煙が出るほどに増え、50グラムが3、4日も保たない状況になっていった。
(2004年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第26回「“日本は独立できた??”の時代」 |
1952年(昭和27年)1月。清洲の町役場から、町の総鎮守で成人式を行うから出るようにとの通知を受けたとき、すでに長いこと成人として生きているつもりの私は、月遅れの雑誌を受け取ったような、間の抜けた感じがした。
生まれて3月目に父が死んで母1人子1人の私は、小学1年になった時、母から戸籍謄本を見せられ、「お前は戸主だから、偉いんだから、私をちゃんと引っ張っていかないかんぜ」と言い聞かされている。
小学2年の終わりには、父の形見の小漢和辞典を与えられ、「私は小学校しか出ていないから、何にも教えたることはできせん。字引の引き方を教えるから、後は自分1人でやっていくんだぜ。私は何にも言わんと後から付いていくだけだから」と諭されている。
それ以来戸主を自覚した成人として、跡取りの叔父がシベリヤ抑留から復員してくる高校2年まで母の実家を守ってきた。その間には隣組の常会に出席したり、中学2年には空襲による焼け跡の整理に取り組み、食糧難には畑仕事や魚捕りに励んで戦中戦後を乗り越えてきたのだ。
「何が今さら成人式だ」
「せっかく役場が通知してきたんだから、行かんと悪いがえ。行かんしょ、行かんしょ。」
中学2年になったとき「あんたとこの息子さんは成績も体も立派だから絶対受かる。町の名誉のために少年航空兵に応募してもらえませんか」と頼みに来て、母をひどく慌てさせた役場に対しては、まだ逆らう気持ちが残っている。祖母にせつかれて行ってみると、やっぱり、しょうもない役を振り当てていた。参加者を代表して祝詞を上げよとのこと。私は戦争体験から神仏を棄てている。戦争被害は、神仏に祈ろうと祈らまいと区別なく降りかかってきたのだ。祝詞を上げて成人になったことを有り難く神に報告し、さらに今後の加護を祈るなんて、逆コースもええとこじゃないか。
「おれは嫌だよ」
「お前が上げなんだら、誰が上げる」
参加者は、ほとんどが小学校の同窓生。私が生徒代表で卒業証書を受け取っていることを知っているので、引き受けるのが当然だといった表情で見つめる。心境を語るのは面倒だ。神官の指示に従い、仕方なく神前で「かけまくもかしこみ、かしこみ申す。……」と、字の鎮守で毎日のように武運長久を祈った小学校時代を思い出しながら祝詞を読み上げる。それ以外に何があったか記憶にないが、信じてもいないのに付き合わされた屈辱感だけが、今も頭の隅に残っている。
大学2回生の後期から、教養部と掛け持ちで文学部の美学美術史学科研究室に出入りするようになっていたが、研究室はまだ講座制が確立しておらず、専任講師1人だけが配属されていた。その名は柏瀬清一郎。東大の大学院を出て間がなく、一見色白の童顔。「先生」というよりは「柏瀬さん」と呼ぶのにふさわしい兄貴の感じ。専攻は仏教美術だが、映画評論の上で卓抜な見解や問題を提起して名古屋のジャーナリズムから注目されていた。研究室は教授・助教授が揃っている他学科の若手講師や助手たちが息抜きに来るサロンの雰囲気。いろいろな話題が飛び交い、いつも活気がみなぎっていた。
「僕はまだ美学概論を教えるような柄ではない。美とは何ぞやの“美学”は19世紀で終わった。これからは、芸術が生み出す感動について考える“芸術学”の時代だ。美学概論なんてものは東大や京大の大先生がいくらも書いてるから、それにお任せするとして、ここでは映画、演劇、音楽などの実際を通して感動とは何ぞや、感動を創造する方法とは何ぞやを追求しようではないか」という口癖の柏瀬さん。ある日私は茶々を入れた。
「ストリップショーの追求はどうですか」
「ホッホッホ、いいですねえ」
と言うわけで家庭教師の合間を縫いながら、ストリップショーを見てヌード芸術に夢を馳せ、学生演劇協会に顔を出して端役ながら演劇の舞台に立ち、学生映画連盟に仲間入りして映画論をたたかわせ、同人誌を企てるグループで文学論に口角泡を飛ばしたが、次第に私の研究分野は映画へと絞られていった。祖母は驚いた。
「へえー、みんなの遊びが、お前ぇさんには勉強かよ」
おぼろげながら私の内部に、真の民主化を図る脱天皇制、地球上から戦争をなくす脱暴力、人類の自由と平等を図る脱差別などが考えるべきテーマとして浮かんでいく。
教養部を終えて4月、正式に美学美術史学科専攻生になったころ、研究室ではイタリアのネオレアリスモ映画『にがい米』が人気の話題だった。映画は毎年水田地帯へ出稼ぎに来る女性労働者たちの姿をドキュメンタリー・タッチで描いたもので、柏瀬さんはじめ、みんながヒロインのシルバーナ・マンガーノにメロメロだった。
「シルバーナ・マンガーノの魅力は素晴らしい。まだ日本の思春期映画には、マンガーノのもつ健全な官能美がない。男もそうだが、女が真の女になるためには、そのこと自体に強い責任がいるんだ。責任を世の中のせいにしたらダメなんだ。真の意味で、マンガーノなんかは最も女性的で、最も女っぽい魅力をそなえている。女はこうあってほしいものだよ」
と、のたまった柏瀬さん。私と同様、あまり自慢できる風貌でもないのに、どんな女性を射止めるつもりなんだろう。15年ほど後に私の現住居で宿泊した結婚後の柏瀬さん、北海道から九州まで、ほとんど日本中のストリップ劇場を渡り歩いたことを逐一報告。ストリップショーを卒業している私に、「辻君もストリップをもっと見なくちゃダメだねえ」とけしかけて、妻を唖然とさせた。
当時朝鮮戦争は米中両者の勢力が伯仲して緊張した休戦状態。明らかにアメリカにとって都合のいい兵站基地・日本の再軍備や右傾化、米軍基地の継続、沖縄の切り離しなどの条項が並ぶ対日講和・日米安保両条約の発効に向けて、火炎瓶を投げ、こん棒を振り回す激しい労働者や学生の反対闘争が頻発していた。
わが文学部でも、(新参の私にはよく事情がわからなかったが)アメリカ型の学園民主化を方向付けるため、GHQの片棒を担いで政府が押し込んでくる米人教師反対の闘争が続いていた。その雄の1人が柏瀬さん。墨で小さな丸を書いた筵旗を立てて気勢を上げた。「あの小さな丸はなんですか」と聞けば、「ホッホッホ、小さい丸は小丸、こまる、困るという意味です」とのこと。
その頃柏瀬さんは、足尾銅山鉱毒問題で政府に立ち向かった明治期の民権政治家・田中正造の弟子だった祖父と2人で住んでいた。話によると、祖父たちは筵旗を立て、官憲を避けてあちこちに逃げ回り、樽を叩いて拍子をとりながら八木節を唄って抵抗したそうだ。
4月28日、講和・安保両条約発効。日本はアメリカ従属色の濃い、不完全な独立を果たした。
資料によると、この日は、明仁皇太子がその年進学した学習院大学政治経済学部政治学科の開講初日だったそうだ。アメリカにお膳立てされたとは言え、象徴天皇制に対する保守政府のマスコミ対策が見え隠れするようだ。
5月1日、独立後最初のメーデーには皇居前広場でデモ隊と警官隊の間で乱闘発生。血のメーデーとなる。その後は共産党指導による革新デモと警官隊の闘争は益々激化。7月には名古屋でも火焔瓶闘争による大須事件発生。政府は「破壊活動防止法」を成立・施行したが今ひとつ。デモに出る前の学生たちが喜々として、警官隊との乱闘に備えてプラカードに5寸釘を打ちつけている情景を見て、忍耐強い活動でなくては真の民主化は不可能だと、私は考えた。
次の衆議院選挙で、共産党は全ての議席を失うことになる。
こうした騒々しい世の中で私の最大の喜びはマドンナと会うことだったが、2人の上に暗雲がたれ込め始めていることは知るよしもなかった。
(2005年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第27回「“おれも往生際の悪い日本人”の時代」 |
1952年、大学3回生になって間もない4月28日。アメリカに対して従属的関係を強いる日米安全保障条約・日米行政協定と抱き合わせて、戦争被害に対する賠償請求権を放棄した対日講和条約が発効。曲がりなりにも日本が独立できたことに、人々は喜んだり腹を立てたりしたが、私は、この日調印された中華民国との平和条約の行方を心配した。
当時の中国には、アメリカの支持する中華民国が台湾に、アメリカと敵対する共産主義の中華人民共和国が本土にあって、アメリカ主導の講和条約から外されていたので、日本はそれぞれに講和を求めることになっていた。日華平和条約で中華民国が賠償請求権を放棄したことは、日本人に対して中国人の温情を感じさせるよりは、戦争加害に対する責任逃れの言質を与え、負けたくせに負けたと言えない往生際の悪さを助長する面もあった。
「それ見やぇ。何にも悪意だけで戦争したわけでなぇから、賠償は取れんわなあ。喧嘩両成敗ということだわさ」
中華民国の賠償請求権放棄は、政府間は問題ないにしても、中国一般の人たちには納得できない、大きな付けを残したと思えた。
私は敗戦以来、日本が引き起こした戦争によって多大の被害を与えた世界の諸国、特に中国に対する賠償問題が気になっていた。幼少年時代の一時期、大人に混じって、当時支那と呼び、チャンコロと蔑んでいた中国との戦争に勇み立って加担した覚えがあるからだ。
「南京陥落ばんざーい!」 「武漢三鎮陥落ばんざーい!」
「日本は神がおつくりになり、神の子孫がお治めになる国だ。この尊い神州日本に刃向かうようなチャンコロなんか、やっつけてしまえばいいんだ!」
この回を書いている2005年4月現在、愛知県では“愛・地球博”が開催されているが、1937年の丁度この頃は、名古屋市の築港で、その名を“汎太平洋博覧会”と記憶している大きな博覧会が開催されていた。その戦争パノラマ館で、私は軍人への夢を大きくふくらませたのである。
海戦のパノラマ館は、軍艦の甲板を通して、ホリゾントを横切って行く敵艦隊を砲撃する状況を見せる仕組みになっている。片側にはホリゾントに筒先を向けた砲塔が造られ、マネキン水兵たちが砲撃操作に取り組んでいる。甲板では、二股に分かれる鏡筒を高く立てた砲隊鏡を置いて射弾観測。耳をつんざく発射音がとどろくと、敵艦隊の前で水柱が高く立ち上がる。
陸戦のパノラマ館では、ホリゾントに向けて片側に戦車が置かれ、それを囲んでマネキン兵士たちが銃剣を構えながら突撃している。もう片側には重機関銃が置かれ、マネキン兵士たちが援護射撃している。天井には、旋回する格好で2枚翼の陸軍機が吊ってある。館内には爆音、機関銃の発射音、突撃の喚声がうずまき、ホリゾントの方では着弾破裂の閃光が走る。
大砲や飛行機、戦車、機関銃など武器・兵器の類は本物ばかりだ。学齢前年の私にとってリアリティ満点。好戦気分を奮い立たせる。
「おれも大きくなったらよう、強い軍人になってチャンコロと戦争やりに行くぜ」
私は戦争パノラマ館に魅せられ、祖母にせがんで何度も足を運んだものだ。
たまたま最近目にした資料によると、この博覧会の正式名称は“名古屋汎太平洋平和博覧会”。名古屋市が人口百万人突破を記念し、万国博に匹敵する規模で開いたもので、期間は3月15日から5月31日。
ところが、この博覧会のほとぼりが冷めない7月7日、日本は支那事変を引き起こしたのである。名古屋第3師団も南京攻略戦に大挙参加。そして12月南京陥落。祝賀行事が大々的に行われた。名古屋市内では花電車が行き交い、旗行列や提灯行列で「ばんざい、ばんざい」とどよめく大群衆が、人いきれに満ちた渦を巻き上げる。忘れるに忘れられない情景だ。
“平和博覧会”の名に隠れて戦争が企まれいたのではないか? ある報道によると、イラクで戦死者の増加に手こずるアメリカは、兵士に代わる戦争ロボットの開発導入を考えているそうだが、ロボットの活躍が目立つ“愛・地球博”には何が企まれているのやら……。
話は元に戻って1952年8月9日、私は満21歳の誕生日を迎えた。毎年のように8月に入ると、戦争を始めておきながら自分らの被害ばかりに焦点を当て、敗戦を終戦と言いつくろう往生際の悪い日本人にカッカとなり、9月近くになって、「あっそうだ。また一つ年を取ってたんだ」と気づいて呆れるのだが、この年は違っていた。父は21歳と1ヶ月で死んでいる。「何にも言い残すことはない。後はお題目を唱えてくれ」と頼み、わずかな家族と題目を唱和しながら死んでいった父を偲んで感無量だった。
「おれも親父のように、往生際よく死ねるんだろうか」
昼は薬の配達、夜は家庭教師とアルバイトに明け暮れた夏休みが終わり、講義が始まって間もなくだった。列車内で洋裁学校に通っている憧れのマドンナが顔をこわばらせて言った。
「縁談が進んでいるの」
相手は、近所に住んでいる町の有力者とされている人の息子だった。彼女は2人姉妹。姉は結婚していて、いつか自分には養子を迎えることになると思っているところへ、強引に縁談を申し込まれたというのだ。その有力者は小学校の校長にまでなった人で、その上私の父母の恩師でもあり、私にも日頃からよくしてくれていた。母と共に叔父の家に居候している境遇では、今さら慌てても致し方ない。実業に就いて婚期に達していた有力者の息子の方が、おれより恋情が強かったのだろう。友情関係を冷静に続けるよりほかになかった。小学校2年から抱いていた初恋は悲哀に終わったのだ。家族が寝静まると農道や堤防の道を放浪して、目ざとい祖母を心配させた。
その後は次々とガールフレンドを漁って振ったり振られたり。ユーコーさんの高周波研究所でとぐろを巻く仲間から、“高周波の辻”と呼ばれた時期があった。
幸いこの頃は、「人間を1人殺せば絞首刑だが、無数に殺せば勲章がもらえる」と帝国主義戦争を皮肉ったセリフが印象的な『チャップリンの殺人狂時代』をはじめ、ビットリオ・デ・シーカ監督によるイタリア・ネオリアリズモの名作『自転車泥棒』、不朽のテーマ音楽に魅せられる『第三の男』、世紀の大作『風と共に去りぬ』等々と、素晴らしい外国映画の目白押し。映画館に入り浸って心を慰めた。さすがの猛者も、失恋には往生際が悪かったのである。
秋中頃、美学美術史研究室では奈良・京都に向けて2泊3日の研究旅行に出かけた。お寺や神社は便宜を図ってくれて楽しく見学できたが、宮内庁が管理する桂離宮、修学院離宮は権柄尽くで不愉快この上なし。つい反抗的になる。桂離宮では示し合わせて何気なく1ヶ所に集まり、監視人の目をかすめてさっと記念写真を撮る。修学院離宮では植え込みに隠れ、閉門後月夜の庭園をゆっくりと楽しんでから塀を抜け出す冒険者が出る始末。嫌なら行かなければいいのに、やはり美の探求者のこと、美には往生際が悪かった。
12月。デパートでお歳暮の新巻鮭を売るアルバイトをした。偉そうにする客に腹を立てていると、係長から「偉そうにする客こそ金払いのええ上客だ。客でなくて、金に頭を下げると思えば腹も立たない。これが商売というものだ」と叱られて、自分は商売に向かないと悟った。しかし金はほしい。往生際が悪いのだ。年末の仕事納めまで何とか務めた。慰労会で、飲めない酒を飲めないと断り切れずに酔っぱらい、終列車で1駅乗り越し。線路伝いに5キロほど、苦しい息を吐きながら帰らざるを得なかった。
(2005年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第28回「“なにごとも、負けたおかげ”の時代」 |
1953年、年明け早々、東映映画『ひめゆりの塔』が大ヒットした。沖縄の最前線へ勤労奉仕に駆り出された女学生たちの悲惨な状況を描いた作品だ。
さすが社会派監督・今井正、と世評は高かったが、私は素直について行けなかった。女学生たちの全滅していく健気な姿が、あまりにもいじらしく、美しく描かれすぎていた。
1945年4月、米軍沖縄本島に上陸。5月、名古屋大空襲のとばっちりを受けて、近郊の田舎町にあったわが家は全焼。戦争にうんざりしていた私は、これ幸いと勤労動員をさぼることにした。
「後は、焼け残った連中で戦争したらええのだ」
というわけで、沖縄戦真っ最中の頃は、当座の暮らしを確保するための焼け跡整理。動員先の鋳物工場のように煤にまみれることもなく、大空の下で気持ちよい汗を流していたのだ。
「ぼくなんか戦争さぼっとったから、後ろめたくて観るのが苦痛、かなわんかったですよ」
「あれはダメだ。映像美と詩情におぼれて、戦争を始めた国に対する怒りを感じさせない。センチメンタルな涙、涙の映画だよ。」
と、わが美学研究室の専任講師・柏瀬さんの評。彼も兵役を逃れるため、成功したかどうか記憶にないが、多量の醤油を飲み、下痢状態になって徴兵検査を受けた口だった。
みんなが戦争すれば一緒になって戦い、戦後になっても戦争の原因や近隣国民に与えた被害を追及することなく、「お互いにひどい目にあったなあ」と涙ながらに慰め合うのが、おおかたの日本人の真情だと改めて感じた。理由はどうあれ、戦争中の非国民は戦争が終わってからも非国民とされる雰囲気が、依然として今もなお続いている。
4月から4回生。当時の名古屋大学美学美術史研究室の教員には、まだ柏瀬さん1人しかいなかった。カバーできない分野は、外来講師の集中講義で補われた。その一つが、著名なチェロ奏者・井上頼豊さんによる『ロシヤ・ソビエト音楽論』だった。第2次世界大戦の捕虜としてシベリヤ抑留をチャンスにロシヤ・ソビエトの音楽を研究したというのだ。講義の内容は忘れてしまったが、余談のほうは今も覚えている。
余談の一つは、捕虜収容所長の夫人に関するものだ。捕虜たちが慰安に催す演芸会のために女の衣裳が必要になり、所長の仲介で夫人に借りに行くと、手を通したことのないような真新しい衣裳を出してきた。「汚すかも知れないから、着古したものを」と断ったら、「着古したものを人に貸すのは失礼に当たる」と言い、頑として引っ込めなかった。「こんな場合、日本人だったら着古したものしか貸さないのに」と、捕虜一同恐縮。夫人は捕虜に混じって演芸会を楽しんだそうだ。
もう一つは、ソビエト映画『夜明け』にまつわる話。『夜明け』は、ピアノ組曲「展覧会の絵」で有名なロシヤ帝政時代の作曲家ムソルグスキーが、国民楽派の音楽仲間や民衆の支持を得て、反動派の妨害を退け、自作歌劇の上演に漕ぎつけるという内容で、歌曲をふんだんに聴かせ、芸術と民衆のつながりの大切さを説く映画だ。井上さんは、ロシヤの人たちがこの映画を観終わると、それぞれがソプラノ、テノール、バスと歌い分け、大合唱して映画館を出てくるのに驚いたと言い、ロシヤ民族の優れた音楽性について熱っぽく語った。
「ロシアには、音痴がいませんか?」と、私。
「それは気がつかなかったね。いることはいるでしょうが、いるとしても、みんな一緒になって、毎晩歌を楽しんでいるとしか思えないない暮らしぶりだった。大らかなものだよ」
度重なる粛正と、勲章で胸を飾らなければ幅の利かないソビエトはゴメンだったが、井上さんの体験談として初めて知る大らかな民衆には共感した。
「ボルガの舟歌」「ステンカ・ラージンの歌」など、どっしりとした感じのロシア民謡は、私の体質に合っているのか以前から好きだったが、ますます好きになり、辺りかまわず歌ったり、ハーモニカや安物のバイオリンで、プープーギーギーと悦に入った。
「お前さん、上手に弾けるようになったなあ」と、祖母だけがほめてくれた。
夏休み、高校時代の女性数学教師バーグマン先生の宅を訪れると、エドワルト・フックスの著作『風俗の歴史』を「面白いわよ」と貸してくれた。頁をパラパラ繰っていくと、エロチックな挿絵がつぎつぎに現れて浮き浮きさせる。内容は確か、西欧の王侯貴族や教会、ブルジョアなどの上流社会から庶民に至る性風俗変遷の歴史だった。初めて知るフックスは、19世紀から20世紀にかけて生きたドイツの偉大な社会主義的文化史家だ。
訳者の安田徳太郎(1898-1983)は、産児制限運動や性科学の確立に努力した医者であり社会運動家。出版の当てもなく戦前から訳し始め、敗戦のおかげで、やっと陽の目を見た本だという。私が『古事記』を通して皇国思想から抜け出たのは、神々や古代天皇家の性風俗を知ることで権威や威光にたじろがない心が育ったからだと気づいた。以後「風俗」は、人間や社会を知るためのキーワードとなった。
早速ある日、親友のKちゃんを誘い、松坂屋の前に立って女性の風俗観察。その年頃のせいだったのか、2人が共通して高い魅力点を与えたのは、年上の人妻らしき女性たち。小説家志望のKちゃんは、勉強を兼ねた実践派。すでに年上の女性を体験していたらしいが、私は見聞派。母の実家に居候している分際をわきまえ、中学で論語を習う前から孔子70歳の境地「心の欲するところに従って、矩(のり)をこえず」に類する生き方が身についる。戦後になって公刊できたオランダの婦人科医ヴァン・デ・ヴェルデの『完全なる結婚~生理とその技巧』や、フランス帝政時代の回想録作家ブラントームの『ダーム・ギャラント(艶婦伝)』、大胆な性描写で衝撃的に紹介されたアメリカの作家ヘンリー・ミラーの『北回帰線』などで性知識を積み上げ、Kちゃんの実践的知識とバランスを取った。
秋、美学の研究旅行から帰ってくると、Kちゃんが「おれなあ、ミチルとできちゃったんだ」と気まずそうに打ち明けた。ミチル先生は、私の高校時代の体育教師。モダン・ダンスの流れを汲む体操舞踊も教えていた。彼女は、戦後の日本に前衛的傾向の舞踊理論を展開した東大卒の舞踊家・邦正美のことや、モダン・ダンスというジャンル誕生のきっかけを作ったアメリカの舞踊家イサドラ・ダンカンの業績など、新しい知識を教えてくれるので、バーグマン先生に次ぐ大切な女性だった。私が年上好みの実践派と知りながら紹介したのが悪かったのだ。
「できちゃったものは、仕方なぇわさ」と言ったものの、ちょっとばかり残念だった。
美学研究室に在籍して最も印象に残っているのは、柏瀬さんの講義によって“壬申の乱”を知ったことだった。壬申の乱は、天智天皇の死後、天智が後継者とみなした実子・大友皇子を頂点とする近江朝廷に対し、吉野にこもった天智の弟・大海人皇子が、7世紀中頃の壬申の年に起こした反乱である。要するに、戦前の国が皇国史観によって国民に隠していた、天皇家の権力争いだ。かつての国や大人たちが教えたインチキ歴史に嫌気がさし、戦後は日本史を無視してきたが、壬申の乱を知って再び日本史に強く興味を引かれた。
柏瀬さんの講義は、この壬申の乱から白鳳時代、天平時代へと続く仏教美術の展開を説くものだった。壬申の乱に勝利した大海人皇子は、天武天皇となり、国の基礎を造るために律令体制を整備・強化していく。こうした変動の時代に生きた工匠たちは、厳しい国家の管理下に置かれながらも、続々と新しい美を生み出した。それは、工匠たちが国からの圧力にめげず、革新気分に溢れて、創造に対しエネルギッシュに、誠実に立ち向かったからだという。
「おれもそんな気分で、卒論に立ち向かえるだろうか」
その頃のわが家は、いろいろな事情で陰鬱の色を濃くしていた。
(2005年5月記)
⇒ 目次にもどる
| 第29回「“待てば海路の日和(ひより)あり”の時代 」 |
「いざとなりゃ、何とかなるわい」
1953年の秋半ばを過ぎても、私は一向に卒業論文を書く気になれなかった。400字詰めの原稿用紙50枚以上にまとめて、冬休み明けの来年1月11日正午までに出せとなっていたが、原稿用紙に向かうのを1日延ばしにしていた。家にじっとしていられる状況になかったのだ。
その頃、戸主の叔父は、軍隊とシベリヤ抑留による人生のおくれを取り戻そうとしても、思うように行かないので焦っていた。結婚の翌年叔母が長女出産と同時に肺結核を発病し、3年越しの自宅療養。私たち母子を居候させていることも重荷になっていた。母は少しでも自分の弟に負担を掛けないよう、家事一切と幼い姪の面倒を見ながら、和裁で家計を補っていたが、疲れがたまると、家計費を増やしてくれと苦衷を訴え、弟との間でよくいさかいを起こした。母が言い負かされて泣きながら姿を消すと、叔父は私に言う。
「男のお前には、わしの気持ちがわかるだろ?」
私は「うん、まあ」と生返事でやり過ごすが、私が卒業するまでは辛抱してくれてもいいじゃないかと、心の中で抵抗する。
母は和裁とお茶・花を教えながら、年齢の離れた叔父の面倒を子どもの頃から見続け、祖母や家を守ってきた自負があり、私が一人前になるまでは実家にいるのは当然だと思っていた。私も叔父の留守中は、子どもながらに祖母と家を守り、戦災後はその復興に努め、叔父がいつ帰還して来てもいいように住まいを整えてきたのだが、私たち母子の将来予測は外れかけていた。
「お前がこの家を出るときは、私といっしょだぜ。私一人この家では生きていけないもん」
(そうだ。少しでも遠くへ離れよう)
母と叔父は8人きょうだいの中で、やっと残った2人だ。仲良くしてほしかった。遠くへ離れたら、懐かしさで仲良くなれるのではないかと私は考えた。2人のいさかいは、単なる姉弟の喧嘩と思うことにし、《待てば海路の日和あり》で生きる気構えを固めていった。
私は、祖母が家計の足しにと小規模に続ける畑仕事を手伝ったり、家庭教師をかけ持ったりし、出来るだけ家の厄介にならないようにしていたが、私たち母子が居候していなければと、いたたまれない気持ちで通学していた。叔父たちが寝る前には帰宅する気になれず、家に用事のない限り、毎日のように行きつけの喫茶店や名古屋駅前のパチンコ屋で時間をつぶした。
こんな私に付き合ってくれたのが、留年を決め込んだ仏文科のKちゃんだった。そのKちゃんも、私が紹介した我が親愛なる高校時代のミチル先生と「できちゃった」後は、そうも行かなくなった。毎日のようにデートを重ねる2人は、最初のうちは私に気兼ねし、仲間に入れて広小路をよくぶらついたが、急速に交情を深める気配を感じさせた。それにKちゃんは、自分の主導で始めた私たちの文芸雑誌『群舞』の創刊号に、つい最近まで交際を続けてきた女子大生とその母の奔放な過去を題材にした120枚の長編小説を発表したばかりだ。Kちゃんは次号に備えて、ミチル先生と交情を深めながら新しい小説を構想しているに違いない。私は彼の邪魔をしたくなかったし、また苦境にある私にとって、彼らの親密ぶりを見るのは気が重くなっていた。行きつけの喫茶店へ終業後の彼女が現れると、私は2人を置いて店を出ることにした。
12月が近づくと、美学の専任講師・柏瀬さんが学生たちに声をかける。
「年末のアルバイトはいつから始めるの」「12月1日からです」「うん、いいね。ホッホッホ」
学生が年末アルバイトに出払うと、柏瀬さんは講義の必要がなくなり、冬休みに入れるのだ。
私は昨年に引き続き、12月1日から松坂屋地下の食品売り場で、歳暮用の新巻鮭を売るアルバイトを始めた。昨年懇意になった2人の魅力的な女性店員もいてくれたし、新巻鮭の売り方にも慣れていて、楽しく働けた。
鮭を売る手順は、(1)客の選んだ鮭の目方を量り、値段を客に告げて承諾を得る。(2)鮭の顎や腹に詰まっている塩を指先で掻き出す。(3)吊り下げ用の荒縄を両鰓穴から口へ通し、輪にして結ぶ。(4)胴を菰で巻いたら、何ヶ所かでイ草の細引きを二重巻きにして縛る。(5)さらに、その上から熨斗紙を巻いて紅白の水引をかける。(6)客に渡して代金を受け取る。
鮭の値段は、「こりゃ立派」なのが5000円から6000円。よく出るのが3000円台から4000円台。それ以下になるとサイズがサバやアジに近くなり、最低は1500円だったように思う。
因みに、当時の小学校教員や巡査の初任給は、週刊朝日編『値段の風俗史』に6、7000円前後とあって、新巻鮭は高い買い物のはずだったが、どのサイズもよく売れた。歳暮の最盛期には、私一人で1日150匹から200匹近く売りさばいた。そうなると休む間もない。指先の皮膚は塩で溶けて赤むけになったり、あわてて口縄を通すはずみに鮭の歯で傷をつける。そこへ塩がしみ込むと1日中チクチク痛む。こんなことまでしていくら稼いだのか、いま全然覚えていない。
暮れも押し詰まった頃の真夜中だった。和裁に追われて夜なべをしていた母が、急に腹を抱え「疝(せん)が起こった」と七転八倒。いつもの発作だ。戦災後、母は疲れがたまると疝をよく起こした。私は反射的に飛び起き、自転車を走らせて医者を呼んでくる。
「まあ胃痙攣でしょう。モルヒネを打っておきましたから大丈夫」と、医者は毎度のように言って帰っていくが、母は「すぐ治るはずなのに、おかしいなあ」といぶかりながら、数日耐えてるうちに痛さを忘れてゆく。これが10年後の死につながるとは、知る由もなかった。
「アルバイトも終わった。さあ卒論だ」と意気込んだ1954年の正月早々、私は風邪を引いてしまった。祖母が懇意の薬屋から「最近出た薬で、風邪によく効くぜえも」と、コルゲンコーワなる新薬をもらってきた。早速飲んでみると、眠くてしようがない。風邪薬に睡眠剤が入っているとは当時知らなかった。「卒論を書かなくては」と気にしながら、ウトウトしているうちに数日が無為に過ぎた。
「提出日まで、後1週間もない!」
私は腹這いになって卒論を書き始めた。戦災後机を調えるゆとりがなく、中学・高校の試験も大学入試も、すべて勉強は腹這いでするのが習い性になってしまっていたのだ。卒論の題名は長い間忘れていて、最近偶然にわかったのだが、『映画芸術論の基礎問題』だった。いつも頭の中で反芻していることを片っ端からか書き連ねていて、清書する時間がないことに気づいた。
「卒論の清書を頼む。来てくれえ!」
どんな手段でKちゃんに応援を頼んだか記憶にないが、Kちゃんは飛んできてくれた。提出日前日のことだ。彼は原稿用紙を広げるのが精いっぱいの小さな経机に体をかがめ、まず書き溜まっていた原稿を清書。後は徹夜につき合い、私が1枚ずつ書き終えるのを待ちながら清書してくれた。規定ぎりぎり50枚の卒論が仕上がると、あわてて大学へ駆けつけた。
「5分過ぎとるがね……」
教務の係員はぶつぶつ言いながら受け取り、先に提出された卒論の上にポンと積み上げた。見ると、他の人の卒論は私のより分厚く、丁寧に表紙をつけたり、きれいなリボンで綴じるなど見栄えよくしてある。私のは、50枚の原稿用紙を黒の綴じ紐で無造作に綴じただけ。見劣りすること、この上なし。「へえ、卒論とはああして出すものなのか」と、気押された思いを覚えている。
私はKちゃんに礼を言おうと急いで帰宅したが、すでに去っていた。ミチル先生とデートの約束があったに違いない。「いい小説を書けよ」と、陰ながら声援を送った。
(就職よりも、先ず遠くへ離れることだ。卒業できなくては身動きも取れない)
以後の私は、卒業単位を取りこぼさないことを念頭に置いて、どこへ旅立つかわからないが、海路の日和を待つことにした。
(2005年8月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ