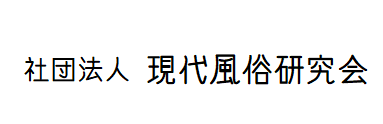| 第40回「“こんな映画をつくっていて良いのか”の時代」 |
「しっかり頼みますよ、先生。私は大和なでしこの血をひいているんで、パンツだかズロースだか、あの窮屈なのが大嫌いなんですからね」
これは、1949年(昭和24年)の夏大ヒットした青春映画『青い山脈』の中で、年増芸者を演ずる木暮実千代さんが、青年医師に自転車の後ろへ乗せてもらいながら、自転車が人を除けてぐらついたとき、青年医師の腰にしがみついてコケティッシュに発したセリフだ。
もちろん、作品の本筋である旧制女学校生と旧制高校生との清新な交際には大いに共感したが、それにも増して、木暮さんの開放的な色っぽい演技は、敗戦後の民主的な新時代を謳歌するマセガキの高校3年生に鮮烈な印象を刻み、以来木暮さんは憧れの的になった。
そして1956年(昭和31年)秋、木暮さんと一緒に仕事をするチャンスが訪れた。その仕事とは、正月映画として製作する長谷川一夫主演『銭形平次捕物控・まだら蛇』である。
話の筋は、幕府の高官が地位権力を利用し、地下の小判贋造工場に罪のない江戸市民を閉じこめて酷使する大悪人団を、御存じ平次が颯爽と登場して、推理の冴えも鮮やかに一網打尽にするという流れだ。
木暮さんの役は、悪巧みを知らずして悪商人に利用され、悪の一味を利する賭場の誘い役として色気を見せる女賭博師。客に変装して探りにきた平次に惚れこんでしまい、最後は一味総手入れのどさくさに紛れて不慮の死を遂げる命のはかない役だった。
私は初めて木暮さんと出会って、あれっと思った。いつの間にか憧れの気持ちは消滅していて、のっけから木暮さんを仕事仲間として接していたのである。憧れ対象ではなくなっていたが、木暮さんは明るく魅力的な女性であった。
しかし製作部や俳優部は、木暮さんの扱いに悩んでいた。土曜・日曜には、必ず東京の旦那の許に帰してあげなければならないというのだ。当時は公休出勤・残業・徹夜は当たり前のことだったので、他の俳優さんとの兼ね合いもあって、スケジュールの立て方に熟慮を強いられていたのだ。木暮さんは38歳の女盛り。スタッフの幾らかは、苦笑いしながら邪推した。
「木暮実千代は、よっぽどあれが好きなんやで」
ゴシップに興味のない私は、事情がわからず邪推に乗ることもあったが、ややこしい業界に対して自分の意志を通す、木暮さんの実行力に感心した。
ところで、この年の7月に経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言したように、前年から続く戦後復興を背景にして、鳩山一郎首相が率いる保守政権は、、革新勢力への攻勢を強めていた。教科書法案を国会提出して教科書検定の強化をねらったり、警官500人を国会に導入して、教育委員を公選から任命制にする新法案を強行可決したり、改憲のための憲法調査会法を公布するなど、保守政権による戦後民主化に対する逆コースの政策は、いっそう鮮明になりつつあった。
このように日本の民主主義社会が危機に陥らんとする一方で、私を取り巻く仕事は、昔ながらの義理と人情を讃えたり、チャンバラで解決する勧善懲悪のプログラムピクチャーばかり。
「こんな映画をつくっていて良いのか」
敗戦を古い日本からの解放と受け止めている私は、新しい哲学と思想を盛り込んだ芸術を創造しようと意欲を燃やして入社したものの、大勢の大先輩・先輩で先がつかえる社内状況ではどうしようもない。ただただ仕事を覚えることだと割り切って走り回った。
『まだら蛇』の次に就いたのは、助監督部の大先輩Wさんの監督デビュー作品だった。
主演は勝新太郎。流しギターの青年が妹の結婚資金を稼ぐため、知らずに密輸団に巻きこまれる恋と肉親愛の活劇編である。
W監督は大映と縁の深い巨匠監督伊藤大輔の愛弟子と言われ、助監督同士で仕事をしていた私は、力強く温厚で頼りがいのある先輩助監督として敬愛していた。しかし監督として就いてみると、評価が違ってきた。言葉がなめらかに出ないのか、演出・演技指導がぎこちなく、現場は上手く進行しなかった。
別々に録音した音楽やセリフなどを1本のサウンドフィルム(またはテープ)にまとめる最終作業の前に、編集したポジフィルム全編をつないで、映画の出来具合をチェックする作業を総ラッシュ試写と言ったが、その総ラッシュ試写を見終わった製作部長は、勝ちゃん扮する主人公が悪者たちに追われ、拳銃をパンパンと撃ちまくって防戦するラスト・シーンに批判の声を上げた。
「勝ちゃんが撃つ拳銃は、いったい何連発やね」
当時撮影に必要な場合は、パトカーも拳銃も太秦警察署から借りることができた。借用を申し込むと、2人の私服刑事が拳銃を持参し、空砲を撃たしてくれるのだ。しかし危険だった。空砲といえども、撃てば10メートル先のボール紙に穴を開ける。いずれにしても当時の警察が所持していたのは、アメリカ製スミス・アンド・ウェッソン式6連発のリボルバーだ。
問題のシーンは、人通りの途絶えた深夜の市街地という台本の設定に従い、深夜の市街地でロケ撮影された。深夜と言えども、ロケすれば見物人は集まる。W監督は、画面の邪魔にならないように見物人の整理に追い回される状況での撮影で、拳銃が6連発であることに気が回らなかったのだろう。急いでロケ現場の一部をステージにつくり、弾を詰め替えるカットを撮り足した。
Wさんは巨匠のバックアップがあったのか、その後何本かの映画を監督できたが、数年後には助監督に戻り、やがて事務系の仕事に配置転換となった。
私はWさんのケースから、いくら地位や境遇に恵まれていても、監督としての実力を蓄えていなければ簡単に消え去る監督の運命を知らされた。
明けて1957年(昭和32年)の春。加戸敏監督・長谷川一夫主演の『刃傷未遂』に就いた。映画の内容は、吉良上野介が浅野内匠頭に刃傷された1年前、同じ松の廊下で正義硬骨の大名のために投げ飛ばされ、怒った吉良が刃傷に及ぼうという話だ。この仕事では、時代風俗考証に苦労した。
脚本は巨匠伊藤大輔。脚本には細々と考証に対する注文が書き込まれている。とくに江戸城松の廊下で刀を振るう吉良の扮装には、衣裳責任者との間に立って困らされた。私も江戸城に関する作品は初めてだ。巨匠の指摘では、浅野内匠頭と同様、この映画に出てくる大名は5位の朝散太夫だから、大きな家紋を要所につけた「大紋」と称する衣服を着すが、吉良は4位の侍従だから「狩衣」と称する衣服を着すとある。しかし、従来の『忠臣蔵』映画を史実だと信じ込んでいる衣裳責任者は、吉良の衣服は大紋だと言って聞かない。当時は現在のように、歴史風俗に関する便利な参考書もなく、撮影所の書庫に入って、時代考証を重視する溝口健二監督の助監督が集めた資料から『柳営秘鑑』や『武鑑』、『故事類苑』などを探し出して調べると、巨匠の指摘通りだった。衣裳責任者は「笑われても知らんえ」と、不承不承に狩衣を用意してくれた。
作品は時代考証によって、格調高い娯楽時代劇に仕上がった。娯楽作品といえども、風俗を知ってつくるのと、知らないでつくるとのでは完成度に大きな違いのあることを痛感した。
以来映画における風俗考証の重要性を認識し、歴史と風俗の関係に興味を深めた。作品に就く度に江戸城大奥、江戸町方役人、吉原遊郭、侠客など風俗を調べ、その知識を積み上げることによって、曲がりなりにも、歴史の実態が頭の中で描けるようになった。
たいていの助監督は作品が完成し、仕事の疲れが治まると直ぐに撮影所の回りをうろついたが、私は次の仕事の呼び出しがかかるまで出社せず、手頃な値段の歴史や風俗の研究書を求めて古本屋を漁った。現代風俗研究会にいち早く入会した遠因でもある。
(2007年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第41回「“監督さんは、お幸せ”の時代」 |
「何が日米新時代だ!」
1957年(昭和32年)は、敗戦以来軍隊不要を信念とする私にとって嫌な年になった。
2月に首相となった元A級戦犯・岸信介は、向米一辺倒の姿勢を強め、アイゼンハワー米大統領と会談して“日米新時代”の到来を強調し、在日米軍地上部隊の撤退と引きかえに自衛隊の増強をたくらみ、戦争放棄・自衛力否定を規定する憲法9条の改変をねらう憲法調査会を強行発足させたのだ。
しかしペエペエの助監督ではどうにもならない。相も変わらぬプログラムピクチャーの製作に追い立てられた。
風俗考証で悩まされた『刃傷未遂』の後、『怪猫夜泣き沼』『女狐屋敷』につづいて、9月から、長谷川一夫主演の娯楽大作『雪の渡り鳥』についた。監督は長谷川一夫お気に入りの加戸敏さん。話の筋は、ヤクザの世界から足を洗い、船大工として地道に暮らしていた男が、悪行の限りをつくす網元一家に再び刀を抜き、雪の降りすさむ中で大殺陣を繰りひろげるというものだ。
ところで主題歌を歌うのは、浪曲師から歌手に転向し、『ちゃんちきオケサ』『船方さんよ』でデビューしたばかりの三波春夫ときまり、ある日の夕食後、主題歌を録音することになった。
「辻くん、長谷川さんのオーケーさえ取れればいいからね」
ちゃらんぽらんでお調子者の加戸監督は三波春夫との引き合わせが終わると、監督部の立ち会いを私一人に任せ、先輩助監督たちを引き連れて近くのマージャン荘へ行ったしまった。
主題歌の録音には、三波春夫が浪曲修業時代の相弟子であった大部屋俳優のNさんが、心配げに付き添った。Nさんの話によると、三波春夫は声が良すぎて渋さに欠け、浪曲師として人気がつかめなかったというのだ。
♪~合羽からげて三度笠 どこをねぐらの渡り鳥……
最初の録音が終わるとNさんは、俳優部の自室で待機している長谷川さんに聞かすためテープレコーダを運んで行った。Nさんはしばらくして、私や録音技師のいる録音ブースへ帰ってくると、顔をしかめた。
「先生は、こんな下品な歌に乗って、うち歩けへん言うてはるんですわ」
長谷川さんの感想をそのまま三波春夫に聞かすのは気が重い。私は録音ステージへ降りていって三波春夫に耳打ちした。
「長谷川さんは、もうちょっと変わった歌い方でと言ってられますので、もう一度お願いします」
三波春夫は不安そうに考え込んでいたが、心を決めて再度の録音を終えた。しかし長谷川さんの返事は不合格だった。どこがいけないんだろう?3度目を試みたが不合格だった。ブースで録音技師とテープを聞き返していて、ふと思い出した。高校時代の音楽時間に、教科書の小節をはぶいた楽譜で木曽節や小原節などの民謡を習っていて、腕白連中が大人たちの歌っているように小節をきかすと、女性教師が「そんな下卑た歌い方はやめなさい」と何度も注意したことを。録音技師も小節をきかす浪花節っぽいところがいけないのではと考え、小節をきかすのをひかえて歌ってもらうように注文を出し、4度目の録音を行った。
長谷川さんの返事を待つ間、軍服まがいの菜っぱ服めいたものを着た三波春夫は、はやく仕事をすませたい楽師たちの焦燥感ただようステージの隅で、しょぼんとたたずんでいた。その貧相な姿は、今なお記憶に残っている。
「長谷川さん、オーケーを出しました!」とNさんが飛び込んできたときは、ステージ中に安堵の雰囲気がみなぎり、終わり良ければすべて良しと、主題歌の録音はめでたく終了。三波春夫は国民歌手へと育っていく。
そして撮影たけなわの10月初旬、インドのネルー首相が撮影所見学に訪れることになった。当然見学のポイントは、大映の代表スター・長谷川一夫が演ずる撮影の状況だ。ステージ内には、高みから撮影現場が一望できるように、前日からお立ち台がつくられた。
加戸監督は、お調子者ぶりを発揮してはしゃぎ気味にテストを繰り返す。ネルー首相一行の到着に合わせて本番撮影の様子を見せらるように、スタッフは準備を整えて待ちかまえた。やがてガヤガヤ声がステージに入ってきて、一行がお立ち台に現れた。ネルー首相を中心に一行の動きが静まるのを見計らって、私が本番撮影の号令をかけようとしていると、監督の声がとどろいた。
「ライト!オーケー?……カメラ!オーケー?」
監督につられて照明部を撮影部も、それぞれ「オーケー」「オーケー」と返答。次いで「よーい、スタート!」と、監督の号令がかかるかと思っていると、変な号令がかかった。
「レディー!」
予期していない号令に、なんや?と瞬間とまどったが、「スタート」の声とカチンコが鳴ったので慌てて演技に入ったと、英語のreadyが“用意”を意味することのわからない俳優さんたちは笑ってこぼした。カメラを回さない模擬撮影だったので笑い話ですんだが、監督は得意だった。
「あれでネルーさんたちは、日本における撮影の仕組みがよくわかったやろう」
引き続いて加戸監督は、長谷川一夫をはじめ市川雷蔵、勝新太郎、黒川弥太郎など当時の大映京都撮影所のオールスターキャストによる正月作品『遊侠五人男』を年末に向けて撮ることになる。ついでに私も引っ張られた。
『遊侠五人男』は、子分の不始末を救うため、身代わりの罪人となって江戸送りにされる親分を取り戻そうと、五人の男が花の吉原で大立ち回りを演ずる義理と人情の娯楽巨編である。従って立ち回りのある場面が多かった。
チャンバラ映画全盛の当時、立ち回りに入るきっかけまで撮影を終えると、たいていの監督は殺陣師に指示を出す。
「あと○分立ち回り。頼むよ!」
殺陣師の登場と入れ違いに、監督は脇に離れ、椅子に座って手空きのスタッフや俳優たちと雑談しながら、立ち回りの流れにちらちらと注意を向け、終わるのを待つ。時には、立って行って注文をつけることもあるが、ほとんどは殺陣師に任せっぱなしだ。
そして、ある場面撮影の時のことだった。加戸監督は殺陣師に任せた後、炭火をおこした大鉄火鉢を囲んで、雑談にふけったまま立ち回りのすむのを待った。
「加戸さん、終わりました」
加戸監督は「もう終わったの」と、立ち上がって驚いた。立ち回りの流れが、終わるべきところで終わっていなかったのだ。
「これじゃ後の芝居につなげられないよ。○○ちゃん(チーフ助監督のニックネーム)、これ、どうしたらええの?」
チーフ助監督が出て行き、殺陣師と打ち合わせながら立ち回りの流れをアレンジして2,3カット撮り直しした結果、その場面全体を無事撮り終えることができた。
歳明けて1958年(昭和33年)には、年間映画館入場者数が史上最高の11億2745万人を数えることになる。“監督さんは、お幸せ”の時代は、まだまだ続く気配が濃厚だった。
(2007年10月記)
⇒ 目次にもどる
| 第42回「“仕事始めは、ラッパの響きで”の時代」 |
1958年(昭和33年)、毎年恒例の新年仕事始めの式場で聞かされたと思う。
「ところで先日、キシクンがねぇ、諸君。総理大臣の岸くんがだよ、ぼくに国鉄(現JRの前身)総裁をやれと言ったんだよ。ぼくは映画屋だからと言って断ったんだが、諸君はどう思うかね」
大風呂敷を声高に広げることから“永田ラッパ”と呼ばれていた永田雅一大映社長は、挨拶の中で私たち京都撮影所員全員にひときわ胸を張ったが、社員は冷笑するほかなかった。
「ラッパやラッパ。またぎょうさんに献金して、おだてられたんと違うか。アホくさ」
当時は、社長が盟友と自認する岸信介くんの反動内閣が、アメリカに追従して羽ばたいていた。東アジアの共産圏に対する砦となるべく軍備増強を図り、教員勤務評定を徹底させて思想の自由を束縛し、警察官職執行法改正案を提出して、警官の権限の大幅な拡大強化に努めるなど逆コースを強引に進めていたのである。
1958年に就いた最初の映画は、勝新太郎主演、三隅研次監督の『ふり袖纏』。勝ちゃん扮する江戸の町の消防組織・町火消“よ組”の小頭が、火消しの失敗で取りつぶしになりかけた組を救うため、女の恋にからんだ他組の邪魔を腕と度胸で打ちはらい、男の意地をかけて火事場に飛び込んでいく痛快鉄火編だ。纏の振り方と、木遣りの歌い方を指導に来た“よ組”の頭から聞いた話は印象的だった。
江戸の町火消は64組あり、各組はシンボルとして纏をもつことが許されていた。
纏(まとい)とは、竿棒の上部から“馬簾(ばれん)”と称する細長く切った皮を円形に何本も垂らし、その上端に“陀志(出し)”と呼ぶ飾り物を配したもので、竿棒を上げたり下げたり回して振ると、馬簾は陀志を中心に跳んだりはねたり拡がって派手に踊る。いざ火事が発生すると、組は纏を振りながら進む纏持ちを囲み、声をそろえて木遣りを歌いつつ、威勢よく火事場へと急ぐのである。
頭の話によると、その陀志飾りの一つに、江戸時代には十六菊の紋をデザインしたものがあった。明治時代になって、「十六菊は皇室の紋だから遠慮せよ」と政府から何度も要請されたが、その度に「おいらは、昔から権現様(徳川家康)を尊敬してきた江戸っ子だい。後からしゃしゃり出てきた天皇に、いまさら乗りかえられるわけがねぇよ」と抵抗・拒否したが、1889年の大日本帝国憲法公布に先立ち、強制的に変えさせられてしまったということだ。
頭の話は、太平洋戦争はじまって間もない小学5年の時に、現人神=天皇の存在に疑問を抱いて皇道精神から脱却し、戦後は天皇制に反対の私に痛快感をあたえ、今日まで記憶に残っている。
【今回の文を書くに当たり、江戸時代に十六菊の陀志飾りが本当にあったかどうか、改めていろ いろ調べてみましたが、私の力では確認できませんでした。まさか、あの実直そうな“よ組”の頭 が嘘をついたとは思えません。どなたか御存じの方があれば教えて下さい】
『ふり袖纏』を製作している頃、“尼門跡寺院で修業する若き尼僧たちの愛欲におぼれた姿を赤裸々に描いた”と宣伝する日活映画『春泥尼』が好奇心を集めていた。
私の母も小学校高等科卒業して父と結婚するまでの約7年間、日蓮宗唯一の尼門跡寺院・瑞竜寺、別称・村雲御所の尼僧をしていたので、私も無視するわけにいかない。つまらない映画だったが、母に感想を伝えると、母は嘆息交じりに、あっさり答えた。
「そうよ。尼僧だからと言って清いことあれせん」
母は実家の緊急事態を救うために還俗したと聞かされているのに、まさか別の事情が?
(母が尼僧になったり還俗する事情、村雲御所については連載30回、31回に既述)
『ふり袖纏』の完成後、私は母の還俗について聞きただすため、松ヶ崎の涌泉寺に住職さんを訪ねた。この寺の先代住職は村雲御所の学問僧を兼ね、母が明治以来の京都で最も格式の高い村雲御所へ入れるように骨折ってくれたのである。私の熱意にほだされた住職は、「私も父を介して知ったことだから」と断り、母には内緒にしといてと、こっそり教えてくれた。
当時全盛の村雲御所では、“一﨟(いちろう)”と称する最高位の尼僧が多くの尼僧を束ね、寺の経営には、男性の執事が当たっていたという。
そして母は、何気なく入った一﨟の部屋で、一﨟と執事が押入に隠れて抱き合っているところを目撃してしまったのだ。母は即座に人目を忍んで門外へ連れ出され、そのまま実家に帰されたという。母は突然御所から姿を消されたのだ。もし、こんな情事に遭遇しなければ、母は父と結婚することもなく一生尼僧で終わり、私はこの世に生まれなかった。私がこの世に生まれる遠因は、一﨟・執事の情事であったというわけだ。その後私は、個人史ではなく、人類史の流れに乗って生きているような解放感に包まれている。
また母の話によれば、当時第三高等学校の生徒であった執事の子息がいつも御所に出入りしていたとのこと。後に彼は東大教授となり、主著『日本官僚制の研究』などで有名な行政学・政治学の大家となる。
母は「○明さんがああした。○明さんがこうした」と彼のことをよく話したが、還俗の真相を知った後、○明さんにまぎらわしい名前を私につけたのは、○明さんに恋心を抱いていたからではないかと思うようになった。
『ふり袖纏』に次いで、任侠痛快編なる娯楽映画をすませた後、入社4年目、20本ほどのプログラムピクチャーに就いてきて、やっと芸術映画らしい仕事が回ってきた。市川崑監督、市川雷蔵主演の文芸大作『炎上』である。原作は三島由紀夫の『金閣寺』だが、映画化を拒む金閣寺の意向を入れ、映画では“驟(しゅう)閣寺”とされた。
この世で最も美しいものは驟閣寺だと亡父から教え込まれた青年が、驟閣寺に憧れて徒弟になったものの、戦後の観光ブームによって驟閣寺は俗気にまみれ、尊敬する住職も戒律を犯して女色におぼれる。不信と絶望感に追いつめられた彼は、ついには驟閣寺を焼失させ、放火犯として護送されていく途中の列車から投身自殺する、というのが映画のあらすじだ。
『炎上』は寺院内部の場面が多く、完成度を高めるには風俗考証が重要な作品だ。しかし先輩助監督たちは風俗考証に熱意も関心もないのか、サードの私に風俗考証の一切を押しつけた。世俗から閉ざされた寺院内部のことはよくわからないので、調べることはいっぱいある。時には夜もいとわず監修を依頼した禅宗の僧侶を訪ね、宗教行事の方式や暮らしぶりなどを調べ、また主人公の父の葬式場面があるので、戦前の田舎の葬式の様子を知ろうと調べ回った。
これまでに就いた監督は作品の内容やテーマの話をしたがらなかったが、市川監督に就いて、やっとテーマを語る監督に出会えた感じがした。脚本の中に、主人公が山門の楼上から寺の廊下に座って活花を見ている若い美しい女を見下ろし「あれは、生きてるんやろか」と見ほれる場面がある。その女役に、監督は新珠三千代を選んでいた。それについて私は疑問を呈した。
「活花を見ている新珠さんに見ほれるような平凡な感覚と、憧れている驟閣寺が俗気にまみれるの恐れ、絶望のあまり燃やしてしまうようなエキセントリックな美意識とは矛盾していませんか」
「この映画のテーマは主人公の美意識ではなくて、何でもない青年の生き方や悩みを追求することなんだよ」
徹夜に近い残業の休憩時に、よく芝生に寝転がって話し合った。
「辻ちゃん、監督はね、私小説が書けるぐらいでないと駄目なんだよ」
と諭されて共感したことは、いまも頭にこびりついている。
そしてある雨の日、『炎上』の撮影に入っているステージセットへ通ずる裏道を、蛇の目の相合い傘で、小さな男が着物姿の女の肩に手を回し、背伸びするようにしてぎこちなく歩いてくるのを目撃した。新婚旅行を兼ねて撮影を見に来た三島由紀夫だった。
(2007年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第43回「“監督昇進いつのことやら、年功序列”の時代」 |
前回は、市川崑監督作品『炎上』の撮影現場を、原作者三島由起夫が夫妻で訪れたところで終わっている。今回はその続きから書きはじめようと心積もりし、原稿提出日も迫ったので、いざワープロに向かおうとした2月14日の朝、市川監督の死去を新聞で知り、その偶然性に驚いた。私は、市川監督の冥福を祈りつつ、50年前の記憶をたどる。
1958年(昭和33年)のある朝。スタッフルームで『炎上』撮影の準備関係に手落ちがないようチェックしていると、市川監督が出勤してきた。
「辻ちゃん。昨夜は全然眠れなかったよ」
「どうしてです?」
「溝口さんの『雨月物語』が再上映されていたので観たんだよ。興奮しちゃった。すごいね」
何がすごいか聞き漏らしたが、さもありなんと推測した。市川監督は、「そのセリフは、フラットにね」「もっとフラットに動けない?」などと「フラット」という言葉を多用し、フラットな演出を持ち味としていたので、溝口監督の奥行きのある立体的で重厚な演出に圧倒されたのではないか。
市川監督は仕事が終わると、脚本を受け持つ妻の和田夏十さんに、丁寧な言葉使いで頻繁に電話をかけていた。その日の撮影状況を報告し、次の撮影場面に対して意見を求めている気配だった。そして1週間か10日ごとに和田さんがやってくると、夫妻だけで試写室にこもり、その間に溜まったラッシュフィルムをチェック。終わると必ずと言っていいほど撮り直しや変更が出たので、スタッフはよくそしり合った。
「崑さんは、まだ夏十さんから乳離れできていないのと違うか」
そのせいかどうか、赤ん坊が母親のおっぱいをくわえたまま離さないように、市川監督はいつもタバコをくわえていた。取材に訪れる芸能カメラマンは、何とかタバコをくわえていない顔を撮ろうとするが、さっと新しいタバコにくわえ変えるのでだめだと、苦笑していた。
市川監督は黒澤明、衣川貞之助、溝口健二などにより、国際映画祭で数々の受賞作品を生み出してきた大映京都撮影所での初仕事とあって、見た目は細身のズボンで明るく軽快だったが、きっと心の内は緊張感に包まれていたのかも知れない。
「演出は配役で80%は決まる」とは、市川監督の口癖で、配役は慎重に進められた。眼力か勘か、役に選ばれた俳優さんたちが見せた素晴らしい演技。名カメラマン・宮川一夫さんの映像美にこだわるカメラワークと相まって、『炎上』は完成度の高い作品に仕上がったが、私の風俗考証もその一端を担ったと自負している。
『炎上』はその年のキネマ旬報ベストテン第4位、NHK映画賞ではベストテン第2位とシナリオ賞、ブルーリボン賞では第3位、宮川さんは撮影賞などに選ばれ、市川監督は巨匠への足場を固めた。
入社以来初めて芸術的意欲を満足させてくれた『炎上』の後、三隅研次監督『水戸黄門漫遊記』につづいて、年末から三隅監督のチーフ助監督を務めてきたNさんの監督デビュー作品についた。
『炎上』製作の前後から年末にかけて、大正末から昭和初年の生まれの助監督3人が年功序列によって監督に昇進したが、その一人がN監督だった。
翌1959年早々、撮影が始まって驚いた。
N監督は、助監督として一緒に三隅組で仕事をしていたときは頼もしげな先輩だったが、「スタート」の号令をかけるやいなや、立って「カット」、座って「カット」、あっち向いて「カット」、こっち向いて「カット」と、撮影カットの短いこと。作品は、二本立て興業の本編に添える1時間前後の中編映画だが、撮影所内ではカットが短いことで有名な三隅監督の1時間半から2時間の本編に匹敵するカット数になる。
「何という演出や。芝居が細切れになってしまうやないか」
チーフもセカンドもN監督同様に、入社当初の私を誘い込もうとした三隅グループだったが、N監督の演出を陰でそしるばかりで示唆することもなく、仲が良さそうで心は水くさい関係なのかと、私は三隅グループに興ざめした。カット数が多ければ撮影時間はかかる。何とか封切りに間に合うよう完成したが、大して評価されず、後1,2本でNさんの監督生命は終わった。
次の仕事にかかるまでの間に、『若き日の信長』を制作する森一生監督から、尾張弁の指導を頼まれた。市川雷蔵演ずる信長をはじめ、尾張出身者の役を演ずる俳優さんに尾張弁のしゃべり方やアクセントを教え、とくに人を叱ったり、ののしる「痴者(しれもの=馬鹿者)」という言葉は清洲近辺では使わないので、「たわけ」とか「たわけ者」と変えさせた。ところが封切り後、雑誌『時代映画』の中で、有名な時代考証家・稲垣史生が、「たわけ」という言葉は信長の時代には使わなかったと批判した。「たわけ」とは「田分け」と書き、分家に田を分け与えること。あまり田分けしてしまうと本家が立ちいかなることが多々あるので、江戸時代中期から、「田分け」を馬鹿なこと、愚かなことの意味で使われはじめたというのである。
尾張言葉で「たわけ」は、馬鹿のほか性行為の意味も含んでいる。
小学5年から愛読している古事記の仲哀天皇の項に、「上通下通婚(おやこたわけ=近親相姦)、馬婚(うまたわけ)、鶏婚(とりたわけ)、犬婚(いぬたわけ)の罪の類を種々(くさぐさ)求ぎて、国の大祓(おおはらえ)して云々」と記されている。だから、尾張の「たわけ」は古くから使われている言葉だ知っていて使ったのに、稲垣史生から批判されて、そのままにしていては森監督に申し訳がない。そのことを森監督に話すと、即座に「わかった、わかった」と了解してもらえた。
そして十年後、三隅監督・司馬遼太郎原作『尻啖(くら)え孫一』の主演・中村錦之助さんから羽柴秀吉を演ずる弟の中村賀津雄さんに尾張弁を指導してくれと頼まれた。この時も「たわけ」を使うか、台本どおり「痴者」を使うかで迷い、前回稲垣史生から批判されたことを三隅監督に説明して、どちらを信用するか意見を求めると、即座に稲垣史生を信用すると言う。私は騒ぎ立てる腹の虫を抑えながら、台本どおり「痴者」を使うことにした。
腹の虫がおさまらない私は、横須賀市に住む艶本研究家・時代考証家の林美一さんに電話で問いただした。『信長公記』にも、信長を指して「たわけにてはなく候よ」と書いてあるがと言っても、林さんは「それは口でしゃべった証拠にならない」と、稲垣史生に軍配を上げる。
そして15年後、1976年に発足した現代風俗研究会で、中学の5年先輩だったという民俗学者の高取正男さんと偶然知り合い、長年の疑問をただすと即座に答えがもらえた。
「そりゃ、辻さんが正しいに決まっていますよ」
話は戻って、私は『若き日の信長』の尾張弁指導の後、加戸敏監督・長谷川一夫主演『王者の剣』についた。この映画は、江戸の初期にタイ国へ渡り、国王の信頼を受けて六昆国王に任ぜらた山田長政の、誠実にして勇敢波乱の生涯を描くというものだ。
お調子者の加戸監督は、初めての海外ロケに出る作品を任されたとあって有頂天。例のブロークン・イングリッシュを連発。主要スタッフのみで構成されたロケ隊は、製作部長が西陣警察署から借り出した押収物のエロテープを聞き、歓喜の呻き声を餞別にタイへ出発した。
タイから帰国した長谷川さんが、ロケ隊に参加できなかった私に並び小便していて囁いた。
「敏さん、タイでなあ。調子に乗って気が狂ったみたいやったえ。あの調子で、後の撮影ええかいなあ」
(2008年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第44回「“からだが映画屋化していく”時代」 |
1959年(昭和34年)春。長谷川一夫主演・加戸敏監督『山田長政・王者の剣』の撮影隊は、大挙して鳥取の砂丘へ3泊4日のロケに出かけた。長谷川一夫演ずる山田長政軍と反対派勢力との大合戦場面を撮影するためだ。
先行したタイのロケで調子に乗りすぎ、長谷川さんを「あの調子で、後の撮影ええかいなあ」と心配させた加戸監督。夕方鳥取市の宿所に到着し、風呂・食事をすませるやいなや、助監督の部屋へ「頼むよ」と顔をのぞかせた。翌日から行う撮影場面のコンテ(ショットごとの構想)作りや段取りの一切を助監督たちに任せ、マージャンの席へまっしぐら。私たち助監督はあぜんとしたが、チーフを囲んで、いかにロケを進行させ、どんなショットを撮影していくかと対策を考えた。
ロケは、鳥取大学の学生さんを中心に、3日連日1000人以上のエキストラを使い、騎馬兵用に馬20頭ほどを使うという初体験の大仕事だ。
まず、役割分担を確認し合った。
チーフは、全体の状況を把握しながらカメラ前で動く俳優さんの演技をつけたり、準備完了を見極めると、携帯スピカーでテスト、本番の号令をかけて撮影を進行させる。
サードの私は、遠景で動くエキストラの演技づけと、エキストラたちの扮装替えを受け持つ。
セカンドは、チーフとサードの間を取り持って、チーフの補佐と、後景で動く俳優の演技づけと、状況に応じてサードを応援する。
ロケの進行対策としては、一方の大軍が押し寄せるショット、両軍が激突するショット、合戦の部分的なショット、主役や脇役など役付の俳優さんなどの戦いを見せるショットなどを想定し、エキストラのスムーズな扮装替えを配慮して撮影の順序が決められた。
翌朝砂丘に着くと、私は大声を上げることから仕事を始めた。カメラアングルの区域外に設定した衣裳や小道具などの置き場へエキストラを集めるのだ。衣裳を着させ、兜をかぶらせ、刀剣・槍などの武器を持たせ、兵士の扮装が整ったところで、カメラアングル内に誘導・配置し、走り回って撮影場面の内容を説明し、演技をつけた。
最初の撮影は、1000人のエキストラ全部を長政軍に扮装させ、大軍が砂丘の稜線の向こうから画面いっぱいに現れ、カメラに迫ってくるロングショットの場面だった。
ロングショットが終わると、カメラは長政軍に接近。長谷川さん扮する長政が馬上で指揮する状況や、長政に従う役付の俳優さんたちの演技を見せるのに必要な近接ショットの撮影。
同じ扮装のままの撮影を終えると、次は両軍激突のロングショット撮影に変わる。急遽、長政軍の半分を敵方へ扮装替えしなければならない。手空きのスタッフが衣裳部さんを手助けするとはいうものの、エキストラはいわば烏合の衆、500人もの扮装替えを急がせることは大変な仕事だ。
私は、敵軍に扮装替えしたエキストラをカメラアングル内に引率し、というよりは追い立て、騎馬兵を先頭に両軍を遠く隔てて配置。両軍の間に立って演技説明を終えるやいなや、いきなり本番・スタートの号令。カメラの視野から逃げる間もなく、両方から騎馬兵を先頭に軍勢が攻撃してくる。地面に伏せているほかない。横目で見ると、真横を馬の脚が駆け抜けていく。敗戦間際、B29の大空襲で焼夷弾の雨を振りかぶって以来の衝撃。九死に一生を得た感じだったが、後で馬屋さんに聞いてみると、そんな場合、馬は上手く除けて走るものだと笑われ、爆弾と馬とは大違いであると知った。
ロケをスムーズに進めるためには、エキストラの扮装替えもスムーズにしなければならない。ロケの途中からは奴隷をこき使う現場監督のように、竹竿を振り上げたり、地面を叩いて(もちろん笑顔交じりだが)叱咤激励し、エキストラを現場へ追い立てた。
こうして3日間、「鳥取にしては珍しい天気続きです」と、宿の仲居さんたちも驚くほどのロケ日和にめぐまれて砂丘を走り回り、大声を張り上げて、私はくたくたになった。
そして3日目の陽が西に傾いた頃、お疲れカット(最終カット)の撮影にたどり着いた。1000人のエキストラ全員を敵方の兵士に扮装替えさせ、カメラから見て砂丘の稜線に隠れる位置に並べた。稜線に立って準備完了の合図を送ると、下から「よーい、スタート」の声。間をおいて、私は「それ行けー!」と合図。全員がいっせいに稜線を乗り越え、砂丘を駆け下りていった。
しばらくして「OK!」「お疲れさま!」の声。私はホッとして立ち上がり、稜線を越えようとしたとき股間に激痛が走った。痛くて一歩も足を出せなかった。しゃがみ込んで体の様子を探りながら下を見ると、俳優さんたちやエキストラが乗り込んだバスがどんどん走り去っていく。辺りはだんだん陰ってくる。置いてきぼりにされたらどうしょう。私は立ったり座ったりして、何とか歩けるようになったところで砂丘の斜面を滑り降り、スタッフが引き上げるバスに間に合った。
その夜、私は帰宅して高熱を発した。風邪薬を飲んで1週間ほど休んでいると、微熱になったので出勤した。撮影工程は最終段階にあり、セット終了後にはアフレコがスケジュールに入ってきた。サイレント撮影したロケ場面のラッシュを編集した画面に合わせて、人の声や物音を録音するのである。たまたま鳥取ロケで撮影した合戦場面のアフレコに立ち会った加戸監督は、賛嘆の声を発して私たちを呆れさせた。
「○○(チーフの名)ちゃん、あのロケはこういう画面になったの、いいねえ!」
完成後の休暇に入っても、私の微熱は下がらなかった。肺結核を心配し、近くの結核予防協会でレントゲン検査しても、情けないことに骨の老化が判明しただけで、診断は風邪が長引いているのでしょうとのこと。1ヶ月ほど経っても微熱はつづいたが、いつまでも休んでいるわけにいかず、次の作品に就くことにした。準備に入って撮影所へ通い出すと体に異変が生じはじめた。バスに乗って座ったり立ったりするときは膝や股間に、つり革に止まろうとすると肩に痛みを感ずるようになった。だんだん痛みが激しくなり、撮影所の入り口で押すタイムカードにも痛くて手が届かなくなった。そうこうしているうちに、ある朝、体全体が痛くてどうにもならなくなった。母が私の病状を報告して欠勤願いの電話をかけると、先輩たちが駆けつけてきてくれた。
当時は遠縁の家で、母と不自由な2階借りをしていたので、「ここで看病するのはお袋さんも大変や。こんな厄介な奴は病院へ放り込んでしまえ」と、直ちに先輩たちは、大映京撮撮影所の診療所長が関係している病院へ入院の手続きをとってしまった。
数日待機して入院した頃には、痛みはほとんど無くなっていたが、病名が急性関節リウマチと知って「慢性になったらどうしよう」との不安が襲った。医学の解説書を読んでも、リウマチは古代ギリシャの頃から知られているが、治療法となると曖昧で不安をかき立てる。同室の患者に聞いてみると、関節リウマチの患者は痛みが去れば、2、3週間で退院するとのことだ。私は3ヶ月の病気休暇いっぱい使い、体が完治を納得するまで入院していようと決心し、同室患者と楽しく交流しながら、雄山閣の風俗史講座、平凡社の中国古典文学全集などを読みふけった。
見舞いに来る先輩たちは、「助監督のほとんどは、入社後に胃潰瘍や十二指腸潰瘍にかかって体が映画屋向きになるんだから、避暑のつもりでゆっくり入っておれや」と言ってくれた。
そんなある日、ネグリジェを着たスタイルのよい若い女性が、逆光に体を透かせながら向かいの病室に入るのを目撃した。彼女はこの病院の元看護師で、数年前白血病にかかっていることがわかり、思い通りに生きて、どうにもならなくなったら帰ってこいと、病院から言われて姿をけしていたのだった。彼女には毎夜のように消灯後、カッカと靴音をさせて見舞いに来る大学生がいた。
そして1ヶ月たった頃、「輸血しても歯茎から吹き出してしまう」と急に廊下が騒がしくなり、彼女はその日の内に亡くなって、夕方にはベッドも運び出されて病室は空になってしまった。消灯後、例の彼が靴音を立ててやってき、ドアを開けて「アッ」と声を上げた。
その印象的な叫びを耳に残しながら、涼しくなった秋口。私は70キロ以上あった体重を60数キロにまで落とし、改めて身の軽さの快適なことを知って退院した。
(2008年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第45回「“撮影所は、お化けの住処?”の時代」 |
「辻くん、ちょっとスマートになったね」
「そうでなくちゃ、なんのために3ヶ月も、病院食だけの精進をやってきたかわかりませんよ」
急性関節リウマチの入院治療から、70数キロの体重を10キロ近くも減らして撮影所に復帰した1959年(昭和34年)の秋、前年から日米安全保障条約の改訂をすすめる岸信介政府と、それに反対する革新団体との対立は、ますます激しさを加えていた。11月27日には、安保に反対する労組や全学連のデモ隊2万人が、国会構内へ乱入する事態が発生した。
そんな社会状況の中で、監督・助監督が所属する監督室の幹事は、12月末まで仕事から外してゆっくり静養させてくれた。
松竹では、同年に入社した同年齢の大島渚が『愛と希望の街』で監督デビューしたのに、年功序列制度を堅持する我が大映京都撮影所では、2期前に入社した昭和初年生まれの世代から、やっと新監督が出始めたばかり。焦っても、慌ててもしかたがない年功序列のありがたさを、スローライフの私は乱読三昧で大いに満喫できたというわけだ。至文堂の日本歴史新書シリーズ、雄山閣の講座・日本風俗史、時には世界性学全集やディキンソン著『人体性解剖学図譜』などなど種々雑多。この延長で買ったり読んだりしてきた本は、大映倒産後に始めた記録映画演出の資料や、いま現代風俗研究会に30年も参加できている肥やしになっている。
ところで、この頃のことだったと思う。映写室担当の古参技師が、常人とはどこか目配りの違う、私には異様と感じられる数人の紳士と連れだって、撮影所内を案内していた。後で聞くと、紳士たちは検事とのこと。知り合いのヤクザの口利きで、検事たちの見学を頼まれたということだった。
「そんな人やったら、堂々と所長に見学を申し込んだらええのにね」
「わしもそう思うが、いろいろわけがあるんやろ」
50年も前のことだが、今なお忘れられない情景である。
そして翌1960年(昭和35年)、『風雲将棋谷』『銭形平次捕物控・美人蜘蛛』に続いて、田中徳三監督・長谷川一夫主演の『大江山酒天童子』についた。
売り文句は、「日本の代表的伝説“大江山の鬼退治”の物語に東西オールスターを配し、撮影所の全機能を動員し、空前のスケールで描く豪華絢爛の時代劇超特作」というもの。
主演者は、長谷川一夫を始め、雷蔵、勝、本郷功治郎、根上淳、林成年、山本冨士子、中村玉緒、左幸子と、なるほど東西オールスター総出演。
映画の筋は、平安の末期、栄華を誇る時の権力者・藤原道長が寵愛する渚の前の身辺に妖怪が出現するようになったので、渚の前を払い下げられた源氏の大将・源頼光は、信頼する坂田金時などの四天王とともに、大江山に隠れて妖怪を背後から操って藤原一門の転覆を謀る酒天童子の討伐に赴くというものである。
田中監督が、デビュー5本目でこんな大作を任されたのは、市川雷蔵演ずる腕っ節に強く情にもろいヤクザの旅鴉と、本郷功次朗演ずるドライで坊ちゃん育ちの将軍若君との奇想天外な股旅道中を痛快にまとめた前作の『濡れ髪三度笠』が当たり、その軽快なテンポと若さあふれる颯爽とした演出力が買われたからだということだった。
私は田中監督に期待して演出を見守った。なるほど田中監督は、自分より5年早くデビューした
4歳年長の三隅研次監督を、陰ながら呼び捨てにしてライバル意識を燃やしていただけあって、緻密で丁寧な三隅監督の粘り強い演出・演技指導とは対称的だった。
「そのセリフ、ちょっと間が詰まりませんか」「その動き、もっと間をつめて下さい」などとの注文が多く、テンポを出すことに気を配ることが演出の主眼で、演技指導はいたって淡泊。撮影も1,2回のテストと本番、「OK」とスピーディ。こういう撮影の進め方も、作品によっては功を奏するのかと思っていると、思いがけないトラブルに見舞われた。
雷蔵演ずる頼光が、夜の館で妖怪・土蜘蛛に襲われる場面撮影の時だった。
妖怪・土蜘蛛が投げかける糸に絡め取られようとする頼光が必死に防いで追い払うカットを終えると、スタッフは、渚の前が、遠くから「どうかなさいましたか!」と声を上げながら駆け込んでくるや、頼光と抱き合うショットの撮影準備に入った。
土蜘蛛が頼光に投げかけた蜘蛛の糸には、能・歌舞伎で使う“巣”または“なまり玉”と称するものを使った。鉛の細い針金に紙を巻きつけて作った沢山の小さな紙テープの端を紙に貼りつけ、その紙に包んで紙テープだけを一度に放り出すと、蜘蛛が獲物に向かって吹き出すように、無数の紙の糸が放物線を描いて相手に飛びかかっていくのだ。
照明準備が進みつつあるのに、土蜘蛛が頼光の座所に向かって投げた紙の糸は、広く板の間の上に残ったままだ。監督はどうするつもりだろう。指示を出さないまま、雷蔵や山本冨士子と談笑して笑い声を上げている。私は呼んできた。
「紙の糸は、このままにしておくつもりですか」
「土蜘蛛が出したものだから、このままでええやないか」
「糸は妖怪が出したものですから、妖怪が消えると同時に糸も消えるのと違いますか」
「そんなら、どうするんや」
「いま撮ったショットと、次に撮る頼光と渚の前が抱き合うショットとの間に、板の間に残る糸が同時オーバーラップ(カメラ操作による現場処理)で消えるショットを挿入すればええと思いますが」
監督はさっとふくれ面になり、「そんな馬鹿なことが……」と、ぶつぶつ言いながら立ち去った。
やがて撮影準備ができ、呼ばれて入ってきた雷蔵は目をむいた。
「徳さーん!こんな紙くずにまみれてラヴシーンするの!おかしくない?」
「そうですね、そうですね、おかしいですね、そうですね」
田中監督は慌てて雷蔵に寄っていく。
私に向けたふくれ面、雷蔵に見せた追従顔。私にとって、まさに妖怪変化だった
結局ラヴシーンは、私の提案どおり、土蜘蛛の糸が消えた後の設定で撮影された。
次いで私は、古くから早撮り監督として有名な渡辺邦男監督の『源太郎船』についた。密貿易につながる陰謀の摘発に身を挺する源太郎と、彼を慕うお浜を中心に、幕府高官が絡んで展開する恋と波乱の痛快時代劇だ。
数々の大作を手がけてきたという渡辺監督の多彩な動作と言葉巧みな演出振りを見ていると、どんな面白い作品ができるかとわくわくさせられるが、いざ試写室でラッシュを見るとそれほどでもない。なぜだろう?その落差が「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の句を彷彿とさせた。
この映画で、私は初めて予告編を撮ることになった。製作部長は私の初仕事が気になったらしく、3分ほどにまとめた完成前のラッシュを見たいというから、2人で試写室にこもった。リーダー部分が終わって最初の画面が写ったとたん、隣の部長は「ギャーッ!」と悲鳴を上げ、あっという間に外へ逃げだし、入り口から顔だけ出して怒鳴った。
「お前なあ、あんなカットがつないであるのやったら、見る前に言うとけ!」
予告編の最初に、本編ショットを流用して、空間の画面にアオダイショウがぶらんと垂れ下がるショットをつないでおいたのだ。
「部長が蛇恐怖症だとは、人から聞いてましたが、本物でなく、映し出された蛇まで怖がられるとは夢にも思いませんでした」
部長は鼻下に髭を生やし、性格は優しいのに、ちょっと見には泣く子も黙る風貌だった。それ以後、私は人の恐怖症について注意をはらうようになった。
(2008年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第46回「“追従は自立にまさる?”の時代」 |
「日米安保は危険だ。日本をアメリカの戦争に巻きこむものだ」
1959年(昭和34年)から、1960年前半にかけて、日本国内は元戦犯・岸信介首相が進める日米安全保障条約の阻止行動に揺れ動いた。
新安保は日米の軍事協力、経済協力などの義務化と強化が目論まれている。対米従属に不安を感ずる市民団体、革新勢力の大反対にもかかわらず、自民党は6月、警官隊を導入して新安保を単独で可決。1ヶ月後新安保発効と同時に、高姿勢で政治主義の岸首相は退陣を表明し、低姿勢で経済主義の池田勇人にバトンタッチした。
こうして岸首相が安保改正できたのは、敗戦・占領の屈辱を忘れて親米化し、従属してでも経済成長を良しとする人たちが増大していたからであろう。
私と言えば、安保改正賛成派にも反対派にも与することなく、将来自分が創るべき映画について考えを巡らしながら、日々の仕事をこなしていた。
当時は、“壬申の乱”に勝利して、天皇を神と仰ぐ古代天皇制を確立した大海人皇子を人間として追求し、天皇制の原点を探る作品を考えていた。
小学校入学時、私を戸主とした戸籍謄本を前に、母から「お前は戸主で私より偉い。そんなお前に、無学の私が教えてやれるものは何もない。今後はお前独りの考えで生きてお行き。私は後ろから黙ってついて行くことにするから、よろしく」と説かれ、以来私は自分の判断で生きてきた。
そして小学5年のとき、戦争を命ずる現人神=天皇の不合理な存在に疑問を抱き、その疑問を解こうとしてきた私には、安保よりも天皇制克服の方が重要に思えたのだ。
1960年7月、池田内閣が成立した頃、私は長谷川伸の戯曲『疵高倉』を原作にした『疵千両』に配属された。三島由起夫の『金閣寺』を映画化した市川崑監督の『炎上』以後、10本余のプログラムピクチャーを挟んで、2年ぶりの文芸作品だ。
芸術性のあるシナリオには満足したが、問題は監督の田中徳三さんだった。田中監督は『大江山酒天童子』の撮影中、妖怪・土蜘蛛が頼光に投げかける糸に使った紙テープを、妖怪が去れば、そのまま残さず、セットから消すべきだという私の意見に厳しく反対しておきながら、頼光役の雷蔵さんから私と同意見が出たらコロッと態度を変えて、私に深い不信感を与えていたからだ。
共についた先輩助監督のMさんも不満だった。
溝口健二監督の内弟子となり、時代風俗考証を重要視する溝口監督の映画作りを叩き込まれたMさんによると、田中監督は『雨月物語』『近松物語』など一連の溝口作品のチーフ助監督を務めたものの、完成度を高める時代風俗考証などには関心がうすく、溝口監督も全面的には信用していなかったそうだ。
「どんな映画になるか、やるだけやってみようや」
私はMさんに教えられながら考証を手助けし、予告編を担当した。
『疵千両』の時代背景は、大坂夏の陣で豊臣氏が亡んで30年ほど後の寛永20年。まだ戦国時代の武骨な風俗、武士気質が濃厚に残っている時代だ。雰囲気は娯楽映画で描かれる、いわゆる江戸時代とは全く違う。
Mさんは、溝口映画をつくるタッチで多くの資料にあたり、考証を進めながら画面に映し出される一切の衣裳や小道具、持ち物、調度品などを吟味選出した。
映画の内容は、無二の親友だった高倉長右エ門と東郷茂兵衛との間で激しい口論を、剛直な会津藩の武士気質から真剣勝負で決着をつけることから始まる、複雑な心理的葛藤と皮肉な運命を描くもので、しっかりした時代考証の上でしか成り立たないようなテーマである。
ややもすれば友情がはみ出る決闘で、高倉は顔面を真一文字に斬られながら茂兵衛を倒すと、茂兵衛の弟・又八郎に兄の仇討ちしなければならない運命が訪れる。茂兵衛に対する友情から、高倉は又八郎に討たれてやりたいけれど、わざと討たれるのには武士の意地が許さない。2人は対決し、互いに傷つき倒れたが、技量は高倉が勝っていた。止めを刺さず、後日を約して別れたが、又八郎は病にかかって仇討ちのかなわぬ身となる。
又八郎の妻・すがは、夫の身代わりにと思ったが、かつて召使いとして敬慕していた高倉には面と刃向かえない。
ある夜、すがは死を覚悟して仇討ちに行くと遺書を残し、黒装束に覆面して高倉宅に忍び入り、不意打ちに突きかかる。高倉はすがと知って驚く間もなく、すがは誤って自分の胸を刺し、命を絶った。
又八郎・すが夫婦には、又市という幼児がいた。すがの遺書を見つけた病身の又八郎は、死なば家族もろともにと、又市を連れて駆けつけたが高倉の前で息絶える。
高倉は泣き叫ぶ又市を不自由な身体で抱き上げ、故郷会津の子守唄を涙ながらに唄ってあやす。やがて又市は、時代を超越した、無邪気な笑顔を浮かべるのだった。
高倉を演ずるのは長谷川一夫。『近松物語』で溝口監督から「2枚目スター・長谷川一夫を忘れて、役に徹しなさい」とリアルな演技を鍛えられていて、文句のつけようがない重厚な演技を見せ、田中監督は「用意。スタート!」と号令をかけているだけで名作が仕上がっていく感じだった。
私には、田中監督が「おそいおそい」「もっと早く何とかならないのか」と、考証に努めるMさんのことを、イライラした口ぶりでグチりながら撮影を進めている情景ばかりが記憶に残っている。
『疵千両』は、田中監督初期の代表作となった。
『疵千両』に次いでの仕事は、森一生監督、市川雷蔵主演『忠直卿行状記』。森監督につくのは入社以来初めてなので緊張した。
森組常連によると、森監督は助監督が台本を見ながら仕事するのを嫌うとのこと。台本を頭の中に叩き込んでから現場に出よというわけだ。強制されるのは嫌だとばかり、私はいつも通りにしたが、私を外様と思っていたのか森さんは何も言わず、どことなく遠慮気味だった。
森組は仕事が終わると、監督を取り巻いて毎日のようにサントリーバーへ繰り込んだ。私は、仕事が終われば自分の時間がほしい。3度の誘いを1度は断って、ふと思った。
「大勢の人たちが慕う森監督を囲むようなグループに、素直にとけ込んでいけない私は、撮影所には不向きな人間なんだな?」
以後森組からは、お呼びがかからなかった。
この仕事で印象的だったのは、作曲家・伊福部昭の大自然に生きる民を彷彿とさせる、重厚長大な音楽に出会ったことだった。
この頃のことだった。東京本社出張への帰途、東京駅八重洲口の改札口に向かっていると、前方から異様な雰囲気を醸しなが3人の長身男性が近づいてくる。チラチラと見たり、横目で見がちな一般の通行人と違って、彼らはそれぞれ、見たいものに視線をじっくり注いで歩いているのだ。大岡昇平、有馬頼義、中村光夫だった。
この時から、サングラス越しに演出する映画監督には疑問を抱くようになった。
(2008年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第47回「“量産競争でキリキリ舞いと釈迦のおかげ”の時代」 |
「映画は古い。テレビは新しい」
「何を言うか。テレビなんて電気紙芝居じゃないか」
1953年(昭和28年)テレビ業界が本放送を始めて以来、お茶の間で見られるテレビに映画業界は対抗せざるを得なくなった。
翌年、東映が他社に先駆けて『真田十勇士』『笛吹童子』など、低予算の“じゃりすくい”とも陰口をたたかれた子ども向け映画を添える2本立て興業を始めて人気を呼ぶ。
「お子さん連れの買い物主婦も、エプロンがけのまま気軽に入れまっせ」
東映の成功を、東宝、松竹、大映、新東宝、日活は黙って見ているわけにいかない。1956年から各社2本立ての大量生産競争に突入した。
さらに1960年(昭和35年)、東映はもう一つの配給系統・第二東映を発足させて、低予算作品の量産にいっそうの拍車をかける。
わが大映も量産による品質を落とさないためにと、しばらく大作1本立て興業を実施したものの評判が悪く、二本立て興業に戻った。
噂によれば、東映のスタッフは次々に取りかかる台本を幾種類も尻ポケットに差し込んで仕事をしていて、1日に撮るカット数は大映の倍近い50~60カット。画面内の廊下や畳が砂埃やごみで多少汚れていても、「わからへん、わからへん」と撮影スピードをゆるめないそうだ。
わが大映京都撮影所の方は、そうはいかない。海外の映画祭でグランプリやアカデミー賞など数々の賞を取り、その賞品のレプリカをグランプリ広場で飾っているプライドが許さない。柱や廊下などは、箒で掃いてワックスを塗り、モッブや乾いた雑巾で行灯の明かりや陽の光が反射するほどピカピカに磨き上げるのだ。
たまたま同じロケ場所で出くわすと、わが大映は天気待ちをしたり、雲の条件待ちをしている間に、東映さんはさっさと撮り終えて引き上げていく。それを「もう終わった?」と見送るばかりだった。
かくして私たちは質を下げないため、月に100時間、150時間と時間外労働が伸びるのも厭わず、こまめに立ち働くことになった。
この年の秋、私は年末に封切る三隅研次監督、市川雷蔵主演の『大菩薩峠(龍神の巻)』に就いた。
この作品には、主人公机龍之介(雷蔵)を頼るお豊の役の中村玉緒さんが裸になり、滝壺に入って水垢離を取る場面がある。その玉緒さんの吹き替えに、ストリップ劇場のストリッパーを使うことになった。彼女がセットで直ぐ裸になれるよう、衣裳部で和服に着替えさせ、セットに案内する道々、セットでしてもらう演技を説明しながら尋ねてみた。
「いつも裸を見せる仕事をしていると、今日のような仕事も平気ですか?」
「いいえ。舞台以外で裸を見せるのは恥ずかしいことです。だから、恥ずかしさを感じさせない人の顔から目をはなさないようにして堪えます」
撮影準備が整い、彼女を滝壺に入れて演技をつけながら辺りを見回すと、カメラの後ろやライトの陰などから、チラチラと盛んに視線が刺してくる。
「なるほど、たまらんねえ」
私は演技をつけ終わってカメラ近くへ戻り、助監督の仕事をしながら彼女をふり返る度に、彼女は追うようにして私を注目している気配を感じた。
「女性に羞恥心を与えない顔とは、どんな顔だろう……?」
今なお私には判らない。
さて大映京撮では、量産再開に備えて、この年から翌1961年初頭にかけ、次々と年功序列による新人監督が生まれた。『幽霊小判』で井上昭監督。『薔薇大名』で池弘一夫監督。『旅はお色気』で黒田義之監督。『おてもやん』で土井茂監督。いずれも私より2期前の入社で1928、9年生まれの人たちだ。これら新人監督の進出によって、三隅研次監督と同世代のぱっとしない監督が何人か篩い落とされ、助監督に戻ったり、配置転換されることになる。
これで当分新人監督は出ないだろうが、滑稽にも大器晩成をひそかに志している私は、「おれは慌てないぞ」と心を括る。
1961年早々、故郷・清洲(現清須市内)の叔父(母の弟)から、「お前の田んぼが売れることになった」と知らせが届いた。ナショナルが新工場を建てるため、広く田畑を買収に来て、その区画の隅にくっ付いていた私の田も、引っくるめて売れることになったというのだ。
あたかもこの年は、対米従属を深める日米新安保条約を成立させた岸信介内閣の後を受けた池田勇人内閣が、これからは政治より経済重視だと、前年の暮れに決定した所得倍増計画に乗り出した年だった。
ナショナルに売れた田は、私が大映に就職できて京都定住を決めた際、不在地主になることを拒んで「農地は農民の手に」と、全田畑を売って売れ残ってしまったわずかな土地だった。
この土地代金で家を手に入れたいと、私は仕事の合間を縫い、母といっしょに売値を基に不動産屋を尋ねまわったが、適当なものはなく、お手上げの状態になった。
何本かのプログラムピクチャーをこなした私は、初夏のかかりから、ヴィスタビジョンカメラで70ミリフィルムに撮影する世紀の超大作・『釈迦』の特撮班に就いた。
突然、叔父から「売値の8割が支払われたので、取りに来るかや」
「仕事中だし、今すぐ使う当てもないので、そっちで何とかしといてちょう」
それから2、3日後の休日、京都へ移った当初から懇意にしている女性舞踊家の宅を久しぶりに訪れた。使う当てのない大金が入って困っていると打ち明けると、「この家を直ぐに買ってほしい」と懇願される。マネージャーとして同居している姉が、借金の連帯保証人になった相手が夜逃げして債権者に責められていた。本人も、主宰している舞踊団の発表会で出した赤字を埋めないと、将来がないというのだ。売値を聞くと150万円。それでは私に入った金額では無理だと140万円に値切った。また、担保物件の恐れがある危ない買い物だと意識して、最初に8割納めることで本登記する条件を強引に出し、残りは半年後に必ず払うと約束して手を打った。翌日、叔父が定期預金にしたばかりの金を引き出すため名古屋へ向かった。
私の定期預金を扱った行員は、高校教師を勤める叔父の教え子。無理矢理頼み込んで金を引き下ろすと、叔父に挨拶するためタクシーを清洲へ走らせた。その途中から凄い土砂降りの雨。「泊まっていけば」という叔父を断って、名古屋へ引き返し特急で京都に向かった。土砂降りは止まず、米原付近の川は今にも溢れそう。この後間もなく、東海道線は不通になった。
翌朝、舞踊家と弁護士事務所へ出向いた。弁護士は私たちの売買契約が10日前にあったことにして、8割の金額が手渡されたの見届けると、直ちに本登記の手続きをしてくれた。
私は女性をいじめたようで気が重かったが、後で聞けば、仮登記があったら差し押さえようとしていた債権者は、気がついてみれば所有者が変わっていて家屋敷の差し押さえができず、舞踊家は家財道具の差し押さだけで事が済んだとのこと。さらに、ある人から不動産屋がつけた家屋敷の値は110万円と聞かされ、私の気は休まった。
もし『釈迦』本編に就いていたら、私の気質として仕事を抜けることは出来なかったし、前々から「こんな家に暮らせれば」と思っていた家も手に入らなかっただろう。助監督の仕事が比較的少ない特撮班に就いていたからできたことだ。神仏を信じない私も、これだけは、なぜか釈迦のおかげと思っている。
(2008年10月記)
⇒ 目次にもどる
| 第48回「“ナメクジからデンデンムシへ”の時代」 |
「やっとナメクジから、殻を持つデンデンムシになれそうだ」
『釈迦』の特撮班を2日さぼって中古家屋の所有権を獲得した1961年(昭和36年)6月、新東宝が資金切れで製作を中止し、6社で成る日本映画界の一角が崩れた。
1958年には史上最高の年間映画観客数約11億3千万人を数え、日本映画界は全盛期を迎えたが、この年を境に早くも下降線を辿りはじめ、1961年に入ると急速に映画観客が減少し出したのである。
この退勢を挽回せんと、大作主義者の永田雅一社長が“世紀の超大作”と銘打ち、三隅研次監督を起用して製作に乗り出したのが、スーパー・テクニラマ方式による日本最初の70ミリ映画『釈迦』であった。
ところが、撮影に使うビスタビジョンカメラは重さ860キロ、本体だけで225キロ。従来使用している35ミリカメラの4、5倍の重さだ。この取り扱いの大変なカメラを、ハリウッドでは機械力によって駆使し、ローマ帝国時代を背景にキリスト教徒への迫害や奴隷の抵抗を描いたチャールトン・ヘストン主演の『ベン・ハー』や、カーク・ダグラス主演の『スパルタカス』などを製作・成功し、画面の大型化時代に突入していた。こうしたハリウッドに影響されて永田社長はビスタビジョンカメラを導入し、1932年伊藤大輔監督の『地獄花』を最初に計7本の作品を製作したが、興行的にも技術的にもパッとせず、1年後にはお蔵入り。そのカメラを引っ張り出し、永田社長は世界進出を夢見て『釈迦』をつくれと、大号令のラッパを吹き鳴らしたのである。
映画のテーマは釈迦の生涯であるが、その内容は、釈迦族の王子として誕生したシッダ太子(本郷功次郎)が出家して悟りを開き、仏陀となって死ぬ迄の間のほとんどを、太子に対抗する従兄のダイバ・ダッタ(勝新太郎)の暴虐ぶりを縦糸にし、仏陀の教えと奇跡によって解決する愛欲の葛藤と勧善懲悪のエピソードで埋めたオムニバス映画である。
日本人が演ずるインド人の映画。果たしてどんな作品になるだろうか。私はときどき本編のラッシュ試写を覗いて首をひねった。
「演技者たちは一応インド人の扮装をし、背景になる建物や風物はインド風だが、演技者たちの立ち居振る舞いが醸し出す画面の雰囲気は、まるで日本の時代劇そのものではないか?」
とは言うものの、画面はスタッフが苦労して撮り上げたものばかりだ。機械力の整ったハリウッドとは違い、従来のカメラより格段に重いビスタビジョンカメラを、撮影アングルが変わるたびに大勢が寄ってたかって持ち運んでいたのである。
それに出演者は本郷功次郎、市川雷蔵、勝新太郎、千田是也、京マチ子、東野栄治郎、中村鴈治郎、中村玉緒、山本富士子、月丘夢路、市川寿海、杉村春子、北林谷栄、山田五十鈴、滝沢修、根上淳、市田ひろみなど、まさに当時の東西オールスターキャスト。そのほか多数の出役。多彩な衣裳、小道具などなど。人扱いや準備、点検など本編の助監督は大変だった。
私が就いていた特撮班の仕事は、カピラ城で太子が誕生した奇瑞として、庭園の花が次々と咲き乱れたり、きれいな鳥が飛び立ったりする画面を構成することや、落雷した大木の枝が火を噴いて裂ける画面作成。大地震で出来た大地の裂け目に落ちたダイバを太子が白い糸を垂らしてすくい上げるシーンで、巨大な裂け目をミニチュアのダイバが引き上げられていく遠景ショットをつくることなのだ。花を咲かせるのは動画や作画の技師任せ。火を噴いて枝が裂ける画面づくりは美術担当や照明技師、撮影技師がやる。俳優無しの画面づくりに助監督の仕事は、ほとんど無い。私はもっぱら特撮監督のもとで技術スタッフの手伝いをしたり、使い走りをした。出来上がる画面はそれなりに珍しく面白く、また特撮班はほとんどが東京勢で、京都のスタッフとはひと味違う交流がもてて楽しい時間を過ごすことができた。
特に動画の鷺巣富雄さんとは気が合い、東京に出てきていっしょに仕事しないかと誘われたが、「天皇の膝元へ行くのはいやです」とお断りした。その後2004年に亡くなるまで交際を続けさせてもらった。
アニメ制作のエキスパートの鷺巣さんは、特撮監督円谷英二の弟子でもあり、特撮ものにも豊かなセンスの持ち主だった、やがて手塚治虫の漫画『マグマ大使』を原作にして、本格的TV特撮番組を開始し、大ヒットを飛ばす。
さて特撮班で楽しんでいる間に、本編のスケジュールは70ミリ映画の大型画面に描く大スペクタクルシーンの撮影に入るというので、特撮班全員が応援に向かった。場所は福知山の広大な元陸軍演習場跡。すでに本編スタッフが造った高さ30メートルほどの魔神像が辺りをにらみ、幾棟かの大神殿が建ち、さらに大神殿を建造中と思わせるセットが準備してあった。
ここで撮影するのは、ダイバ・ダッタが大勢の囚人や意に添わぬ仏教僧を酷使して、さらに大神殿を建造している途中に大地震が発生。魔神像や大神殿が崩壊し、ダイバが大地の裂け目に落ち込むというシーンだ。
参加するスタッフは数百人。俳優のほかに毎日1000人、2000人のエキストラが真夏の炎天下に動員された。囚人役の扮装は、ほとんど半裸だ。撮影部は建設労働の過酷さを強調しようと、汗を光らせるために囚人役のエキストラたちの背中や肩、額に油を塗らせる。油を塗ったところは陽に焼かれて水ぶくれとなる。どんなショットを撮影したか忘れたが、水ぶくれが破れて痛がる学生エキストラたちから恨まれたことは、強く印象に残っている。
かくして8月の末『釈迦』の撮影は終わり、後の仕上げはロンドンに移った。製作に、今の金額で70億円とも80億円とも言われる巨費を投じたとのこと。みんなが努力した『釈迦』がどんな作品に仕上がるか。私は半信半疑に期待した。
その頃まで私は気が向くとの、大映就職に力を注いでくれた永田社長の母堂を見舞いかたがた茶飲み話に病床を訪れ、「面白いことお言やすなあ」と喜んでもらっていた。母堂は日蓮宗の厚い信者。『釈迦』の仕事についてでも話しに行こうと思っていた矢先、とんでもない事件が発生した。社長が武州鉄道汚職事件で東京地検特捜部に逮捕されたのだ。母堂はショックで病状悪化。以来亡くなるまで面会できなかった。
社長のワンマン振りを批判する私の話に、オホホ、オホホと耳を傾ける母堂との茶飲み話は、私を可愛がって育ててくれた祖母と合わせて、今も懐かしく思い出している。
9月半ば、『釈迦』に次いで記憶も定かでないプログラムピクチャーに就いているときだった。
『釈迦』特撮班に就いていた6月に所有権を手に入れた家屋を、先住者は明け渡してくれなかった。売買が成立したとき、残金は半年後に必ず払うから、それまでに移転の都合がついたら明け渡すと約束したはずだった。尋ねてみると、全額払うまでは空けないと言う。当時私は、大きな元農家の2階を借りていたが、そのことを大家のSさんに話すと、「それなら私の金を使って下さい。辻さんのことだったら利子も借用書も要りません。ご自由に使っておくれやす」とのこと。
間もなく私は、わずかな家財道具を運送店の軽トラに積んで運んでもらい、母と共にSさんの家から引っ越した。新居は6畳2間に4畳半2間。家財道具を押入に収めてしまうと、引っ越し疲れが出た。柱と壁だけのがらんどうの空間で大の字に寝ころんだ。
「これで、やっとナメクジからデンデンムシに進化したんだ」
同じく横に並んで寝ころんでいた母は「ほんとだわねえ」と、感慨深げにつぶやいた。7年前、実家から夜逃げするように、慌ただしく京都へ移住した頃をふり返っているに違いないと、私は察した。
(2008年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第49回「“結婚は結婚、仕事は仕事”の時代」 |
1961年(昭和36年)の初夏、私が自宅を手に入れた話が知れると、まだ住んでもいないのに、方々から縁談が舞い込みはじめた。30歳近くになっても経済的に恵まれず、余儀なく母を連れて借り部屋住居を続けていて、大映京都撮影所・助監督部ではただ1人売れ残っていたからだ。
ある日加戸敏監督が、助監督室で私に耳打ちした。
「祇園の大きな料亭の娘さんはどうかね。きれいな人だけど、おっぱいが4つあるそうだが…」
「副乳があるというだけのことですから、おっぱいが4つはかまいませんが……」
副乳は、私にとって驚くようなことではなかった。大学で美学専攻中、研究室の蔵書であったドイツの医学者シュトラッツの『女体美体系』によって、副乳に関する知識をある程度もっていたのだ。副乳は、通常の乳房の上下にそれぞれ対になって見られる小さく退化した乳首のことで、日本人女性には割りと見られ、時には男性にも見られる現象だ。
「……料亭の娘さんでは、あまりに生活感覚が違いすぎるようで……」
加戸監督の話にためらっていると、母の知人から話が来た。
「○○市市長の娘さんと会ってみませんか。ご本人は名古屋の金城女子大を出た才媛。お家は三重県で有数の大地主だそうですが」
この縁談話を聞いて、京都の府庁勤めしている大家の娘さんが「あの市長さんは、被差別部落の出だと、府庁ではもっぱらの噂ですから」と母に忠告。
「そんなことはどうでもいいよ。それより三重県の噂が京都まで広まっていることが驚きや」
私は少年時代から差別問題に関心があった。「縁ができたらできたで、また新しい道が開けるんだよ」と、心配する母を説得しているうちに、先方から断りが来てしまった。
「なんや。おれの貧乏が差別されちゃったのかなあ」
これから8年後、やっと被差別部落の生活環境の改善や教育の充実などを図る「同和対策事業特別措置法」ができた。
また母の実家からは、跡を継いでいる叔父を通して遠縁から「400万円の株券と名古屋市内の土地200坪を持たせるから、娘をもらってくれんかね」と申し込み。さらに「中学校の校長の娘さんはどうですか」と、小学校時代の恩師から。返事を渋っていると叔父から小言が来た。
「お前の結婚は、そんなに難しいことかや。おれなどは1回の見合いでうまいこといっとるのに」
2、3回デートしたばかりの女友達に「結婚話はうんざりや」とぼやいていると、突然彼女は目を輝かした。彼女は、私が新居を購入する過程で出会った先住者の知人だ。
「好きなように一生暮らさせてあげますから結婚して」
某国立大学の助手をしていた彼女は、仁和寺近くに借りている材木屋の2階で、親に早く知らせたいから返事をくれと、私を膝詰め談判に追い込んだ。
彼女は、長野県の大正池周辺に広がる大山林地主の一人娘だった。そのためか、彼女に寄ってくる男性は彼女の財産目当てばかり。私はそれまでの男性と違い、自分を安心して任せられる人だというのだ。
彼女は新居の先住者から、私が購入価格の交渉で「女の人を叩くのは心苦しい」と、先住者が密かに調べた業界評価額よりも可なり高い金額で手を打ったことを聞いていた気配があった。
切迫する彼女の重圧に困り果て、私は「ちょっと考えさせてほしい」と、延長戦に持ち込んで急場をしのいだ。
<まだ、おれには結婚の機が熟していない>
結婚話から当分離れようと決めた私は、10月初めより、がらんどうの新居から心新たに京撮へ通勤することになった。
この年は、急速に映画観客が減少しはじめ、映画館の転業や兼業経営が盛んになった。
わが大映も、京撮の時代劇に活を入れて斜陽化を跳ね返さんと、現代アクション映画に強いと定評のある井上梅次監督を、市川雷蔵・勝新太郎・大木実・山本富士子共演の豪華キャストによるコメディ・タッチの異色時代劇巨編『女と三悪人』の監督として起用した。
この映画の助監督には、チーフとして助監督に戻った元監督のWさん、セカンドには名匠溝口健二監督に鍛えられて時代考証力抜群のMさん、そしてサードに私が就いた。
映画の内容は、幕末の種々雑多な群衆がひしめき合う江戸両国の盛り場を背景に、1人の女役者(山本)を中心に、役者くずれの流れ者(雷蔵)、ひねくれ者の素浪人(大木)、大道芸人の元締めとして睨みをきかす生臭坊主(勝)の三悪人が織りなす恋模様を、息もつかせぬ迫力と面白さで絢爛に描くというものだ。
冒頭の両国盛り場のシーンは、マルセル・カルネ監督作品『天井桟敷の人々』の群衆でごった返す“犯罪大通り”がイメージだという監督の先触れ。これは大変な芸術をねらっている。Mさんと私は綿密に時代考証して衣裳や小道具・持ち道具などを準備したが、監督立ち会いの衣裳調べになって監督のハッタリがばれた。私たちが準備していた衣裳をどんどん捨て、派手派手の御存じ時代劇の衣裳に変えてしまった。井上監督にとっての時代考証は、シナリオに「時は幕末」と書くか、画面に「時は幕末」とタイトルを乗せておけば済むようなものの感じだった。
「後は気楽にやろうよ」となったが、時間や予算に合わせてシナリオのイメージをてきぱきと変更し、可能なイメージをスピーディに追求していく井上監督の仕事ぶりに圧倒された。口下手なチーフのWさんはぽんぽんと言い返され、面と向かって打ち合わせがスムーズにできない始末。
ある夜間オープン撮影でのことだ。井上監督と同年配のWさんが、背丈ほどに積み上げた廃材の山を危うげに乗り越え、椅子にかけて待機している監督の後から、腰をかがめて打ち合わせする姿を私は見た。前から向かえば簡単なことだのに、とその情景が今も目に浮かぶ。
また芝居小屋内部のセット撮影の時のことだ。舞台の上で、予告編の制作を担当する凝り性のMさんと井上監督が激しく対立した。
「これまで30数本の予告編をつくってきて、最高の出来です」とMさん。
「私もそれ以上の予告編をつくったり観てきたが、最低の作だ」と監督。
それからのMさんは編集室にこもり、ラッシュフィルムを凝視しての編集を繰り返し、なんとか完成させて東京本社に送ることができた。しかしその間の無理がたたり、中心性網膜炎にかかったとかで、まともに仕事ができなくなってしまった。
結局、オープンセット・両国界隈の大群衆シーンの撮影は、私だけで受け持つことになっていしまった。もっともWさんと同じ身分の元監督が応援に来て「辻くん、何でもいうてや」と言ってくれたが、そんな悠長なことを井上監督の下でやっている暇はない。両国盛り場のシーンの撮影は、延々と組み立てた高台の上に移動車用のレールを敷いて、俯瞰の大移動ショットの撮影から始まった。私は走り回り、数100人の俳優さんやエキストラに演技をつけた。群衆が出る両国盛り場のオープン撮影は数日続き、お陰で、私に大群衆に演技をつける自信を与えてくれた。
かくして『女と三悪人』は1962年の正月作品として絢爛豪華な大娯楽編に仕上がり、がらんどうの自宅で、私は無の空間を咀嚼する新年を迎えられることになった。(2009年2月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ