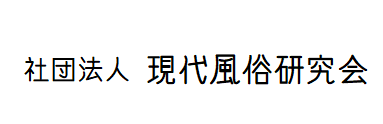| 第70回「“♪どこまでつづくぬかるみぞ!!” の時代」 |
「会社も倒産したことだし、マイペースでボチボチ行くか」
1972年(昭和47年)、のんびり正月気分に浸っていると、いらだたしげに電話のベル。電話は、新しく映像制作に乗り出した大阪のエクスプレス社(以後、EX社)でプロジューサーになっていた、T君からだった。
「“びわ湖放送”の番組制作は、4月1日の開局に間に合わせればいいので、その間に突っ込める仕事を引き受けました。急な話で恐縮ですが、すぐ打ち合わせに来て下さい」
T君は元大映京都撮影所へ中途入社したコマーシャルの営業部員。入社以来職場になじめないのか、巨漢のT君は体を縮め、製作部の片隅でポツンとさびしそうにしていたので、私はいつも元気づけていた。そんな事情があったからかもしれない。T君は、倒産前後から私に協力を求めていたのだ。
「まだ正月3ヶ日が過ぎたばかりじゃないか」
「先輩。そんなダダこねていると、フリーランサーで監督はやっていけませんよ」
私は、未知の記録映像業界へ演出の股旅(またたび=近世、博徒・遊び人などが諸国を股にかけて渡り歩くこと)に出る覚悟でEX社に出向いた。社長以下幹部から期待満々に挨拶され、私はEX社のメイン監督としてワラジを脱ぐことに決めた。
仕事は滋賀県教育委員会が企画したもので、滋賀県指定の無形文化財技術保持者7人の技術を映像記録し、『近江の伝統工芸』と題する1本の記録映画にまとめることであった。
技術保持者には、「本藍染」「揉み紙」「雁皮紙」「毛筆」「金箔」から各1人、「信楽焼」からは2人が指定されている。
各技術は、材料の栽培・加工など季節に支配されたり、時間がかかったりする各種多様な工程で成り立っている。現実の作業工程に合わせて記録していかざるを得ない。1月の寒い間は野外行程は不可能。まず屋内でできる本藍染の染めの工程を取材すると、次は信楽焼の粘土を手びねりして形を作る工程へ、さらに次は、箔打ち紙を仕込む金箔の工程などと、野洲町(現・野洲市)や草津市、信楽町(現・甲賀市内)などを、あちこち飛び回って取材を重ねた。
虚構で描く劇映画と違い、現場に立ち現実に向って記録映像の仕事をしていると、それなりの心にひびくエピソードに出合う。
金箔の技術者・今越清次郎さんは当時89歳。そんな高齢で満足に作業できるかな。不安気味に出向くと、船越さんは元気そのもの。その秘訣を聞くと、毎朝の乾布摩擦にあり。では、その様子を記録しようよ。カメラを用意していると、出てきた今越さんは手ぬぐいを持っただけの素っ裸。今越さんの乾布摩擦とは、睾丸を下から上へ100回こすり上げることだった。それは公表できません。笑いをこらえながら、あわてて背中の乾布摩擦に変更してもらう。
また、胃潰瘍の手術をしているという雁皮紙の技術保持者・成子佐一郎さんは、「なんで、こんなにしんどいのかなあ」とこぼしながら、記録のために雁皮紙を漉く。
私は成子さんが治療不可能の癌にかかっていることを家族から聞いていた。成子さんが息を吐くたびに、胆のう癌で死亡した母の看病で知った癌の膿の臭いを感じた。せめて完成試写までは生きながらえてほしいと祈りながら、すべてを記録できた。
しかし、翌年4月の完成を前に成子さんは亡くなった。仏前試写を行い、家族の方々から良い記念を残していただけたと、深く感謝されたことを今に覚えている。
ところで、 『近江の伝統工芸』にかかっている間に、びわ湖放送が開局する4月1日が迫りつつあった。『近江の伝統工芸』の制作はひとまず置いて、びわ湖放送の番組制作の合閒を縫うことにした。
さて、びわ湖放送での仕事は、大津、彦根、長浜、近江八幡、守山、草津、八日市など当時の滋賀県内七市がスポンサーの『ふるさとと私たち』と題するシリーズ番組の制作だ。市政解説を中心とする各市の社会教養30分ビデオ番組を毎月2本。同じく『近江歴史紀行』を副題とするスポンサー各市の歴史紹介30分ビデオ番組を毎月1本。これらの構成演出が私の仕事だ。月3本の番組制作となると、つねに次の番組を重ねて進めていかなければならない。厳しいスケジュールが予測されたが、ぜいたくを言える場合ではなかった。
『ふるさとと私たち』は、スタジオ対談と取材フィルムの構成番組。各市の広報部が提起する問題を討議して番組のテーマを決める。それに基づいて予備取材し、構成台本を作成。市側のOKが出ると、スタジオ対談に挿入の必要なフィルム画面作成のため、予備取材した場所へロケ。取材したフィルムの編集を終えれば、びわこ放送のスタジオに出演する行政の関係者やゲストを集め、構成台本に沿ってビデオ収録となる。
第1回目収録は暗中模索の連続だった。まず私の役割は、スタッフがカメラや照明などスタジオ準備の間に、別室で、司会者と出演者との打ち合わせをすることだ。台本に基づいて司会者や出演者に演出計画を解説し、対談内容を打ち合わせながら煮詰めていく。しかし出演者は、司会者役のタレント以外はすべて素人。まず初出演の緊張を解きほぐすのに苦労する。試行錯誤の上、軽い色恋話を交えることが効果的だとわかる。出演者の緊張がほぐれたところで、準備完了したスタジオへ案内する。
スタジオでのビデオ収録は、出演者と同じく私も初体験。他のスタッフも、短期研修は受けたものの、実際の番組制作は初体験。すべてが初体験者で番組収録を開始した。緊張で乾きがちになる舌を湿らせ湿らせ、ガラス窓を隔ててスタジオが見通せる副調整室から、インカム(ヘッドフォーンとマイクが合体した機器)を通して、スタジオのフロアにいる演出助手やカメラマンに指示を出したり、スタジオカメラから送られてくるモニター画面を見ながら、画面の切り替えを隣のスイッチャーに指示を出す。撮影、編集、音楽入れ、タイトル出しなどを同時に操作し、ステブレ(ステーションブレイク=番組を切り替えるための時間)1分を除いた29分ジャストの30分番組を一度に完成させてしまう。一カット毎の撮影、フィルム現像、編集、音楽録音、ミックスダビングなど多くの過程を踏んで完成させていく劇映画との違いを実感しながら、また、演技を直接見て行う劇映画の演出と異なって、モニター画面を介しての演出は、隔靴掻痒の感じでもどかしいと思っているうちに、司会者が質問を抜かしているのに気づく。あわてて司会者を外した画面に切り替え、その間に、フロア助手に指示して、司会者に番組の流れを修正させるなど、横で演出補助してくれる機械慣れした若いプロデューサーに助けられて、何とか最初のビデオ収録を終えた。
帰りがけの女性出演者たちから「夫たちには聞けないような話がたくさん聞けて、ほんまに楽しいお仕事だったわァ」とお礼や労いの言葉をかけられたが、帰宅途中のバスの中で、座席に沈み込んでいくような生まれて初めての不安感に襲われた。近所の医者に診てもらったら、血圧が160を軽く突破。半年間降圧剤を飲む破目になった。
番組制作が何本も重なり、徹夜して台本を仕上げ、A市での打ち合わせを終えると、B市へ急ぎ、次の企画を打ち合わせ、飛んで帰って企画書をまとめていると、C市の台本を至急仕上げてほしいの電話。原稿用紙に向かってシコシコ書いていると、つい軍歌が口から出てくる。
♪どこまでつづくぬかるみぞ/三日二夜食もなく/雨ふりしぶく鉄兜♪
私も、現人神・天皇を単なる人間と見破り、天皇崇拝から脱落した小学5年生までは、誰よりも軍国少年だった。腹が立つことに、それまでに私の音感は、軍歌になじむ音感になってしまっていたのだ。
(2012年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第71回「“あやかり信長、困惑”の時代 」 |
♪どこまでつづくぬかるみぞ/三日二夜食もなく/雨ふりしぶく鉄兜♪
1971年(昭和46年)勤めていた大映株式会社の倒産をきっかけに、私は劇映画界から外れ、翌1972年早々より、単発注文の記録映像・映画のほかに、4月からテレビ放送を開始した“びわ湖放送”で、滋賀県内の全市をスポンサーとする番組『ふるさとと私たち』を月2作と『近江歴史紀行』、計月3作の構成演出に追い立てられた。
追い立てられたり耐えようとすると、やはり馴染みの軍歌、かつての旧満州(中国東北部)で日本軍が匪賊を討伐しに行く状況を歌った『討匪行』が体内から湧き出てきてしまう。
80歳を超えた今に続く、反戦・平和主義者の困った不条理だ。
『ふるさとと私たち』と平行して担当している『近江歴史紀行』は、スポンサー各市の歴史から『大津京と壬申の乱』『彦根城と佐和山城』『秀吉と長浜』『湖賊の町・堅田』などとテーマを決めて制作される30分番組である。
テーマが決まると、私は歴史小説家・徳永真一郎さんの監修を受けながら、まず構成台本を書く。台本に基づいて、各地の史跡や資料、風景などをフィルム取材し、ナレーションや音楽を入れて十五分の完全な映画作品にまとめる。その後は放送局のスタジオを使い、フィルム映画の後に続けてテーマに関連した徳永氏と郷土史家との対談をビデオに収録し、一本化して30分番組に仕上げるのだ。
ところで、『近江歴史紀行』の制作にあたり、スポンサー各市の歴史を取材に行く先々で、わが故郷尾張清洲の英雄・織田信長の旧悪をしばしば突きつけられた。
信長は天下を掌握するに際し、尾張から京への通路に当たる近江の天台宗比叡山延暦寺系や真宗本願寺系の寺院に軍用金や領地の供出を義務づけるなどの難題を持ちかけ、抵抗すれば片端から壊したり焼き払ったとのことだ。有名なところでは湖東三山の金剛輪寺、百済寺、西明寺などが焼き払われたという。
「あれも信長が焼いたんですか。えっ、こっちもですか。どうも申しわけありません。まあ、大昔のこと
ですから、どうか許してやってください」
故郷の英雄として、信長にあやかって生きてきた面のある私としては、謝るほかなかったのだ。
織田信長は父の死により18歳で尾張の大名になる。27歳の時、京に上る駿河の大名・今川義元を桶狭間に迎え撃って敗死させ、「尾張に信長あり」と武名をとどろかす。その勢いで信長は、群雄割拠する多くの大名を制覇して天下を統一するが、その強大な権力によって大名を統制したり、兵農分離の新しい武士団への変革など急激な政策が反発を呼んだのか、京都の本能寺に宿泊していた49歳の信長は、1582年(天正10年)6月2日、明智光秀に襲われ自害し果てる。
私が小学生だった戦前の清洲では、信長が“本能寺の変”で自殺した命日の6月2日には、信長の偉業を顕彰する運動会が、“桶狭間の戦い”に出陣する信長の勇姿を彫った銅像の立つ清洲公園で毎年行われた。
また故郷の英雄の話として、“桶狭間の戦い”の話をくり返し読んだり聞いたりしているうち、いつしか“桶狭間の戦い”への出陣に際して信長が舞ったと『信長公記』に記されている幸若舞の“敦盛”の詞章が脳裡に貼りついてしまった。
「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。一度生を得て滅せぬ者のあるべきか」
人間は生まれた瞬間から、死に向かって進みはじめるのだ。幸若舞“敦盛”の詞章は、私の人生観に底流している。
さて、守山市の歴史をたどる『守山・歴史の人々』を制作取材していたときのことだ。案の定、金森(かねがもり)町の歴史に信長が顔を出してきた。
この地方は、大和朝廷が成立するといちはやく直轄領となり、租税を確保して朝廷の財政を支え、平安時代には貴族・寺院などの荘園が入り組んで、その支配権が争われた。
特に宗教の面では、近江を一望できる比叡山延暦寺が力を備えてくると、この地方は延暦寺の地盤となり、多くの天台宗寺院が栄えるようになった。しかし室町時代に入ると、本願寺8世の蓮如が15世紀の半ばから、比叡山の勢力と対抗して、金森の道場を拠点に強力な布教を展開し、この地方は真宗本願寺勢力の地盤ともなる。
信長が魔手をのばしたころの金森は、各集落の回りを土塁や濠で囲んだ防衛能力の高い寺内町となっていた。
金森は元亀2年(1571年)、信長勢の攻撃に3ヶ月も抵抗し、ついには金森に楽市楽座を開かせ、諸役を免除するという朱印状を勝ち取るほどの成果を上げた。
私が“あやかり信長”であることを知った地元の郷土史家は、「お気の毒でしたね」と慰めてくれたが、私は心の中にホッとするものを感じた。
信長が犯した数々の所業。信長側から見るのと、信長に犯された側から見るのとでは大違いだった。それまでの私は「あやかり信長」として、主に信長側から信長の行動を見ていたのだ。
日中戦争の見方でも、韓国併合の見方でも、攻める側と攻められる側、併合する側とされる側とでは大きな違いがある。その違いをはっきり理解しなければ日中関係、日韓・日朝関係は友好的にならないと、金森を取材しながら改めて思い起こした。
私は『近江歴史紀行』や『ふるさとと私たち』の制作をつづけるうちに、現地に立って思考することの重要性を痛感し、私の性格として劇映画から外れたことが正解のような気がしてきた。(2013年3月記)
⇒ 目次にもどる
| 第72回「“七転び八起き”の時代 」 |
「新しい琵琶湖の歴史が始まる」
1972年(昭和47年)6月の『琵琶湖総合開発特別措置法』成立に際し、当時の滋賀県知事・野崎欣一郎氏は胸を張った。
ところで『琵琶湖総合開発特別措置法』は、琵琶湖の保全・治水・利水の3つを柱にすえているとは言え、実際は、高度成長期の影響によって水需要の増大した京阪神など下流域の水利用が主眼だった。
4月から開局して私が番組制作の一端を担うようになった“びわ湖放送”(以後BBC)へも、琵琶湖総合開発をPRする滋賀県発行のパンフレットが盛んに出回った。そのパンフの表紙には、湖岸道路をドライブする乗用車、点在するカラフルな家屋など、ヨーロッパの湖を思わせるような未来予想図が使われているのに違和感を感じた。
「こんな未来予想図をかかげるセンスで、ほんまに琵琶湖の保全なんてできるのかい?」
翌年には、県から琵琶湖の富栄養化が着実に進行していると発表され、彦根付近の琵琶湖では淡水赤潮が発生した。
あたかもその頃だ。BBCで私が構成演出を担当する滋賀県下の市政紹介番組・『ふるさとと私たち』シリーズに彦根市を取り上げる番が回ってきた。ゲストのメインは、言うまでもなく“彦根の殿様”で知られた井伊直愛市長。江戸時代より彦根藩主を代々受け継いできた井伊家の流れだ。
井伊市長は単なる殿様ではない。アミ類の新種を約50種も発見した生物学者で、文部省資源科学研究所や滋賀県水産試験場の講師も歴任してきた。
番組収録前の打ち合わせで、不安げに井伊市長から質問が出た。
「監督さん、私はどんなふうに話をしたらよいのですか」
井伊市長は、察するところテレビ出演に不慣れだろうし、私もテレビ番組の製作には日が浅い。思いつくままに意見を伝えた。
「きっと視聴者の皆さんは、市政を受け持っている人はどんな人か、その人間性に興味を持っているはずと思いますので、市長さんの市政に対する考えをざっくばらんに話されたらどうですか」 ということで始まったBBCスタジオでの番組製作。井伊さんは彦根市政を説明する中で、野崎知事が浜大津に人工島をつくると発表するなど琵琶湖総合開発に対する県の施策を批判した。
スタッフや放送関係者の間には県に気兼ねする意見もあった。
「これは市のスポンサー番組や。県に遠慮することはないや」
放映後、県の噂が私の耳に入った。
「『ふるさとと私たち』は傾向番組だ」
しかし一方、野崎知事には八日市市にダークホースが出現していた。1971年、30歳代で市長に当選した武村正義市長だ。清新で革新的。私と同類に感じた。『ふるさとと私たち』シリーズの番組制作で、会うごとに激励し期待を披露した。
そして1974年、「琵琶湖を守る」を公約とする武村氏は大方の予想をくつがえし、田中角栄土建国家の申し子・野崎知事を激戦の末に破って当選を果たした。
ところがである。翌1975年3月、武村滋賀県は財政危機で非常事態を宣言。5月、県の補助を受けるBBCの負債は8億円。経営立て直しのため、私のシリーズ番組は吹っ飛んでしまった。
「味方してやったのに、なんちゅうこっちゃ」
滋賀県の財政危機がきっかけでBBCの仕事が減り、時間にゆとりができた。当時大きな社会問題となっていたスモン訴訟をすすめるための抗議行動に加わることにした。
スモンとは、下痢の治療剤キノホルムが原因と考えられる神経障害だ。重症化すると歩行障害を生じたり、ときには視力障害から失明にいたる。患者数は1万人を超えているという。
スモン患者たちは薬害を発生させた国と製薬会社を相手に、損害賠償請求の訴訟を東京地方裁判所に提起した。しかし厚生省や製薬団体などの怠慢で裁判はなかなか進まない。スモン患者たちは解決しない薬害の怖さを訴えに、集団で街へ出た。
8月の末には、関西各地にあるスモンの会が、合同で田辺製薬へ抗議のデモ行進を実行することになった。
私はJR京都駅から「京都スモンの会」の会長の車イスを押して、抗議行動に参加した。大阪駅を降りると、駅前広場に集合していた各地の会と隊列を組み、歩行障害の人は車イスに乗ったり、松葉杖を腋に挟んだり杖をついたり、視力障害の人は手を引いてもらったりして田辺製薬へとデモ行進した。
「スモン患者の怒りを知れ!」
「田辺は薬害の責任とれ!」
シュプレヒコールをあげながら田辺製薬に到着して、私は建物の異様な状景に愕然とした。道路に面してヨロイ戸を降ろした1階部分全体に、機械油が分厚くべったりと塗りつけてあったのである。会長が説明してくれた。
「張り紙ができないようにしとるんや」
ブラインドを降ろした2階の窓では、薄板の間からカメラが幾つも覗いている。
「後で損害賠償を請求できる証拠を写そうとしとるんやわ」
さんざん声を上げて抗議行動を終えると、デモ隊は油でべたべたのヨロイ戸にプラカードを立てかけたり、貼り紙は巻いてヨロイ戸沿いに寝かしたりして、よろよろと帰途についた。私はデモの後の様子が知りたくて、会長の車イス押しを代わってもらい、田辺の向かいにある喫茶店の2階に座を占めた。
デモ隊が去ってしばらくすると、構内に通ずる大きな開き戸の小扉が開いて警備員が顔を出す。あちこち見回しながら恐る恐る道路に出てくる。デモ隊が去ったのを確かめると、社内に向けて手招きする。事務職員がカメラ片手に出てくると、デモ隊が去った状景を丹念に撮影して社内に姿を消す。間もなく開き戸が開いて、何とか日常に戻った気配。私は一部始終見とどけたと思って去りかけたが、もう少し粘ることにしてコーヒーを追加した。
その時だ。大勢の女性によるザワメキが遠くから聞こえてきた。やがて隊伍を組んだ女性従業員たちが続々と帰ってきて、社内に吸い込まれていった。
激化が予想されるデモにショックを受けないよう、前もって会社がどこかへ避難させていたに違いない、と私は判断してコーヒーを飲み込んだ。
「犯すもの犯されるもの。儲けるもの儲けられるもの。支配するもの支配されるもの……。なぜ人間は2つに分かれたり、分けられたりしてしまうのか」
この日の体験を契機に、人間が1つになれる思想を導き出すにはどうするかが、その後の私に対する課題の1つとなる。
(2013年5月記)
⇒ 目次にもどる
| 第73回「“偶然は、活かさなくちゃ”の時代 」 |
1974年(昭和49年)11月、滋賀県知事が自民党系で琵琶湖開発派の野崎欣一郎氏から、「琵琶湖を守ると」と公約して立候補した革新的な前八日市市長の武村正義氏に交替した。
その翌年3月、武村新知事は滋賀県が財政危機に陥っていると非常事態を宣言。県の補助を受けるびわ湖放送(BBC)だけでも負債は8億円。1972年4月の開局以来、私がコンスタントに演出を担当してきた滋賀県下各市の市政紹介番組『ふるさとと私たち』と歴史紹介番組『近江歴史紀行』の両シリーズが、BBCの経営立て直しと称して中断されてしまった。
飯のタネが急に減って、のんびり屋の私もいっとき慌てた。
「一寸先は闇だ。何が起こるかわからない」
しかし考えてみると、この3年半に、『ふるさとと私たち』シリーズを約70回、『近江歴史紀行』シリーズを約30回の脚本・演出を担当し、扱った分野は行政、福利厚生、福祉、教育、同和問題、老人問題、琵琶湖の水質問題、自然環境問題、文化財保護問題、滋賀県の古代から今に至る歴史などなどと多種多様。そのお陰で、記録映像界への第一関門が突破できたことでもあるのだ。
「人生は偶然の積み重ねだ。良い偶然も悪い偶然も、未来を開くチャンスと捉えて活用しちゃえばええのや」
と言うわけで、その後は大阪、京都、岡山、姫路、今治などの映像制作会社に活動の場を広げることができ、近畿、山陽、四国の三地方をベースにして、ときには九州、関東、東北に足をのばし、国や地方自治体、企業などがスポンサーの映像作品を比較的マイペースで作り続けてることができたのである。
〈マイペース〉と言えば聞こえはいいが、実際は〈細々と〉ということであり、妻も職に就く必要に迫られるなど、家族に多大の迷惑をかけてしまった。
私が生来小回りがきかないのと、制作過程のすべてにタッチするのが演出だとの責任意識から、他人に任す場合が生じないように、ゆるやかなスケジュールを組み、多くの作品を同時にダブらせて取り組むことをしなかったからだ。
さてBBCでの仕事が減って時間にゆとりができたので参加した「京都スモンの会」の田辺製薬に対する抗議行動の後、依然として田辺は被害者救済に対する冷酷な態度を変えないので、会ではたびたび抗議集会がもたれた。
田辺製薬は、社内で行っていた動物実験でキノホルムがスモンの原因であることを知りながら、その事実を隠して「スモンはウィルス感染が原因だ」とするある学者の説を固守し、薬害被害者の救済を拒否し続けていたのである。
「京都スモンの会」の抗議集会では、田辺の社員と称する人物が、田辺の薬害被害者に対する態度を批判し、涙ながらに社員として反省していることを訴えた。
私は「京都スモンの会」の会長にささやいた。
「田辺には良心的な社員もいますね」
「まさか。あの男は、スモンの会の状況を探ったり、私たちの結束を崩すために、会社が送り込んでくるスパイですよ」
私が絶句していると、会長は追い打ちをかけた。
「そのくらい悪辣な会社に、私たちキノホルム被害者は救済の訴訟を起こしておるわけですよ。察して下さい」
薬害救済を訴えられてる武田薬品、チバガイギー、田辺製薬など3社のうちで、田辺製薬が最も質が悪いとのことだった。
その後私は仕事を探すためにゆとりなくなり、「スモンの会」から離れざるを得なくなった。
資料によると、やがて1977年の4月、東京地裁から和解案が示され、訴えられている3社のうち、武田薬品とチバガイギーは和解の方向でまとまっていく。
これに対して田辺製薬は、相変わらず和解拒否の姿勢をくずさず、薬害救済を訴える原告たちの主張する症状が鑑定結果よりも軽いことを立証するため、原告たちの日常生活を8ミリフィルムで盗み撮りし、証拠として地裁に申請する却下されるなど悪辣な行動を続けるが、事態の収拾を急ぐ国の画策にさすがの田辺も折れざるをえなくなっていったとのことだ。
話変わって1977年(昭和52年)5月のことだった。新聞記事を見て思わず声を上げた。
「ええっ!こりゃ、オレのためにできた研究会みたいだぞ」
昨年・1976年の9月、京都を拠点に『現代風俗研究会』なる組織が発足したというのだ。
私は“風俗”という言葉に弱い。目にした瞬間、頭がクラクラッとするほどだ。急いで事務局長・宇野久夫さんのお宅へ入会申込みに走った。
というのは、大学時代に光文社が出版したドイツのマルクス主義者で風俗研究家のエドゥアルド・フックス(1870-1940)が著した『風俗の歴史』(安田徳太郎訳)を手にして以来、“風俗”なる言葉が脳裡に焼きついてしまったからだ。
私は小学5~6年時代に幼稚な好奇心から、当時生き神様・現人神(アラヒトガミ)として崇拝された天皇の全盛時代に、その正体を探ろうとした経験がある。古事記を読んで、天皇の先祖とされる神々の愛欲にふける暮らしぶりを知ったり、天皇を中心とする貴族たちが展開する恋慕の情あふれる万葉集の相聞歌を読み解いていたり、親たちが大切にしている天皇の写真に小便をかけても罰を当てられない天皇は、私たちと同じ人間だと確信できたのだ。そうなると天皇崇拝の念を失い、それまでチャンコロ、チャンチャン坊主などと軽蔑してきた中国人も私と同じ人間に思えてきて、忠君愛国によって始められた日中戦争など天皇の大御稜威(オオミイツ=天皇の威徳)を広げるための戦争に疑問を感じて反戦的になっていった。
こうした経験は、フックスの『風俗の歴史』を参考にすると、私は天皇たちの“性風俗”を探ることによって天皇の真実が解明できたというわけだ。
それ以来風俗はその人間の真実を示すもの、風俗研究はその人間の真実を探る手段と認識してきた。
そして、いろいろな風俗研究をまとめて人間の真実を探る学としての『風俗学』なるものを勉強できると、映像業界に生きる私には偶然出現したとも思える現代風俗研究会に期待した。
(2013年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第74回「“風俗学はいずこ?”の時代 」 |
日記手帳で調べると、1977年(昭和52年)6月4日午後のことだ。複数の記録映像作品を平行して制作している私は、どうにかスケジュールをやり繰りして、京都は鹿ヶ谷の法然院へと急いだ。14時から現代風俗研究会の第7回研究会が行われるのだ。
なんとか開始時間に間に合い、会場の大広間へ畑違いが迷い込んだようにたどり着いた。高いなと思いながら会費5000円を入り口で払い、末席に座を占めて見まわすと、元京都大学人文科学研究所長でフランス文学研究者の桑原武夫さん、「ベトナムに平和を!市民連合(べ平連)」の中心的人物として活躍した哲学者の鶴見俊輔さん等々雑誌や新聞の写真で見覚えのある学者さんや、学術本の背表紙でしか見たことないような名前の実物らしい学者さんたちが綺羅星のごとく並んでいらっしゃる。
「……ここで気後れしてはいけないぞ。人間の真実を探る学としての風俗学を学ぶことは当然として、お前は映像業界以外の人たちと交流して、自分の考えや意見を確かめたり、豊かにするために入会しに来たことを忘れるな!」
この日の研究報告者は池井望という学者さん。聞いたこともない名前だが、綺羅星さんたちとは和気あいあい、懇意の様子。きっと業績のある学者さんなんだろう。研究報告のテーマは、私が保存しているレジメには『自然と風俗~盆栽私見~』とある。池井さんの話はレジメから察するに、小さな鉢の中に植物や岩石などで壮大な自然の景色を創り出す盆栽は、人工か自然かの両面性を感じさせ、生け花や茶の湯などと同じく、日本文化の特性を象徴するということだったと思うが、因習や流行などと「風俗」の意味づけがせまく、人間の真実をさぐる学として、私がイメージしている「風俗学」を満足させるもではなかったと記憶している。
それよりも私は、大勢の学者・学徒に混じって談論風発できる雰囲気には大いに気をよくし、会費が高いという不満はあっさり消えてしまった。
研究会の後は懇親会。さっそく会長の桑原さんに体当たりした。
「風俗学を勉強したいと思って、きょう入会しました」
桑原さんは毅然として答えられた。
「風俗学という学は、ありません。これから現代風俗研究会が、既成の学問から落ちこぼれているものを学際的に拾い集めて新しく創るのです」
「風俗学を創るって……」
私は桑原さんの発した言葉の力強さに期待して、現風研と共に歩むことを決めた。
となると、学者さんたちとの交流が重要だ。桑原さんに続いて、誰彼となく体当たりしていった。
誰よりもベ平連で活躍した鶴見さんに魅力を感じた。
研究会やフィールドワーク、読書会などへの出席を重ねるに従って、私はいつの間にか鶴見俊輔さんとの間で親しく話を交わせるようになっていた。研究会における私の物怖じしないアマチュア的発言から、鶴見さんも私をマークしていたらしい。裸の話を引き出そうとすれば、まずこちらが裸にならなければならない。小学3年生のときに成績優秀を理由に「町教育界賞」を受けたことを話したかもしれない。鶴見さんは突然目をむいた。
「辻さんは優等生でしたか。私は不良少年だった、ワッハッハッハ」
笑い飛ばす鶴見さんに、私は言い返さざるをえなかった。
「母1人子1人の母子家庭に、不良はゼイタクなんですよ!」
毎回のように懇親会が終わると、大学の先生方は大学院生・学生たちを引き連れ、2次会に向けて河原町方面の繁華街へ繰り出していった。
しかし稼ぎの悪い記録映像監督の私は、持ち金もわずか、そうそう仲間には入れない。
その日も懇親会の後、家路をたどって法然院から市バスの通る白川通りへ坂道をぶらぶら下ってくると、後ろから「辻さん」と呼び止める声。振り向くと、鶴見俊輔さんだった。
「辻さんはフリーの映画監督で一匹狼。ならば私も一匹狼。給料の出ない者は、働かないと金が入らないよね」
「鶴見さんと一緒にされては困りますね。私は離れ小猿ですよ」
その後白川通りまで何を話し合ったか忘れたが、鶴見さんには、家でする仕事が待っている様子であった。
タクシーで帰る鶴見さんを見送った私は、鶴見さんが私に寄せる程よい好意を思い返し、年甲斐もなく胸をふくらませた。
その頃の私は、彦根市にある工業会社のPR作品と平行し、岡山市にある船舶用推進機器メーカー、ナカシマプロペラが製造している可変ピッチプロペラの製造記録PR作品のシナリオ制作に取りかかっていた。
可変ピッチプロペラとは、羽根のピッチ(角度)を自在に変えることができるスクリュープロペラを指し、ピッチを変えることにより一定の回転方向、回転数のまま、任意の前後方向の推進力が得られるなどメリットの多いことから、漁船、タンカー、フェリーやタグボートなど広く採用されている。
すでにナカシマプロペラは、船舶用固定ピッチプロペラでは世界トップのシェアを誇っている。
新たに導入した大型のホストコンピュータに続いて、精度の高い工作ができる大型のNC(制御装置)翼面加工機を導入し、可変ピッチプロペラでも世界トップのシェアを目指そうというわけだ。しかしシナリオ制作の段階で、製造工程を細かく表現しようとする技術担当重役と、鑑賞者に与えるインパクトを重視する営業担当重役との意見が合わない。会社の重役という人たち接するのは初めての経験だ。風俗観察と思って両重役の口論議論を横目で楽しみながら、なんとかシナリオを完成させた頃、現風研の第2回総会が待っていた。
10月15日午後、私はイソイソと法然院にむかった。やっぱり現風研に期待しているのである。 会場は何となくざわついていた。会員が老人や主婦、OLにまで広がったというのだ。驚いたことに、わが家の近所にある郵便局長の奥さんが入会していた。私に出合ってはにかまれた。
「新聞記事で、面白そうやったから入会したんやけど、無学の私なんかに続けられるかしら」
「アマチュアの私でさえ大丈夫ですから、大丈夫ですよ」
私は現風研の前途に希望を感じた。しかし「風俗学」に関してはどうなんだろう。
配布された『現代風俗’77』には、桑原会長の「風俗ということ」に続いて、多田道太郎さんの「風俗学事始」と題する論文が出ている。
急いで目を通した。民俗学と風俗学について比較されている。農村の不変の(比較的変わりにくい)文化を研究する民俗学に対して、風俗学は、変化の観点から都市文化を研究するものだと解説されているが、風俗学そのものについは皆目わからない。
おりしも総会におけるシンポジウムのテーマは「流行について」だ。
私が劇映画の制作に助監督として17年従事し、その間に受け持った風俗考証で扱う「風俗」とは、映画の内容や画面にリアリティを与える人間現象のすべてということであった。どうも先生方の考える風俗感と、私の風俗感にはズレがありそうだ。その内に何とかなるだろうと思い直して、懇親会に混じり込んでいった。
懇親会の終わり頃、ある社会学者が、私の「風俗学」を咎めるように耳打ちした。
「辻さん、風俗学をやるんだったら、まず風俗学の概念を固めないとダメですぜ」
アマチュアの耳にきつく響いた。
(2013年8月記)
⇒ 目次にもどる
| プロレス文化研究会15周年に寄せて |
1998年7月のことだった。京大会館の一室。19人が集まった第1回集会。誰が来るのかさえわからない状態での集まりだった。「プロレス文化研究会」と聞いてどんな会を想像するのだろうか。19人の中にはファンの集いのようなものを思い描いて参加したカップルもいた。途中で姿を消した。
当日のアンケートの回答から抜粋してみる。「私が生まれる以前の話が多く貴重だった。概論的な話があってよかった。」「プロレスを軸にして幅広く様々なことが考えられる。」「参加者によってプロレスのどこを見ているのかが異なっていて勉強になった。」「もう少しプロレスを勉強してから参加したい。」「ディスカッションというより岡村、井上氏の話を聞くという感じで楽しめない。」
次回の研究会に参加すると回答したのは5人だけだった。第3回までは会のフォーマットが確立しておらず、会場も転々とした。第4回から会場がル・クラブジャズに定着し、報告者、ビデオ上映、フリーディスカッションという流れが確立された。ホームページができた。しかも、朝日新聞に告知記事が出るまでの出世ぶりだった。ジャイアント馬場が亡くなってから半年が経過していた。
2002年に『力道山と日本人』が出版された。参加者のうち、「研究」色の強そうなメンバーによるアンソロジーだった。2004年にはNHKBSのテレビ撮りがあった。拙宅、ル・クラブジャズに撮影クルーが訪れ一日中つき合わされた。三条通りを、セリフをしゃべりながら歩かされた。このときの第18回そのものがテレビ収録のために企画された特別な集会だった。結局、「NHKの都合」によりオンエアされなかった。
2008年、拙著『力道山 人生は体当たり、ぶつかるだけだ』の上梓を経て、2010年には『現代風俗 プロレス文化』の出版に至る。2009年の現代風俗研究会例会での報告を中心にまとめた年報である。8年前のアンソロジーに比べて執筆者の数は増し、プロレス文化研究の裾野は広がったというべきか。
7月14日(日)に予定されている第45回は久しぶりに梅津顕一郎さん(宮崎公立大学)の報告だ。新しい視点を取り入れた先鋭的な発表になることだろう。乞うご期待。
(プロレス文化研究会世話人 岡村正史)
⇒ 目次にもどる
| 第75回「“独断と偏見で、風俗学だ!”の時代 」 |
1977年(昭和52年)10月15日、現代風俗研究会第2回総会後の懇親会でのことだ。ある社会学者が、私を咎めるように耳打ちした。
「辻さん、風俗学をやるんだったら、まず風俗学の概念を固めないとダメですぜ」
<アマチュアだと思って馬鹿にするな。その内に煮詰めてやるわい>
私は内心反発したが、プロの率直な助言にも受け取れて、やはり気になった。
<風俗学の概念を固める、とはどういうことだ>
私は帰宅するや、国語辞典や漢和辞典を本棚の片隅から引っ張り出し、まず“概念”の意味から調べることにし、ページを繰った。
“多くの似かよったものごとから、共通の性質をぬき出してまとめあげた観念”
<……、具体的にはどういうことだ>
別の辞典を順に当たってみる。
“「…とは何か」ということについての受け取り方(を表わす考え)”
“事物の本質をとらえる思考の形式”
“(哲)個々の事物から全般的に共通的な性質をぬき出して構成した一つの普遍的な観念。同類のものに対していだく意味内容”
調べれば調べるほど、訳がわからなくなる。プロの先生方や知識人・文化人の方々は“概念”なる言葉をよく使われるが、本当に理解しているのだろうか。意味あいまいのまま、慣れで使っているのではと邪推したくなるほどだ。
こうなると私は、持ち前の独断と偏見でいかざるを得なくなる。
<要するに、風俗学の確立ということでいいじゃない>
それまでは風俗考証、風俗観察、風俗研究など別々に扱ってきたが、以後はまとめて<風俗学の確立>が、生涯最大のテーマになっていく気配がした。
そして、ふと子ども時代に思い馳せると、一つの言葉が浮かび出た。
<“風俗差別”か。いいぞいいぞ>
名古屋市近郊の町で小学生のガキ大将であった頃、私たちガキ集団は小川の水泳場を取り合って、隣村のガキ集団とよく喧嘩し、罵りあった。
「○○(隣村の名)のガェロ(蛙)、何食って肥えた。ガェロ食って肥えた」
相手がどんな罵りをぶつけてきたか忘れたが、お互いに食い物の違い、食風俗の違いで相手を差別し、馬鹿にし合ったことを思い出したのだ。
また戦前のことだが、ドンドンと太鼓を叩いて賑やかに読経する日蓮宗信者の家と、子守歌のように静かに読経する真宗信者の家とは、信仰風俗の違いから密かに反目し合い、お互いに娘を嫁入りさせるのは可哀想だとばかり、縁談が成立しなかったのを思い出した。
<差別の原点は、風俗の違いにあるのでは>
かくして風俗差別は、私の風俗学の一角を占めるようにる。
翌1978年(昭和53年)当時、私は『京の和紙』『西陣織』『明日の伝統工芸』など、京都の伝統工芸を紹介する記録映画や、船舶のスクリュープロペラ製作会社のPR映画、滋賀県議会を録画・編集してローカル放送の行政番組制作などを監督する傍ら、現風研の例会に顔を出し、風俗学の確立に思いを馳せた。
11月4日、第3回の現風研総会が新装なった京大会館で開かれ、桑原武夫会長が基調演説の中で、「一つ一つの現象を現代文明の文脈の中で考えるのが風俗学には必要だ」と強調された。
私は、私の風俗学に対する思いを言い当てられた気がして意を強くした。
そして総会後の懇親会で、その日に配布された年報『現代風俗’78』を手にして桑原会長から尋ねられた。
「辻さん、糞尿算て、そんな算術があったの?」
会長は、年報の「はがき報告」に、私の報告として掲載された「排便風俗雑記」の中に書いた糞尿算に目をつけられたのだ。
以下、排便風俗雑記の中から糞尿算の部分を転記する。
* * *
昭和25年敗戦直後、戦災で全ての本をなくしていた中学2年の私は、毎日のように名古屋の戦災による焼け跡を伝って参考書を探し歩いたが、ある古本屋で『数学大全』なる書物を見つけた。
喜び勇んで帰宅し、よくよく見れば、それが明治時代発行の算術を主とした、中学生には使いものにならぬしろもの。ガッカリしたが、その中に鶴亀算などと並んで糞尿算と称する項があったのが、奇異で印象的だった。
チッソや燐など各成分の価格を基準にして、人糞1貫目、尿1升の値段を割り出す算術だった。
* * *
糞尿算が縁になり、その後会長から、なんとなく目をかけていただいている気がし、自由に言いたいことを言わせていただいた。
翌1979年(昭和54年)度の第1回研究会が、1月13日、法然院講堂で行われた。
報告者は、文化人類学者の深作光貞奈良女子大教授をリーダーに8名。
テーマは「身体から出るもの――便and便所研究」だ。
第1部、日常的な「便文化」。第2部、「便」への関心と「羞恥心」。第3部、「便所」および「便」の未来学。報告がすすんで、最後は会員との質疑応答の部に入った。
すると驚いたことに、女性会員から「尾籠な話ですが…」とか、「不潔な話で恐縮ですが…」とか、「人前では、はばかれるような話ですが」などと、言い訳をいちいち前置きして「排便」や「便所」に関する自分の経験や見聞が、熱心に続々と披露された。その熱っぽさに清浄な法然院講堂の中が便の臭いで蒸すような雰囲気になってきた。
となると、大声を張り上げる映画屋の出番だ。私は「テスト!」「本番!」の要領で、会員席に号令をかけた。
「現代風俗研究会は研究会で、カルチャーセンターではありません。言い訳からはじめるのは止めて、研究者としての報告だけにして下さーい」
一瞬会場は唖然としたが、「そうだそうだ」と手を叩く人があって、会場は研究会らしい雰囲気を取りもどした。
手を叩いた人は、どうも鶴見俊輔さんらしかった。
(2014年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第76回「“わが原点とは?”の時代」 |
首相・安倍晋三さんよ。平和憲法に生きる日本をどうするつもりなんだい。
昨2013年12月、安倍内閣は「特定秘密の保護に関する法律」、通称「特定秘密保護法」を強行採決し、強引に成立させた。
おそらく安倍政権は、防衛、外交、スパイ活動などの防止、テロ防止など4つもの面から、自分らに都合の良いように特定秘密を指定し、漏らしたら罰してやるというわけだ。
先の軍国時代・戦争中に実施されていた防諜週間を思い出す。
怪しげな人影や、闇夜に光る鋭い目などの絵を背景に、「壁に耳あり、障子に目あり」とか、「第5列(敵方のスパイ)の恐怖」などの標語を重ねたポスターを授業で描かされ、町のあちこちに貼りだして、秘密を漏らすなと、小学生ながらも国の政策に協力させられた。陰気な記憶だ。
次いで、この連載自分史第76回の構想に取りかかった2014年5月、安倍首相は憲法9条で禁止してる「集団的自衛権」の行使に向けて、戦争のできる国へと意欲を燃やした。
平和憲法で培った非武装中立の頭がカリカリしていると、突然60年前の古い歌詞がバラバラに浮かびあがり、やがて1本につながった。
ラ・リベルテ/これこそ命/
けれど見よ/この浮き世は/法律や規則づくめ/
我らを待つは牢獄/ほんとにやりきれない/
人生美しく/出かけようぜ自由の/空気を吸うために/
自由が我がものなら/どこも酒と歌/恋の花開こうよ/
我らに自由を。
軽妙なタッチと風変わりなユーモアで有名なフランスの映画作家、ルネ・クレールが作ったトーキー初期の代表作『自由を我等に』の主題歌をベースにした替え歌だ。1953年(昭和28年)暮れに、私の参加してる学生演劇集団が公演した演劇の中で歌ったものである。
当時、私たち学生は戦後の自由・民主化をすすめる一方で、戦前への逆戻りをねらう復古的な動きを警戒し、肌をピリピリさせていたのだ。
3回生の私はアルバイトに忙しくて練習ができず、端役にしか出演できなかったが、歌だけは記憶の底に潜んでいたとみえる。
安倍首相の暴走が、沈澱している記憶の底を引っかきまわして浮かび上らせたのだ。
調べてみると、『自由を我等に』が生まれたのは1931年。私と同い年だ。
私は『自由を我等に』の替え歌をいただいて、今後の自分を象徴する歌に決定する。
その後、6月に入ると手術を重ねたり、体の不調もあって自分史を書きあぐんでいる間に、7月1日安倍内閣は憲法9条の解釈を変更し、強引に集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。
「戦争も知らない2代目3代目の政治家連中が、ゲーム感覚で火遊びにふけり、平和日本の屋台骨を揺るがそうとしているのが安倍内閣だ」
私なりに結論を出すと、青春を取りもどした後期高齢者よろしく『自由を我等に』を心の中でわめきながら、連載自分史第76回に取りかかることにした。
さて、前回の連載自分史第75回は、1979年(昭和54年)1月13日に行われた現代風俗研究会‘79年度の第1回研究会の<便所臭い報告>で終えた。
そして3月早々、私はある広告代理店からシリーズ30分番組の企画を頼まれた。KBS・近畿放送で制作・放映するものだ。私は日頃から考えていた企画を提案した。
「『21世紀への発想~京都で考える』と題し、識者・論客を京都の伝統・文化と対決させ、21世紀への生き方をグローバルに探る番組はどうでしょうか」
企画が採用されると、私は西陣織を題材にした番組の構成を頼まれ、西陣織会館によく出入りした。その度に玄関脇に建っている『村雲御所跡』の石碑が目に入る。かつてこの地にあった村雲御所・瑞龍寺は、格式の高い日蓮宗で唯一の尼門跡寺院。母が尋常高等小学校の高等科を卒業した後の一時期、この寺で尼僧となり、修行していたのである。
母の実家が不幸続きだったので、身内の誰かを仏門に捧げれば六親眷属(ろくしんけんぞく=一切の血族・姻族)が浮かばれるという俗信を、信心家の祖母が深く信じたからだ。
しかし母は還俗(僧籍から離れ、俗人に還ること)して結婚し、私を産んだ。
母の話では、実家の跡取りである弟がまだ幼いので、一人前となるまで面倒をみるために還俗したということだった。
そして私の最初の記憶は、川に溺れたことだ。4歳の頃の初夏、母や祖母に無断で野良へ出かけ、タンポポやレンゲの花を摘んでいるうちに、突然天地がひっくり返った。幅約2メートル、深さ約1メートル半ほどの田に水を引くための用水に落ちたのだ。流れの速い水中をもがきながら流されるうちに自然と浮いて流れ出しだし、土手の草をつかんで危地から自力で脱出できた。
この経験を生まれて最初の偶然として、私はいつからか「人生は偶然の積み重ね」と意識するようになった。
しかし私には、川で溺れた偶然より前に、偶然の原点に当たる“大偶然”なるものがあったのだ。
私は西陣織会館へ出入りする度に、玄関脇の石碑に彫られた『村雲御所跡』の文字に気を引かれ、母の還俗に疑問がわいてきた。
幼い弟の存在を承知の上で、母は六親眷属を救うため、一生を僧籍で生きる覚悟で尼僧になったはずだ。それが、どうして弟のために還俗したのか、私には解せなかった。
京都の遠い親戚に当たる寺から、尼僧時代の母を知る住職さんが、母の年忌にお経を上げに来てくれていた。その住職さんに、私は機会あるごとに母が還俗した理由を確かめたが、母と同じような説明しか得られなかった。
そして西陣織会館の『村雲御所跡』の石碑に接するようになり、改めて母の還俗理由を電話で尋ねたが、返事は同じだった。
しかし数日して、住職さんから電話がかかった。
「辻さんがあまりにも熱心だし、私も老い先短いから、生きているうちにお母さんのことを伝えておかねばという気になりました。……驚かないでくださいよ」
母が尼僧になった数年目、尼僧たちを取り締まる最高位の尼僧が寺の執事と抱き合っている現場に偶然出くわし、その日のうちに僧籍を解かれ、実家へ返されたとのことだった。
住職さんの話によると、私は他人の情事がきっかけで、偶然に生を得ることになったのだ。
この偶然を、私は愉快に受けとめた。
母はときどき尼僧時代の話を聞かせくれたが、その度に「清明さん」のことを話題にした。清明さんは執事の子息で、寺によく出入りしたらしい。当時の旧制第三高等学校の生徒で格好良かったとのこと。母は清明さんに憧れていた感じがした。私の名前・光明を清明さんにあやかって、母は名づけたようだ。
後に清明さんは、行政学・政治学者となり、『日本官僚制の研究』で名を成し、やがて文化功労者となる。若い頃、私はどこまで清明さんにあやかれるかと考えることもあった。
しかし私は、わが道を行くのである。
(2014年8月記)
⇒ 目次にもどる
⇒ 目次にもどる
■過去ログ