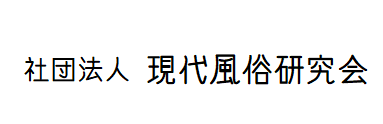| 第31回「“上洛早々、いきなりくじかれた出鼻”の時代」 |
「いよいよ新聞記者になれる!」
1954年4月末、転居先の都合で先発した母を追い、意気揚々と京都へ旅立った。
「織田信長が足利15代将軍義昭を従え、天下統一を狙って上洛したのは何歳のことだったろう? 今のおれよりは年取っていたはずだが、……」
車中でいろいろ考えた。
「国や社会の正邪をただすには?……真のジャーナリズムとは?……」
この年は、年頭から揺れ動いていた。正月、一般参賀の皇居で大混乱のため多数の死傷者発生。3月、マグロ漁船第5福竜丸がビキニ環礁の米国水爆実験により死の灰を浴びる。革新勢力の反対運動にもかかわらず、アメリカへの従属を深める日米相互防衛援助協定成立。犬養法相の指揮権発動により、自由党幹事長・佐藤栄作の造船疑獄容疑を闇に葬るなどなど。
しかし、目ざす京都は府知事も市長も革新。第2の故郷とするのに不足はなかった。
京都へ着くと、意気込んで夕刊新聞社へ直行した。新聞社は烏丸通りから東へ入った御池通りに面していた。社屋は、さほど大きくない木造モルタル造りの2階建て。表の掲示板には、その日の新聞が貼りだしてあった。つまらない記事で埋まる新聞面に失望したが、気を取り直した。まあ映画欄の刷新からでも始めさせてもらうか。
応接間で、母の知人の弟という編集長が会ってくれた。新聞づくりに対する意向を聞かれるままに話していると、編集長が温厚にさえぎった。
「うちの新聞は八百屋や魚屋のあんちゃんが相手の新聞やから、あんたのような立派な考えの人には向かんと思いますよ」
体の良い断りだった。「古い価値観をぶっ壊してやる」と出立したあやかり信長は、上洛早々あっさり出鼻をくじかれた。こんな新聞、こっちから払い下げだ。次のチャンスを待つことにした。
その夜から通称村雲御所、堀川今出川の西陣織会館の地にあった瑞龍寺での部屋借り生活が始まった。
村雲御所は尼寺で日蓮宗唯一の門跡寺院。豊臣秀吉の姉が秀吉に切腹を命じられた息子秀次の菩提を弔うために建てた寺である。代々有栖川宮や伏見宮、そのほか皇族・華族などの女子が九条家に入籍した後に入寺する習わしになっていた。母が仕えた門跡さんも、某子爵家の女子だったが九条公爵家の養女として入寺していた。
明治から大正にかけての先代門跡は、伏見宮の皇女。そのため当時の京都では最も格式が高かったが、休む間もなく全国を行脚して信者を増やし、村雲婦人会や尼衆修道院を設立するなど寺院経営のために尽くし、絶大な尊敬を集めたことで知られている。
やがて私が就職することになる大映の永田雅一社長の母堂が、村雲婦人会の会員だったそうで、「村雲さんにいた人の息子さんだったら」と、私の就職を取りもつ一因にもなった。
母の仕えた門跡さんは、知る人ぞ知る美貌が災いしたのか僧職におさまりきれず、村雲婦人会の解消に追い込まれたり、中国戦線への慰問文で知り合った元兵隊と情事の噂が立つなどして日蓮宗身延派の僧籍をはずされていた。私たちが入居した当時の寺はさびれていたが、門跡さんの気位は高く、因習的な格式を維持していて、私たち庶民は表門の通行が許されず、扉が開いていても脇の小さなくぐり口を出入りさせられた。このことは大変な屈辱だったが、この際忍ばざるを得なかった。私に反して、母は実家を継ぐ弟との確執を逃れた解放感からか、私の就職が決まらなくても活き活きと、楽しそうに門跡さんの世話する尼さんを手伝った。
借りた部屋は襖と障子に囲まれて昼も暗い。私はせいぜい街へ出て土地勘を養うことにした。 そんなある日、京都市美術館へ展覧会を見に入って、観覧者の風体に驚いた。名古屋の美術展であれば、粋にベレー帽を被ったり、コールテンのジャケットやコートを着たりして、いかにも文化人、美術愛好家でございといった人が多かった。しかし京都では、ジャンパーやナッパズボンに雪駄草履を履いた一見労働者風の人たちが目についた。後で聞けば、京都の美術展には西陣織や友禅染など伝統工芸の職人さんたちが多く見に来るとのこと。京都は職人の街でもあったのだ。戦時中に名古屋近辺で聞いた京都の兵隊が弱い理由が類推できた。京都では兵隊の階級より、職人の腕前が高く評価されていたに違いない。京都の兵隊は弱くて良いわけだ。
そうこうしているうちに、門跡さんをよく訪ねてくる小母さんから私の就職を世話したいと申し出られた。小母さんは、身延派でない宗派の日蓮宗本山寺院の布教師で、そこの管長さんに引き合わせたいとのこと。訪ねた管長さんは永田大映社長の幼友達だった。
「私は社長もお袋さんも両方よく知っているので、どちらにコネをつけたらいいのかわからない。あなたが決めて下さい」
何かが突き動かすように、私の答えは即座に出た。
「そりゃお袋さんです。私はお祖母さん子ですから、お袋さんの方にお願いします」
数日後管長さんから知らせを受けて、下賀茂の永田邸を訪れた。社長の母堂は足腰立たずの長期療養中だった。永田母堂は上体を起こしたり寝たりしながら楽しそうに語らってくれた。
「あんたはんのようなお顔だったら、俳優さんにおなりやしたらどうどす」
「いや、私は助監督になりたいのですが」
「そうどすか。もったいないことだけど、あんたはんのようなお方が助監督さんにおなりやしても、まあええことどすわなあ」
母堂は話し相手がほしかったのか、自分が足腰立たなくなった原因は、若い頃から信仰のあまり水垢離をしすぎて腰を冷やしたからで、「信仰もほどほどにしないといかんことどすなあ、オホオホ」と自嘲気味に笑って打ち明けるなど、話が弾んで2人は時の経つのを忘れた。帰りがけの私に、母堂は嬉しい言葉を投げかけてくれた。
「お母はんが村雲はんにおいやした方だったら、そそらには出来しまへん」
捨てる神あれば拾う神あり。天下は広いのだ。統一は無用。おれだって、自分が統一されることは嫌いなはずではなかったか。私は運を天に任せ、母堂を信じることにした。
1月ほどして、門跡さんが私に苦情を抱いていると尼さんから聞いた。絣のような下賤の着物で廊下を歩かれるのは困るというのだ。絣が何で下賤だ。年甲斐もなく、おれをまぶしそうに見てポッと顔を赤らめるくせに。まだ修行が足りないのだろう!
翌日遠縁に当たる松ヶ崎の日蓮宗寺院に移転し、本堂の1室を貸してもらうことが出来た。
8月に入っても、いっこうに母堂からの知らせが来なかった。心配した母は、私が行かなくてもいいというのに京極の高島易断へ行き、見料を始末して私の生年月日からだけの占いを見てもらってきた。それによると、すごいコネがついているから11月には必ず就職でき、私は看板絵描きでなく本当の芸術家になる大器晩成型だが、金には恵まれないとのことだった。必ず就職できるとの占いが出て安心したのか、母はよく眠った。
そして9月の下旬、永田母堂から京都撮影所の所長に会いに行けと知らせが入った。2日ほど前、母堂はなぜか体調が良かったので、撮影所に祀ってある稲荷神社へお参りに行き、そのついでに私のことを所長に話してきたというのだ。その翌日から再び母堂の足腰は立たず、そのまま8年ほど亡くなるまで続いた。奇跡が生じたのだ。私には見えない、何か大きな流れに運ばれているのを体に感じた。チャンスに接近しつつあるのだ!
(2006年1月記)
⇒ 目次にもどる
| 第32回「“掴んで放すな、チャンスの前髪!”の時代」 |
子どもの頃から、私には誰からともなく教え込まれた言葉がある。
「チャンスには後髪がない。後からは掴めないぞ」
1954年9月下旬、永田大映社長の母堂から京都撮影所の所長に会いに行けと知らせを受け、直ちに撮影所へ急いだ。庶務課の女性社員が出迎えてくれた。
「所長は東京本社へ出張中ですが」
「えっ!いない?」
「今月いっぱいは、帰らないと思いますが」
来月までには数日ある。待つには長すぎる。翌日考えに考えた。長引く失業状態を解消したい焦りが、限りなく疑心暗鬼を生む。
《所長は居留守を使って、いい加減にあしらったんだ。そうはさせないぞ》
翌朝、嵯峨の所長宅へ直行した。
「主人は昨夜帰ってきて、いま撮影所へ出かけたところです」
《勘が当った。ついてる!》
撮影所で受付を通すと、所長が会ってくれた。
「君のことは社長のお袋さんから聞いているが、確か助監督志望だね。丁度いい。いま総務部長が助監督募集を進めているはずだ」
所長室へ呼ばれた総務部長が言った。
「ぼつぼつ募集を打ち切ろうと思っていましたが……。それじゃこの人を最後にして、来月早々入社試験を行うことにしましょうか」
かくして私は、辛うじてチャンスの前髪を掴むことが出来た。
10月初旬、筆記試験が行われた。4人募集のところへ応募者は百数十人。大中小の3部屋に詰め込まれた。
最初は時事問題の解答。かなり多く出た問題の中で、“モーテル”という言葉だけが解けなかったことを覚えている。当時は、我が国で初めて日産自動車が大衆向けの小型乗用車・ブルーバードを売り出した直後で、マイカー時代が始まろうとしていた頃だ。車好きならいざ知らず、今に至るまでマイカーに関心がない私には、どだい無理な問題だったのだろう。
次は映画評論。反ファシズム・反体制の姿勢で定評のあるリベラル派監督フレッド・ジンネマンと、彼が監督した戦争映画について書いたことだけを記憶している。どんな映画だったのか。戦争中から日本の帝国軍隊や戦争に批判的だった私のことだ。恐らく『地上(ここ)より永遠(とわ)に』を取り上げて書いたものと思われる。この映画は日本軍の真珠湾奇襲を背景に、初めてアメリカの軍隊生活に鋭くメスを入れた作品だ。前年の1953年に、作品、監督、脚色、撮影など数多くの部門でアカデミー賞を受賞していた。
最後はシナリオの創作だった。花瓶だか、バラの花だか、指定された小道具を使って1場面のシナリオを書かされた。入社して最初に付いた加戸敏監督が、「君のシナリオが一番よかった」と誉めてくれたことを覚えている。
この頃、『山椒大夫』でベネチア映画祭銀賞を受賞したばかりの溝口健二監督が、芸術祭参加作品『近松物語』を制作の最中。撮影所全体に創造的な活気が満ち溢れているようだった。
後日、受験者を15人ほどに絞って面接が行われた。
大会議室の一方に監督や先輩助監督など10数人がコの字型に居並び、3方から次々と質問を浴びせてきた。たいていの質問にはしっかり答えたつもりだが、以下は冷や汗ものだった。
「君の支持する政党は何党かね?」
「とくに支持する政党はありませんが、強いて言えば共産党です」
「それでは、知っている共産党員の名を上げてみて」
「徳田球一、それから……」
幸か不幸か、緊張していたのか、どうしても他の共産党員の名が出てこなかった。
「どんな映画を見てるんだね?」
「主に外国映画です」
「大映の映画は?」
「……、ほとんど見ていません」
大映映画は、題名すら思い浮かばなかった。
さらに日をあけて、身体検査。受験者は5人になっていた。いつしか仲間意識が芽生え、「この中で1人、落ちるのは君かな?僕かな?」と、冗談まぎれに探り合って別れた。
その翌日だったと思うが、永田母堂から至急の呼び出しを受けた。身体検査の結果、私の胸部レントゲン写真に陰があり、結核にかかっているようだから落としてもいいかと、労政課長が電話で了解を求めてきたとのことだ。
「あんな元気そうなお方がそんな馬鹿なはずがない。私が直接お尋ねするよって、と返事を待たせているのどすが、あんたはん、どうどすか」
母堂は私の健康を確かめると、直ちに病床から電話で労政課長に通告された。
「辻さんのような苦労したお方を、ええ加減なことで落としてはなりまへんぜ」
数日後、11月からの採用通知を持って、永田母堂宅へ報告とお礼に伺った。母堂はことのほか喜ばれたが、強く念を押して頼まれた。
「女優さんには、くれぐれも手え出さんとおくれやっしゃ。お頼(たの)申します」
2,3年ほど前に世話して入れた助監督が、女優にうつつを抜かして仕事をしくじり、面目をつぶされたことがあったというのだ。
私は就職が決まると解放されたように、まだ不慣れな京都の街をさまよって探索した。
そして初出社の前日、花街先斗町の狭い路地に迷い込み、ふと前方に気づいて驚いた。所長が2人の舞妓に挟まって近づいてくる。今さら逃げようがない。私は体をすぼめて脇へと寄って行き、舞妓の肩と触れあうようにすれ違った。知ってか知らずか、所長は女性たちと談笑を交わしながら過ぎ去った。
翌日、新入り助監督全員で所長室へ挨拶に出向いた。《昨日は悪いとこ見ちゃったかな》と、私は緊張気味だったが、所長は役者が1枚上だった。先斗町とは打って変わった真面目くさった顔で、厳かに訓示した。
「健全なる精神から健全なる芸術が生まれる。諸君はそのつもりで仕事に専念してほしい」
《健全なる芸術とは何ぞや》と考えながら、次いで総務部長へ挨拶に行くと、部長は私だけを残して怒鳴った。
「どこのどいつかわからんお前はな、わが社にとってどうでもええ奴や。試験の成績は2番やったが、入れたのは永田のお袋さんのお陰だちゅうことを忘れるなよ!」
私と共に故郷を捨てて京都へ脱出してきた母を思うと、こんな脅しにへこたれてチャンスの前髪を手放すわけにはいかなかった。
《入社試験の成績が2番だったら、コネもくそもあるか!》
(2006年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第33回「“撮影所に迷い込んだ感じ”の時代」 |
「どこのどいつかわからんお前はな、わが社にとってはどうでもええ奴や!」
私は、思いもよらず劇映画の大映京都撮影所に就職が決まり、今後どうすれば会社のために働けるかといささか緊張気味だったが、出社早々総務部長に怒鳴られて意外と気が楽になった。
「そっちがそっちなら、こっちはこっちで自由にするわい」
総務部を出た廊下で、パイプに火をつけ気分転換。当時は余程のことがないかぎり、喫煙はどこでも自由だった。一息ついて製作部長へ挨拶に向かう。パイプをくわえながら製作部のドアを開けると、居合わせた社員がいっせいに振り向いた。パイプをゆっくり胸のポケットに差し込みながら部長に近づいていく。ぼそぼそと囁き合う声が聞こえる。
「あれ誰や?」
「松竹の重役と違うか」
私は学生時代から着古した黒サージ製で上下揃いの背広を着ていたのだ。
社員たちの囁きを背に受け、新参者らしからぬ自分の老けた顔を自覚しながら製作部長への挨拶をすますと、私は助監督部の控え室で待っていた3人の同期生と合流した。
遅れた理由を問われ話し合っているうちに、それぞれ他の3人にも、大監督の溝口健二、伊藤大輔、文豪谷崎潤一郎のコネがあったことを知った。3人のコネは、いずれも当時の大映にとって重要な、総務部長の力の及ばないものばかり。総務部長はあらかじめ自分を含めて各コネを配慮し、4人の採用者を心づもりしていた。そこへ私が、社長の母堂をコネに最後の応募者として割り込んだため、総務部長は自分のコネを切り捨てる羽目に追い込まれたんだ、とみんなで推察した。前々から撮影所に出入りしていた事情通の溝口コネや伊藤コネによると、ワンマン社長といえども絶対頭が上がらないお袋さんの存在は社内で周知のことだった。
「君の勝ちや。総務部長が怒鳴るのも無理ないぜ、辻くん」
1954年11月、前途が思いやられる入社となった。
当時の大映京都撮影所は、所長室や総務、経理、企画、製作など事務系各部が入っている総合社屋など、正門から見える限りの建物はモルタル造りの当世風だった。しかし、その奥には3棟の古びた板張り木造ステージを囲むように、同じような安っぽい木造家屋が混み合って建ち、助監督部や装飾部、照明部など多くの部署に割り当てられていた。
薄暗い飯場のような助監督部屋を出て、幹事の案内で各部署を挨拶回りしている合間に、ずっと裏の方には3棟の大きなコンクリート造りのステージが建ち並んでいることを知ったが、スタッフの居住区として中心部を構成するうらぶれた建物群、その周りに所狭しと雑ぱくに置かれた廃材や壊れた作り物の数々を目にして、私は初めて接する撮影所の雰囲気に気が滅入った。
しかし、人々は実に生き生きと動き回っていた。あたかも、近松門左衛門原作『大経師昔暦』を脚色し、後に名画と評価される溝口監督作品『近松物語』が、追い込み撮影に入っていたのだ。幹事の許しでステージへ見学に入り、もの静かに厳しく張りつめた撮影状況に、息をのむ。
《所長が訓示した「健全なる精神から健全なる芸術が生まれる」とは、このことか》
気を取り直すよりほかになかった。せっかく就職できた撮影所だ。
当時撮影所では、1作品にチーフ、セカンド、サードと3人の助監督がつき、私たち新入りは使いものになるまではフォースとして配属された。チーフはステージを出入りして、制作スケジュール全体の段取りを受け持つ。セカンドは撮影現場に密着し、監督の演出補助と予告編制作。サードはセカンドの補助や俳優の衣裳・持ち物の点検など、もっぱら撮影進行の円滑化に努める。
最初に就いたのが正月番組として撮影中の加戸敏監督作品『怪猫逢魔が辻』。嫉妬によって惨殺された女歌舞伎人気役者の飼い猫が、主人に化けて復讐する話だ。
「おーい、そのライト、もっとあっちやあっちや!」
「助監督さん、タンスの位置変えるから手伝ってくれや!」
その騒々しいこと。溝口組の撮影に比べて、えらい違いだった。
《これも「健全なる芸術」のうちか? おれは、新憲法に基づいた、新しい哲学や思想を盛り込んだ芸術を求めて撮影所へ入ったのに、義理人情に絡んだ、単なる勧善懲悪ではないか》
コネを通じて撮影所に出入りしていた他の同期生と違って、私は全くの初心者。助監督は何をすべきか見当もつかない。「判るまで見ていなさい」という監督の後ろに立って見学していると、監督が見上げた。
「その服装では仕事にならないね」
なるほど。松竹の重役に間違われる服装では、埃まみれのセットでの動きがとれない。仕事を終えると飛んで帰り、部屋借りしている寺の近所を走り回ってジャンパーや作業ズボンなどを調達した。私たち母子の持ち金は5千円を切ってしまった。飛び出した母の実家に借金するのはシャクだ。寺の電話を借り、高校の恩師イングリット・バーグマン先生にSOSを発した。
翌日から監督の後ろに立ち、時々パイプをくわえながら見学していると、3、4日して監督が声を上げた。
「君はかなり苦労してきたと聞いたが、苦労が全然身についていないようだね」
監督は、すでに他の同期生が助監督として使いものになっていることを知っているに違いない。気疲れして帰ると、バーグマン先生から2万円届いていた。私の初任給は7200円。ほっとすると意欲がわいた。その気になったら飲み込みは早い。先輩の見よう見まねで「テスト!」「本番!」と声を上げ、カットが変わるごとに小道具を除けたり、元へ戻したり、畳を掃いたり、廊下や柱を磨くなど、小道具さんや大道具さんを助けて、少しでも撮影がはかどるように立ち働いた。
いずれにしても助監督はエリートのうちだ。新入りは会社の将来を担える人材になれるかどうか値踏みされたり、少しのことで虐めの対象にもなった。当時、力仕事の照明さんや大道具さんは荒っぽかったが、私は老けた容貌とがっちりした体格が幸いしたのか、大した虐めには遭わなかった。スタッフの多くは年下かと思っていたら、ほとんどが年上だった。年頃のはっきしりしない社会だと驚いたことを覚えている。
それでも最初の頃はよく迷わされた。
「助監督さん、涙が足らん、取ってきてえ!」
「はいーッ!」
助監督は迅速を旨とする。ステージの小さな潜り戸を飛び出す拍子に頭を打ったり、体をぶっつける。涙なんてどこにあるか判らない。取りあえず小道具部に駆け込む。
「涙?ここは小道具や。そんなもんあるかい!」
「どこにありますか」
「知るかい」
走り回った末に、涙は目薬のこと。メーキャップを担当する美粧部に用意されていることが判る。 大宴会の場面で、カメラ近くのお膳には小道具さんが本物の刺身や“つま”を盛りつけるが、遠くのお膳の盛りつけを手伝えと、薄切りのこんにゃくと細削りの鉋屑を渡される。
「これ何?」
戸惑いながら小道具さんに見ならって盛りつけすると、あら不思議。ラッシュ(未編集のポジフィルム)試写では、俳優さんの演技で本物のように見えた。
そして、大変な失敗が待ち受けていたのである。
(2006年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第34回「“M的+W的”の時代」 |
《人間商売カラリと捨てて、ゴビの砂漠で野垂れ死に》
敗戦後のいつからか、私の脳裡に中国大陸を横断してゴビ砂漠を目指す自分の幻影が焼きついた。心の隅に、中国人に対する懺悔の気持ちがこびりついているからだ。
小学3年生から4年生にかけての一時期ではあったが、南京攻略戦に参加した復員軍人から「戦地では強姦強盗、どんなことでもやりたい放題だ」という体験談に触発されて、戦争に行けば自分も中国人婦女子を暴行できるのではと、猟奇的な欲望にとらわれた。当時の私は教育勅語の教えどおり、「一旦緩急アレバ義勇公ニ報ジ」る「朕ガ忠良ノ臣民」として、熱烈な軍人志望者だったのだ。
しかし5年生になったとき、古事記や万葉集を読むことによって神々や、その子孫に当たる古代天皇たちの性風俗を知った。
「大人たちは何を考えてるんだ。天皇を神さまとあがめているが、ただの人間じゃないか」
私は天皇崇拝から脱落し、忠義の呪縛をはずして「軍人志望は止めだ」と非国民化し、中国人婦女子に暴行を欲望した記憶は、忌まわしい記憶へと変化した。
1954年4月末、故郷清洲から脱出する思いで西方へ向かう京都移住に重ねて、密かにイメージしていたゴビ砂漠行きは、11月、大映京都撮影所の助監督に就職が決まって取りあえず中断。“ゴビ砂漠で野垂れ死に”なんて、私のような者に実行できるわけはないが、生意気にも中断は心残りとなって今に続き、時々の考え方を左右する。
私が最初についた加戸敏監督作品『怪猫逢魔が辻』は、正月映画として撮影が進行した。封切り日は12月29日。その10日前か1週間前には完成していないと、大量にプリント現像して全国の封切り映画館へ配給する間がない。また封切り前には、マスコミやフアンの間に宣伝効果を盛り上げるため、各地で少しでも多くの試写会を開く機会が必要だった。
しかしお化け映画には、お化けをいかに怖く見せるかという仕掛けや工夫がいろいろあって、撮影に手間がかかる。遅れがちになるスケジュールの中で、記憶に残る場面の撮影がやってきた。雨が降る夜の荒れ土塀が続く道で、化け猫が悪役を翻弄する場面だ。
撮影は、化け猫が悪役の行く手をさえぎるために、土塀の壊れ目からフワリと飛び出すカットから始めることになった。
雨降らしは効果係の役目だ。画面の奥の雨は、天井に吊り渡した鉄パイプに水道をつなぎ、無数にあけた細い穴から水を雨のように噴出させる。カメラ前の雨は、直接効果係が水道ホースの口に指先を当てて、ホースから噴出する水を巧みにさえぎり、カメラ横から画面内へ雨のように飛散させる。技を要する撮影所ならではの技術だ。また雨にリアルさをつけるため、カメラ横から扇風機で風を送る。扇風機の操作は電気に関係するので照明係だが、主に手空きの助監督に任される。風の送り方が気にくわないと、撮影技師や監督からどやされる。
「もっと風の気持ちになるんだ!」
その日、私はカチンコ打ちを任された。この撮影所では録音係がカチンコ打ちを受け持つが、雨や風、高速度撮影などがあってシンクロ撮影ができない場合は録音係が現場につかないため、カチンコは助監督が打つことになっていたのだ。
一応準備ができると、撮影技師がカメラを覗き、雨風のテストを行う。同時に照明技師は、雨が効果的に表現できるようにライトの当たり具合を調整。そして準備OK。監督が準備中に出役と打ち合わせを済ませていたのか、撮影はテストなしのぶっつけ本番となった。先輩に合わせて「本番!」と声を張り上げ、ふと土塀の割れ目を見ると、いつもの女役者からメイキャップを変えて、初めて化け猫に扮したヒロインが現れた。その化け方の見事なこと!
ヒロインの入江たか子も、悪役として共演する板東好太郎も、私が幼少年時代に絵本の1冊として繰り返し見ていた、スターのグラビヤ写真集を飾る若手の美貌スターだった。それから凡そ20年。2人は若い頃の人気が衰え、お化け映画の常連役者になっていた。
一方、加戸監督は化け猫映画の成功で時代劇作家の地位を確立したという。
人それぞれに移り変わっていく人生に感慨を抱きながら化け猫に見とれていると、みんなが私に向かって怒鳴っている。雨音や扇風機の音が大きくて何を言われているのかわからない。戸惑っていると、監督はカメラを止めさせて言った。
「これで君の月給は、ぱーだ」
監督の「用意、スタート」でカメラを回したが、私がカチンコを叩かないので演技が始まらず、その間のフィルムが無駄になったというのだ。その上、化け猫がフワリと飛び出すスローモーション効果を出すため、カメラの回転を3、4倍ほど上げていたのだ。私がぼやっとしていて無駄になったネガフィルムは300~400フィート。当時ガフィルムは、1フィート当たり15円前後とのこと。300フィートで約4500円。私の初任給7200円の半分以上が吹っ飛んだわけだ。入社早々、フィルムの大切さを教え込まれた。
化け猫映画のクライマックスは、殺されたはずの女役者がニタリと笑うと、見る見るうちに口は耳元まで裂け、顔はおどろおどろしい化け猫に変貌。ものに戯れる猫の手振りで目に見えない神通力を働かせ、逃げる敵を引き戻してきりきり舞いさせる。
こういう場面には、音楽ダビングで必ず〈チャンリン〉と称する和楽を入れるのが、化け猫映画の常道になっていた。「チャチャチャンリン、チャンリン、チャンリン」と聞こえるお囃子の繰り返しに乗って、敵は操り人形のように操られる。弱ったところで首根っこをガブリと噛み切られ、観客は溜飲を下げるというわけだ。
この映画には、その夏『花の白虎隊』で市川雷蔵と同時にデビューした勝新太郎が、白塗りの2枚目で出演。ステージの隅で出番の合間に、当時の大スター・長谷川一夫の演技を器用に真似してみんなを笑わせていたが、まだパッとしない存在だった。勝は1960年製作の森一生監督作品『不知火検校』で独自の芸域を開拓するまで、雷蔵をライバルとして苦悩することになる。因みに、当時雷蔵の出演料は35万円、勝の出演料は5万円とのことだった。
ところで仕事は、残業に次ぐ残業。完成間際になるとスケジュールが立て込んで、夜間オープン撮影、タイトル撮影、残部のアフレコ、効果音入れ、音楽取り、ミックスダビングなどと徹夜もどきが続く。その間先輩たちは要領よく休むが、新入りの私は要領がわからず、意欲と負けん気で仕事の全部にタッチ。「君はすごいね」と監督にほめられた。おかげで12月分の給料は17000円。当時大学卒の初任給は1万円前後。私は残業代で友人たちを追い越したわけだが、残業は200余時間に達していた。
さて1作品終わって、ふと気づいた。「何か変だ」
新米助監督はまわりのスタッフから何かと偉そうに小突き回され、出した指示に剣突を食わされる。入社時にどこかの重役かと錯覚された私から見ると、最初のうちは彼らが皆若そうに見え、年下が何を言うかと腹が立った。しかし、実はほとんどが年長者だとわかってくると、割合に「はい、はい」と従えるようになった。次第に、小学校時代から腕白・硬派として保持してきたM的要素がたわめられ、W的要素が増えて細胞を変質させていく気がして、一種の生理的な困惑を感じたこともあったが、やがて両要素がこんがらがって、現在見られるややこしい人間が形成されていったようだ。
(2006年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第35回「“新米助監督が歩くのは、ジグザグ道”の時代」 |
1954年12月、正月作品『怪猫逢魔が辻』を済ませた私が、休む間もなくフォース助監督としてつくことになったのは、準備段階を終えてクランクイン間際の長谷川一夫主演、三隅研次監督作品『七つの顔の銀次』だった。
時代背景は明治の中頃。紳士、書生、着流し姿の粋人などと、7つの顔を持つスリの名人・仕立屋銀次が運命の金時計を狙う、スリルに満ちた人情と恋の物語である。
封切り予定は翌年2月中旬。製作スケジュールが年末年始の休日をまたぐので、年内に少しでも撮影を進めておこうと、あわただしくクランクインした。しかしフォースの私は準備段階から加わっていないので、スタッフ会議でどのような打ち合わせがされているのかわからない。監督やチーフ、セカンド、サードなど先輩助監督が指示する使い走りや衣裳点検、小道具点検などで、いろいろ戸惑うことになった。
例えば監督や先輩の意を受けて小道具係へ走る。
「小道具さん、この徳利では雰囲気が出ないと監督が言ってますが」
「今ごろ何言っとんだ。打ち合わせでちゃんと決めてたんやないかと、そう言うたれ」
「辻くん、そんなことで引き下がってきたら駄目やないか。打ち合わせた後でも、監督の希望が変わることはよくあるんだ。相手を監督の意に添うようにさせるのが助監督の腕だよ。よし、わしが行ってきたる」
ほどなく先輩が2、3種類の徳利を手にして戻ってくると、監督を囲んで和気あいあい。「ほんなら、この徳利でいこか」と、撮影が進行する。私は疎外されている感じだが、いわゆる新米いじめとは、どことなくニュアンスが違う。やがて彼等から誘いが来た。
「三隅グループに入らないか。この京都撮影所では、これから伸びるグループやで」
確かに三隅監督は、同年代の間では成長株に思えた。ところで私は、少年時代から組織に束縛されて自由を失うことが何より嫌な性格である。本心を伏せ、「入社したばかりで、まだ所内の事情がよくわからないから、今のところは」と、彼等の親切心らしきものをやんわり断った。
入社して2ヶ月にもなると、社員(月給)監督や助監督が所属する監督室の事情がわかり、師弟関係の流れが何となく飲み込めてくる。師弟関係の流れは大別して、伊藤大輔・森一生・田坂勝彦の系統、溝口健二・弘津三男の系統、稲垣浩・安田公義・天野信の系統などがあり、三隅研次は衣笠貞之助の系統で、三隅グループはその仲間を増やそうとする新興勢力の感があった。
同期の新米助監督4人のうち、伊藤大輔コネは伊藤大輔・森一生の仕事を中心に、溝口健二コネは溝口健二の仕事を中心にそれぞれ配属され、谷崎潤一郎コネと社長母堂コネの私は必要に応じて使い回されることになる。
その後も三隅グループから、機会あるごとに勧誘された。その一環なのか、セカンドが役立つ助監督として認められる秘訣を教えるという。
「撮影準備の間に、紙くずか何か写っては困るものを見逃しそうな場所に置いてくんだ。本番で監督が用意スタートと言いかけたところで、ちょっと待って下さい!と声を張り上げ、走り出てそれを取りのけ、はい本番どうぞとやったら、みんなが一目置くこと間違いなしだよ」
私は「そんな見え透いたことは出来ません!」と言下に拒否したが、策士の彼は数年後、重いノイローゼにかかって廃人になってしまった。
年明けて1955年。正月気分を取り払い、『七つの顔の銀次』の撮影はクランクアップに向けてスピードを上げた。撮影現場の雰囲気もあわただしくなり、殺気立つ瞬間が目立つようになる。そんな頃、ステージ内でのことだった。次のカットを撮影するため、カメラアングルを変えて照明の準備中、天井に吊った照明の足場から高峰三枝子に罵声が飛んだ。
「こらチョウセンジン!動くな!」
《革新府政を支える労働組合の職場に、こんな言葉が生きているのか》と、先が思いやられた。
おそらく高峰は照明を当ててもらいながら、他の出役かスタッフとおどけていたのだろう。じっとしていないため、その照明係は方向を定めて器具を固定できず、怒りを暴発させたに違いない。当時高峰は、韓国人系と思わせる容貌から「チョウセンジンだ」との噂があったようだが、例えそうであっても非道すぎる。高峰の反応は記憶にないが、伝統的な筑前琵琶宗家の娘として、案外けろっと受け止めていたのかも知れない。
そしてある日、私がセットへ行く途中の便所で小便しているときだった。
「辻やん、お前ええ体してるなあ。きっと強いやろ?」
後ろから私の肩をなでながら、長谷川一夫が横に並んで小便をはじめた。以来長谷川さんとは冗談が言い合える仲となった。
終業後の風呂で体を洗っていると、長谷川さんは寄ってくる。
「お前は、ほんまにええ体してるなあ」
「気持ち悪いから、そばへ寄らんといてください」
さすがに長谷川さんも、裸の私には触ろうとしない。離れて体を洗い出す。歳を数えてみると、長谷川さんは亡父より年長だ。最初私は同性愛嗜好かと警戒したが、長谷川さんの方は、息子の林成年と同い年の私を息子のように思っていたのかも知れない。
この仕事中にあったことで、印象的に覚えていることがある。
「辻くん(長谷川さんは、真面目な場合は“くん”。親しさの場合は“やん”と使い分けているようだった)、鎖につながった懐中時計は、こやってスルんやて」
長谷川さんは本職に教わったと言いながら、人差し指の先で中指の背に渡した鎖を一瞬に押し切り、その2本の指で時計を挟んでスリ取る技を、セットの隅でやって見せてくれた。真似ごとでは鎖を切ることは出来なかったが、俳優はかくあらねばと長谷川さんの研究心に感銘した。私は今も時々思い出し、人差し指の先で中指の背をこすっている。
この後私には、溝口監督・市川雷蔵主演の『新・平家物語』のような芸術作には縁がなく、『鬼斬り若様』、『踊り子行状記』、など義理と人情、勧善懲悪、若く明るい恋をテーマにした〈健全なる芸術〉作品が続いた。
『踊り子行状記』では、富士山を背景にした御殿場ロケを初めて経験。往きの普通夜行列車で小道具係が酔っぱらい、名古屋当たりで床に転がり落ちた。酒癖が悪いから起こすなと、みんなで放っておいたら、そのまま御殿場線に乗り換える沼津駅まで眠り続けた。
この口べたな小道具係はその後巨大宗教団体に入会した。会員集めの折伏に熱中するうちに弁が立つようになり、遂には所長室に出向いて直接抗議できる男へ成長した。私も深夜の果てしない折伏に閉口したが、宗教の怖いような凄さを思い知らされた。
入社して3ヶ月後、試用期間が終わって正社員になり、自動的に大映労働組合の一員になった。7月、私にとって初めてのボーナスが出た。幹事に連絡場所を教えて故郷清洲の実家へ母と急いだ。親戚・友人・知人、みんなが安心し喜んでくれた。入社時にイングリッド・バーグマン先生から借りた2万円のうち1万円を返すことが出来てホッとした。
しかし大映就職を契機に京都永住を決心してみると、自分が不在地主になることに気がついた。私は清洲で約1500平米のわずかな田畑を保有する地主だったのだ。敗戦による連合国の占領政策とは言え、不在地主を否定する農地改革に賛成の私は、不在地主の存在を農業民主化のルール違反だと思っている。何とかしなくてはと考えはじめた。
(2006年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第36回「“パイプ煙草復活へ”の時代」 |
「農地は、農民の手に!」
1955年(昭和30年)夏。大映京都撮影所に就職して10ヶ月、仕事にも慣れた。京都定住の目途も立った。私は帰郷して、叔父(母の弟)に私が所有する田畑の売却譲渡を頼んだ。
「税金はおれが払っといてやるから、このまま持っとったらええがや」
「不在地主でいるのはいかんことだと思うもん。民主主義に反する」
「なにを言っとる。誰でもやっとることだがや。今手放したら百姓にただでやるようなもんだぞ」
叔父は私の農地改革賛成論に根負けした。やがて叔父から返事が来た。
「畑は簡単に売れたが、田んぼの方はどうしても買い手がつかんわ」
約1000平米の畑の譲渡価格は17000円。私の1ヶ月分の給料と大差ない。当時の諸物価に比べて、あまりにも安すぎる。それでも、叔父が農地委員会に手を回した結果、法によって国が認めている買収・売り渡し価格より10何倍も高く売れたとのことだ。
「そりゃ買った人は恩着せがましかったが、あんなええ畑だもん、陰で大喜びだわさ」
喜ばれたら、それでええのだ。叔父に「お前は馬鹿だ」と笑われたが、私の気分は解放された。
売れ残った500平米ほどの田んぼは、やがて思わぬ幸運をもたらすことになる。
この夏は、米軍立川基地拡張に反対する砂川町民の闘争激化、第1回原水爆禁止世界大会広島大会開催などから、敗戦以来天皇制社会の変革を求める私の心は揺れ動いた。
一方、撮影所では、監督溝口健二、撮影宮川一夫、主演市川雷蔵の芸術超大作『新・平家物語』の製作で活気づいていた。雷蔵演ずる若き日の平清盛が、激しい情熱で旧権力と闘いながら如何にたくましく成長していくのか?撮影所内を鎧武者や僧兵が右往左往した。
私は溝口映画が革新的に成功することを期待しながら、荒井良平監督の娯楽作品『悪太郎売り出す』についていた。主演は勝新太郎。情にもろくて喧嘩っ早い追分宿の若い人気者が、ヤクザにあこがれ、悪代官悪親分を正義のドス振りかざしてやっつける話だ。
荒井監督は50歳台半ば。撮影所では、衣笠貞之助、伊藤大輔、溝口健二の御大に次ぐ長老監督だが、大きく差をつけられていた。1930~40年代に活躍してドル箱監督の地歩を築いたプライドからか、御大たちと張り合うためか、弱いものいじめの威張りたがりに見えた。
セット撮影では、小道具係がタンス・長持ち・火鉢などの置き道具をはじめ、茶碗やお盆、お膳や料理、徳利や杯など演技に使うもの一切を用意するが、それらについて監督は駄目出しをよく出した。たいていの監督は普通に言うが、荒井監督はぼろくそに怒鳴った。それではと、代わりに出してくるもの出してくるものに文句をつけた。その小道具係に何か恨みでもあるのかと、セット撮影のたびに不愉快な思いをした。
ロケーションでは、見物人が増えるに従って荒井監督の態度がでかくなっていくようだった。
最初は見物人の集まりを窺いながら掌の皮をむきはじめる。掌に水虫が出来ていたのかも知れない。見物人が増えるにつれて皮むきは盛んになり、やがて掌の皮をむきつつ大声でスタッフに駄目出ししながら歩き回り、監督としての存在を見物人に印象づける気配があった。
また、ロケでは“天気待ち”をすることがよくある。曇るとカメラ写りが悪くなるというので、陽が出るのを待つのだ。
ある山の中腹で天気待ちしていたときである。なかなか陽がでない。スタッフは不安になり、イライラをつのらせた。すると荒井監督が記録係の女性に声をかけた。
「記録さん、山の上へ行って見せてきてくれよ」
「はっ?」
「ちょっとパンツをずり下げたら、お陽さんがニコッと笑って顔出さはるんや」
「いややわ!」
記録係の困惑がスタッフのげらげら笑いを誘った。いかにも古くさいセンスの荒井監督は、この作品を最後に大映京都撮影所から姿を消したと記憶している。
この頃、エリア・カザン監督、ジェームス・ディーン主演のアメリカ映画『エデンの東』を観る。シネマスコープの横長画面を巧く使いこなす演出とカメラワークに、いたく感心させられた。やがて大映京都のスタッフは、このシネマスコープ横長画面の処理に手こずることになる。
ところで当時、私の残業は毎月100時間から150時間。残業が22時を過ぎると交通の便がなくなり、帰宅は自動車部が出すバスの夜間送りとなる。バスは近いところから順々に回ってスタッフを降ろしていくので、市街地北端松ヶ崎の山腹に住む私はいつも最後となり、帰宅できるのは1時間から1時間半後になる。松ヶ崎の寺からの通勤に疲れが出てきたので、本堂の鍵もかからない襖でしきられただけの不用心な座敷住まいを打ち切って、撮影所に比較的近い遠縁に当たる人の住居の2階へ引っ越した。私たち母子は、京都へ出てきて初めて住まいらしい住まいに落ち着くことができた。
さて私は、年末に向けて加戸敏監督、雷蔵・勝新太郎共演の『怪盗と判官』、田坂勝彦監督、雷蔵主演の『又四郎喧嘩旅』と、立て続けにつけられた。
まだ当時の大映にはゆとりがあり、撮影スケジュールの中頃にはスタッフの慰労を兼ねた2泊3日程度の宿泊ロケが組み込まれ、とくに岐阜へはよく出かけた。定宿は岐阜市の繁華街・柳ヶ瀬にある料理旅館。夕食がすむと、麻雀好きはすぐ台を囲んで夜更かし。20時になると近くのストリップ劇場から割引合図のベルが聞こえる。ストリップを楽しんだ後、ある人たちは居酒屋やバーで戯れ、ある人たちは遊郭へ繰り込む。そして翌朝、前夜の歓楽に話の花を咲かせながらロケに向かうのだ。
『怪盗と判官』の時だったと思う。川の流れに逆らって船をこぐ場面を撮影していた。櫓をこぐのは大部屋の俳優さんだ。なかなか巧く漕げない。スタッフが笑う。俳優さんは慌てふためく。夕陽が沈もうとしているのに笑いは高まるばかり。下を見ると加戸監督まで笑っている。私は切れた。
「何がおかしいんだ。陽が沈むぞ!」
私の怒鳴り声でいっせいに笑いが止まった。監督が私を振り仰いでおもむろに言った。
「君は怖いねえ」
「すみません」
私が切れたのは、小学2年の時に私をいじめていた学年一のガキ大将を教室の羽目板に力一杯投げつけて、気絶に近いダメージを与えて以来のことだ。
私が怒鳴った後、撮影は静かに終了。私は集団とは何かが掴めたように思った。
入社して1年、私はたいていの新入りが経験する事故に出会ってきた。夢中でステージ内を動き回っているうちに、使い捨てられた板から突き出ている釘で足を踏み抜いた。天井から落ちてきたライトの笠で頭を3針縫うケガもした。捨てられている板は踏むな。天井でライトを扱っているときは下に立つな。こうした撮影所の鉄則も体得でき、身のこなしに自信がついた。私は就職当時、製作部の上司から生意気だと嫌みを言われて、自粛していたパイプをくわえることにした。
「誰にも文句言わせないぞ」
年末、私は自分を取り戻したようにパイプ煙草をくゆらせ、母とともに故郷清洲へ向かった。名古屋のイングリッド・バーグマン先生から就職時に借りた残りの1万円を、冬のボーナスから返すためだった、が……
(2006年11月記)
⇒ 目次にもどる
| 第37回「“美空ひばりに出あったり、火事場面の撮影初体験”の時代 」 |
飛行機雲を引きながら飛ぶ飛行機を仰いで、グアムやサイパンへの旅を楽しんだ孫は言う。
「お祖父ちゃん、あの飛行機はグアムやサイパンへ飛んで行くんやで」
太平洋戦争末期の昼間、私はグアムやサイパンから飛行機雲を引いて飛んできた米軍の超重爆撃機B29から目の当たりに焼夷弾を浴びせられた。その体験からか、飛行機雲を引いて飛ぶ飛行機には、今なおB29の機影がどうしてもダブってしまう。ときには爆弾を落とすのではないかと恐怖感が走ることがあって、あらぬ返事を心の中で口ずさむ。
「アホかいな」
マシンガンを撃ち合っている孫は言う。
「ほんまの戦争はダメやけど、うその戦争だったらええのやで。バンバン、バン!」
私が軍国主義まっ盛りの幼少年時代に明け暮れた戦争ゴッコは、本当に人を殺しに行くための練習だった。
そして戦後60年、戦争を肌で思い出せる人はめっきり少なくなった。戦争の怖さを忘れた“戦争ぼけ”の日本人どもは、理屈さえつけば何時でも戦争ができるように、2007年1月防衛庁を防衛省に格上げしてしまった。
わが人生70数年。何が起こるかわからない年月を、よくも延々と生きてきたものだ。
、
何が起こるかわからないと言えば、1956年(昭和31年)から邦画界の封切館は、東映につられて2本立て上映の時代に入った。すでに東映は、54年頃から東千代之介、中村錦之助などを起用して、『真田十勇士』『笛吹童子』など子ども向けの連続活劇短編を製作し、長編に併映して新作2本立ての上映体制をとっていたのである。
最初のうち、他社は東映の子ども向き短編を“砂利すくい”と称して見くびっていた。その短編が子どもたちから圧倒的な人気を集め、それにつれて片岡千恵蔵、市川右太衛門などが主演する一般向けの長編時代劇も興行成績を上げてくる。他社は無視できなくなった。要するに大量生産競争時代の幕開けである。
この年の最初の仕事は、『銭形平次捕り物控・死美人風呂』であった。加戸敏監督にとっては初めての長谷川一夫主演映画。大映秘蔵っ子の大スターを任されて緊張したのか、ご機嫌取りか、監督は毎朝のように撮影開始前、チーフ助監督を長谷川さんの控え室へ差し向け、その日の意向を探らせた。毎度のようにセットでは、長谷川さんが共演の女優さんたちに演技指導するのを、傍らに膝をついてニコニコと頷きながら見守った。カメラ横へ戻ってくると、監督椅子に腰を下ろしながら、ときどき感嘆の思いを口走った。
「さすがに長谷川さんや。いいこと言わはる」
あるとき長谷川さんは、私と並び小便していてつぶやいた。
「辻やん、ビンさんは素直な監督さんやねえ」
私は返事に窮した。
特にこの映画では、美空ひばりが歌のうまい軽業娘として平次の子分に扮し、長谷川さんと共演することが大きな話題になった。当時18歳のひばりは、歌や映画でヒットを飛ばし、すでに長谷川さんをしのぐほどの大スター。いつも組んで仕事を進めるひばり母子は、大スターの人気をかさに、態度がでかい、生意気だ、扱いにくいなどと、歌謡界や映画界から悪い噂が流れていた。そのためスタッフは警戒気味だった。しかし会ってみると全く違っていた。「初めての職場で猫をかぶっているんや」と陰口を叩く人もあったが、ひばり母子は物腰が低く、礼儀正しかった。
まず録音技師が、「ええ声や。こんなええ声は初めてや」といかれた。
長谷川さんもいかれた。
「あの子はすごい子やで。たいていの俳優さんはうちに気押されるんやが、あの子はものおじせずに、初っぱなから芝居をぶつけてくるんや」
私は私で、ひばり母子とはけっこう馬が合った。何かの打ち合わせでひばりの控え室に入り込んだとき、ひばりが大スターになれた原因を母親に尋ねてみた。
「松竹映画に初主演が決まって出演料を聞かれたとき、こうして(と、しぐさを見せて)開いた片手を出しました」
母親は5万円のつもりだったが、松竹側は50万円と勘違いしたらしい。そのため高額の出演料を払うことになった松竹は絶対に失敗できないと、ひばりの売り出しに全力をかけ、それが重なって人気が上がったのだろうと母親は謙虚に話してくれた。以後、密かにひばりのファンとして現在に至る。
ところで『死美人風呂』は、死体が浮かんだ女風呂で浴客たちが悲鳴を上げ、裸のまま石榴口(ざくろぐち=かがんで通った湯船への出入り口)から飛び出してくるシーンから始まる。
当時、女優さんに裸の出演はさせられない。代役を絵画のヌードモデルに依頼していた。その10人ほどのヌードモデルに演技をつける役を、いきなり先輩たちから押しつけられた。新米を仕込むためかと善意に考え、初めての経験だったが、泰然自若のふりをして何とかやりおおせた。その後も女性の裸が必要な作品についた場合、代役に頼んだヌードモデルの扱い係を押しつけられた。そんなことから、先輩たちは夜の悪遊びにたけていたものの、「役得やな」と冷やかすスタッフの前でヌードモデルに接することは、実は照れくさくて苦手だったのだと思うようになった。
次いで、江戸の町を焼き尽くそうとする悪浪人たちに斬り込む『花の兄弟』(監督三隅研次、市川雷蔵・林成年共演)では、火事場面の撮影を初体験した。
カメラの位置が決まると、監督は出役の俳優に演技をつけ、スタッフに出役の動きを理解させる。照明係が準備を進める一方で、手空きのスタッフは協力し合い、演技に対して炎が効果的に撮影できるよう、カメラマンと相談しながら位置を決め、燃やす材料を仕掛けていく。油や石油を染みこませた綿や布切れを障子の桟に取りつけたり、柱に巻き付けたり釘止めして垂らしたり、畳や板の間に広げるなど火の材料を配置する。すべての用意ができ、監督が出役に火の位置を注意しながらテストを終えると、スタッフはいっせいに火をつける。炎の具合を見計らって、監督は「用意、スタート」と号令。すかさず鳴るカチンコの音で演技が始まる。
撮影が続く間、炎がどこまで燃え広がるか、スタッフは細心の注意を払いながら見守る。撮影を止めるために監督がかける「カット」の号令で、スタッフはいっせいに飛び出す。濡れ布で包んだり、濡れむしろを被せて、あらかじめ各スタッフに決めてあった責任部分の火を消す。カットが長くなると、炎はかなり拡大するので油断できない。
あるとき炎が燃え上がって、ステージの天井に火がつきかかったことがある。スタッフは大あわて。用意してあった消防ポンプの強力な水圧で消そうしたとき、三隅監督は「セットを壊すな、セットを壊すな」と叫び続けた。その冷静さに「ステージが火事になってもええのんかい」と、スタッフ一同唖然とした。
こうして火事場の撮影は、ドラマの筋に合わせ、カットが変わるごとに火の仕掛けを変えるのだ。一度段取りを急ぐあまり、まだ完全に火の消えていないむしろを上げてしまった。ボッと燃え上がった炎が、ぺろりと顔面をなめて眉毛を焦がし、唇や鼻の先に火傷を負わせた。
「火の接吻や、火の接吻や!」
スタッフは大笑いしたが、私は唇がひりひり痛んで、笑おうにも笑えなかった。
因みに、1950年に封切られたフランス映画、「ロミオとジュリエット」の現代版としてアンドレ・カイヤット監督が映画化して注目を集めた『火の接吻』が、当時はみんなの記憶に広く残っていたのである。
(2007年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第38回「“映画とヤクザ、持ちつ持たれつ”の時代」 |
《もはや戦後ではない》
1956年(昭和31年)7月に経済企画庁の発表した『経済白書』が、前年をふり返って「戦後経済最良の年」と位置づけて締めくくった言葉だ。デパートの売り上げは戦後最高。海や山へ、人出は戦前戦後を通じて最高を記録したという。
映画界も興行成績を挙げたはずだが、わが大映では社員の給料に反映されることもなく、この年からはじまった2本立て上映興業のための量産に追われた。
利益は、ワンマン社長が業界最高の配当率を誇る3割台の株主配当や、プロ球団経営、あるいは年頭の訓辞などで、大物政治家の岸信介や河野一郎を指して「岸君がね・・」「河野君がね・・」と言いたいための政治資金に回したり、若い頃世話になって以来目をかけているヤクザ組織の援助に流用していると言われていた。
当時はロケーションに出た場合、どの会社の撮影所も一般通行人や見物人の整理をヤクザ組織に任せていた。大映では社長と関係のあるヤクザ組織の人たちが取り仕切っていた。
彼らはロケの整理人、整理係として撮影所に常駐同様にしていたので、スタッフは仲間のように親しくしていた。このような人たちがロケに必要だったのは、国内のほとんどの地域で縄張りを張り合っているヤクザから因縁をつけられたり、ロケ現場付近や通りがかりの分からず屋から邪魔されるなど、どんなトラブルが発生するかわからないからである。
京極で夜間ロケしたときのことだ。島原を縄張りにしているヤクザ組織の酒に酔った若い衆が、「お前ら、誰の許可取ってロケしとんね」とロケ現場へ割り込んできた。大映が事前に筋を通しておいた京極のヤクザ数人がサッと飛び出し、彼を取り囲んで路地裏に引っ張り込んでいった。私たちは聞き耳を立てる。ブスッとやった気配。瞬時の出来事だった。様子をうかがっていた大映方の整理人が戻ってきて「何でもない、何でもない」とスタッフの緊張をやわらげ、撮影の続行を促した。何でもなかったように、私たちは撮影を再開した。
翌日整理人の一人から、彼の親分が京極と島原のヤクザ組織の中に立って丸く収めたとの報告があった。
遠方ロケの場合は、製作主任や製作進行係が土地のヤクザに前もって挨拶し、場所使用料に類する金を払うなど筋を通してロケのお膳立てをしていた。
制作主任たちの話では、漁師町が最もロケのしにくい土地とのことだった。荒くれた漁師たちには、ヤクザもにらみがきかない。ヤクザへの所場代を払った上に、一升瓶をもって漁師一人一人へ挨拶に回らなければロケが不可能だったそうだ。
この年の夏頃、加戸敏監督、長谷川一夫主演の『逢いぞめ笠』で乗鞍岳へロケに行った。
股旅姿の長谷川さんが、三橋美智也の歌う主題歌に乗って道中する場面を、上州路に見立てた乗鞍頂上付近の道で撮影することになった。準備をしていると乗用車が着いて、パリッとした服装の男が降り立った。すかさず製作主任が寄っていって挨拶を交わした。横にいた進行係が耳打ちした。
「この辺のヤクザや。様子見に来たんや」
乗鞍の頂上のようなところも、ヤクザの縄張りの内かと驚かされた。
いつだったか、ロケ整理人に関係のある組織の親分が、神戸か大阪かにあるヤクザ組織の刺客人に刺されて入院したとの噂を聞いた。
そして数日後。スタッフルームで監督と打ち合わせかたがたくつろいでいると、ロケの整理人が2人づれで入ってきた。いつもと違った固い表情だ。声をかければ跳ね返されそうな、人を寄せつけない雰囲気に息をこらして見つめていると、兄貴分の方が小腰をかがめながら右手を差し出した。
「お控えなすって、お控えなすって・・・・」
それまで聞いたこともない声の調子で仁義を切りはじめた。ヤクザ映画ではちょいちょいお目にかかるが、現実に見るのは初めてだ。みんな呆気にとられていると、言うだけ言った彼らは平生見せないような丁寧な物腰で退去し、次のスタッフルームへ入っていった。
仁義の趣旨は、親分の事件を知った松竹や東映の監督たちは見舞いに行ったり、見舞いの品を届けたりしたが、自分たちが出入りしている大映の監督たちからは何もない。子分としての面子が立たないから見舞いの気持ちを表してほしいということだった。
監督たちは見舞いに行ったか、見舞いを届けたかわからなかったが、全快後の親分が撮影所の中を見舞いのお礼に回っているらしい姿を見かけた。
どの作品だったか、山里の風景を求めてロケハンしたことがある。原谷という地区へ向かうことになった。御室・仁和寺の裏山から峠を北へ抜けると、シナリオ指定どおりの山に囲まれた別天地のような山里が開けていた。
「あんな人気のない山間部やから、まさかヤクザの縄張りにはなってないだろう」
というわけで、整理人を連れないでロケに行った。一部で市街地開発のための地盤整備がはじまっていたが、その地域をカメラアングルから避けて撮影を済ませた。ロケバスに引き上げて帰ろうとすると、開発作業をしていた10数人の作業員たちが駈けよってきた。
「黙って帰る手はないだろう!」
乗車口をふさいで製作進行係が二言三言やり合っているうちに、中の屈強な一人が製作進行係を押しのけて「監督は誰や」と乗り込み、目星をつけて監督につかみかかろうとした。私たちはあわてて引き離してバスから押し出しすと、すかさず運転手がバスを急発進させて危機を脱した。
「それみいな。やっぱり整理の人らを連れてこなきゃダメやったんやないか」
ロケを取り仕切る製作進行係が、スタッフから口々に文句を言われた。
「そんなこと言うたかて、他の組とてっぱって段取りがつかなかったんや」
「急に予定を変更したんがアホや」
「詰まったスケジュールをこなすために、どうにもならなかったんや」
「わしらがこんなことまでして仕事やってんの、社長や重役連中は知ってんのかいな」
「東京にのほほんとしとって、わかるわけないやろ」
「まあまあ、無事すんだんやからええやないか。静かにしいな。ちょっとでも寝さしてほしいわ」
「あぁあ、今日もまた残業か」
ワイワイガヤガヤは撮影所に着くまで続いた。
当時、私は思った。不特定多数の人々の理解と協力を必要とするロケは、さまざまな予期しないトラブルに遭遇する恐れがあり、余程善良な社会が実現しない限り、映画とヤクザとの腐れ縁は続くだろうと。
(2007年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第39回「“大映に、ハリウッド出現”の時代」 |
1956年(昭和31年)の春から夏にかけてのことだった。大映京都撮影所は、ちょっとしたハリウッド映画界の様相を呈した。米国映画『八月十五夜の茶屋』の撮影が、大映スタッフの協力のもとに行われたのである。米国スタッフに交じって、大スターのマーロン・ブランドをはじめグレン・フォードなどの外国人俳優たちが構内を行き来し、大映ロケ隊の何倍も車を連ねてロケに出た。
監督は、52年に『愛しのシバよ帰れ』で華々しくデビューしたダニエル・マン。アメリカ占領下の沖縄を舞台に米国軍人と島民との交流を描くとのことだった。日本側からは、ヒロインとして京マチ子、ほかに根上淳や清川虹子らが出演した。
この間に何よりも興味を引いたのは、彼我における仕事ぶりの違いであった。
例えば、朝9時の仕事始めの場合である。
通常大映スタッフは、前日に予定がわかっていても、一応製作部の指示放送に基づいて作業を始めることになっている。
「○○(監督の姓)組、第××(ステージ№)セットを開始します」
セット開始を告げる放送を聞いてから、大映組スタッフはおもむろにセットへ集まり、撮影準備にかかる。予定表にある午前9時セット開始とは、スタッフがセットへ集合する時刻である。
しかし米国の“マン組”は、前日に午前9時のセット開始という予定が出ていれば、開始の放送など必要とせず、その時間までにスタッフ・キャスト全員がセットに勢揃いして、9時に撮影を開始するのである。
大映組は予定表と放送の2本立てで作業を進行させたので、作業開始時刻にはセット撮影開始やオープン撮影開始、あるいはロケ出発など幾組かの開始放送が、われ先にと入れ替わり立ち替わり続いて、構内はしばしば騒然とした。
一方、マン組はほとんど放送を使うこともなく、予定表に基づいてスマートに作業を進めていたことを印象的に記憶している。
次いで、本番撮影が始まるまでの違いだ。
当時の大映が、1本の作品を撮影するために割り当てていたネガフィルムの量は、だいたい仕上げ時間数の2倍だった。一秒の撮影に要するネガフィルムは、約1.5フィート。長さ90分の仕上げであれば、約16200フィートのネガフィルムが使えるというわけだが、これは非常に厳しい予算である。1カットずつ撮影を重ねていけば、カメラを回したり止めたりするカット撮影の前後に何フィートかの無駄が出る。NGでも続けば、忽ちネガ不足に陥る。
2年ほど後に就いた『炎上』の撮影中のことだったが、撮影所では手に余る巨匠扱いの市川崑監督でも、社長に直接談判し、フィルムを4倍まで使えるように苦心する姿を覚えている。
さて演技のテストも終え、撮影準備も完了して監督が「よーい」と号令をかけると、カチンコ係がカチンコをカメラ前に差し出す。
カチンコは黒板の付いた拍子木。黒板にはシーンナンバー、カットナンバー、録音テー プのトラックナンバーなどを記入し、撮影しておいて編集の頼りにする。カチンコが打たれた画面と「カチン」の録音点を一致させ、画面フィルムと録音テープをたどっていくと、動きと音の合ったシンクロ画面が編集できるのだ。
引き続いて、監督の「スタート」でカメラが回る。録音部が録音テープの回った合図のブザーを鳴らす。カチンコ係がすかさずカチンコを打ち鳴らして引き下げる。カチンの音から一息置いて、俳優は演技をはじめる。この間の段取りを手際よく進めて、少しでもフィルムを無駄にしないように撮影スタッフは腐心する。そして最後、監督の「カット」で演技は終わり、カメラを止める。
以後、こうしたスタート・カットを繰り返し、監督の編集意図を盛り込んだコンテ(撮影台本)に基づいてアングルやサイズを変えたりしながら撮影を進めていく。時には1分、2分と長回しする場合もあるが、10秒、5秒、20秒、3秒などとドラマを区切って、フィルムが減っていくのを気にしつつ、しこしこと撮り重ねていくのである。
しかし、マン組スタッフのやり方は、違っていた。
撮影準備段階のどこに、カメラを回す時点を置いているのかわからないが、まだスタッフがカメラ前でうろちょろしているのに、気が付くとカメラが回っている。それから、のそのそと助監督らしい男が大きなカチンコをぶら下げてカメラ前に出てくると、カチンコを叩いてゆっくりと引き下がっていく。その後も、まだカメラ前ではごそごそあって、どうやら静まったところで監督が「アクション」と号令し、やっと演技が始まる。それまでに、いったいどれだけフィルムは回っているんだろうと、見ていて驚くばかりだった。
次いで、シーン撮影の進め方における違いだ。
米国側はアングルやサイズを変えて、シーン全部を通しで撮影する。いわゆる1シーン1カット撮影を何通りもするのだ。従って使用フィルムは、仕上げフィート数の何倍にもなる。さらに、カットを撮影する毎に1000フィート(約10分撮影可能)入りのフイルム容器・マガジンをカメラにセットし、撮影がどの時点で終わろうが、残りは捨ててしまう。巨匠でもフィルムに困る大映スタッフから見ると、まさに湯水のごとく使っている感じ。当時の本に、アメリカではB級作品でも20万フィート以上のフィルムを使うと書いてあったのを覚えている。幾らなんでも、使いすぎではないか。
眼下に集まっているのを民間人と知りながら、大量の焼夷弾爆撃を仕掛けたB29の大編隊を思い出し、目的のためには手段を選ばない、大量消費のヤンキー気質を見るような気がした。
では、これだけ大量に撮影しておいて、監督は後の編集をどうするんだろう?
プロデューサーシステムの米国では、プロデューサーが全権を掌握していて、プロデューサー・ディレクター以外のディレクター・監督は演出を任されるだけ。編集権はプロデューサーにあり、どのフィルムのどの部分を使うかは編集マンと相談して作品を仕上げていくとのことであった。
こうして贅沢に完成した『八月十五夜の茶屋』は、当時どんな成功を収めたかわからないが、現在、“ぴあ”発行の『シネマクラブ』からは、監督ともども無視されているようだ。
マン組のスタッフルームには、事務社屋2階の大会議室が当てられていた。彼らの昼食時間は、12時から14時まで。料理には、都ホテルからコックを招いていた。ビールを飲みながらのゆっくり・たっぷりの食事の後、開けられた窓から傍若無人に靴履きの両脚を突き出して、のんびり憩っている様子を見上げると、米国占領下に逆戻りした感じがしないでもなかった。
昼食時間が12時から13時までの私たち大映組は、カレーライスやカツ丼、簡単な定食などで安直に食事を済ませ、後は「今日も残業か」と、疲れ気味に時間を持てあます。撮影開始の放送がかかると、救われたようにセットへと追い込まれていたのだ。
当時驚いたことに、マン組のロケにはコーヒー車が単独で牽引されていった。協力参加の大映スタッフに「自由にコーヒーが飲めてええなあ」と聞くと、腹立たしそうな返事が返ってきた。
「あんな、うす味のコーヒーなんか、まずくて飲めたもんじゃないわい。あんなものをがぶがぶ飲んで、いったい奴らの口はどうなってるんやろ」
そのコーヒーとは、現在一般化している“アメリカン”コーヒーではなかったろうか。
複雑な印象を残して米国勢が去った頃、私は正月作品となる加戸敏監督の『銭形平次捕物控・まだら蛇』についた。美空ひばりちゃんと再会し、『青い山脈』を観た高校時代から憧れの的、成熟した女性の健康な色気を発散する木暮実千代さんに出合うこととなる。
(2007年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第40回「“こんな映画をつくっていて良いのか”の時代」 |
「しっかり頼みますよ、先生。私は大和なでしこの血をひいているんで、パンツだかズロースだか、あの窮屈なのが大嫌いなんですからね」
これは、1949年(昭和24年)の夏大ヒットした青春映画『青い山脈』の中で、年増芸者を演ずる木暮実千代さんが、青年医師に自転車の後ろへ乗せてもらいながら、自転車が人を除けてぐらついたとき、青年医師の腰にしがみついてコケティッシュに発したセリフだ。
もちろん、作品の本筋である旧制女学校生と旧制高校生との清新な交際には大いに共感したが、それにも増して、木暮さんの開放的な色っぽい演技は、敗戦後の民主的な新時代を謳歌するマセガキの高校3年生に鮮烈な印象を刻み、以来木暮さんは憧れの的になった。
そして1956年(昭和31年)秋、木暮さんと一緒に仕事をするチャンスが訪れた。その仕事とは、正月映画として製作する長谷川一夫主演『銭形平次捕物控・まだら蛇』である。
話の筋は、幕府の高官が地位権力を利用し、地下の小判贋造工場に罪のない江戸市民を閉じこめて酷使する大悪人団を、御存じ平次が颯爽と登場して、推理の冴えも鮮やかに一網打尽にするという流れだ。
木暮さんの役は、悪巧みを知らずして悪商人に利用され、悪の一味を利する賭場の誘い役として色気を見せる女賭博師。客に変装して探りにきた平次に惚れこんでしまい、最後は一味総手入れのどさくさに紛れて不慮の死を遂げる命のはかない役だった。
私は初めて木暮さんと出会って、あれっと思った。いつの間にか憧れの気持ちは消滅していて、のっけから木暮さんを仕事仲間として接していたのである。憧れ対象ではなくなっていたが、木暮さんは明るく魅力的な女性であった。
しかし製作部や俳優部は、木暮さんの扱いに悩んでいた。土曜・日曜には、必ず東京の旦那の許に帰してあげなければならないというのだ。当時は公休出勤・残業・徹夜は当たり前のことだったので、他の俳優さんとの兼ね合いもあって、スケジュールの立て方に熟慮を強いられていたのだ。木暮さんは38歳の女盛り。スタッフの幾らかは、苦笑いしながら邪推した。
「木暮実千代は、よっぽどあれが好きなんやで」
ゴシップに興味のない私は、事情がわからず邪推に乗ることもあったが、ややこしい業界に対して自分の意志を通す、木暮さんの実行力に感心した。
ところで、この年の7月に経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言したように、前年から続く戦後復興を背景にして、鳩山一郎首相が率いる保守政権は、、革新勢力への攻勢を強めていた。教科書法案を国会提出して教科書検定の強化をねらったり、警官500人を国会に導入して、教育委員を公選から任命制にする新法案を強行可決したり、改憲のための憲法調査会法を公布するなど、保守政権による戦後民主化に対する逆コースの政策は、いっそう鮮明になりつつあった。
このように日本の民主主義社会が危機に陥らんとする一方で、私を取り巻く仕事は、昔ながらの義理と人情を讃えたり、チャンバラで解決する勧善懲悪のプログラムピクチャーばかり。
「こんな映画をつくっていて良いのか」
敗戦を古い日本からの解放と受け止めている私は、新しい哲学と思想を盛り込んだ芸術を創造しようと意欲を燃やして入社したものの、大勢の大先輩・先輩で先がつかえる社内状況ではどうしようもない。ただただ仕事を覚えることだと割り切って走り回った。
『まだら蛇』の次に就いたのは、助監督部の大先輩Wさんの監督デビュー作品だった。
主演は勝新太郎。流しギターの青年が妹の結婚資金を稼ぐため、知らずに密輸団に巻きこまれる恋と肉親愛の活劇編である。
W監督は大映と縁の深い巨匠監督伊藤大輔の愛弟子と言われ、助監督同士で仕事をしていた私は、力強く温厚で頼りがいのある先輩助監督として敬愛していた。しかし監督として就いてみると、評価が違ってきた。言葉がなめらかに出ないのか、演出・演技指導がぎこちなく、現場は上手く進行しなかった。
別々に録音した音楽やセリフなどを1本のサウンドフィルム(またはテープ)にまとめる最終作業の前に、編集したポジフィルム全編をつないで、映画の出来具合をチェックする作業を総ラッシュ試写と言ったが、その総ラッシュ試写を見終わった製作部長は、勝ちゃん扮する主人公が悪者たちに追われ、拳銃をパンパンと撃ちまくって防戦するラスト・シーンに批判の声を上げた。
「勝ちゃんが撃つ拳銃は、いったい何連発やね」
当時撮影に必要な場合は、パトカーも拳銃も太秦警察署から借りることができた。借用を申し込むと、2人の私服刑事が拳銃を持参し、空砲を撃たしてくれるのだ。しかし危険だった。空砲といえども、撃てば10メートル先のボール紙に穴を開ける。いずれにしても当時の警察が所持していたのは、アメリカ製スミス・アンド・ウェッソン式6連発のリボルバーだ。
問題のシーンは、人通りの途絶えた深夜の市街地という台本の設定に従い、深夜の市街地でロケ撮影された。深夜と言えども、ロケすれば見物人は集まる。W監督は、画面の邪魔にならないように見物人の整理に追い回される状況での撮影で、拳銃が6連発であることに気が回らなかったのだろう。急いでロケ現場の一部をステージにつくり、弾を詰め替えるカットを撮り足した。
Wさんは巨匠のバックアップがあったのか、その後何本かの映画を監督できたが、数年後には助監督に戻り、やがて事務系の仕事に配置転換となった。
私はWさんのケースから、いくら地位や境遇に恵まれていても、監督としての実力を蓄えていなければ簡単に消え去る監督の運命を知らされた。
明けて1957年(昭和32年)の春。加戸敏監督・長谷川一夫主演の『刃傷未遂』に就いた。映画の内容は、吉良上野介が浅野内匠頭に刃傷された1年前、同じ松の廊下で正義硬骨の大名のために投げ飛ばされ、怒った吉良が刃傷に及ぼうという話だ。この仕事では、時代風俗考証に苦労した。
脚本は巨匠伊藤大輔。脚本には細々と考証に対する注文が書き込まれている。とくに江戸城松の廊下で刀を振るう吉良の扮装には、衣裳責任者との間に立って困らされた。私も江戸城に関する作品は初めてだ。巨匠の指摘では、浅野内匠頭と同様、この映画に出てくる大名は5位の朝散太夫だから、大きな家紋を要所につけた「大紋」と称する衣服を着すが、吉良は4位の侍従だから「狩衣」と称する衣服を着すとある。しかし、従来の『忠臣蔵』映画を史実だと信じ込んでいる衣裳責任者は、吉良の衣服は大紋だと言って聞かない。当時は現在のように、歴史風俗に関する便利な参考書もなく、撮影所の書庫に入って、時代考証を重視する溝口健二監督の助監督が集めた資料から『柳営秘鑑』や『武鑑』、『故事類苑』などを探し出して調べると、巨匠の指摘通りだった。衣裳責任者は「笑われても知らんえ」と、不承不承に狩衣を用意してくれた。
作品は時代考証によって、格調高い娯楽時代劇に仕上がった。娯楽作品といえども、風俗を知ってつくるのと、知らないでつくるとのでは完成度に大きな違いのあることを痛感した。
以来映画における風俗考証の重要性を認識し、歴史と風俗の関係に興味を深めた。作品に就く度に江戸城大奥、江戸町方役人、吉原遊郭、侠客など風俗を調べ、その知識を積み上げることによって、曲がりなりにも、歴史の実態が頭の中で描けるようになった。
たいていの助監督は作品が完成し、仕事の疲れが治まると直ぐに撮影所の回りをうろついたが、私は次の仕事の呼び出しがかかるまで出社せず、手頃な値段の歴史や風俗の研究書を求めて古本屋を漁った。現代風俗研究会にいち早く入会した遠因でもある。
(2007年8月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ