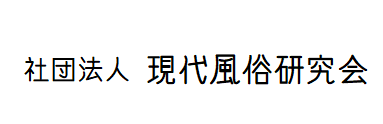| 第51回「“人の幸せを願って”の時代」 |
“部落差別をなくせ!”
第2次大戦後、労働者や農民の運動をはじめ、さまざまの社会運動が復活する中で部落解放運動も復活した。戦前からの指導者たちは大同団結して部落解放委員会を結成。さらに大衆組織にふさわしい部落解放同盟へと発展させ、部落解放を国策として樹立せよと根強い運動を繰りひろげた。その結果、1960年(昭和35年)内閣に同和対策審議会の設置が決まり、やがて同審議会の答申が提出され、同和対策事業特別措置法が公布される運びとなる。
こうした時代の流れを意識して、私は市川崑監督作品『破戒』に就いていた。
1962年1月末に始まった撮影は、2月に入ると本格化した。
『破戒』の主人公は、被差別部落出身を隠して飯山小学校の教師を勤める瀬川丑松(市川雷蔵)。部落出身を隠さず差別解放運動に取り組む思想家・猪子蓮太郎(三国連太郎)に傾倒して、その重要性に目覚め、「身分を隠して生きよ」という父の戒めを破って教え子たちに素性を隠してきたことを告白・謝罪し、反対派壮士に殺害された蓮太郎の意志を継いで新しい自分を活かすべく東京へ旅立つというのが話の筋である。
シナリオの後半は雪のシーンばかりだ。
林のセットでは、雪のないシーンばかりの撮影終了後、雪景色に模様替えして雪のシーンを撮影する。家並みの続く信州飯山の町のオープンセットでも同様だ。
遠景の草木には、当時撮影所では“カポック”と呼んでいた発泡スチロールの溶液を噴霧器で吹きつけて雪が降りかかったようにし、近景の枝葉や石、屋外の積荷などには積雪をかたどって綿を乗せたり、さらにカメラ近くになる葉には綿がばれないように、霧吹きで水をかけ塩を振りかけて雪が積もったように細工する。道には積雪したように塩を大量に敷き詰める。
屋内場面のセットでも外の見えるガラス窓がはまっている場合、窓向きのカメラアングルになれば、窓の桟に雪が積もったように塩を乗せ、ガラスに霧吹きで水を吹きつけ、その上に、指で塩を弾き飛ばして、いかにも雪がガラスに張りついたようにしなければならない。
とにかくスタッフは、手間のかかる雪景色に振り回された。
しかしロケーションの場合は、ごまかしがきかない。実際の雪景色が必要だ。丑松がみんなに見送られて東京へ旅立つという、シナリオが指定する「千曲川の流れに沿った堤」のラストシーンは雪景色だ。ところがこの年は、なかなか京都近辺では積もるほど雪が降らない。果たしてラストシーンは撮れるのだろうか。スタッフはイライラしながら撮影を続けた。
予告編担当の私も、いら立ちながら制作を進めた。予告編は、本編封切りに先だって少しでも早く封切りできるに越したことはない。しかし撮影がはかどらない。焦っていると、宣伝部から予告編に使う三国連太郎さんの紹介カットと、三国さんと雷蔵さんが絡む場面を、その日の内に撮ってくれと急に言ってきた。宣伝スチールの撮影後、本編の出番まで三国さんのスケジュールが取れないというのだ。本編の出番を待っていたら間に合わない。それに三国さんは、一旦スケジュールから外れると行方不明になって、連絡の取りようがないことで有名。私は急いで三国さんと打ち合わせ、午後の本編セット撮影に便乗し、チャンスを掴んで撮影することに決めた。
昼食後、予告編の撮り方を前もって考えるため、午後の撮影開始を待たずにステージへ行くと、セットの奥のホリゾントに沿ってぶつぶつ言いながら行ったり来たりしている人影がある。近づくと三国さんだ。私は恐縮した。
「本編との兼ね合いですので、いつ撮影できるかわかりません。呼びに行くまで俳優部で待っていて下さい」
「心配しないで下さい。急に言われても、私は飲み込みが悪いので、ここで、こうしていたほうが」
結局三国さんの出番が来たのは3時間後だった。私は三国さんに謝りながら、本編に出ていた雷蔵さんと2人を位置に着けた。テスト、本番となり、「よういスタート」とカメラをまわしてカチンコが打たれると、三国さんは突然ゴホンゴホンと咳はじめる。なかなかセリフが出てこない。ダメかと思ってカメラをストップさせようとしたら、おもむろに三国さんはセリフをしゃべり出した。
三国さんは結核患者としての役を演じていたのだ。私は三国さんの役が重症の結核患者だったことを忘れていた。「ストップ」をかけなくて良かった。私は大いに反省した。
かくして、撮影所長の意に反して構成した『破戒』の予告編は完成した。試写を見てほしいと宣伝部の担当者が呼びにいくと、所長は「見る気ない。そんなもん送っても、本社から突っ返されてくるに決まっとるわい」とのこと。試写後、市川監督は言った。
「辻ちゃん良かったよ。音楽が素晴らしかったね」
翌日、本社試写へフィルムを持ち込んだ宣伝部の担当者から「社長は、これが予告編だと言って、2回もご覧になった」と宣伝部長に報告があったことを知らされた。
そして或る日、福井県永平寺に雪が降ったとの情報が入った。私たちは永平寺の麓の九頭竜川堤防へ急行した。期待したほど深い積雪ではなかった。カメラ位置になった場所はスタッフに踏まれて雪が解けてしまう。近所の農家から借りたスコップと一輪車を使い、アングルが変わる度に解けた場所へ雪を運んだ。スタッフに交じり、一輪車で雪を運ぶ市川監督の姿が印象的だった。
撮影は、ほのかに心を通わせ合ったお志保(藤村志保)や小学校同僚、教え子たちに見送られ、殺された蓮太郎の遺骨を抱く蓮太郎の妻(岸田今日子)を守りながら東京へ旅立つラストシーンだ。監督の指示通りに演技が出来ない志保さんは泣き出す。口の悪い雷蔵さんがからかう。
「お前は才能があると思ってるから、ダメ出しされると腹が立って泣くんやろう」
「違います!お芝居が出来なくて悔しいんです」
解けつつある雪との競争で撮影しているスタッフは気が気でない。つい怒鳴り声が上がる。
「雷ちゃん、いい加減にしときいや!」
雷蔵さんは間近に結婚式を控えていて、気が苛立っていたのかも知れない。
私が『破戒』に就いて以来、子どもの頃に私を可愛がってくれた被差別部落の人たちを思い浮かべながら終始気にしていたのは、現在の被差別部落の人たちに納得され得る作品に仕上がるかどうかだった。丑松の苦悩を演ずる雷蔵さんのイメージが、青年の清純さは表現しているかも知れないが、どうも弱々しい。どんなことにも苦悩しやすい性格に思えた。力強い苦悩こそ、社会の苦悩の大きさ深さを表現できるのではないだろうか。教え子たちに素性を隠していたことを教室で告白した後、土下座までして、とりのぼせたように謝まりつづける丑松の姿に、差別者は同情と共感の涙を誘われるだろうが、部落差別解消に取り組んでいる被差別者はどう感ずるだろうか。私にはプライドを無視した屈辱表現以外のなにものでもないと思えたが……。
いずれにしても、『破戒』は手間のかかった作品だった。2月の時間外は150時間。3月は205時間にも達した。こんな時間外労働を要した作品は、後にも先にもなかった。
4月6日、全国一斉に封切られたが、JR京都駅前にあった封切館では、近くの被差別部落の人たちから抗議を受け、数日で上映中止との噂を聞いた。
『破戒』は、その年の監督賞、脚本賞、作品賞など数々の映画賞に輝き、市川監督はさらに値打ちを挙げた。
『破戒』の後、私は初めてチーフ助監督として、三隅研次監督作品『斬る』に就いた。
(2009年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第52回「“結婚とは、お互いに飛んで火にいる夏の虫”の時代」 |
1962年3月下旬、市川崑監督作品『破戒』を終え、次の仕事は市川雷蔵主演三隅研次監督の『斬る』に決まった。そして初めて、私にチーフ助監督の番がまわってきた。
「えっ、おれをチーフに!」
入社7年目の私が驚くほど、当時のわが大映京都撮影所では、監督の先がつかえているどころか、助監督の先もつかえていた。
入社11~12年目の二期先輩たちがやっと中編娯楽映画で監督デビューし始めたばかり。一期先輩たちはチーフとセカンドの間を上がったり下がったりの最中。入社後7年経っても後輩ができない私たち同期生は、時にはセカンドを任されるが、もっぱらサードを押しつけられていたのだ。
一方他社では、すでに私と同期同年輩たちが時代に挑戦する新鋭監督として盛んに活躍していた。松竹では『青春残酷物語』の大島渚、『秋津温泉』の吉田喜重、『乾いた湖』の篠田正浩。東映では『誇り高き挑戦』の深作欣二。日活では『キューポラのある街』の浦山桐郎などなど。
とくに日活の浦山監督には、写真を見て「あの男だったのか」と驚かされた。私が名古屋大学文学部に在学中、うつむき加減の暗い表情で、いつも顔にかかる前髪を掻き上げ掻き上げ構内を歩いている彼の姿をよく覚えていたからだ。
彼は東京へ、私は京都へ向かったのが運命の分かれ道だったのかと、感慨にふけってみても仕方がない。私は大映京撮の現実を受け止めることを、覚悟するほかなかった。
どこまでつづくぬかるみぞ 三日二夜食もなく 雨ふりしぶく鉄兜
人生の土壇場にさしかかると、皇国史観・軍国主義はとっくに克服しているはずなのに、つい子どもの頃に歌い慣れた軍歌『討匪行』が、いつも意識の底から湧きだしてくるのだ。
三隅監督の組が立つまでには間があった。時はあたかも学校関係の春休み。奈良市郊外にある奈良女子大の先生宅で、京都市内の私立高等女学校に勤める奈良女卒の女教師に紹介される運びとなった。すでに彼女の容姿や家族状況は、前もって送られてきた写真や書面で承知している。彼女の頬は健康そのもののようにふくれ、針で突けば水が噴き出すかと思われほどだったが、私に断る理由も資格もない。家を出るとき母に言った。
「決めてくるからね」
「お前が気に入ったら、誰でもええよ」
そして奈良から京都へ帰る近鉄電車でのことだった。彼女が文庫本を差し出した。
「この中から、私のいちばん好きな写真を当ててみて下さいな」
その文庫本は、多彩な文人・若杉慧が出版した写真集『野の仏』を文庫版にしたものだ。私は受け取るやいなやパラパラッとめくり、“紅花地蔵”のページを開いて差し出した。とたんに彼女は声を張り上げた。
「あなた、いつの間に私の財布をのぞいたの?!」
その凄い剣幕に、私はビックリ仰天。混んではいなかったが、思わず辺りを気にして見回したほどだった。彼女は、朝日新聞の書評欄に掲載された紅花地蔵の小さな写真に惹かれて『野の仏』を購入し、掲載写真の切り抜きを財布に忍ばせていたのだ。
『野の仏』は、各地の道端や野原にある石地蔵や馬頭観音、道祖神などの写真を集めたものだ。すでに私は映画作りにおける風俗考証上の参考書として愛用し、紅花を前景にあしらった可憐な石地蔵の写真を載せて“紅花地蔵”と称するページを、いつも楽しんでいたのである。
彼女は私の説明に納得した。そんな彼女が私には天の賜物のように思え、空爆を生き延びた戦争体験から神仏を失っているのにもかかわらず、心の中でつぶやかざるを得なかった。
「お地蔵さんが取りもった縁や」
私は結婚を前提とした交際を希望したが、彼女は私を知るために1年くらい欲しいという。しかし諸般の状況から、私には結婚の前提もなく、1年も交際していくような余裕はなかった。
「私は未だに自分のことがわからんよ。1年ぐらいで私のことがわかれば、そんな有難いことはない。そうなったら、ぜひ教えてもらいたいものだね」
私は、彼女の方が興信所に身元調査を頼まなくても済むように、恥も外聞もかまわず、私の方のことを洗いざらいぶちまけて彼女と別れた。
4月中旬から三隅組が立って『斬る』の製作準備に入り、5月クランクインと歩調を合わせるように労働組合の春闘が始まった。
当時は池田勇人内閣の所得倍増政策が功を奏し、産業界は高度成長への歩み速めていた。しかし映画界だけは、受信契約1千万台を突破したテレビに押されて不振の一途だった。
『斬る』は、16年ぶりに決行するという激しい春闘にもまれながら製作された。
話の背景は江戸末期。異常な出生の秘密を知る養父と義妹が殺されたことを契機に、数奇な運命をたどる多感な天才剣客の若き生涯をたどる話だ。
三隅監督は「ようわからん」と言いながら、新藤兼人の脚本を詩的で感覚的と受け止め、私の質問にも「ようわからん」の一点張りを通し、脚本に忠実な画作りを進めた。
しかし、主人公の数奇な運命を予感させる「すさまじい夕陽」は最後まで表現できず、平凡な夕焼け空の画面で済まされてしまった。
春闘は5月いっぱいで終結。スタッフはスケジュールの遅れを時間外の連続で取り戻し、なんとか7月1日の封切りに間に合わせた。
三隅監督はこの作品により、前作の勝新太郎主演『座頭市物語』とともに感覚的で虚無的な映像美を描く異色な監督として注目されていく。
当時の新聞に載った映画評に「こんなに美しく殺人を描く三隅研次は、無意識の作家か」とあったのを今に覚えている。
次の仕事も三隅組。作品は、仙台藩伊達家のお家騒動を題材にした山本周五郎の小説を原作とする、長谷川一夫主演の文芸時代劇巨編『青葉城の鬼』だった。
しかしチーフ助監督には2期先輩が配され、私が再びチーフになるのは3年先の話となる。
製作準備でゴタゴタしている間に、彼女との関係は結婚に向けて進展。結納は売買婚の名残だと思いこんで避けていたが、先方の母親の要請でプレゼント交換ぐらいはとなり、私は真珠の指輪を贈り、彼女は私の手首に腕時計を巻きつけた。これまで腹時計でいっさい済ませてきた私は、腕時計に束縛されることになった。結婚式の日取りは、撮影スケジュールを延ばしがちな三隅監督の仕事ぶりを考慮して、完成予定日の10日先に決めた。
次は式場だ。信じられない神仏の前で結婚を誓うのは嘘になる。あるレストランに彼女と出向いた。ここで結婚式を挙げたいという私たちに、支配人は披露宴の申し込みかと思いこんでいる気配。「結婚式は平安神宮ですか、北野神社ですか」となかなか呑み込めない。「ここで式も披露宴もするんです」と納得させ、結婚行進曲の用意を含めて交渉を済ませた。残りの手配はほとんど彼女に引き受けてもらった。式の翌日、彼女の家族は東京へ移転することになっている。
しかし、『青葉城の鬼』の完成は予定日を越えて、どんどん先へずれていく。
(2009年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第53回「“融合するか、水と油?”の時代」 |
1967年(昭和32年)夏。果たして結婚式に間に合うかどうか。私の苛立ちを尻目に、三隅研次監督作品『青葉城の鬼』の完成は遅れに遅れた。
<助監督は親の死に目に会えない職業>
オーバーな話かも知れないが、チーフ、セカンド、サードとチームを組んで細かい役割を受け持つ助監督を7年もやっていると、いつしか私は、映画制作に参加していると親の死に目に会えないこともあると覚悟を決めていた。
映画の制作スケジュールは、天気の都合でロケーションやオープンセット撮影の予定が狂ったり、監督の演出に思わぬ時間や手間がかかったり、他社と掛け持ちの俳優さんが出番に遅れるなど、つねに変動が激しい。いつどうなるかわからないのだ。従って私事に関する予定は、かなり余裕をもって立てることにしていた。変更ができない結婚式の日取りには、とくに余裕を持たせていたつもりだったのに……。
結局、『青葉城の鬼』の完成試写を終えたのは結婚式の当日、8月26日午前2時過ぎのことだった。ふらふらになって帰宅してみれば4時近い。疲れ果てた姿では結婚式には出られない。式は10時からだ。「少し睡眠を取るから先に出かけて」と母に頼んでふとんに潜り込む。ふと気がつくと10時近い。タクシーを飛ばして30分の遅刻。母がポツンと建物の外で待っていた。
式場ではひっそりと参列者が待っていた。妻側から病気療養中の父を除いて、母・弟・妹など親族6人。親族の少ない私側からは母に叔父と従兄、数合わせのため3人の知人に出てもらうことになっていた。しかし、東海地方に早朝から台風襲来。東海道本線が不通となり、名古屋方面から来るはずの叔父と従兄が出られなくなって、式はもっと小人数になった。
結婚式は、場外に出た私の合図で、店の人が『結婚行進曲』のレコードをかけることから始まった。曲に合わせて私たちカップルが入場し、席について挨拶。続いて私たちを紹介した奈良女子大の先生と知人の1人にお願いし、婚姻届の証人として参列者が見守る前で署名押印していただくことで式を済ませた。その後は小人数で和気あいあい、談論風発で宴を閉じた。
母子家庭の簡素な暮らしで育った私は、少年時代から抱いた天皇制に対する疑問や戦争・空襲体験などから形式や儀式張ったことが嫌いになった。結婚式に関しても、最重要は結婚の約束であり、その時点からずれた結婚式は月遅れの月刊誌を読むように間抜けたことに思っていたが、私たちの月遅れは意外と面白く読めた。
かくして、片や官僚の娘。片や没落小地主の田舎ん坊。強いて共通点といえば、お互い美術が好きなこと。育ちも価値観も違い、強者・富者にあこがれる女と、弱者・貧者に共感する男の凸凹生活がはじまった。
その日宿泊したのは、瀬戸内に面した漁港近くの旅館。翌未明から、新婚の私たちを祝福するのか、あざ笑うのか、焼き玉エンジンの音をポンポンと何かが弾けるように響かせて、幾艘となく漁に出て行った。
「お地蔵さんが取りもった縁だ。うまくいくだろう」
結婚前後のどさくさが去って、教師の妻は私立女子高校の勤務にもどったが、私の方は助監督を宰領する幹事の配慮か、山本薩夫監督作品『忍びの者』の応援に就く程度。
「結婚したからには頑張らなくちゃ」と言ったところで、「何に頑張るんや」。
風格ある文芸時代劇巨編、颯爽痛快股旅時代劇、異色感動のドラマ等々と、下っ端助監督の手の届かないところで企画され、シナリオ化されて製作現場に降りてくる作品は、けっこう知恵を絞っているだろうけれど飽き足らないものばかり。
「それじゃ俺が」と構想を練りはじめたのが、仮に『深夜の殿様』と題する時代革命喜劇だ。
時はアメリカの捕鯨が最盛期を迎え、黒船と呼ばれた捕鯨船がしきりに日本の沖合を往来し始めた頃。海に面するある藩の若殿が、長崎に遊学してフランス革命のことを知る。帰藩した若殿は、生まれたときから養育係を勤めてきて信頼できる老臣に、欧米遊学の計画を打ち明けて気脈を通じ合わせ、密かに冒険心に溢れる屈強な若者を10数名募る。漁に出て漂流に見せかけ、救助に来た捕鯨船を買収して先ずアメリカへ。
老臣は息子やその親友に協力させて、若殿御殿を厳重に藩士の目から遠ざけ、若殿の乱心平癒を待つ状態に見せかける。
一方藩は、藩主が病気になり、生きている間に跡継ぎを決めて幕府に届けなければならない状況になる。跡継ぎもなく藩主が死ねば、幕府によって藩は取りつぶされる恐れがある。若殿乱心を利用して、藩主の弟が跡継ぎになろうと陰謀をたくらむ。
そして3年後のある夜、どこからともなくセレナーデが流れ、城下は甘い雰囲気に包まれる。若殿一行が深夜密かに帰藩したのである。それも青い目の恋人を連れて……。
フランス革命の経緯や欧米の新知識を学んできた若殿は、先頭に立って藩民を教育指導し、民主革命を進めていく。
藩の革命を内乱と受け止めた幕府は、監察のため大目付を派遣する。奴踊りを先頭に「下にー下に」と城下を進む大目付の行列を、若殿は家臣にマーチを演奏させて混乱に陥れる。
しかし10月の半ば、日本の陰湿な壁を破りたいと進めてきた構想は断ち切られた。正月封切りの主演市川雷蔵、監督三隅研次の『新選組始末記』に就くことになったのである。
映画の内容は、武士らしい武士が少なくなった幕末期、武士出身の若き剣客・山崎蒸(雷蔵)が、その理想像を農民上がりの近藤勇に見出して佐幕派の新選組に入り、人を斬り殺すことによって、自分が生き残る努力をする話だ。
その背後には、組の内紛による近藤たちの局長暗殺、勤王派の黒幕に対す拷問、勤王派が集まった池田屋への襲撃など陰惨な事件が生々しく連なる。
このようなシナリオを三隅監督は、リアルに描くためと血糊を多用し、グロテスクで凄惨な殺人を演出した。
『新選組始末記』の評判は記憶にないが、私の構想しているドラマとは全く対称的だった。
私は一緒に就いていた先輩助監督に『深夜の殿様』の原稿を読んでもらっていたが、黙って返された。
後に、彼は近しい人の間で「助監督で最大のライバルは辻だ」と、密かに漏らしていると知る。賞賛か、警戒心のあらわれかと判断に迷った。
この頃、会社は業績の不調な経営体質改善を図って、株の無配を考えているとの噂を聞くようになる。
年明けて1963年(昭和38年)。正月早々『新選組始末記』は賑々しく封切られたが、前途の不安は増すばかりだった。
(2009年10月記)
⇒ 目次にもどる
| 第54回「“映画づくり+子づくり”の時代」 |
1963年(昭和38年)3月、数々の映画賞に輝いたことが自慢の、わが大映株式会社の株はとうとう無配に転落した。
前年3月には、テレビの受信契約が1千万台を突破していた。もはやテレビの流れは食い止められないのだ。経営面の暗い話に、撮影所は湿ったムードに包まれた。
当時私は、監督井上梅次、主演市川雷蔵の 『第三の影武者』に就いていた。原作は残酷物で流行作家となった南条範男の短編小説だ。
映画の内容は、戦国時代に城主(雷蔵)に似ているところから影武者にされた軽輩の武士(雷蔵)が、やがて残酷な城主を殺し、自ら城主になりすまして強く生き抜こうとするが、最後には無惨な生涯に終わるというものである。
4月に入ると、春闘の波に乗って賃上げ闘争は激しさを増していくが、井上監督は春闘の合間を縫い、持ち前の時間や状況に合わせるスピーディな演出によって、残酷さとエロティシズムの充満した異色時代劇を完成させ、封切りにしっかり間に合わせた。
完成試写の結果はかなり好評だったようだが、私には面白くなかった。城主と影武者の1人2役は、雷蔵さんの演技に惹かれる人には面白かったであろうが、リアリティや内容を気にする私には、映画の特質に頼った安易で不自然な、子供だましのようで納得できなかったのだ。ほかに方法はなかったのか? 文章表現と映像表現とは違うのだ。後年の黒沢明監督作品、仲代達也が2役を演ずる『影武者』も同様に感じた。
というわけでもないだろうが、試写会での記憶はぼんやりあるものの、製作に関してどんな仕事をしたのか、全く覚えていない。
この間、『野の仏』が取りもつ縁で結婚した妻の妊娠と、腹の中で成長しつつある胎児の動きに気を取られていた気もする。妻の腹に手を当てると、いつの間にか成長した胎児が、脚で蹴るらしいのが伝わってきた。由来に思いをはせて、自分が生物の一種であることを実感した。
ところで風俗考証の参考にと古本屋で求めた1冊に、1946年(昭和16年)発行の『日本風俗史』がある。その序文の冒頭に、著者の風俗史家・江馬務は記している。
『風俗といふ語は、支那では、風を自然に起こりし人類の行動、俗を意識的に起こりし行動と解しているが(風俗通)、この定義は曖昧を免れない。我が国では之を古来「てぶり」「ならはし」と譯して、人類の行為とその慣習となれるものと解し、その方が寧ろ意味が明白であり、之を約言すれば人類の生活相といふこととなる。(以下略)』
『風俗通』は、2世紀頃の後漢に仕える博学の応劭が、中国古代の事物や名称の意義を検討し俗説や邪教を正しなおした書である。江馬は『風俗通』の定義を曖昧だとして、我が国に古来から伝わる譯を紹介して解説しているが、私には『風俗通』の定義の方が意味が明白に思えた。
「私たちカップルが行っている行為。これこそ風俗の風ではないか」
この辺りも、風俗学を勉強しようと、後に現代風俗研究会に入会した遠因の1つとなった。
さて春闘の方は、24時間ストを2次にわたって打ち、第3次を通告して何とか解決した。しかし5月末、会社は再建策として、営業面では大作主義、製作面では3年以内に京都撮影所を閉鎖して東京撮影所へ移転する構想を発表した。
「そんなことを絶対にさせるもんか」
撮影所の東京移転構想に社員はどよめいた。
その頃、私は三隅研次監督作品『舞妓と暗殺者』に就いた。
内容は、幕末の京都を舞台に、高田美和が演ずる祇園の舞妓と、下級武士の惨めな境遇から脱藩して討幕派の一味に加わり反対勢力の暗殺に命を賭ける若者との純愛物語だ。
予告編は私が担当した。高田美和が激しく頬をふるわせて「うちは貧乏きらいや!」と叫ぶ場面を効果的に使ったため、賃上げ要求の春闘が終わって間もなかったからか、本社試写で永田社長が「この作品は、傾向映画か?」と、思わず戸惑いの声を挙げたそうだ。この報告を宣伝部から聞いて痛快に感じたことを覚えている。
傾向映画とは、1920年代後半の世界大不況期を中心に、商業映画の中で社会の矛盾を訴えたプロレタリア映画のことである。日本では鈴木重吉の『何が彼女をそうさせたか』、内田吐夢の『生ける人形』、溝口健二の『都会交響楽』、伊藤大輔の『下郎』などがある。
次に就いたのが、大監督・衣笠貞之助の『妖僧』だった。
<一代の怪僧として歴史にその名をとどめる弓削道鏡を主人公に、巷間伝えられる伝説にこだわらず奔放な想像力を駆使した文芸大作>というのが売り文句。製作は永田雅一社長だ。
台本を読んで、これが会社の再建策とされた大作主義の一端かと思うとがっかりした。内容は、病気を治した縁で称徳女帝の寵愛を受けた道鏡が、政界に進出したものの政治的野心にとらわれることもなく、女帝への愛に身も心も焼き尽くし、女帝の死を追って死んでいくというもの。要するに、貴族たちが権力闘争に明け暮れた歴史を無視した奈良時代のメロドラマに過ぎなかった。
或る日の午後、衣笠監督邸でメインスタッフや助監督を集めて打合会がもたれたが、監督は終始セットの設計図に身をかがめ、美術監督とセットデザインの打ち合わせを続けるばかり。内容や演出に関しては、他のメンバーとほとんど話し合うこともなく解散した。
「こんなんやったら、美術だけ呼んだらええやんか」
帰り道、美術監督以外はぶつぶつ不平を並べたが、私には、ドラマづくりにこだわる溝口健二の作品と、画面作りにこだわる衣笠貞之助の作品との違いが納得できて面白かった。
以前、溝口が監督した『新・平家物語』の画面は、画面の外へもドラマの広がり感じさせたが、衣笠が監督した『義仲をめぐる三人の女』は、画面内で如何に大勢の武者が演技していても、画面の直ぐ外にはライトやレフの存在を感じさせられたのだ。
また、衣笠監督の撮影は「用意!」と「スタート!」の間が長いことで有名だった。
撮影準備が整って「本番!」と助監督の声。カメラサイドの椅子にかけた衣笠監督が「よーい、よーい」と繰り返すうちに「ちょっと待った!」と、出演者が広げる着物の裾を直しに行く。また「ようーい」を繰り返して、今度は髪の毛の垂れ具合を直しに行く。
時には「バカモーン、鋏持ってこーい!」と、鋏を持って木の枝や葉を間引いたり、形を切りそろえに行く。本番前の手直しが多い衣笠組には、いつも大道具のバンバちゃんと美術助手のカモンちゃんがセット付きになっていて、監督はどちらかに用があるとき、「バカモン」と叫んでいた。
毎日のようにラッシュを見ても、宮廷の雰囲気が重々しく表現されているばかりで、ドラマの面はぱっとしない。私たちの不評を耳すると、監督はいつもニコニコと反論した。
「いやいや、あれでお客さんは有り難がるもんや」
完成後間もない10月2日、長女が生まれた。授乳時になると、新生児室から看護婦さんたちがそれぞれの母親の部屋へ抱いていく。その情景を遠くから眺めていて、自分の子が瞬時に見分けられるのが不思議だった。水鳥の繁殖地で、大群の中を間違えないように母鳥がわが子に餌を運ぶことを連想して、自分は生物の一種だとの思いを深めていった。
ベッドの上で乳房を吸わせながら長女と一体になってくつろいでいる妻の方は、どう考えているかわからない。
(2009年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第55回「“三島由紀夫に操られてたまるか”の時代」 |
1964年(昭和39年)、生まれて2月目の長女を抱いて正月を迎えた。後ろから若い芽が育っくる。なんと生物的にバランスが取れていることか!私は、精神衛生上なんとも言えない快さを感した。
「よくぞ生まれてきてくれた!」
正月明けから、私は三島由紀夫原作、主演市川雷蔵主演、三隅研次監督作品『剣』に就くこになり、台本を読んでうんざりした。その硬直した主人公国分次郎(市川雷蔵)の設定や内容に戦時中の旧制中学で嫌な思いをした部活動を連想したからだ。
少年の頃から剣道一筋に生きてきた国分は、某私立大学剣道部の主将になると、全国大会優勝を目指し、部員を励まして猛稽古に追い込む。しかし夏休みの強化合宿の最終日、全員鉄則を破って海水浴を実行。その夜、裏山から剣道着姿の国分が死体で発見される、というの台本のあらすじだった。
製作準備打ち合わせの中で、私の問いに三隅監督は答えた。
「強者の自殺がテーマや」
「へえ、強者が自殺するんですか?」
「強者のまま、自殺することによって自分の意志を貫いたんやな。いさぎよい人生や」
なんと感傷的な。部員に背かれた程度で、自殺することが三島の美学か?
三隅監督は大学一般の問題として制作したかったのか、京都大学の剣道部からロケハンしいというので、つい言ってしまった。
「『剣』に書かれているような剣道部は、私立大学ならあるかもしれませんが、今どきの国公立にありませんよ」
京大剣道部をたずねてみると、三隅監督の説明を全部聞かないうちに、「うちの剣道部は自ですから」と、マネージャーは一笑に付した。同志社大学へ行っても、京大ほどではなかったがかなり自由の雰囲気がただよっていた。仕方なく私立R大学へ行ってみると、それがあった。私カルチャーショックを受け、思わず胸の内で口走った。
「日本の秘境ここにあり!『剣』より、ここの記録映画をつくった方が面白いじゃないか」
その日は先輩が稽古をつけに来る日であったらしい。先輩が入り口の土間に立つと、稽古中あろうと、すべてをさしおいて数十人の部員全員が上がり端に駆けつけ、膝と手をついて「お願しまーす!」と大声を張りあげる。
先輩が着替えの場にすわると、部員が1人ずつ傍らに正座し、先輩が脱ぐ衣服を丁寧に折りたんでいく。付ける順番に剣道具を手渡す。そして稽古は再開する。稽古が終われば面を外て、部員が下座へ何列かに居並ぶ。上座に先輩が居並ぶと、主将が先輩たちに声を張り上げる。「本日は有り難うございました。○○さんから本日の御講評をお願い致します」
各先輩は指名されるごとに「おう、…」「おう、…」と講評。終わると、当番が各先輩の着替えを伝う。先輩が去りかけると、また部員全員が上がり口に駆けつけ、正座して大声に送り出す。
「本日は有り難うございました!」
なんともったいぶった先輩と、ことさらにかしこまった後輩のドラマだ。
戦時中の中学で、私は先輩たちに脅されて銃剣道部に引っ張り込まれたが、敗戦後は先輩ちに頼まれて相撲部に入り、先輩後輩のへだてなく、楽しく相撲に励んできた。その経験から、戦後わずか10数年で、ここまで戦前の雰囲気が復活してるいるのかと、感無量だった。
結局、R大学剣道部が、『剣』の製作を応援することになった。R大剣道部監督と三隅監督と大学の同窓ということで、最初から話ができていたようだった。
撮影にはいると、実にR大剣道部は使い勝手がよかった。学内試合とか稽古など、剣道部員が大勢必要な道場の場面には、俳優さんに交じってR大全員が出演してくれた。その他大勢の道部員をエキストラで間に合わせていたら、撮影現場は混乱したはずだ。主将に伝えれば即時員に要望が伝わるR大部員の応援のおかげで、私たちスタッフは実に助かった。そのことをR大督に言うと「そりゃ、奉仕の精神が剣道部のモットーだから」と返答があった。
映画の内容は、夏の出来事だ。しかし製作日程は1月と2月の間。強化合宿の全場面は広県の鞆の浦で撮影することになった。海水浴の出番が来ると、R大全員が冬の海に駆け込み、気いっぱい演技し、監督は満足のカットが撮れて喜んだ。
クランクアップの日、R大監督は剣道部員に関する感想をメインスタッフに求めてきた。答え一様に感謝と賞賛だったが、私は感謝のあとに疑問をつけ足した。鞆へ向かう混み合った車で、R大部員たちが座席をわがもの顔にして他の乗客に気遣いしなかったことを説明し、剣道がかかげる“奉仕の精神”は部内限りものかと尋ねてみた。周りのスタックは顔をしかめたが、「よ気づいてくれました」と監督は暖かくお礼を述べた。
こうして、私には堅苦しく滑稽で、哀れな時代錯誤に思える『剣』は完成した。
ちょうどこの頃、私は三島由紀夫がカニを怖がることを某文芸誌で知った。三島は、カニと聞ただけで顔面蒼白となり、身ぶるいして鳥肌立つというのである。その筆者は、三島のカニ恐怖は、彼の文学には関係ないように解説していたが、私は大いに関係していると思った。
蛇の画面を見ただけで、悲鳴とともに飛び上がる人。ニワトリが近づくと手が震えてマッチのれない人。生き物に対する恐怖症にはいろいろ接したが、特筆すべきは有名俳優の化粧箱持をしていたAさんのカエル恐怖症だ。ある春先のロケ現場で、小指の先ほどの小さなアマガエルスタッフの1人が、Aさんのシャツの胸ポケットに放り込んだ。トタンにAさんはケイレンを起こしてっ倒れ、口から泡を吹いた。悪戯のつもりが飛んでもないことになって、私たち周りのスタッフもあわて。ケイレンするAさんの身体を押さえつけてカエルを取りだした。その後Aさんは、30分近も立てなかった。カエルを除かなかったら、Aさんは死んでいたかも知れなかったのだ。
さて三島は、いつからカニ恐怖症になったのか。生来病弱だった三島は、幼児から中学生にるまで両親から引き離され、ヒステリックな祖母のもとで男の子らしい遊びもできず、女言葉を使て育ったそうだ。この間に、三島はカニ恐怖症になったのだろうか?
当時は軍国主義全盛への時代。男の子であれば、立派な軍人なることが夢であり、天皇のた戦争に参加して、忠義の戦死することが名誉の時代である。三島のカニ恐怖症を腕白坊主がったら、男の勇気を試すと三島の口にカニを押し込むような悪さをするかも知れない。そうなれ命取りだ。意識的には時代のせいで軍人にもなりたいし、名誉の戦死もしたいが、体格・体質がわない。歌舞伎好み、小説好みの祖母に育てられた影響で、小説家や劇作家ならばなれるかもれない。戦争が終わると、三島の多彩で豊かな才能は、矛盾をはらみながら各分野に分裂して虚構を飾り立てていったものと、私には思われた。
もともと三島文学には、あまり関心がなかったものの、58年に『金閣寺』を原作にした市川崑督の『炎上』に就いていたとき、新婚旅行でセット見学に訪れた三島がそぼ降る雨の中を、片手蛇の目傘を差し、片手で妻の肩を後ろから背伸びして抱いていく、いかにも作り物めいた男のを見て以来、文学もさることながら、彼の人生に興味を持つようになった。
そして数年後、2・26事件を背景に、軍刀で割腹自殺した軍人の屈折した忠義と、手本を引写したようなラブシーンを描いた『憂国』を読んで、三島にうさん臭さを感じはじめた。
「三島さんよ。自分の不安をごまかさんで、本心に立ち返ったらどうやね」
しかし、シャープな演出と雷蔵の演技と相まって、三隅監督の『剣』が三島ファンに喜ばれるこは予測できた。
(2010年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第56回「“宙に浮いた気分”の時代」 |
1964年(昭和39年)4月、10年ぶりに大映京撮監督室へ新風が吹き込んだ。
それまで企画部からの配転など同年輩で助監督を補充していたところへ、4人の新卒若手が一挙に入ってきたのである。当時衰退傾向の映画界にあって、勝新太郎主演の『座頭市』シリーズなどにより大映だけが持ち直しを見せ、将来に向けて体勢強化と若手育成を図ったのだ。
さて私は、三島由紀夫原作・三隅研次監督『剣』の後、市川雷蔵主演・田中徳三監督『忍びの者・霧隠才蔵』を済ませると、秋から三隅監督『座頭市血笑旅』に就いた。勝さんと仕事をするのは井上梅次監督『女と三悪人』以来3年ぶりだった。
座頭市シリーズ8作目ともなると、豪快・滑稽・繊細を取り合わせたキャラクターは格段に磨きがかかっていた。
作品のあらすじは、甲州路に足を踏み入れてヤクザの事件に巻きこまれた座頭市が、5人組の殺し屋に狙われながら、自分の身代わりに殺された若い母親の赤ん坊を抱えて子守の旅をつづけるというものだ。
しかし、座頭市だけに注目していればそれなりに面白いが、筋全体を通して考えると、あれこれ疑問がわいてくる。ヤクザ同士の義理や人情のための果たし合いとは言え、どうして大勢が座頭市に次々と斬りかかっては殺されていくのか。殺されに出て行くのが馬鹿らしくならないのか。以前の「チャンチャカ、チャンチャカ、チャンチャカチャン」と音楽が入るロマンチックな舞踊的チャンバラ映画の時代には気にならなかったろうが、黒澤明監督の『用心棒』や『椿三十郎』以後のリアルさを求める剣劇映画になると、圧倒的な強敵を恐れて義理や人情を欠くようなドラマが、刃向かう側の間で発生するような気がしてならない。
ときあたかも、この年の前半は安部公房原作・勅使河原宏監督『砂の女』、アラン・レネ監督『去年マリエンバードで』、イングマール・ベルイマン監督『沈黙』などの前衛的な問題作が上映されて、私にはかなり刺激的だった。
また8月早々にはベトナム戦争がはじまり、東京をはじめ各地で社会・共産・総評など多くの革新団体によるベトナム反戦運動が展開されていた。先の戦時中、私は現人神・天皇を人間と認識した小学5年生のときから戦争反対派だが、軍隊嫌悪派でもあったので、団体行動に参加する気にはなれず、イライラしながら新聞やテレビの報道を見守った。
こうした時代を背景に『座頭市血笑旅』は、私を精神的消化不良に陥れながら出来上がっていった。
そして冬のかかりから、正月作品として製作される市川雷蔵主演・三隅監督の『眠狂四郎炎情剣』に就いた。
この仕事で印象的だったのは、札差(江戸時代、旗本や御家人の代理として禄米の受領と、その換金を請け負った浅草蔵前在住の商人)の看板を考証することであった。
私は近世文学研究で有名な京都大学の野間光辰教授を訪ねたり資料を調べたりして、札差に看板はないと結論を出した。しかし監督は承知しない。当時私も考証力には自信があったので自説を主張したが、決定は監督次第でどうしょうもない。
そこで私は、艶本研究家の林美一さんが出している個人誌の購読者であることから、横須賀市のお宅に電話で相談したが、私と同意見。演出上どうしても札差の看板が必要ならこうすればどうかというデザインとメモに添えて、貴重な資料が参考にと送られてきた。しかし監督はOKしない。
「なんで元大映社員に聞くんや。信用できない。もっと専門家に聞いてんか」
それではこの学者ならと訪れた立命館大学の林屋辰三郎教授から、札差研究の第一人者として少壮学究の脇田修さんを紹介された。すぐさま脇田さんのご都合に合わせ、夜おそく向日町(現・向日市)のご自宅訪問。事情を聞くと、すかさず脇田さんは、いともあっさり述べられた。
「看板に関しては、林美一さんの方がご専門ですよ」
結局札差の看板は、林さんの意見を参考にして作られた。
当時林さんは、数年前に出版した『艶本研究・国貞』の特製本購入者に贈呈した『参考資料』(伏字集)が、猥褻図画頒布罪に問われて裁判中でもあったので、三隅監督は林さんとの関わりを避けたのかも知れなかった。何回かの電話の中で、林さんは苦情を漏らした。
「国貞を買ってくれた人で、よその人はみんな国貞は良い本だと裁判で弁護してくれたが、大映の人たちは誰も弁護してくれなかった」
私は三隅監督も購入していることを知って感想を求めると、迷惑そうに一言答えた。
「しょうことなしに買わされたんや」
『眠狂四郎炎情剣』も、狂四郎だけを追っていればクールで格好いいが、作品全体からは疑問が浮かんでくる。
シリーズ5作目となれば、江戸の町で狂四郎の強さは知る人ぞ知るのはずだし、剣客なら一度接すれば狂四郎の強さは判るはずだ。それにもかかわらず、上役に対する忠義だてか、狂四郎の刃で次々に殺されていく。
また下段の構えから刀身を上段へ、円を描いて半月の形にまで回し、狂四郎の目が刀身に隠れた瞬間をスキと見て、斬りつけてくる相手を瞬時に切り倒す円月殺法。1対1であれば颯爽と形よく決まるが、多数を相手にすれば役に立たないのだ。
私の思いをよそに、『眠狂四郎炎情剣』は正月封切りを目ざして製作が進行していった。
ところでこの年は、私より7年後に入社してきた森弘太君から、広島の原爆被害に関する意見をよく求められた。彼は広島の原爆被害者をテーマに映画をつくるつもりだったのだ。
しかし私は、小学3年生のとき南京攻略戦の経験者から、気の向くままに中国の女性たちを暴行殺人した話を面白おかしく聞いて、おれも大きくなったら軍人になり、戦地へ行って同じようなことをしてみたいと、猟奇的な加害意識を一時的にも抱いて、その経験から、敗戦後は中国に対して戦争加害に対する責任を果たさねばと意識している人間だ。森君の話をおいそれとは聞けず、前々から抱いてる自分の考えを主張した。
テニアン島から、原爆を運んでくるB29爆撃機の搭乗者たちの様子と、天皇に忠義を尽くして日本は勝つんだと頑張っている軍都・広島市民たちの状況をカットバックし、世界の民主主義を守るという大義と、東亜の盟主として大東亜共栄圏を守るという大義とが、最後にぶつかり合って大惨事を引き起こす。この人間のどうともならない悪業を表現したいというのが私の考えだった。
森君は翌年大映を退社。フリーとなって自主製作に乗り出し、2年後に広島の被爆者を題材にした『河―あの裏切りが重く』を完成させて注目を浴びた。
この時期、私は社会情勢にも乗り切れず、一緒に仕事を始めた新人助監督たちとも歳が離れすぎて意思の疎通がままならず、欲求不満を引きずってどこか宙に浮いた感じだった。
それでも翌1965年(昭和40年)の正月は、1歳の誕生日を過ぎた長女を膝に抱いて迎えることができた。生まれたときはシワシワの子猿のようで上手く育つかと思ったが、よちよち歩きができる頃になると、「かわいいね。ちょっと抱かしてほしいわ」と方々で抱かれるような娘に育ち、私の宙に浮いた気分を地上に引き戻してくれた。私はしみじみ感じた。
<なんと生物的な営みのすばらしいことよ>
(2010年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第57回「“大映入社10年目に迎えた崖っぷち”の時代」 |
1965年(昭和40年)の正月は、行く先々で「かわいい」とちやほやされる孫娘のよちよち歩きを、嬉しそうに追う母の姿が印象的だった。その情景は、11年前私とともに裸一貫の状態で故郷・尾張清洲を離れた母が、やっと手にした幸せを物語っていた。
この幸せがいつまでも続くようにと、祈る思いで新年度の通勤をはじめた。
しかし、世間には厳しい風が吹いていた。物価高騰や株式市場の低迷など池田勇人内閣がすすめた高度成長政策の歪みの中、前年のオリンピック景気も終わって、世間は不況と倒産におびえていたのだ。その矢面に立たされていた会社の1つに、わが大映があった。テレビの進出とレジャーの多様化による観客減少で久しく衰退ぎみの映画界にあって、大映は永田雅一社長のワンマン経営による弊害もあり、他社に比べて経営基盤が弱かったのだ。したがって先鋭的となった労働組合は、春闘への狼煙をはやばやと上げ、総会を繰り返して意思統一をはかった。
この年最初の仕事として、正月気分が抜けた頃より三隅研次監督の『鼠小僧次郎吉』に就いた。それと並行して賃上げの春闘が始まったように思う。東京で行われる会社との交渉は、はかばかしく行かない。交渉に臨んだ組合執行部による報告総会がたびたび開かれた。賃上げの行方が気になっていたのか、『鼠小僧次郎吉』に関して、台本は残っているものの、どんな仕事をしたのか全く記憶にない。
まだ春闘続行中の5月、東京撮影所から初めて出向してくる井上芳夫監督の『青いくちづけ』に、チーフ助監督として就くことになった。チーフ助監督になるのは、三隅研次監督の『斬る』以来3年ぶりのことだった。
井上監督は東撮でも口数が多いとの噂があり、京撮では敬遠されるタイプ。先輩の間ではチーフに成り手がなかったので、監督室の幹事がチーフ級にまだ定着していない同期生の中から、好き嫌いのない、誰とでもフランクに接する私にお鉢を回してきた格好だった。
映画の内容は、北陸の温泉地から京都の大学に学ぶ女子大生が、一緒に上京した高校のクラスメートや大学で知り合った男子学生たちといろいろな人生経験をし、1人の男子学生と意気投合して青春を謳歌するというものだ。
温泉地の場面は、加賀温泉郷の片山津温泉でロケをすることになり、女子大生と男子学生が京都へ向かったり、京都から温泉地へ帰る車内場面は、ロケに向かう往復の車内で撮影することになった。
ところが5月の半ば過ぎ、クランクインした頃、東京撮影所で春闘に絡むトラブルが発生した。封切りに合わせてプリントしなければならない作品のネガフィルムの現像所への搬出を、組合員たちが阻止したのだ。
会社は直ちに、初めてのロックアウトを強行したり、警視庁警官隊を導入したりして、関係者6人を懲戒処分にした。
組合は対抗して、撮影所に懲戒処分の撤回を求める時間外拒否の遵法闘争を指令した。午前は9時から12時まで、午後は1時から5時まで。それ以外の時間に、組合員は絶対に仕事してはならないというのだ
遵法闘争は、渉外に無関係の撮影部や照明部、録音部などの技術部門は簡単に実行できるが、渉外が必要な助監督部、製作部、俳優部などは、ゲスト俳優のスケジュール調整や、必要品注文の変更やらに四苦八苦しなければならない。
それまでも闘争解決後さえ、助監督など渉外に関係ある部署は、さんざん苦痛を味合わされてきた。闘争によってスケジュールに遅れが出た場合、渉外と関係のない組合員スタッフは、遅れを取り戻して封切りに間に合わせようと、スケジュールの調整が下手だとか、準備が悪いとか、違う立場の組合員の尻を叩きにかかるのだ。
いつかの闘争解決後、ある組合執行部員がニコニコと撮影所長に話している声を耳にした。
「ご安心ください。必ず封切りには間に合わせますから」
以来私は、時間外であろうとスタッフルームに入って撮影の準備作業をしたり、小道具・持ち道具、衣裳が整っているか点検に行くなど、落ち度のないように自分のやり方を押し通した。
片山津ロケ往復の車内撮影では、昼の休憩時間にかかってはならない、またトンネルに入れば撮影できないので、列車時間表とトンネルの位置を示す地図と首っ引きで撮影計画を立てたり、監督に状況説明を密にするなど手を尽くしたが、撮影を完了するまで身の縮む思いだった。
丁度その頃、会社は東西撮影所の監督、俳優、技術者の契約者グループに闘争の実情を説明し、協力を要望していたという。そんな流れの中から、会社に協力的な新組合結成の動きが出てきた。組合に残るか、新組合に移るか、所内は動揺した。
助監督部でも各人の去就を決めようと、夕方から部会が持たれた。誰も言葉を発しない。時間は経つばかり。私は、これまでの組合に抱いてる思いや、家族の幸せを考えて、いつまでも闘争を続ける気を失っていた。子どもの頃から培ってきた私の人生観も、反抗的ではあるが闘争的ではない。私は立ち上がって第1声を発した。
「僕は、この撮影所に入って得るものが沢山ありました。入って間がない人と比べ、このまま組合に留まれば失うものが多いような気がします。新組合に移ります」
私の発言を契機に、先輩たちも口を開いた。ほとんどが新組合へ移るという声だった。
『青いくちづけ』はどうにか封切りに間に合い、7月の或る日、組合の分裂総会が開かれた。なんと、入社して10年間組合運動にタッチしたことがなかった私が、その議長に選ばれた。
総会は、去るも地獄、残るも地獄、お互いに恨み合わないということで、和やかに閉会した。
8月に入ると、母は叔父(母の弟)に誘われて身延山詣りから東京見物に行くことになった。姉弟いっしょの旅は、2人にとって初めてのことだ。母は喜び勇んで出かけた。しかし数日後、母は「センが出た」と倒れ込むように、旅の途中から帰ってきた。母が言うセンとは、昔から癪(しゃく)・差し込みと呼ばれ、胸や腹がキリで突いたように痛む突発症状のことだ。和裁で生計を立てていた母は仕事が立て込むと、よく「センが出た」と言って、数日寝込んだ。
「私の身体は私が一番よく知っている。寝とればその内に治るわ」
病院行きを強固に拒む母を、私はこの際とばかり、京都府立病院へ連れて行った。X線検査の結果、胆のうにかなり大きな石のあることが判った。医師は、母の血圧が下がりすぎているので、早急に手術はできないという。手術に備えての検査入院ということになった。
母の入院と同じ頃、私は市川雷蔵主演、三隅研次監督の『剣鬼』に就いた。そして完成後の10月19日、母の手術が行われた。母は「胆石手術は30分ほどで済みますから」と、医師に力づけられて手術室へ入った。同じ頃入室した患者は次々出てくるのに、母は出てこない。待ちくたびれた。3時間ほど経って、白衣に血痕を飛び散らせた医師が出てきた。私の目に閃光が走った。
「お母さんの胆石は、癌になっていました」
報告する医師の声が遠くなり、全身から血が引いていき、視界は暗くなった。私は懸命に身体を持ちこたえて、去る医師の後ろ姿を見送った。
(2010年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第58回「“生まれて以来の同志倒れる”の時代」 |
1965年(昭和40年)10月14日午前。摘出手術の結果、母の胆石はガン化していたのがわかった。何たることだ。当時偶然読んだ週刊誌の記事によると、胆石がガンに転化するのは20数例に1例だというのに。
そのうえ、病室へ戻ると、主治医が執刀外科医の診断を持って追い打ちをかけてきた。
「お母さんの余命は、あと3ヶ月です」
〈そんなバカな!〉私は言いしれぬ怒りを覚えた。
母はまだ56歳。胆のうを摘出して縫い合わせた傷口こそ無惨だが、母の肌はみずみずしく、乳房もこぢんまりとふくよかに整っているじゃないか。
数日後、出社すると新しい仕事が待っていた。さっそく私は、派出看護婦に昼間の母の看護を頼み、夜の看護は、仕事を終えた私がする段取りをつけて仕事に入った。準備中も最初のうちは夜に入る仕事がなくて何とかなったが、さすがクランクインが近づくとどうにもならなくなり、仕事を降りて母の看護に専念することにした。
私立女子高校の教師だった妻は、長女が1歳半になった4月、自分で子育てがしたいと時間講師に転じてはいたが、学校・同僚に多大な不義理をして突如退職し、母の看病を助けることにしてくれた。
さらに妻は自分の貯金を下ろして派出看護婦の支払いに当てた。それ以後家族は、不振続きの大映社員が置かれている不如意な境遇を嫌と言うほど味合わされることになる。
「思ったより検査の結果は良好だし、予想より保つのではないか」
という主治医の判断で、11月半ばに母は退院した。
母は「おばあちゃん、おばあちゃん」とまとわりつく長女を床に座ってあやしたり、「やっぱり家の食事はおいしい」と元気を取り戻した気配をみせた。
しかし母は、入院中から見舞客の多いのを不審に思っていた。
「こんな手術をしたくらいで、どうして大勢の人が見舞いに来てくれるのだろうかなあ」
母は親しい親戚・知人が見納めに来てくれることに気づいていなかったのだ。この時代、ガンの告知は病人にしないのが一般的だったが、隠し事の嫌いな私自身は、母と心の会話を深めるために本当のことを打ち明けたかった。が、あえてしなかった。最後まで希望を失ってほしくなかったからでもある。
妻は家事や2歳の長女の面倒を、母の看護は私が受け持った。母の食事は少量ながら1日4食。最後の食事は夜の12時前後になる。
妻たちが寝室に引き取った後、4食目の世話をし、母の横に布団を敷いて枕を並べ、一日中しんどかったこと、胃がむかむかすることなど、ポツリポツリと話し合う。
ある夜、母は昼間同じ夢を2回も見たと笑顔で語った。
「名古屋の姪の誰かは知らないが、子どもを連れて送りに来たと言うから、まだ私は死んでないから送ってもらわなくていいよと言うと、そうかと言って帰っていったけど、変な夢だね」
母は密かに死の近いことを予感していて、私の生後3ヶ月目に夫を失って以来、共に支え合って生きてきた私の心配を、少しでも和らげようと気づかっているようにも思えた。
その後、次第に母の頬はこけ、肌は衰えた。行動半径は徐々に狭まり、歩いて行けた便所は這って行くようになり、ついにはオムツを当てるなど、「余命は、後3ヶ月」という医者の言葉が真実として実感できるようになった。
いつからか、母は枕元に数珠を置き、経本を開いて見るようになった。
12月に入ったある夜、母はつぶやいた。
「寒い寒い、私はこのまま寝ていたらいいの?」
「うん、いいよ。安心して寝ていたらいいよ」
すでに実家の叔父叔母が、亡骸に着せる経帷子を用意してくれていたのだ。
大晦日の夜は、母が急に痛みを訴えたので、病院を紹介していただいた近くの家庭医に往診を頼んで、痛み止めを注射してもらうなど、慌ただしい年の瀬を送った。
明けて1966年(昭和41年)早々から、市川雷蔵主演、井上昭監督の『眠狂四郎多情剣』に就き、セカンド助監督として予告編を担当することにしたが、母の看病は相変わらずだった。
ある夜、母は横で眠っている私を「お腹が冷たい、お腹が冷たい」と言って私を起こした。布団の中に手を差し入れ、母の腹部を探ってみると、何だかベトベトしている。そのベトついた手を戻して近づけると、その強烈で不快な臭いに半ば卒倒しそうになった。その、くさいこと。まるで排便直後のニワトリの糞を何倍も凝縮した臭いだ。その臭いは今なお鼻が記憶している。
上布団を剥いでみると、縫い合わされた手術後のキズ口がぽっかりと開いて、膿をあふれ出していた。私だけではどうにもならない。起こされた妻も膿の臭いに仰天した。拭いたり洗ったりを繰り返して、何とか異変を治めた。
そして、予告編の製作が最終段階に入った2月中旬のことだ。夜遅くまでかかってフィルムを編集し、あと音楽ダビングすれば完成というところまで作業し、12時過ぎ玄関口まで帰ってくると、中から咽をがらがらさせているような音が聞こえる。
「あす朝診に来ると言って帰られたお医者さんの診断では、肺水腫を起こしているらしいの。」
母は仰向いたまま口を半開きにし、うがいをするように咽をがらがら言わせている。語りかけても無表情で会話の余地はない。しかし、最後に言うことはないか、いつか声を発するかも知れない。並べた布団へ横たわってじっと様子を窺った。
私は母の余命を聞いてから言いしれぬ怒りを覚え、母を常識的に弔いたくなかった。私独自の弔いをしてやりたかった。予告編が完成したらゆっくり考えよう。
母を視ながら思いを募らせていて、つい疲れからか眠ってしまったらしい。
ふと目覚めると、妙に静かだ。外は薄明かり。サッと母の額に手を当てた。冷たい。母の口に耳を当てた。息をしていない。上布団を半開きにして、母の寝間着を開いた。脚や太腿の布団に接する面が紫色に変色している。知らない間に死んだのだ。
すべては予告編が終わってから。家庭医さんに往診を頼むと撮影所へ急いだ。朝一番に編集ラッシュの所長試写会がある。OKが出れば音楽を入れて予告編は完成となる。
しかし3分前後のラッシュ上映画面を観ている間、小学校入学時に母が戸籍謄本を見せて「お前は戸主だから先頭にお立ち。私は黙って後からついて行くから」と言い渡して以来、30年余歩いてきた2人3脚の人生模様が脳裡で点滅し、長い間忘れていた涙をにじませた。
ラッシュ試写は無事通過。「さあ音楽ダビングしょう」と促した編集マンが、いつもの私らしくないことに気づいた。母の死をぼそっとつぶやくと、みんなが騒いだ。「葬式は予告編が終わってから」と主張する私は、「後は誰かがするから」と、葬式を取り仕切るための庶務課の人たちといっしょに帰宅させられた。雪の舞う翌日、常識的な葬式がスムーズに済まされた。
母の人生は短かったが、可愛い孫の顔が見られたからいいやと、私は自分を慰めることにした。すでに妻は次の子を身ごもっていた。時は流れる。
(2010年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第59回「“旧日本の亡霊をモグラ叩きしながら”の時代」 |
「私らの会に入ってはったら、こんな不幸に合わはらしません。これを機会にお入りやす」
思っていたより早い母の死を聞きつけた創価学会のおばさんが、折伏に来て入会をしつこく勧めた。母の死から1ヶ月もたたない1966年(昭和41年)3月半ばのことだ。再三再四断っても、次々と有難そうな宗教論を吹きかけてきて一向に退散しようとしない。
かつて同じように折伏しに来た大映の同僚社員が、夜がふけるのもかまわず粘るので、「僕は淫祠邪教なら好きだが、そんな正しい、立派な宗教は嫌いだ」と追い返したことがあった。言い方は若気の至りだったかも知れないが。
今回も、言わずもがなのことを言って追い返さざるを得なかった。
「そうです。母は、私が殺したようなものだと自覚している。その何処が悪い。あなたがとやかく言う必要はないでしょう。それより、人の不幸につけ込んで折伏にくるような真似は、公明正大じゃない。あなたたちの会にとっても止めた方がいいじゃないですか」
「情けない人やなあ」
かつての同僚と同じような捨てぜりふを残して、おばさんは立ち退いた。
当時は、結党間がない公明党の母体として、創価学会は会員増大を目ざして“折伏大行進”と称する大勧誘活動を展開していたのだ。
(大行進は3年後、その強引な手法が社会問題となり、ひとまず終幕を迎えることになる。)
4月中旬、三島由起夫による原作・主演・監督の『憂国』が東京で封切られ、センセーショナルな注目を浴びていることを知り、観ないうちから不愉快になった。そうなるには、私なりの経緯があったのだ。
★ ★ ★
私は1958年に、三島の『金閣寺』を原作にした市川崑監督作品『炎上』の製作に携わって以来、三島に関心を払うようになった。
『炎上』の製作中に、三島は新婚旅行を兼ねて『炎上』のセット撮影を見に来たが、その時偶然目撃した三島夫妻のセットへ行く姿が、今も目に焼き付いている。
「普通に相合い傘で行けばいいのに、ことさら格好を付けて」
三島は小雨の中を右手で蛇の目傘を差し、背が足らないのか、背伸びするようにして左腕を後ろから新妻の肩に回して歩いてくる情景が、いかにも妻を保護しているといった、典型的な日本の夫振りを意図的に無理して演じているようで、あまりにも滑稽に感じられたのだ。
そして1961年、三島は2・26事件から題材を得た小説『憂国』を中央公論1月号に発表した。内容は、主人公である若手将校の親友たちが日本の刷新を目ざして決起したものの、昭和天皇の激怒にあって反乱軍とされてしまい、その討伐を命じられそうになった主人公は、「親友を討つことは俺にはできん」と、自分は切腹し、妻は夫の死を見届けて後追い自殺するというものだ。軍が敵味方に別れて争う国の状況を憂うのが作品のテーマらしいが、それより気になったのは、『炎上』製作中にセットへ向かう道行きで、三島夫妻が見せた関係位置が、『憂国』の主人公夫妻に重なり、旧弊な夫の身勝手な倫理が美化されていることだった。
★ ★ ★
4月の末、東京の日比谷公会堂で神社本庁、日本郷友連盟など右派的勢力によって紀元節復活をめざす「紀元節制定推進国民大会」が開かれたと新聞に記事が出たが、モグラ叩きのモグラのように、また過去の亡霊が出てきたかと、私は不愉快な思いに包まれた。
中国侵略戦争を続行していた小学5年生(1949年)のとき、私は日本の歴史をより詳しく知ろうとして古事記を読んだ結果、天皇の祖先である神々が、エロチックで人間味溢れる暮らしをしていたことを知り、果たして天皇は現人神かと疑問を感じた。天皇の写真に小便をかけてみても罰が当たらない。儀式で校長が広げて読んでいる教育勅語を、上から覗き見しても目がつぶれない。「ありゃ神さまじゃない、人間だ」と天皇崇拝の呪縛を断ち切った。
すると目から鱗が落ちるように、当時チャンコロと呼んで軽蔑していた支那人(中国人)が私と同じ人間に思え、南京事件などで日本軍が支那人をほしいままに暴行虐殺をしていることに強い罪悪を感じ、密かに中国分捕り戦争を拒否した。その後、とかく体格・運動神経・腕力にすぐれた私は、軍国主義の風当たりを避けるのに苦労した。そんな私にとって紀元節復活はナンセンスそのものだったが、復活運動はやがて「建国記念の日」として実を結ぶことになる。
5月の半ば、母に死をもたらした何ものかに対してやり場のない怒りを何とか鎮めたころ、監督室幹事から呼び出しがかかった。
「こんど井上組が立つんや。チーフをやってんか」
私がチーフ助監督になるのは、三隅研次監督作品『斬る』から、なんと4年ぶりのことである。先が思いやられた。
井上昭監督の作品は、主演安田道代(後の大楠道代)の明朗青春編『私は負けない』だった。 話の筋は、父の浮気から生まれた娘が、継母や腹違いの姉たちから女中代わりにこき使われても、持ち前の明るい性格を失わず、ついに実母に巡り会い、素晴らしい恋人を得るというものだ。 井上監督は大阪駅前の雑踏で盗み撮りを敢行したり、ディスコの場面には新進気鋭のコンボを起用するなど、新感覚をうかがわせる手法を随所に使い軽快なテンポの一編に仕上げた。
ところで製作期間中に、京都市内で『憂国』を観ることができた。評者の間では、洗練された構成と優れた描写で完成度の高い作品とされていたが、私には予想どおり、不器用なラブシーンとグロテスクの何ものでもなかった。その後三島は、昭和天皇に対する呪いや批判をテーマとする『英霊の声』を発表したり、自衛隊に体験入隊したり、民族派の学生を中心に民兵組織「楯の会」をつくるなど天皇制に関する問題意識をますます深めていく。
また『私は負けない』の製作たけなわに次女が生まれた。私たちカップルは、長女には心の寛い人になるの願って命名しているので、次女には伸び伸び育ってくれることを願って命名した。作品が完成した頃には、あやしあやされる長女と次女、2人の姿が何ともいえない愛らしい情景をかもし出していた。
「何とセックスは……」
一人っ子で育った私は、生物としての営みに改めて素晴らしさを実感した。
夏のかかりに就いた次の仕事も井上監督のチーフだった。
作品は新藤兼人の原作・脚本、勝新太郎主演の『続・酔いどれ博士』。傷害事件を起こして免許を取り上げられた外科医が、あるスラム街にふらりとやってきて、街にはびこる悪党の本拠をブルドーザーでぶっ壊すと、またふらりと立ち去っていくという、ヒューマニズム溢れる暴力編だ。
まず、スラム街のセットを作るための参考になると、大阪市大正区の埋め立て地にある通称オキナワ部落を訪ねた。そして驚いた。その被差別的な集落の佇まいに。
集落は街並みから遠く外れ、埋め立てのために運ばれたまま山並みに連なる土砂の斜面に、麓から積み上がるように寄り集まって、トタン屋根板張りの掘っ立て小屋のような住まいが建っていた。低地には家庭排水が広く溜まって汚水の池となり、いかにもヤマトンチュウによるウチナンチュウ差別の象徴的な様相を呈していた。
1時間ほどだけ接したオキナワ部落の情景は、いまも原罪として私の心の中に底流している。沖縄から米軍基地をなくせるのは何時の日か。
(2010年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第60回「“眠狂四郎と無頼を考える”時代」 |
1966年(昭和41年)秋、前年から米軍の本格的介入によって、ベトナム戦争はますます激化の一途。日米安保条約の義務を果たすべきだと、沖縄米空軍基地の使用を援助したり、LST(戦車揚陸艦)の乗組員を斡旋するなど、わが国は憲法9条を無視して間接的に戦争参加。それから派生する特需によって、日本の景気は回復し、国民の間には観光熱や消費傾向が高まりつつあった。
しかし、わが映画界は斜陽の一途だった。
9月の半ば、狂四郎シリーズ8作目『眠狂四郎無頼剣』に就いた。監督は三隅研次。市川雷蔵、天知茂、藤村志保などが出演した。
脚本は往年の大巨匠・伊藤大輔監督。読みはじめて、文体の格調は高そうだが、ふりがな付きの漢字や古めかしい漢字がパラパラと散らばっているのに往生した。
〈叱ッ〉〈嗟嘆〉〈竦然〉〈錯愕〉〈奴輩(やつばら)〉〈僵して〉〈淡如〉等々。
スタッフの間では字を知っている方の私でも、広辞苑や漢和辞典を片手に読まざるを得なかったのに、皆どうしたんだろう。
〈叱ッ〉は、どう読むのか広辞苑でもわからない。やっと漢和辞典で、いまいましいとき、意気込んだときにする〈したうち〉だとわかる状態だった。
ある日伊藤監督が、「そんなことは字引が間違っておるんじゃ!」と、大声を残して企画部室から出てくるのに廊下で出会い、ああいう老人にはなりたくないと、自戒の念を抱いたことを印象的に覚えている。
そして脚本を読み終えた。
〔何や、この題名は。「無頼剣」じゃなくて、「正義の剣」そのものではないか〕
話は、真っ昼間に江戸の油問屋へ浪人が押し入った事件から始まる。その裏に江戸全土を火の海にして、世直しの野望を遂げようとする暴徒一味のあることを知った狂四郎は、同じ流派の円月殺法の使い手・天知茂扮する首謀者・愛染と対決。
「城も焼け!大名屋敷、問屋・札差、焼きたくば焼け!ただ罪科(つみとが)もなく、焼き立てられて住むに家無く、食うに明日(あした)の生計(たつき)も絶えた八十万江戸の庶民を何とするのだ。主義が、主張がどうであろうと此の暴挙は愛染!断じて許さぬぞ」
愛染に勝って狂四郎の正義は成就するが、狂四郎と愛染が円月殺法で対決するのは伊藤監督の新機軸。下火になりつつあった狂四郎シリーズを盛り返そうと、会社は伊藤監督を脚本に起用した甲斐があったらしいが、私には題名に偽りがあるような気がしてならなかった。
かつて雷蔵さんと狂四郎について話し合ったことがあった。
「いつも狂四郎は無頼の徒ぶって出てくるが、途中でキャラクターを変えたように、お前たちの悪事断じて許さんとばかり、正義の人になってエンドとなるけど、無頼は無頼のまま終わるように工夫すると、もっと味が深くなるんじゃないかなあ」
「そんなら、どうしたらええのや」
「無頼がテーマになるのは、無頼というか、アウトサイダーになって、はじめて真実を見抜く目が備わるということだろが、悪事断じて許さんとばかり毎作品やってると、無頼というより単純な正義漢になってしまうような気がするよ」
「うーん、よう判らんけど、考えてみるわ」
この件について、その後雷蔵さんと話し合ったことはないが……
ところで、通行の庶民が激しいにわか雨に合うシーンの撮影のときのことだ。
通行人が雨宿りのために飲食屋へ飛びこんでくる。しかし藤村志保扮する女芸人は、からげた裾から雨に濡れた白い脚をなまめかしく見せながら、のれんの外の軒下にたたずんで中へ入ってこない。その白い脚に魅せられて、店の奥で狂四郎と同席していた髪結いの男が手許を狂わせ、続いて事件が起こるという話の筋だ。
私が、雨宿りにくる20人ほどのうち半数は店に入って飲食させ、軒先にとどまらせた人の間から女芸人の脚が目立つように演技指導していると、奥のカメラ位置から三隅監督が怒鳴り声を上げながら出てきて、女芸人以外は全部店の中へ入ってきて飲食するように演技変更した。
「通行人の中には貧しい人たちもいるでしょう。全部が全部、雨宿りの度に飲み食いするようなことはしないでしょう」
抗議しても、監督はだんまりだ。
「僕は僕なりに時代考証して芝居をつけていますよ。認識の違いが大きかったら、はじめに演出意図をきちんと説明して下さい。以心伝心は嫌いです」
チーフ助監督には、サードの頃から三隅監督に私淑して、ほとんど毎作品就いている先輩がいた。私は以後、内容にタッチせず、言われるままに現場処理し、予告編の制作に専念した。
10月下旬、『眠狂四郎無頼剣』は三隅監督のきめ細かい演出と、鋭利な画面構成が相まって、内容についてはいざ知らず、雷蔵ファンを喜ばす、尤もらしい時代劇映画に仕上がった。
この頃、名古屋大学・美学美術史研究室の恩師・柏瀬清一郎さんは、居心地が良いのか、京都の仏教美術研究のため2、3度わが家の粗末な小部屋に宿泊した。
柏瀬さんは2年前、名大が派遣したアフガニスタン学術調査団を率いて4ヶ月ほどアフガニスタンを訪れ、古代仏教美術を調査してきて、その報告書と論文をまとめる途上にあった。
私にとってほとんど未知の世界であるアフガニスタンのことを、柏瀬さんは「アフガンは、古代から東西文化の十字路だよ」と熱く語り、アフガンへ行くには使い古した旧式の航空機しかないから、まるで翼手竜に乗って行くようだよと笑わせた。
柏瀬さんの祖父は、足尾銅山鉱毒問題で政府に抵抗した明治の民権政治家・田中正造の弟子で、“困る”を意味する小さな丸を墨で書いたムシロ旗を立て、官憲を避けて逃げ回りながらも、樽を叩いて拍子を取り、八木節を唄って運動を盛り上げたそうだ。その話を、柏瀬さんは祖父から聞かされながら育ったという。
旧制浦和高校の同窓であった大映の井上芳夫監督によれば、柏瀬さんは学生寮の不潔王と呼ばれ、便意を催すと居室の窓から尻を突き出し、垂れ流していたそうだ。
深夜、警官の尋問にもビクともしない柏瀬さん。京都の有名なイノダコーヒー店では、砂糖で味付けした珈琲を店の味として出され、「勝手なことをするな、僕はブラックがほしいのだ」と抗議する柏瀬さん。後に、三派系全学連に共鳴する柏瀬さんは、民青系の強い名大から私大へ追い出されることになる。
年明けて1967年。丙午の年であった昨年の出生率は、前の1965年に比べて25%減少。人口統計史上最低と発表された。「丙午年生まれの女は男の寿命を縮める」などと伝わる迷信の影響だとのこと。正月の餅を食べながら、膝に抱いている丙午年生まれ半年目の次女に言う。
「迷信なんて無視して、名前どおりに伸び伸び生きていけよ」
(2011年2月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ