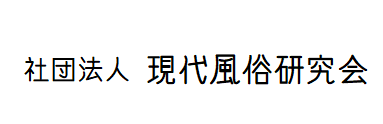| 第61回「“むなしい監督昇進”の時代」 |
「何だこれは」
1967年(昭和42年)新春早々、顔の欠けた巨大な石仏立像の珍しい写真葉書が舞い込んだ。名古屋大学美学美術史研究室の恩師・柏瀬清一郎さんからだった。写真はアフガニスタンはバーミヤンにある高さ55メートルの大仏で、前年死去した母の仏前に捧げますというのだ。私は戦時空襲体験から神仏の存在を否定していたが、柏瀬さんのご好意に応え、例外措置として母の位牌の前に立てかけ、守り本尊とした。
柏瀬さんは名古屋大学が派遣するアフガニスタン学術調査団長として学生を率い、1964年5月下旬から9月下旬にかけ、交通ままならぬヒンドゥークシ山脈を馬に乗って越えるなど、バーミヤンをはじめ各地のアフガン文化を踏査し、当時は報告書や論文の作成に苦心の最中だった。
この柏瀬さん、一方でストリップ劇場の愛好家でもあった。同好の士であった私も、名大在学中は柏瀬さんと名古屋のストリップ劇場を廻ったものである。柏瀬さんはバーミヤン大仏の写真を送ってくれた後、研究旅行と称して京都へ来た場合、わが家をときどき宿にしたが、当時は国鉄沿線のストリップ劇場をしらみつぶしに踏査中だった。
私はとっくにストリップは卒業したと言って誘いを断っていると、柏瀬さんは「ダメだよ辻くん、そんな中途半端なことでは」と寂しそうだった。しかし大学時代に於ける柏瀬さんの影響が底流していたのか、私は老境に達したころヌードトルソの木彫を始めることになる。
そして2月11日は、初の『建国記念の日』。30数年に及ぶ自民党、右翼・保守陣営の執念、各党の馴れ合いによって実現した。この日は法律によると「建国をしのび、国を愛する心を養う日」だそうだが、日本にどんな建国の歴史があるのか、暗に史実でない神武天皇の即位を建国として偲べというのか。神武天皇の即位以来万世一系の天皇を讃える戦前の祝日『紀元節』が、いい加減な趣旨でカモフラージュされて復活したのだ。多くの人にとっては休日が1日増えたことくらいらしいが、私は新憲法の復旧的修正と思い、脱天皇制をテーマとする劇映画がつくれないかと思いをめぐらしたが、大映京撮では絶望的だった。
さて、本年に入って2作品に就いた後、6月に入って思わぬ仕事が舞い込んだ。大映テレビ室制作による午後の連続テレビドラマ、1話30分番組を10話で構成する井上芳夫監督・高田美和主演『祇園花見小路』のチーフ助監督に就けということだった。
作品の内容は、舞妓が女子大生になって花街祇園の因習的な伝統に対して批判的になるものの、恋人になっているカメラマンの卵が、京都の有力資本家に取り入って世に出るための個展を開こうとする行為から、一般社会にも祇園と同じ因習があると知り、祇園の革新を目ざそうと覚悟し、大学を退学し恋人とも別れ、舞妓から芸妓になって再出発するというものである。
撮影はオールロケ。客を接待するお茶屋とか、舞妓芸妓を抱える置屋、あるいは京都の情景をバックにする場面を選択的に撮影した。京都撮影所からの参加は、私と美術監督のUさんだけ。後は全部東京から来たスタッフで三条京阪駅近くに旅館に合宿した。
私はチーフ助監督として、京都のことは判らないと私を頼る監督の演出補佐に終始、テレビ映画ではチーフを格下げしてつくセカンドはスケジュールと段取り交渉に、サードは撮影に着くと、美術助手とともに界隈を走り回って小道具や装飾品などを借り集めてくる。
撮影終了して宿に帰れば美術監督と助手が首っ引きでポスター類やパンフなどの作成に終始。美術費の予算を聞くと五万円。「1話がか」と聞くと「何を言ってるの。10話全部で5万円だよ」。劇場映画であれば、斜陽とは言え1時間30分程度の作品には60万円前後出ているのにと、テレビ映画の低予算に愕然とした。
20人前後の東京スタッフを京都にとどめておくのは滞在費が大変だ。京都での摂り分が終わると、残りは東京でということになり、私と美術のUさんも上京することになった。
京都組に対し、テレビ室が低予算で用意した宿舎は、新宿駅に近い場末の連れ込み兼用旅館。京都からテレビ室へ1時間番組の演出で出向する監督たちには、厚生年金会館などのホテルが用意されるのにと不満だったが、旅館で良かったと後で気づくことになる。
東京での撮影を始めた矢先、突如井上監督は東京撮影所の劇映画制作へと抜け出し、テレビ室は私を監督に起用して残りの撮影や仕上げ工程を続行することになった。「これでスムーズに仕事ができる」とスタッフは大喜びだった。
とにかく井上芳夫監督は、何かにつけてわんわんと言葉数が多く、それをさえぎりながら撮影を進行させていくのにスタッフは困惑し、イライラしていたのは確かだった。
井上監督の後を引き継いだ私は、何回となく撮影ショットの時間調整を記録さんから迫られる。
「監督、5話が3分オーバーです」
「4話がまだ6分足りません」
「5分オーバーだと編集に困ります」
全話それぞれ30分番組に完成するには、時間が足りないとどうにもならない。つい安全をねらって長めに撮影すると捨てる部分が多くなり、時間通りに編集するのが困難になる。
撮影が終わって宿へ帰ると、ショット撮影の長さを調整しながらのコンテ作りに没頭した。
しかし、美術のUさんは宿へ帰ると手持ち無沙汰。テレビを見たり週刊誌を開いてゴソゴソしてるが、新宿の夜を満喫せんと繰り出していけば、部屋はシーンと静まりかえり、いろんな物音が聞こえてくる。
「お客さん、全然肩もなにも凝ってないですけど」
「そうだげぁ。独りで泊まっているとよう、淋しいでしょう。だまもんで呼んだのだぎゃあ。まあ寿司を取り寄せておいたでよう、食べよまぁか」
昼間見ると、隣室の客は名古屋方面から出稼ぎに来ている左官屋さんらしかった。
ある夜は、子犬の鳴き声が聞こえてくる。そうかなと思っていると、どうもセックスしてる女性が発していると気づいて、馴れるまでコンテ作りが中断したりする。
私はアンリ・バルビュスの小説『地獄』を連想した。小説の筋は、ある銀行に職を見つけ、田舎からパリに出てきた若者が、止宿した素人下宿の部屋の壁穴から、隣室でいろんな職業・階層の人たちが展開する愛欲場面を覗き見した結果、虚偽の仮面をかぶった人間どもの真実を悟り、絶望して田舎に引き返すというものである。
撮影が終わりUさんも帰って仕上げ日程に入ると、比較的暇になり、旅館にいる場合が多くなった。ある昼間、廊下でお手伝いさんが幼児を抱いてあやしていると、一室から中年の男性が去っていき、間もなく少し若い女性がにっこりとお礼を言いながら幼児を抱き取って去っていった。お手伝いさんの話によると、男性は小学校と校長とのこと。
また、ある深夜、廊下を隔てた部屋から女性のすごい声。3、40分経って静まると、間もなく「毎度ありー」と何か食べ物を運んできた気配。そして再び復活戦。今度はピピーの口笛を吹きながら去っていく気配。彼は夜遅くまで働かされている寿司屋の店員とのことだった。
1ヶ月ほど逗留していて多様な人生を見聞きしたが、『地獄』の主人公が感じた絶望とは反対に、多くの生きる意欲を知った。
この間に『祇園花見小路』は滞りなく完成した。
その後大映テレビ室から1時間番組の監督にとお声が2、3回かかったが、時の製作部長から「次の仕事が待っているから」とすべてキャンセルさせられた。偶然とは言え、1期先輩を飛び越えて監督できたことは、年功序列に徹する上司たちの思いもよらなかったことだろう。
年末、日本映画監督新人協会から監督昇進記念にパーカーのボールペンをもらったが、大映京撮にとっても私にとっても、何の意味はなかった。
(2011年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第62回「“独立独歩再確認”の時代」 |
大映テレビ室では監督昇進を果たしたものの、年功序列を重視する京都撮影所からはまったく無視され、今後はテーマや内容にタッチしない段取り助監督に専念しようと、私は心を入れかえて1968年(昭和43年)を迎えた。
すでに前年末から井上昭監督・安田道代主演『秘録おんな牢』に就いていたが、テーマや内容にタッチしないと割り切ってみれば、それだけ心の負担は軽くなり、私にとって仕事は楽になった。かといって性格的に手抜きはできない。可能な限り歴史を調べ、社会の皮膚とも言うべき風俗を考証して、画面に反映できるようにした。
ところで私には、井上監督と考え方の違うことがハッキリわかっていた。
かつて東京ロケでのことだった。すでにテレビ映画の仕事などで東京にくわしい井上監督は、東京の現代を象徴する画面が撮影できると、高架の高速道路が縦横に立体交差する複雑な情景が眺められる場所に案内し、「辻チャン、東京の進歩はすごいだろ」と同意を求めたが、私はなんだか肯定できなかった。
「うーん、ぼくには過密都市の病理現象としか見えませんが」
このように考え方が違っているのにもかかわらず、井上監督は私の助監督ぶりを買ってくれたのか、『秘録おんな牢』に続いて、市川雷蔵主演の『陸軍中野学校・開戦前夜』、峰岸隆之介主演『講道館破門状』、安田道代主演の『関東女やくざ』と、連続して3作品に就くことになる。
しかし、就く作品のすべてが客受けを性急にねらったようなものばかりだ。テレビ普及率が83%を突破したというのに、こんな他愛ない映画を作っていていいのかと不安をつのらせたが、監督昇進を無視された一介の社員ではどうにもならない。
私は覚悟を決め、できるだけ暇をつくって読書にふけり、読書癖を高めるほかなかった。
こうして映画業界は不況の波にさらされたが、国民総生産(GNP)は世界第2位に迫る勢い。世の中は、「やれ“いざなみ景気”だ」「“昭和元禄”だ」と浮かれに浮かれた。
一方、この年は国内外とも大揺れに揺れた。
1月のアメリカ原子力航空母艦エンタープライズの佐世保寄港反対闘争に始まり、登録医制度導入に反対する東大医学部学生自治会の無期限スト、成田空港建設反対闘争、アメリカ黒人運動指導者キング牧師暗殺、フランスの学生と労働者の反政府運動など、突発事件が続発した。
以上のような世界の情勢から、私はいろいろ企画を考えたが、子どもの頃から天皇制を批判してきたような頭では、わが大映に採用されそうなものは思い浮かばなかった。
井上監督作品をすべて終えた秋のかかり、三隅組からお呼びの声がかかった。仕事のすすめ方で三隅研次監督とは合わないので拒んでいると、製作部長に呼び出された。
「三隅君は何でも言ってくれていいと言っているから、就いてやってくれよ」
私が入社二本目に就いたのが三隅監督・長谷川一夫主演の『七つの顔の銀次』。その当時、大映京撮には、巨匠伊藤大輔、森一生につらなる“森グループ”と、巨匠衣笠貞之助、三隅研次につらなるNさんをリーダーにSさん、Tさん三人の助監督から成る新興の“三隅グループ”があって、私は三隅グループより「これからは三隅グループの時代だよ」と仲間入りを誘われたが、独立独歩で行くと断った。
4年後Nさんは監督に昇進するが、2本でダウン、やがて配置転換。Sさんは精神疾患にかかって入院中に死亡。残ったTさんは、仕事後も喫茶店のハシゴや骨董品店巡りにつき合うなど、三隅監督が夜遅くタクシーで帰宅するのを見送るまで、腰巾着のように助監督を勤めたが、内臓疾患にかかり、ダウンして入院。快復後配転されそうになり、助監督にとどまれるよう三隅監督に助けを求めたが断られたとのこと。結局配転となって、三隅グループは消滅し、お鉢が私にまわってきたというわけだ。ゴシップに興味のない私は全然知らなかったが、密かに社員の間で、三隅監督は「吸血鬼」と呼ばれていたそうだ。
さて、新しく就くことになった三隅監督作品は、勝新太郎主演、座頭市シリーズ19作目に当たる『座頭市喧嘩太鼓』だった。
座頭市は一宿一飯の恩義を受けたヤクザへの義理で男を斬ったが、そのヤクザが前々から男の姉・お袖をねらっていたことを知ると、護衛をことわるお袖につかず離れず、ヤクザの追撃を防ぎながら諏訪明神まで送っていくというのが話の筋だ。
座頭市シリーズも19作目になるとだれてくる。そうならないように、勝さんのアイデアを受け、3人の脚本家を起用して、いろいろ工夫してあるものの、お袖の心理の流れなどに御都合主義的な無理があると感じたが、私は言いたがる口をあえて閉じ、段取り仕事に徹した。
この作品で、監督が問題にしたのは、座頭市の耳に聞こえるお袖の足音だった。自由自在に刀で斬り合いのできる座頭市は、盲人の中でもとくに鋭い聴覚の持ち主で、単にワラジばきで土を踏むのとは違う足音を聞いているはずだと、監督は主張するのだ。私は監督の凝り性に合わせ、音響効果技師と録音技師に頼んで、お袖の足音作りにかかった。私たちはワラジばきの足で踏んで音を出す砂場に、おが屑をまいたり、布地を敷いたり、小切りにしたワラを叩きのばしてばらまくなどして、いろいろな音を作り出したが、監督はなかなかOKを出さない。ついには、屑フィルムを丸めて敷いたり、あるいは録音テープに替えてみたりして足音をつくった。どの音でOKが出たか忘れたが、徹夜に近い足音作りをしたことを覚えている。
そして製作工程の最終段階、音楽ダビング前の総ラッシュ試写で問題が出た。
映画の冒頭のシーンで、子供たちが草むらにかくれ、スズメを生け捕りしようと狙っている場面がある。長いヒモをつけた棒を支えに、ザルの片方を差し上げて地面に伏せ、その中にまいた米粒を食べにスズメが入ったら、ひもを引っ張って棒を倒し、ザルの中に閉じこめようというわけだ。スズメが寄ってきそうにないので子供たちがイライラする情景を、監督はシナリオどおり、鳴き声だけで構成していたが、スズメを見上げる子供の見た目で、スズメの画面が欲しいと突然言い出したのである。
翌日私は音楽ダビングから外れ、撮影部を連れてスズメのロケに出かけた。しかし、スズメは警戒心が強く、数人の集団でもカメラを担いで寄っていくと、可なりの距離を隔てて逃げ回るので撮影不可能。私はふと気づいて、急遽岡崎動物園へ行くことにした。
動物好きの私は独身時代にときどき岡崎動物園を訪れていたが、その眺めから、沢山のスズメが目の粗い檻をくぐり抜けて、水鳥コーナーの餌をついばんでいる情景を思い出したのである。動物園で暮らすスズメなら人に慣れているはずだ。思ったとおり、園内では樹木に群がるスズメの群れや、単独、接写などの画面があっという間に撮影できた。
岡崎動物園へ撮影に行くと連絡を受けたとき、三隅監督はバカにしたように声を上げたそうだ。「あいつら、カバかゾウでも撮りに行ったんかいな」
三隅監督と私は尻を向け合ったままで、『座頭市喧嘩太鼓』は完成されていった。
私は独立独歩、自分がアマチュア哲学思想家への道を歩んでいる気配を感じた。
(2011年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第63回「“仕事より、気を奪うのは社会”の時代」 |
「この事件は迷宮入りだ!」
1968年(昭和43年)12月10日の夜、封切りが迫る正月作品・三隅研次監督の『座頭市喧嘩太鼓』に就いていた私は、残業帰りで遅めの夕食をとりながら、その日の朝、東京・府中市で発生した3億円強奪事件を報ずるテレビニュースを見たり、夕刊を読んだりしているうちに、イライラがつのって思わず口走ったのだ。警視庁の捜査が、全くの方向違いに思えたからだ。
事件は、日本信託銀行国分寺支店から東京芝浦電気(現・東芝)府中工場へ送る従業員のボーナス約3億円を、3個のジュラルミン・トランクに入れて運ぶ途中、警官を装って偽装白バイに乗った犯人に現金輸送車ごと奪われたというものである。
当時の日本は、第2次池田勇人内閣の打ち出した所得倍増計画により、高度成長まっしぐら。国民総生産(GNP)は西独を抜いて世界第2位となった。2年後には国威発揚と人類発展のための大阪万博開催を控えて、日本は金がものを言う時代になりつつあること。また政界や財界に奥深い闇が存在することなど諸般の情勢から、私は3億円強奪事件を、帳簿に記載しないで使用できる裏金作りのために、組織か誰かが仕組んだ計画に基づく犯行と直感したのだ。
報道によると、事件発生後警視庁は直ちに大がかりな捜査体制を固め、1時間後には早くも工場近くの林の中で輸送車を発見。しかしトランクは持ち去られていた。警視庁は事情を知った者の計画的犯行と断定し、犯人の足どりや犯行経路の聞き込み捜査を始めたとのことであった。
しかし、すでに時遅く、後の祭り。社会に事件を見せつけることと、迅速な行動を主眼とする緻密な計画に基づいて、犯人はなんなく3億円をだまし取り、裏金にとりこむ犯行をあっさり完遂した。要するに、後から追いかけても無駄な事件と私には思えたのである。
盗まれた3億円は、日本の保険会社が支払った保険金で補填され、その保険会社は再保険に加入していた別の国の保険会社から補填されて、企業は何の損失もなく事を済ませたとのこと。警視庁は超大規模な捜査をくり広げたが犯人を挙げられず、多くの人びとに被害や迷惑を与えながら、事件は7年後時効となって消滅した。
暴力を使わず計略だけで成功している3億円強奪事件は、いろいろ取りざたされ、その後小説や映画、テレビドラマなどで様々に作品化されているが、いまも私は、事件は裏金作りであり、その裏金は政財界の間で資金や賄賂などに使われたものと信じている。
さて『座頭市喧嘩旅』はなんとか完成した。コマーシャルへの出演をすすめられたこともある2人の娘は、妻のおかげですくすくと育っている。私は1969年の正月を無事に迎えることができた。
しかし社会は騒然としていた。
前年から続いている東大や日大の紛争は、パリの労働者・学生約1千万人がベトナム戦争や国家権力に反対し、自由と平等と自治を主張して行ったゼネスト、いわゆる5月革命の影響もあって激しさを増し、ついに1月18日、東大の要請を受けた警視庁は機動隊8500人を出動させ、安田講堂に立てこもる学生たちを4000発の催涙弾で排除する状況であった。
当時私は、権威・権力に対抗する学生側に立ってニュースに注意しながら、安田公義監督『東海道お化け道中』の助監督に就いていた。
話の筋は、凶行現場を目撃したために悪い親分から命を狙われることになった少女を、八つ墓村の妖怪たちが助けて、悪人どもを退治するという他愛ないもの。どんな仕事をしたのか、段取り助監督としては全く覚えていない。
そんなある日、わが母校・名大の文学部長が私に会いに来た。美学美術史研究室の恩師・柏瀬清一郎講師について聞きたいというのである。大学紛争は名大へも波及しているらしかった。
柏瀬さんはどんな先生だったかの問いに、私は、ストリップ劇場の研究をいっしょにしたことは伏せておいて、壬申の乱と興福寺にのこる仏頭に象徴される大らかな後期白鳳彫刻や天平彫刻の関係、お祖父さんが足尾銅山鉱毒事件で農民のために奔走した田中正造の弟子として、どんな抵抗を官憲に対して見せたを聞かせてくれたことなどから、柏瀬さんは私にとって有意義な先生だったと答えた。
しかし、授業を几帳面にやらない柏瀬さんは、現在の学生から不評を買っているとのこと。私たちが学生の頃は、授業より交流を重視しましたがと言うと、部長は答えた。
「いまの学生は、払った授業料に見合った授業をしてほしいのです」
部長を追うように、間もなく柏瀬さんが私の家を宿にして京都の美術研究にきた。
「先生、のんびり大学を留守にしていて良いのですか」
「学生たちが、あとは悪いようにしないので、旅にでも出かけていてくれと言うもんだから」
やがて柏瀬さんは、東海大学へ追い出された。同期生の話によると、名大は学生、職員とも民青系が主流で、反代々木系を支持する柏瀬さんは、美学美術史研究室の講座化に当たって邪魔な存在だったとのこと。
翌年4月、美学美術史研究室は業績のハッキリした美術史家の吉川逸冶氏を東大から教授に、また小説家辻邦生夫人で少壮の美術史家・辻佐保子氏を助教授に招いて、長年の念願だった講座化を実現した。
ところでこの年1969年、私の方は3月封切りの『東海道お化け道中』の後、9月までどんな仕事をしたのかしないのか、さっぱり覚えていない。
ただ岩井弘融著『病理集団の構造~親分乾分集団の研究』を読んで、わが国では皇室の御安泰を信奉していればどんな悪い集団も許される、どんなに良いことをしても皇室の存在を危うくする集団は許されないという国民感情が、社会に根強く底流していることを印象的にわからされたことが記憶に残っている。
そして9月、司馬遼太郎原作・三隅研次監督『尻啖え孫市』の主演・中村錦之助さんから羽柴秀吉を演ずる弟の賀津雄さんに尾張弁の指導を頼まれた。台本を見ると、秀吉が人をののしる言葉として、あほう、愚か者を意味する「痴れ者」が使ってある。
10年ほど前、『若き日の信長』を監督する森一生さんから尾張弁の指導を頼まれた。そのとき「痴れ者」を「たわけ」「たわけ者」と修正した結果、有名な時代考証家・稲垣史生から「たわけ」という言葉は信長の時代には使わなかったと、こっぴどく批判された。「たわけ」は「田分け」と書き、分家に田を分け与えること。あまり田分けしてしまうと本家が立ちいかなくなることが多々あるので、江戸中期から「たわけ」を馬鹿なこと、愚かなことの意味で使われ始めたというのである。
しかし私が小学5年から愛読している古事記の仲哀天皇の項に、罪として「上通下通婚(おやこたわけ=近親相姦)、馬婚(うまたわけ)、鶏婚(とりたわけ)、犬婚(いぬたわけ)の罪の類を云々」と記され、「婚」を「たわけ」と読ませている。だから尾張弁の「たわけ」は、性行為と罪を犯す愚かの2つを意味する古くからの言葉だと知って使ったのに、稲垣史生は批判した。
三隅監督にどちらを信用するかと尋ねたら、即座に稲垣史生を信用すると答えた。私は騒ぎ立つ腹の虫を抑えて監督に従った。
それから7年後、1976年に発足した現代風俗研究会で、中学の5年先輩だったという民俗学者の高取正男さんと偶然知り合った。長年の疑問をただすと即座に答えがもらえた。
「そりゃ、辻さんが正しいに決まっていますよ」
私は溜飲を下げたが、あまりにも遅すぎた。
(2011年8月記)
⇒ 目次にもどる
| 第64回「“おのれの愚かさを自覚する?”の時代」 |
「タバコは肺ガンの原因だ!」
1960年(昭和40年)代の半ばから、東京都三鷹市本庁舎を皮切りに、公共施設などで分煙がはじまったように、喫煙の害を説く声や施策を求める声が急に高まってきた。
しかし一方で、「紙巻きタバコに対して、パイプタバコはガンにかかる率が低い」と言った学説やら風評が流れた。
1969年(昭和44年)のある時、大映京都撮影所でただ1人パイプをくわえている私に、パイプタバコの吸い方を教えてくれという人が出てきた。田中徳三監督、井上昭監督ほか10数人はいたと思う。
そして驚いた。後ればせに製作部長が加わってきたのだ。彼は、私が入社当時の製作課長。パイプをくわえて行き来している私を生意気そうだとか、仕事をしているように見えないと非難した。そのため、私は場慣れするまで撮影所でのパイプタバコを1年ほど止めざるを得なかった。そのことを言うと、「まあ、そんなこと言わんと教えてくれや」と、悪びれもせず上司風を吹かせた。
さて、パイプタバコを覚える段になるといろいろ問題が出てくる。パイプ喫煙を粋な趣味、洒落た行為と思っている人は、手にしたパイプの値段やブランド名をひけらかした。パイプの使い方が呑み込めない人は、煙道の詰まりを通そうとして吸い口を折ったり、葉を詰めるボウルの灰を落とすために叩いて壊してしまう。せっかちの人は口慣らしもせず、その日から紙巻きを止め、すべてパイプに乗り換えて口内を荒らした。紙巻きのように肺まで煙を吸いたい人は咳き込んだ。
「パイプタバコは体の中に吸い込むものではなく、口の辺りでゆったりとくゆらすものですよ」
肺喫煙の紙巻きタバコに慣れていると、口の当たりでくゆらすだけの口腔喫煙では、刺激が弱くて満足感を得られないらしい。結局パイプタバコを習得できたひとは、コソコソと抜け目がないと評判の製作部長と、監督路線から外れても動じない先輩の2人だけで、残りは1週間から半年ほどですべて多数派に戻ってしまった。不思議な結果ではあった。
ちなみに、そのころ数万円もするダンヒルのパイプをぎこちなくくわえて闊歩してる人を、テレビ局の内外でしばしば目にした。彼らはその後どうしたのだろう。
ところで1969年度後半の仕事は、安田道代(現・大楠道代)が任侠女を演ずる、井上昭監督作品『関東おんなド根性』から始まった。以前の青春ものよりは道代チャンに似合っている作品だと思ったが、段取り助監督としては、バタバタしているうちに終わった感じだった。
次いで安田公義監督の『二代目若親分』から、森一生監督の『忍びの衆』へと続いた。いずれも、前年よりガンのために命が危ぶまれた市川雷蔵の代わりに、東映からレンタル移籍した松方弘樹が主演だ。七月に雷蔵さんは亡くなっていたが、どちらの作品も雷蔵さんが傑作を遺した『若親分』シリーズ、『忍びの者』シリーズのリメイク版だ。
雷蔵さんとは10歳近くも若く、イメージも違う松方には、松方なりの使い方があるのではないか。私は会社の企画力の貧困・安易さを憂いながら、段取り仕事に終始。余力は読書に向けた。
そこで印象的な本に出合った。ドイツの精神医学者、ホルスト・ガイヤー著『馬鹿について~人間-この愚かなるもの』(満田敏久・安井俊三共訳)と題する、馬鹿についてまとめた本である。
著者は、知能が低すぎる馬鹿、知能が正常な馬鹿、知能が高すぎる馬鹿と、馬鹿を3つに分類いて解説している。独断と偏見で自分なりにしか理解できないが、人間は知能の高低にかかわらず皆馬鹿だということ。要するに、おのれの馬鹿を自覚することが大切だいうわけだ。そして、本文中に散在してある昔の人からの引用文をはじめ戯曲や民謡、結びの章としてある「人生の愚かさについての格言集」などに心を引かれた。
人は一人ずつでは、少しは賢く、分別があるようだが、
一緒になると、すぐ馬鹿に化ける。(シラー)
(戦争中の小学5年、天皇崇拝を放棄してから集団行動が嫌いになり、戦後の中高時代は修学旅行に参加する気になれなかった。おれは賢人だったかしら?)
愚行がなくなれば人類は滅亡するだろう。
(肺ガンにかかりにくいと、パイプタバコを改めて続けるのは愚行かもしれないと思ったが……)
文字どおりの人類絶滅を企てるものは賢人である。
愚者には原子爆弾や火薬など造れるはずがない。
(敗戦から得た俺の教訓は、「人類が怠ければ、地球は平和になる」だった。)
修業とは、上役よりも馬鹿らしく装う術のけいこである。
(俺は上役や先輩の言いなりにはなれない。俺は愚者?それとも賢人?)
後年、高校生になった長女が勉強に悩んでいたとき、私から「この本には、人間はみんな馬鹿だと書いてある」と、本棚にある『馬鹿について』を見せられてホッとした表情になり、「いつか読んでみるわ」と言ったことを覚えている。
年末になってショッキングな事件が起こった。女優の毛利郁子さんが殺人を犯してしまったのである。現役の女優が殺人を犯すのは初めてだと話題になった。 あの人の良い毛利さんがどうして殺人を? 噂や新聞記事によると毛利さんは男運が悪く、最後に交際していた妻子持ち興行師を、他にも女性関係があったことにカッとなり、刺殺してしまったとのことだったらしい。
1957年(昭和32年)肉体派女優としてデビューした蛇好きの毛利さんは、26歳での遅いスタートを挽回するためか、裸体を見せるほかに、裸体で蛇をもてあそぶ異色性を加味して役柄を広げていった。
私の入社当時、母校名古屋大学の美学美術史研究室が例年行う奈良・京都の美術研究旅行のコースに、私の案内による大映京都撮影所見学が組み込まれた。OB会などで私に会うと、記念写真に入ってくれた毛利さんを懐かしく思い出す人が今もいる。
明けて1970年(昭和45年)、正月をまたいで制作してきた『忍びの衆』は、1月の半ば過ぎに完成した。 そして3月14日。 待っていたように大阪千里で日本万国博覧会(大阪万博)が開幕した。
万博には多くの人が何回も足を運んでいるのに、私はついに行かなかった。みんなが行く所には興味がわかなかったのだ。
それより、万博と前後して出版された吉行淳之介の小説『暗室』の269ページに注目した。
男根が子宮口に当り、さらにその輪郭に沿って
奥のほうへ潜り込んで貼り付いたようになって
しまうとき、細い柔らかい触手のようなものが
伸びてきて搦まりついてくる場合が、希にある。
小さな気泡がつぎつぎに弾ぜるような感覚が
つたわってくる。
この文章に接して、吉行も性の奥義を極めているなと私は共感し、愚かなことかもしれないが、人生の未来が楽しくなった。
(2011年10月記)
⇒ 目次にもどる
| 第65回「“万博は、うずまく矛盾の走馬燈”の時代 」 |
1970年(昭和45年)3月14日、『人類の進歩と調和』をテーマに大阪府千里丘陵で開幕した日本万国博覧会が、国民総生産(GNP)世界第2位に達した日本の高度成長と経済大国の姿を誇示する一方、わが家は長女の小学校進学問題から夫婦の間で討論の嵐が吹き荒れた。
乳児期に父を失った私は、母から小学校入学時に「これからお前が戸主だから先頭に立て。教える力のない私は、黙って後から付いていくから」と突き放された。以来私は、農村のど真ん中でフナやドジョウを相手にしながら、自ら鼻先にニンジンをぶら下げて大学を突っ切り、社会に飛び出してきた独断と偏見の固まりだ。
片や妻は、国家官僚の長女として母を助け、弟や妹たちの面倒を見ながら高学歴の親族・知人に囲まれて成長し、常に上を目ざす賢女だった。
当然私たちは価値観も考えも違い、結婚以来いざこざが絶えなったが、長女の小学校選びに至って対立は極まった。
父なるものを知らないオリジナル・ファーザーの私は、「娘の教育は平等なスタートラインから」と簡単に考え地域の小学校を望んだが、妻は毛並みのそろった優良種に仕立て上げようと京都教育大学付属小学校への進学を主張したのだ。
付属小へ入るためには入学テストのほか、クジにも当たることだった。両親対立の雰囲気を嫌悪したのか、行きたがらない長女を引っぱって、妻はテストとクジ引きに出かけていった。
しかし、幸か不幸か長女はクジに外れた。子どもの将来に対し父親としての熱意がない、という不満を妻に残して事態は平静に復した。
さて大阪万博は、会場の入り口で行列待ちしていた日本人が開場と同時に、お目当てのパビリオン目ざしてわれ先にと突進する状況を、外国人記者が西部劇でおなじみの野牛の暴走に見立てて風刺するほどの連日大盛況。
そんな国家仕立ての賑わいに、水を差すような事件が突発した。
3月31日、日本で初のハイジャック事件が発生したのである。
世界同時革命を目的とする共産主義者同盟赤軍派の学生が、乗客・乗務員を人質にして日航機よど号を乗っ取り、北朝鮮への亡命を図ったというわけだ。テレビや新聞ではいろいろな報道が飛び交った。人質をどうするか。よど号は朝鮮戦争停戦ラインを越えられるか、北朝鮮は入国を許すかどうか。最終的には、時の運輸政務次官が乗客の代わりに人質となり、赤軍派学生を北朝鮮に送り込んで事件は決着するが、私は報道に接しながら考え続けていた。
〈現代は、あっという間に国境を飛び越えられる航空機にとって不幸な時代ではないか。国境の存在は鉄道交通、あるいは道路交通にふさわしい存在。国境を固持する国際関係は時代遅れではないか〉
長女が小学校に通い出した頃、私は安田公義監督の『怪談累が淵』に就いたはずだが、映画不況の波にもまれていたのか、どんな仕事だった全く記憶にない。
大阪万博に関して、日米安保条約反対に取り組む人たちは、大イベントで条約改定に対する議論や反対運動から国民の目をそらすものだと批判し、約80万人が安保反対闘争に取り組んだ。しかし、「政治より金だ」との意識が労働者に働いたのか盛り上がりに欠け、自民党政府の思い通り、安保条約は平穏に自動延長されてしまった。
私は思った。やはり国民の関心は、「安保」より「万博」に向いていたのだ。
「万博を見ずして現代がわかるか」とばかり、私以外の隣人知人、撮影所仲間こぞって万博にイソイソと足を向けた。妻も幼い娘2人をつれて出かけていった。
私は少年期に現人神・天皇に対する崇拝心を捨て去り、日本人がこぞってのめりこんでいる忠君愛国の戦争に反対感情を持って以来、皆が“こぞる”ことに疑問を感じてきた。そのため、万博が象徴する高度成長の陰にある公害、自然破壊、浪費、長時間労働などによる諸問題の方が気になって、万博には足が向かなかったである。
そして、あたかも7月18日、東京都内の各地で日本初の光化学スモッグが発生。資料によれば、車の排気ガスと工場排出の亜硫酸ガスもからんだ複合汚染とされ、4日間で5200人から目やのどの痛み、吐き気などの被害届が出されたとのことだった。
8月、わが大映京都撮影所の半分が売却され、撮影以外は急造されたプレハブ建築で仕事をする羽目になった。
9月頃から、大映テレビ室と東京12チャンネルの制作で、安田道代(現・大楠道代)主演の連続テレビ映画『命を賭けます』の製作が始まった。
内容は、安田演ずる女柔道家が、柔道塾を経営する病弱の父を助けて、次々と塾乗っ取りに現れる男性柔道家を相手に、孤軍奮闘して父の塾を守り通すというものだ。
私はメイン監督の推薦で、第6話『地獄攻め紅吹雪』と、第11話『暁の対決』を監督することになった。とにかく低予算での製作スケジュールは過密に詰まっている。登場人物のキャラクターやテーマなどに関しては企画の段階から参画するメイン監督がレールを敷いているので、私としては目くるめく忙しさでスケジュールをこなしていくだけだ。
撮影に関して記憶に残っているのは、柔道塾のセット撮影で、3種類の試合を、同じ向きばかり中抜きして撮影したり、付随する父の部屋や廊下の場面など、9時から17時までの定時間の間に105カットを取り上げ、「のんびりそうで、早撮りもできるのか」とスタッフに驚かれたことぐらいだ。
救いは、病弱の父を演ずる美川陽一郎さんから、「辻監督の演出は、これまでつき合ってきた監督とひと味違う。本編を監督される場合には、ぜひ使って下さい」と言われたことだ。俳優さんに特有のお追従かも知れないが、私は素直に聞きとどめて今に覚えている。
因みに美川さんは、当時、TBS連続刑事ドラマ『七人の刑事』でレギュラーの老刑事役を演じ、その地味な老け役の演技は、多くの視聴者から注目されていた。
『命を賭ける』を終えて、次の仕事を待機しているときのことだ。いつかは起こると予測していた事件が起きた。
11月25日、三島由紀夫が楯の会会員4人と市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地に乱入し、クーデターを呼びかけて失敗。東部方面総監部室で楯の会の1人に首を斬る介錯を頼んで割腹自殺したという、時代錯誤のグロテスクな事件を引き起こしたのだ。
私が1958年(昭和33年)に三島由紀夫著『金閣寺』を原作にした市川崑監督作品『炎上』に就いたときのことだ。ある雨の日、新婚旅行を兼ねて撮影見学に来た三島由紀夫が、『炎上』撮影中のステージに通ずる裏道を、右手で蛇の目傘をさした小さな三島が、着物姿の新妻の後ろから背伸びするように肩の上から左手を回し、いかにも保護するごとく抱えるようにして、ぎこちなく歩姿をのを目撃した。それ以来私は、三島がどうして等身大に生きられないのかと注目してきた。
調べによると、三島は幼時に祖母から女の子的に育てられた特異な精神状況と虚弱体質のため軍人になれなかったとのこと。おそらく三島は、戦死が名誉の時代に軍人になれず、名誉の戦死ができなかったコンプレックスを敗戦後も持ち続けきたと、私は推察した。
小説家として大成する過程で、三島は男としての自信をつけ、筋トレに励む。その結果、蟹嫌いで有名な三島は、ホモ仲間から皮肉にも“平家蟹ちゃん”と陰で呼ばれるような肉付きになった身体を、切腹にふさわしい身体と自認し、憂国の思いで、やっと名誉の戦死に代わる死を遂げたのだと、私の独断と偏見が結論づけた頃、1971年が間近に迫っていた。
(2011年12月記)
⇒ 目次にもどる
| 第66回「“三隅監督とは、いつも二律背反”の時代」 |
「辻!お前はしゃれたことしゃべっとるそうやが、わしは三隅研次を信じとるんじゃ!」
大映京都撮影所のワンマン所長が怒鳴った。1971年(昭和46年)早々、それまで参加させたことのなかったチーフ級助監督を参加させた企画会議席上でのことである。
当時の大映は、テレビの発展と多彩な娯楽やレジャーの普及などに押された映画不況の影響で、倒産の噂が濃くなりつつあった。そのため、所長としては会議の冒頭に私を槍玉にカツを入れ、社運の形勢挽回を参加者に考えさせようとしたのだ。
17年間勤めてきても、年功序列のため一向に自己実現できない会社など即座に飛び出したかったが、私は生来マイペースでスロースターター、なかなか飛び出す準備が整わないでいた。幼い2人の娘をかかえる家庭人の立場から、その場は我慢に耐えておどけるよりほかなかった。
「そぉおーですか。勝手にしはったらよろしいがな」
企画会議では、大した考えなど出なかったと記憶している。
2月に入って間もなく、私は製作部長に呼ばれた。新しく立つ三隅組に就けというのだ。
「部長は、私が三隅さんと気が合わないことを知っている筈やのに?」
「まあ、そんなことは忘れて就いてやってくれよ。こんどの仕事に三隅君は緊張してるようで、君をぜひ就けてほしいと言っているから頼むよ」
私が三隅監督に就くのは、尻を突き合わせて仕上げた勝新太郎主演の『座頭市喧嘩太鼓』以来、2年ぶりのことであった。
仕事は、敗戦の年(1945年)に制作されて時代劇の幕開けを飾った名作、丸根賛太郎脚本監督・阪東妻三郎主演『狐の呉れた赤ん坊』の再映画化だった。
内容は、人情味はあるが人一倍気が荒く、酒が入ると喧嘩ばかりしている大井川の川越え人足・張り子の寅八(阪東妻三郎)の物語だ。
寅八は、人を化かすと怖がられている狐の退治に入った森の中から、泣いている赤ん坊を拾ってくる。狐の化け姿だと疑っていた寅八は、捨てようかと最初は迷ったが、善太と名づけてもらって育てているうちに情が移り、身を慎んで、6年後には皆に愛される立派な少年に育て上げた。
しかし突然、善太が某藩主の妾腹にできた御落胤とわかる。そして某藩から、病死した嫡子のかわりに世継ぎとして善太を引き取りたいと、大井川を越えて使者がくる。深い情愛で結ばれた2人は別れたくないと悩むが、最後には将来に向けて覚悟を決め、明るく別れることになる。
善太を引き取って藩に向かう行列の川越えに際して、善太は蓮台に乗ることを拒否。寅八の肩車で行列の先頭に立つ。寅八は「殿様になっても領民のみんなに優しくするんだぞ」と善太に教えさとしながら大井川を渡っていく。
敗戦後の国連軍による占領中、時代劇に顕著な封建性や残酷性、非科学性などの表現を抑えるよう総司令部から指示されて、忠臣が活躍したり、チャンバラがあったり、幽霊の出るような時代劇はつくれなくなってしまった。
そんな情勢から、『狐の呉れた赤ん坊』のようなチャンバラのない、人情喜劇の名作が大映で生まれたというわけだ。
そして20数年後、倒産への苦境を救う企画として、勝新太郎主演、三隅研次監督で『狐の呉れた赤ん坊』の再映画化が持ち上がったようである。
丸根監督は「時代が飛んでいるから」と訂正した台本に目を通すと、何処をどう訂正されたかわからなかったが、それなりに面白そうな筋運びになっていた。
スタッフが決まって、三隅組は準備に入った。その段階で最も重要な問題は、大井川のシーンを何処で撮影できるかということだった。
監督以下主要スタッフは、ロケのしやすい川の状況を下調べして、まず山陰本線は亀岡の先、千代川駅付近を流れる千代川へロケハンに向かった。
そこは両岸から砂州が張り出し、中央に流れがあって、広重の『東海道五十三次』でお馴染みの大井川の情景に似ていた。川越えのシーンが撮影できるどうか調べるため、スタッフ一同流れに近づいて水際に立つ。人足が渡りきれるどうか、真ん中当たりの深さがわからないので、一同やや焦れる。三隅監督が「誰か調べてくれないかなあ」と、物欲しげにひしゃげた声をくり返す。
私は助監督だ。私に聞かせている気配。「エッ糞」と衣服を脱いで流れに入っていく。春先でまだ水は冷たいが、腰までつかっても何とか耐えられそうだ。前進していると、突然深みに落ちて息が止まり、中央に押し流される。瞬間、雨後の濁流に飛び込んで溺れる少年を救った高校三年のときの経験が、脳裡にきらめいた。冷静になるんだ。ここで呼吸したら心臓が麻痺する。私は息を止めて懸命に泳ぎ戻った。
濡れたパンツを脱ぎ捨てて衣服を着ていると、ねぎらいもしない監督の声が聞こえた。
「やっぱり、ここはダメやなあ」
結局川越えのシーンは、京都府南部の浅瀬が続く木津川でロケが決まった。
ところで丸根シナリオが気に入らないのか、寅八を演ずる勝さんと監督の間でしきりに訂正が進められた。最大の訂正は、寅八と善太が別れるラストシーンだった。
丸根シナリオのラストは、善太を肩車にした寅八が「いまに殿様になったら、御領内の皆にやさしくしてやるんだぜ」と善太に教え諭しながら愉快に川越えする情景だった。
しかし三隅・勝の合作訂正は、善太と別れるのがつらい寅八が、善太を見送る善太ファンの群れの中に姿を見せず、離れた川の中から顔を出して、秘かに5本の指で別れを告げた後、一点を見つめて去っていくというものである。
作品は、多くの演技者やスタッフを川の水に長時間つけるなど、苦労の末に完成した。試写会でどんな感想が出たか覚えていないが、丸根シナリオを改訂して、暴れん坊でイメージアップしてきた寅八をドンデン返しでイメージチェンジし、水の中から顔と手だけで見送り、孤独に去っていくセンチメンタルなラストの画面は、観客を通じて社会に何を訴えようとしているのだろう。
チーフ助監督となって最初に就いた三隅監督作品『斬る』に関して当時の図書新聞で読んだ「こんなに美しく殺人を描く三隅研次は、無意識の作家か」とあった映画評を連想しながら、私には感情に甘えた腰砕けの映画に思えた。
こうして三隅さんを批判するものの、5年前に私が狭い自宅で行った亡き母の告別式の際、表に立って会葬者に挨拶する役を引き受けてくれた人たちのうちで、三隅さんだけが断続的に激しく降る雪を避けもしないで立ち続けたという印象的な話を聞いて以来、私は心の奥底に、もう1人の三隅像を抱き続けている。
妾腹の子として生まれ、成人するまで母に会うことなく育った三隅さんは、生後3月目に父を亡くした私を独りで育ててきた母の死に対し、私の悲しみに共感してくれていたのかもしれない。
しかし私は、小学校入学の直前、母から「今後はお前が先頭に立て」と社会へ押し出されて以来、遠くに見える明かりを目当てに何かを掴もうと、トンネルの暗闇を手探りしながら前向きに生きてきた。何を掴まんとするのか、テーマのぼけた映画に共感できるわけがなかった。
その後、1期先輩の監督昇進作品を「こんな映画でデビューさせられたらた往生するなあ」と思いながら終え、5月に入ると「これは厄介になりそうだ」と思われる仕事が舞い込んできた。勝新太郎の初監督作品『顔役』である。(2012年2月記)
⇒ 目次にもどる
| 第67回「“勝新初監督の『顔役』は、異色のやくざ・ボンノと共に”の時代」 |
1971年(昭和46年)の5月の半ば、勝新太郎の監督デビュー作品『顔役』のチーフ助監督を勝プロダクションから頼まれた。待機していると、とんでもない噂がれてきた。
「勝ちゃんの『顔役』には、山口組が協力するらしいぞ」
大映の1960年代は、『若親分』『悪名』『座頭市』『女賭博師』など、東映と共にヤクザ路線を突っ走ってきたが、東映に大きく水をあけられて青息吐息の毎日。ある脚本家からは、同じように書いてやっても、東映では極彩色の油絵に仕上がるのに、大映では、どうして淡泊な水彩画になってしまうのかと不思議がられる状況が続いていた。
準備に入る前のある日、勝さんが事務や宿泊に使っているバスに呼ばれていくと、勝さんは熱っぽく語った。
市川雷蔵亡き後、大映京都を背負って立つ勝さんは、俄然ライバル意識をかきたてられ、東映がチャチなヤクザの泥臭い暴力を売り物にしているのなら、こっちはスケールの大きい広域暴力団暴力の近代的スマートさを叩きつけんと一大発憤。自ら製作・監督・主役の一人三役で本格的暴力映画の制作に乗り出し、完成度を高めるために、本格的な暴力団風俗の考証家を呼んでくるということだった。そんな考証家がいたのかなあと、考証尊重主義の私は、期待しながらも半信半疑で聞き止めた。
ところで脚本家と勝さんが首っ引きでシナリオを仕上げつつあった6月17日、日米安全保障条約の自動延長と引き換えに、広大な米軍基地は存続したまま、多くの日本復帰賛成派の期待とは裏腹の沖縄返還調印式が行われた。
数日後。私は沖縄県民の受けた屈辱感に思いを馳せながら、『顔役』の製作準備に入るためのスタッフ顔合わせと、シナリオの読み合わせに臨んだ。勝監督の代理プロデューサーが、いつになく低音を活かした厳かな口調で忠告をのたまった。
「今度の映画には大した方が直接指導にみえるから、スタッフは言うまでもなく、中でも接触を密にするチーフ助監督の辻さんは、応対に粗相のないよう、くれぐれも注意してください」
そして、指導に来るのが、「ボンノ」のあだ名で知られた山口組系の組長・菅谷政雄という人だと教えられた。
スタッフには緊張感が走ったが、私には今ひとつピンとこない。山口組組長ならいざ知らず。子分の1人では、なにが大した方なのか。誰とも分け隔てしないことに心がけている私は、勝手に来いやと楽天的に開き直った。
しかし帰宅してみると、全くの予備知識なしでは仕事に差し支えるのではと気にかかる。本棚から岩井弘融著『病理集団の構造・親分乾分集団研究』などを出して見ても全然わからない。ふと気づいて物置に山と積んである古雑誌の1冊に山口組の特集記事があり、簡単な説明付きの有力子分衆の一覧表から菅谷政雄の名前を見つけるやいなや、ショッキングな文字が飛び込んできて目がチカチカ。「元国際ギャング団領袖」「戦後神戸の山中で女を飼育」「山口組で最も戦闘的」「配下に30余組をもつ」などとあり、管谷組長は山口組配下120人ほどの幹部の中で10人に満たない大もの幹部の1人とされていた。いくら楽天的でも暴力には緊張する。こんな男と2ヶ月も付き合わされるかと思うと、いささか憂うつになったが、持ち前の楽天性から、何事も経験だとスイッチを切りかえた。
『顔役』のあらすじは、破天荒ながら成績を上げる無頼刑事(勝)が、2組の暴力団のからむ信用金庫の不正融資事件の黒幕を暴こうとするが、途中で警察上部からいきなり捜査を止められる。しかし無頼刑事は、警察手帳を捨てて真相を追求し、犯人たちを倒すというものだ。
さて勝組は、大阪のロケハンから行動を開始した。最初の目的地・大阪南港埋立地から、新世界のストリップ劇場へ移ろうとすると、勝監督より「少し待て」の指示。当時広大な現場は、ゴミや廃棄物で埋め立て工事が進行中だった。方々で表土の間から中身が露出して悪臭を放ち、メタンガスが炎を吹き上げ、炎天下の熱風がしばしば砂塵とともに襲ってくる。不快な思いに耐えて待っていると、ダンプカーが踏み固めた凸凹道の彼方から、ピカピカに輝く乗用車が砂塵を巻き上げて疾走してきた。見なれない大型の外国車だ。安定した車体の下で、車輪がボンボンと弾んでいる。
「こんなところで無茶しよるな」「物好きなやつがいるもんや」などと、一同唖然としていると、車は見る見る接近。目前で急激に方向転換して停車した。
降り立った男のスマートに見えたこと。花柄のアロハシャツに、薄色細身のスラックスを粋に着こなし、端正に刈り上げたゴマ塩頭の前髪を浜風になびかせて、一見60歳前後の文士風だ。次に行くべきストリップ劇場の経営者が、勝監督に敬意を表して迎えに来たか。独り合点していると、なんとそれが、山口組系で最も暴力的とされる菅谷組長のお出ましだった。
組長のすすめで監督は早々に助手席へ。尻込みする監督補佐と私は監督に強いられて後部席に座らされた。
新世界への途中、切れ切れに聞こえる前の2人の会話から、乗っている車が、当時国内に1台とか、関西に1台とかのリンカーン・コンチネンタル・マークⅡで、これが暴力団組長の間ではステータス・シンボルとして憧れの的になっているということだった。
やがて車は、物騒な風体の男たちがウロウロする釜ガ崎をゆっくり通り抜けていく。ときどき男たちが前に立ちはだかる。車を止めて組長の顔を覗く。しかし組長のにらみが効くらしくて、あっさり避けていく。新世界で車を降りると、組長は先頭に立ち、恐そうな人たちの誰彼となく如才のない言葉を交わしていく。スタッフだけでは緊張を要する従来のロケハンと異なり、私たちはのびのびと思うままにロケハンができた。
私は、組長=親分衆の祝儀不祝儀に、政財界の有力者や有名芸能人の顔や名前がちらつくのは無理もないとつくづく思った。
昼食は、組長の知り合いらしい料亭で摂った。勝監督以外は何となく遠慮気味。隣同士でぼそぼそと話し合っているが、私は今後の仕事を思うと遠慮しておれないし、その気もない。機会あるごとに何でも聞こうと思い、「菅谷さん」と呼びかけて、食事の前後にいろいろ聞いてみることにした。
「菅谷さんでも恐いものがありますか」
「そりゃあるよ。何が恐い言ったって、愚連隊やチンピラほど恐いものはないよ」
これには皆驚き、かつ大笑いした。彼らは仁義も切らず、いきなりブスッとやってくる。だから、どこかの組に属している“筋もの”は抗争関係でもない限り、お互いに安全だというわけで、一般社会同様、暴力団の社会でもアウトサイダーは危険分子だった。 最も尊敬している人は誰ですかと聞くと、即座に答えが返ってきた。
「全学連の学生諸君や」
山口組組長の名を予期していたのに意外な返事だった。
「学生運動の連中は堂々と警察に向かっていきよる。あの姿を見ると、僕らは頭を下げなしようがないがな。彼らは私利私欲でやっとらんから、あんなことができるんや。暴力団の連中はケツの毛まで欲にからんだ動きやから、情けないことに警察が出てくると自然に背中が向いてまうんや」
「どうして暴力に訴えるのですか」
「警察も自衛隊も暴力やろ。そやから僕らも、ちょっと暴力を使わしてもらうわけや」
「責任を感じませんか」
「天皇さんも戦争責任とってないやないか。僕らだって・・・」
「悪いとは思いませんか」
「そりゃ悪いと思っているよ。そやから無闇やたらに使わんよ。幸い世の中には叩いてやるとホコリの出る奴が大勢いるから、ちょっとずつ叩いてみるんや」
「一般の市民にも暴力が及んでいるが?」
「そりゃ、時たまとばっちりの飛ぶこともあるやろが、実際には一般の人に暴力をふるうような連中は、暴力団の中でも食いはぐれの屑や。そういう奴は警察の方でビシビシ取り締まってくれると、僕らの社会でも大いに助かる。ますます組織が強化されるばかりや」
当時は、警視庁・各県警本部が行う暴力団壊滅のための第2次頂上作戦の最中だった。
「どおすれば暴力団をなくせますか」
「君もきついことを聞くんやなあ。そりゃ世の中がよくなったら暴力団はすぐつぶれるがな。何でもない人に暴力は振るえんよ。政治がよくならんうちは、世の中も良くならんし、僕らは生きていける」
「一番大切なものは?」
「僕らの掟。山口組の憲法だな」
「国の憲法を大切にしてもらわないと困るんだけど」
「そんなこと言うけど、僕らの社会に入ってくるような連中は、ほとんどが生まれ落ちた時から日本国憲法に見放されたもんばっかりや。何でそんな奴が、国の憲法を守る気になるねん。山口組憲法の下にこそ、僕らの生きていく道が開けとるのや。その代わり実力主義1本やから、いつも命を張ってなきゃ、目から鼻へ抜ける連中がてんでに競争しとんのや。ぼやぼやしとるとアッという間に蹴落とされるんやで。始終危険がつきまとっとるけど、それなりに実力のある奴には生き甲斐がある。しかしやな、僕らも命は惜しい。好きこのんで殺し合いはしとうないから、それぞれの組が組長を立てて掟を守っとる。その最高が山口組の組長であり、山口組の憲法や」
対談は組長相手というより、理屈にたけた苦労人としている感じだった。ヤクザは偽るのがうまいと言えばそれまでだが、真情も含まれていると思えた。彼が自分を指すのに「僕」を使っているのが印象的だった。他にも彼は、実に面白い映画批評、社会批評を披露したが、しゃべり過ぎを自嘲したのかのように付け加えた。
「話に聞いたり読んだりした昔のヤクザは、口数少なく、腹がすわって立派だったということやが、僕ら近頃のヤクザは口先ばかり達者になって、度胸のある喧嘩もなくなり、映画のように格好のええもんじゃなくなった。口喧嘩で形がつかんと、へっぴり腰で突っつき合うのが関の山だ。だから今じゃ口から先に生まれた弁の立つ奴らで、僕らの社会が成り立っているわけや」
昼食後、神戸のロケハンに向かう車の中で組長との対談を思い返すと、いろいろな考えが駆けめぐった。
親分が白いものを黒いと言えば、「はい」と答えなければならないような掟が、現在どこまで守られているかわからないが、こうした理性を超越して存在する親分=組長の存在は、ある意味で天皇の存在と共通し、象徴天皇制を規定する憲法第1条は、暴力団の存在にとって大きな後ろ盾になっているのではないだろうか。
こうして見ると憲法第1条は、さらに多くの社会悪の存在に役立っているのではと考えが発展し、真実を探る風俗学への幻想がいっそう深まった気がしてきた。(2012年4月記)
⇒ 目次にもどる
| 第68回「“異色を発揮する勝新太郎監督”の時代 」 |
1971年6月下旬。勝新の初監督作品『顔役』を製作する勝組のメインスタッフは、午前の大阪ロケハンに引きつづき、リンカーン・コンチネンタル・マークⅡを運転する異色のヤクザ・菅谷政雄組長によって、神戸・北野のとあるクラブに案内された。
「ここは、山口組幹部の社交場やねん」
本格的なやくざ映画の製作に当たって、参考のために大物組長たちの生態を見ておいたらどうやというわけだ。
菅谷組長は、小声であちこちのテーブルに座を占めているグループについて解説した。
「あのテーブルを囲んどるのは、地元の○○組と大阪の△△組の組長や。……その向こうで騒いどるのは、広島から来た□□組長と横浜から来た××組長や。久しぶりなんやろ。……」
私は菅谷組長の話を耳にはさみながら、彼らの衣装や行為行動を観察し、チェックした。室内装飾はすべて豪華でぜいたくだが、しばしば傍若無人の笑い声が上がったり、野卑な大声がテーブルからテーブルへ飛び交って違和感を感じさせた。
また、何をされたのか突然ホステスが悲鳴を上げ、大笑いする男たちに見送られて泣きながらトイレへ走り込んでいったのが印象的で、戦国時代の遊里もかくやと思われた。
さて菅谷組長は、クランクインする頃から毎日のようにリンカーンで撮影所に現れた。食堂の一部に設けられた応接コーナーに座り込み、次々と現れる組関係らしき来訪者と間をつなぎながら、私の相談相手になってくれた。
私の仕事は、その日の撮影現場にも立ち会い、翌日の撮影準備に気を配りながら、少しでも早めに予定を組むことだ。多忙で気が疲れる。こんな私にとって、何でも気軽く相談に乗ってくれる菅谷組長の存在は実にありがたかった。
しかし、時々見せる陰惨で鋭い目つきには、吐き気を催すような嫌悪を感じ、彼はどうしてこんな人生を歩むようになったのか、と否応なく考えさせられた。
そして、何よりもスケジュールに関して不安だったのは、多数の暴力団員が出演する賭場と手打式のセット撮影、それに、遠方から手打ち式に駆けつけてくる客人衆が大阪空港ビルから大挙して出てくるロケ撮影であった。
先ず、花札に似た札を使う手本引による賭場撮影の件では、菅谷組系下部団体30余組の1組が出演できれば、寺銭(博奕の手数料)を扱う胴元、札を操る札師、札師を助ける強力(ごうりき)など賭場スタッフはそろい、残りの者は俳優の混じって張り方(客)にも使えるできるので、撮影は可能になる。しかし、各組とも仕事(=博奕)に追われていて、なかなかスケジュールがつかめない。菅谷組長も方々の縁故に当たってくれていたが、「お手上げだ」と弱音を吐く始末。私は思わずつぶやいた。
「こんなに博奕が行われていて、警察はいったい何をしているんだ」
「まあまあ、いろいろとな……」
組長は得意げに含み笑いをするばかりだった。
ところが、やっと来てくれたのかと思ったら全組員の目は真っ赤。仕事の徹夜明けで直行してきたとのことだ。
「ご苦労はんやな。頼むで」
最高位の組長にやさしく出迎えられ、それぞれ冷たいコーヒーやジュースを手渡しされた組員たちは、顔を洗って懸命に眠気を覚ました。ステージへ入っていけば、すでに中で待っていた菅谷組長は、子供に言うように言葉をかけた。
「お前ら、顔を写されて困るやつは顔をカメラに向けるなや。警察に追われとるもんがおったら遠慮なく言えよ。後ろの方に回してもろうたるさかいに」
助監督の指示に従い、全組員がセットに配置されると、菅谷組長は私の耳に強く念を押した。
「あいつら、腹をへらしたら何をするかわからん連中やから、かならず、昼には早い目に飯食わしたってな」
と、暴力団的労働配慮。暴力団も一般の企業経営と似たところがあるように思えた。
照明その他の準備がおわり、いざ「テスト!」ということになって、スタッフは驚いた。諸肌脱ぎになっていく札師の肌から極彩色の刺青が現れたのだ。朱と墨でおなじみの伝統的な刺青とは格段の相違。目を見張る鮮やかさに、ヤクザ社会も近代化が進んでいる気がした。
私は撮影が無事始まったのを見届けると次の段取りに移るので、その後はかいま見る程度だったが,札師を介添えする強力たちの金勘定の速さ、何枚もの紙幣を集配する見事な手さばきのなど、並々ならぬ仕事の熟練ぶりを見せていた。その情景を、勝監督はカメラを覗きながら撮影技師に指示して画面に収めていった。
そして翌日、ラッシュ(未編集のポジフィルム)試写を見て驚かされた。博奕の状況がわかるフルショットはほとんどなく、アップショットばかりの連続。スタッフはつぶやいた。
「勝ちゃん、アップばかり撮って、シーンをどうまとめるつもりなんやろ」
クランクイン当初から勝監督は、望遠鏡を初めて手にした子どものように、撮影の前にはいつもカメラを持ち、演技する俳優たちの顔にカメラを覗きながら近づいて行ったり、窓ガラスや車のボンネットなどに映る情景のアップからカメラを後退させて全景にパンするなど、何か既成のものとは違う画面を求めている様子だった。そのため撮影技師も、ときどき意図がわからなくて勝監督と衝突していたようだった。
私の場合は、不正融資を行う信用金庫の社長が、家族とドライブの途中大事故に遭遇して全員死亡する事件と、直後の検証シーンを撮影するロケでのことだった。アップ撮影ばかりで処理したので、勝監督との打ち合わせてどおりに用意していった警官や通行の見物人など俳優には、全く出番がなかったのである。
「勝ちゃん、経費が無駄になるから、打ち合わせをしっかりしてよ」
「いいから、いいから。適当に考えて用意してよ」
勝監督は私の忠告を意に介しない。以後私は、勝監督が自由自在に撮影できるように準備する段取りに徹した。
勝監督と撮影監督とは緊迫をはらみながらも、なんとか撮影は進行した。
そうなると、どんな作品が完成するか、ある面では楽しみでもあった。
いよいよ手打式撮影の日が来た。菅谷組長の伝手で10人以上の組長が和歌山、堺、大阪方面から、それぞれ数人の子分を連れて乗り込んできた。経営不振が原因で売り払った結果、敷地が狭くなっていた撮影所内は、子分衆がうろつき、高級車が思い思いに空き地をふさぎ、食堂内では菅谷組長を囲んで、組長たちが辺りかまわず談笑にふけるなど、異様な活気を呈した。
手打式とは、それまで敵対していた組の間に仲裁人が入って仲直りさせるための盃を交わす儀式で、親子の盃、兄弟の盃など盃事の中では最も厳しい儀式だという。なにしろ殺し合っても飽き足りない同士が向き合うので、ちょっと間違えば、どんな修羅場が展開されるかもしれないからだ。 従って、こうした儀式を無事終わらすためにヤクザの社会には、古くからの仕来りに明るい有職故実家のような特殊な儀式執行者=盃人が存在しているとのことだ。
この日来た盃人は組長クラスの貫禄があって仕事が忙しくて、別に組を立てなくても生計が成り立っているとのことだった。
盃人の仕事は、儀式が無事とどこおりなく済むように取り仕切るのは勿論のこと、式場の飾り付け、祭壇への盛り物、捧げ物、向鯛(本作品の場合は、鯛の代わりに背中合わせにした鯉2匹。仲直りができた時点で腹を合わせる)など用具の全てに及んでいた。
とにかくヤクザの社会は形式にうるさくこだわる。準備する用具は仕来りに従ってこまごまとある。それでも盃人は、傍らから見守る菅谷組長と冗談を交わしながら手際よく整えていく。式場に貼り回す「春日大明神」「八幡玄武神」など神の名や、列席者名、式次第など、それぞれの目的にあわせて裁断した和紙に肉太の達筆で手早く書き上げていく。
菅谷組長は感嘆する。
「相変わらず君は、うまい字を書きよるなあ」
「君は昔から暴力が取り柄やったから、書けんでええやん」
「ほんまに、そうやなあ。僕には暴力しか取り柄がないねん」
「人には、それぞれに取り柄があるというこっちゃが、1つでも取り柄があったらええやん。そやろ」
「そやなあ」
私は、雑談を交わす2人の近くのテーブルで調べものをしていたが、菅谷組長の淋しげな口調が今も耳に残っている。
盃人は手打式の撮影に出演し、儀式開始の挨拶で立派な口上ぶりを披露した。彼はさしずめヤクザ社会の知識人といった感じだった。聞く所によると、彼も若い頃は検察官になろうと司法試験に挑戦し、学科に合格しているとのことだ。
この日、子分衆に関して印象に残っていることが2件あった。
1件目は、出演している親分をステージの隅から見守る子分と、不況の映画界で汗を流しながらライトを操作していた照明助手との対話だ。
「お前ら、こんなしんどい仕事して、なんぼもろうとるねん」
「5万円くらいかなあ」
「1日に?」
「いいや、1ヶ月でや」
「なんや、しょうもな」
2人は互い白けて離れたが、照明助手の目の生気の無さと、子分の目の輝きが対称的だった。
2件目は、食堂で数人の子分が輪になって話し合っていたことだ。私は、彼らが親分の仕事が終わるの待ちくたびれているのかと思ったら、とんでもない。彼らは真剣な表情で侃々諤々、目を輝かせて仁侠道を論じ合っていたのだ。彼らは彼らなりに青春を生きている感じがした。
7月下旬、『顔役』はキツネにつままれるように完成した。『顔役』は、断固たる前衛映画だとか、わけのわからない素人の実験映画など、賛否両論のうちに時は流れ、私は10月の初め三隅研次監督作品『子連れ狼~子を貸し腕貸しつかまつる』に就くことになった。(2012年6月記)
⇒ 目次にもどる
| 第69回「“会社倒産は人間解放?”の時代 」 |
「いよいよ倒産か!」
1971年(昭和46年)10月に入った頃から、封切りを11月20日に予定して製作中の作品を最後に、わが大映は資金切れにより映画製作を中止するという情報が流れ、京都撮影所内では迫り来る倒産への不安がいっそう高まった。
ところが10月の末、勝新太郎の設立した勝プロダクションのプロジューサーが、東宝系の映画館で上映が決まっている作品だと称し、監督三隅研次・主演若山富三郎の『子連れ狼~子を貸し腕貸しつかまつる』の助監督に就いてくれと頼みに来た。
「ぼくが三隅さんと合わないことを、よく知っているくせに」
「そんなこと言わんと頼むよ。三隅くんは、ぜひ君に就いてほしい頼んでいるから」
「またかいな。……」
私は根負けして就くことにした。
仕事は、すでに小池一雄・小島剛夕が週刊漫画アクションに連載中のヒット劇画、『子連れ狼』の映画化だった。
作品の内容は、公儀介錯人(架空)=幕府から切腹を命ぜられた大名の横にいて首を斬るというの職を柳生一族の陰謀によって追われ、妻をも殺害された拝一刀(若山富三郎)が、一子・大五郎を箱車に乗せ、「子を貸し腕貸しつかまつる」と書いた幟を立て、柳生一族に対する怨念を秘めながら、すご腕の刺客として殺人請負いの旅を続けるという、荒唐無稽なものである。
しかし、シナリオに書かれた殺陣場面は、斬った首が飛んだり、首から血しぶきが噴き上がったり、なで斬りにされた両足首が飛んだり、箱車の柄が仕込み槍として飛び出すなど、三隅監督好みの残酷で超リアルな仕掛けをふんだんに要求していた。
それらに合わせて、私は撮影がスムーズに進行するような段取りに徹した。
ところが大五郎を演ずる子役の扱いには難渋した。
話の筋の導入部分は、3歳の大五郎を箱車に乗せて旅する現実場面と、公儀介錯人の職を追われた拝一刀が1歳の大五郎と旅に出る経緯を説明する回想場面が交互する。そのため、撮影進行の都合上、3歳の大五郎と、その吹き替えである1歳の大五郎がいつも必要になる。
しかし3歳児までの幼児は、疲れたり退屈すれば時・所をかまわず眠ってしまう。眠られてはどうにもならない。従って両方の大五郎に吹き替えが必要になる。場合よれば全部の幼児が使えなくなり、スケジュールを遅らせないためには、さらに別の吹き替えが必要な場合を考えておかなければならない。幼児が出演する場合はスタッフ全員が気をつかって撮影をこなしていかなければならない。当然監督にも同じことが要求されるのである。助監督としては監督に演出の時間を充分与えて上げたいのは山々だが、そうは言っておれない場合がある。その場合がやってきてしまった。事情は忘れたが、私はスタッフルームでカッと切れてしまい、三隅監督を怒鳴り倒した。プロデューサーが、顔色を変え慌てて止めに入った。 生まれて3回目のことだった。
1回目は小学2年の時。私をいつもイジメようとしていたクラス一番の腕白の手足をつかんで体を振り回し、教室の板壁に叩きつけて目を白黒させた。以後、私は文武両道に秀でたガキ大将とされ、仲間うちでイジメのないように目を光らしてきた。
2回目は大映入社間もない岐阜ロケで、大部屋の俳優さんが川の流れに逆らって舟を漕ぐ場面を撮影していたときのことだ。なかなかうまく漕げない。スタッフが笑う。俳優さんは慌てふためく。夕日が沈みかかったいるのに笑いは高まるばかり。下を見ると監督椅子に腰掛けた監督まで笑っている。私は切れた。
「何がおかしいんだ。日が沈むぞ!」
私の怒鳴り声でいっせいに笑いが止まり、撮影はうまく進んだ。監督が私を振り仰いでおもむろに言った。
「君は怒ると怖いねえ」
「すみません」
私は温厚な性格だと思っていたが、切れることがあることを自覚し、その後切れないように警戒していたが、ついに3回目を三隅監督にぶっつけてしまった。
この怒りが原動力となって、とりあえず私は劇映画から離れ、記録映画の分野に移ることになる。
すでに全員解雇を通告されている中で、12月初めに完成した『子連れ狼』は高評で迎えられたが、今後の私には関係ないことだった。
とはいうものの、新聞の映画欄で「これだけ殺人を美しく描ける三隅研次監督は無意識の作家か」と評され、将来の残酷指向を予見させる市川雷蔵主演『斬る』のチーフ助監督を勤めた1972年以来、三隅監督を反面教師として多くを学んできたきたことを忘れるわけにはいかなかった。
大映での仕事がなくなると、ある監督から「フリーで仕事を続けるのに有利だよ」と日本映画監督協会への入会を勧められたが、丁重に断った。
「自分に納得できる作品ができるようになったときには、ぜひお願いします」
捨てる神あれば拾う神あり。大映京都が形勢挽回をねらって2年ほど前に作ったコマーシャル営業部に入ってきたT君が、協力を求めてきたのだ。
入社以来T君は巨体を縮め、製作部の片隅でさびしそうにポツンと存在していたので、私はいつも元気づけていた事情があったからかもしれない。すでに業界を渡り歩いて目端の利くT君は、解雇通告と前後して映像制作会社エキスプレスに入社していた。翌1972年4月1日から開局する“びわ湖放送”の番組制作に協力してくれというのである。
私に断る理由はなかった。
小学5年以来、忠君愛国を強要する天皇制に反対してきた私は、太平洋戦争に負けたとき日本からの解放を感じたが、大映倒産は17年間勤めたしがらみからの解放、人間解放でもあった。
小学2年の長女、幼稚園児の次女をかかえて将来を心配する妻をなだめながら、私は新しい前途に意欲を燃やして1972年を迎えた。
( 2012年7月記)
⇒ 目次にもどる
| 第70回「“♪どこまでつづくぬかるみぞ!!” の時代」 |
「会社も倒産したことだし、マイペースでボチボチ行くか」
1972年(昭和47年)、のんびり正月気分に浸っていると、いらだたしげに電話のベル。電話は、新しく映像制作に乗り出した大阪のエクスプレス社(以後、EX社)でプロジューサーになっていた、T君からだった。
「“びわ湖放送”の番組制作は、4月1日の開局に間に合わせればいいので、その間に突っ込める仕事を引き受けました。急な話で恐縮ですが、すぐ打ち合わせに来て下さい」
T君は元大映京都撮影所へ中途入社したコマーシャルの営業部員。入社以来職場になじめないのか、巨漢のT君は体を縮め、製作部の片隅でポツンとさびしそうにしていたので、私はいつも元気づけていた。そんな事情があったからかもしれない。T君は、倒産前後から私に協力を求めていたのだ。
「まだ正月3ヶ日が過ぎたばかりじゃないか」
「先輩。そんなダダこねていると、フリーランサーで監督はやっていけませんよ」
私は、未知の記録映像業界へ演出の股旅(またたび=近世、博徒・遊び人などが諸国を股にかけて渡り歩くこと)に出る覚悟でEX社に出向いた。社長以下幹部から期待満々に挨拶され、私はEX社のメイン監督としてワラジを脱ぐことに決めた。
仕事は滋賀県教育委員会が企画したもので、滋賀県指定の無形文化財技術保持者7人の技術を映像記録し、『近江の伝統工芸』と題する1本の記録映画にまとめることであった。
技術保持者には、「本藍染」「揉み紙」「雁皮紙」「毛筆」「金箔」から各1人、「信楽焼」からは2人が指定されている。
各技術は、材料の栽培・加工など季節に支配されたり、時間がかかったりする各種多様な工程で成り立っている。現実の作業工程に合わせて記録していかざるを得ない。1月の寒い間は野外行程は不可能。まず屋内でできる本藍染の染めの工程を取材すると、次は信楽焼の粘土を手びねりして形を作る工程へ、さらに次は、箔打ち紙を仕込む金箔の工程などと、野洲町(現・野洲市)や草津市、信楽町(現・甲賀市内)などを、あちこち飛び回って取材を重ねた。
虚構で描く劇映画と違い、現場に立ち現実に向って記録映像の仕事をしていると、それなりの心にひびくエピソードに出合う。
金箔の技術者・今越清次郎さんは当時89歳。そんな高齢で満足に作業できるかな。不安気味に出向くと、船越さんは元気そのもの。その秘訣を聞くと、毎朝の乾布摩擦にあり。では、その様子を記録しようよ。カメラを用意していると、出てきた今越さんは手ぬぐいを持っただけの素っ裸。今越さんの乾布摩擦とは、睾丸を下から上へ100回こすり上げることだった。それは公表できません。笑いをこらえながら、あわてて背中の乾布摩擦に変更してもらう。
また、胃潰瘍の手術をしているという雁皮紙の技術保持者・成子佐一郎さんは、「なんで、こんなにしんどいのかなあ」とこぼしながら、記録のために雁皮紙を漉く。
私は成子さんが治療不可能の癌にかかっていることを家族から聞いていた。成子さんが息を吐くたびに、胆のう癌で死亡した母の看病で知った癌の膿の臭いを感じた。せめて完成試写までは生きながらえてほしいと祈りながら、すべてを記録できた。
しかし、翌年4月の完成を前に成子さんは亡くなった。仏前試写を行い、家族の方々から良い記念を残していただけたと、深く感謝されたことを今に覚えている。
ところで、 『近江の伝統工芸』にかかっている間に、びわ湖放送が開局する4月1日が迫りつつあった。『近江の伝統工芸』の制作はひとまず置いて、びわ湖放送の番組制作の合閒を縫うことにした。
さて、びわ湖放送での仕事は、大津、彦根、長浜、近江八幡、守山、草津、八日市など当時の滋賀県内七市がスポンサーの『ふるさとと私たち』と題するシリーズ番組の制作だ。市政解説を中心とする各市の社会教養30分ビデオ番組を毎月2本。同じく『近江歴史紀行』を副題とするスポンサー各市の歴史紹介30分ビデオ番組を毎月1本。これらの構成演出が私の仕事だ。月3本の番組制作となると、つねに次の番組を重ねて進めていかなければならない。厳しいスケジュールが予測されたが、ぜいたくを言える場合ではなかった。
『ふるさとと私たち』は、スタジオ対談と取材フィルムの構成番組。各市の広報部が提起する問題を討議して番組のテーマを決める。それに基づいて予備取材し、構成台本を作成。市側のOKが出ると、スタジオ対談に挿入の必要なフィルム画面作成のため、予備取材した場所へロケ。取材したフィルムの編集を終えれば、びわこ放送のスタジオに出演する行政の関係者やゲストを集め、構成台本に沿ってビデオ収録となる。
第1回目収録は暗中模索の連続だった。まず私の役割は、スタッフがカメラや照明などスタジオ準備の間に、別室で、司会者と出演者との打ち合わせをすることだ。台本に基づいて司会者や出演者に演出計画を解説し、対談内容を打ち合わせながら煮詰めていく。しかし出演者は、司会者役のタレント以外はすべて素人。まず初出演の緊張を解きほぐすのに苦労する。試行錯誤の上、軽い色恋話を交えることが効果的だとわかる。出演者の緊張がほぐれたところで、準備完了したスタジオへ案内する。
スタジオでのビデオ収録は、出演者と同じく私も初体験。他のスタッフも、短期研修は受けたものの、実際の番組制作は初体験。すべてが初体験者で番組収録を開始した。緊張で乾きがちになる舌を湿らせ湿らせ、ガラス窓を隔ててスタジオが見通せる副調整室から、インカム(ヘッドフォーンとマイクが合体した機器)を通して、スタジオのフロアにいる演出助手やカメラマンに指示を出したり、スタジオカメラから送られてくるモニター画面を見ながら、画面の切り替えを隣のスイッチャーに指示を出す。撮影、編集、音楽入れ、タイトル出しなどを同時に操作し、ステブレ(ステーションブレイク=番組を切り替えるための時間)1分を除いた29分ジャストの30分番組を一度に完成させてしまう。一カット毎の撮影、フィルム現像、編集、音楽録音、ミックスダビングなど多くの過程を踏んで完成させていく劇映画との違いを実感しながら、また、演技を直接見て行う劇映画の演出と異なって、モニター画面を介しての演出は、隔靴掻痒の感じでもどかしいと思っているうちに、司会者が質問を抜かしているのに気づく。あわてて司会者を外した画面に切り替え、その間に、フロア助手に指示して、司会者に番組の流れを修正させるなど、横で演出補助してくれる機械慣れした若いプロデューサーに助けられて、何とか最初のビデオ収録を終えた。
帰りがけの女性出演者たちから「夫たちには聞けないような話がたくさん聞けて、ほんまに楽しいお仕事だったわァ」とお礼や労いの言葉をかけられたが、帰宅途中のバスの中で、座席に沈み込んでいくような生まれて初めての不安感に襲われた。近所の医者に診てもらったら、血圧が160を軽く突破。半年間降圧剤を飲む破目になった。
番組制作が何本も重なり、徹夜して台本を仕上げ、A市での打ち合わせを終えると、B市へ急ぎ、次の企画を打ち合わせ、飛んで帰って企画書をまとめていると、C市の台本を至急仕上げてほしいの電話。原稿用紙に向かってシコシコ書いていると、つい軍歌が口から出てくる。
♪どこまでつづくぬかるみぞ/三日二夜食もなく/雨ふりしぶく鉄兜♪
私も、現人神・天皇を単なる人間と見破り、天皇崇拝から脱落した小学5年生までは、誰よりも軍国少年だった。腹が立つことに、それまでに私の音感は、軍歌になじむ音感になってしまっていたのだ。
(2012年12月記)
⇒ 目次にもどる
■過去ログ