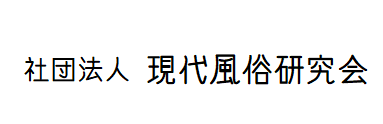| 2019年度3月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:3月30日(土)午後2時~
場所:徳正寺さん(四条富小路下ル)
発表者:水谷知生さん(奈良県立大学教授、元・環境省職員)
テーマ「国立公園をめぐる人々」
日本の国立公園は1934(昭和9)年に指定が始まり85年になる。明治期に米国の国立公園が紹介され,大正昭和初期に国内で国立公園選定が行われるが,その経過と関わった人々とその役割を見る。内務省・田村剛が中心となって選定を進めるが,地域によって様々な思惑がからむ。その中で選定,指定に難航した吉野熊野国立公園について,地元の岸田日出男の動きと考えを中心に,指定までの経過を見る。
| 2019年度2月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時: 2月16日(土)午後2時~5時
場所:徳正寺さん(富小路通四条下る西側)
*今回のお部屋はいつもの本堂ではなく、奥のお座敷になりますので、ご注意ください。
発表者:寺岡伸悟さん(奈良女子大学教授)
タイトル:奈良の「土産」話あれこれ
大仏、鹿、法隆寺、吉野山の桜・・・、インバウンド観光の恩恵を受けて地味な観光地である奈良(県)も観光客が増えています。報告者が見聞してきた奈良の土産にまつわるお話をとりとめもなく、お話します。
| 一般社団法人現代風俗研究会 総会開催のお知らせ | 2007/07/16 |
■一般社団法人現代風俗研究会 総会開催のお知らせ■■
(社)現代風俗研究会会長 高橋千鶴子
一般社団法人現代風俗研究会の総会を以下の要領で開催します。年末のお忙しい時期だと存じますが、ぜひご出席願います。
日時 12月8日(土)
場所 京都精華大学 黎明館 L-103
(京都市左京区岩倉木野町137 電話:075-702-5100)
■主な議題(予定)
(1)平成30年度事業報告及び収支決算についての事項
(2)平成31年度事業計画及び収支予算についての事項
(3)一般社団法人現代風俗研究会役員選挙
(4)その他
■プログラム
13:30~ 受付開始
14:00~15:00 総会・選挙
15:00~17:00
記念講演 針谷順子さん『現風研草創期の京都、東京の人びと』
18:30~ 懇親会(会場:ミュンヘン(四条河原町))
記念講演 針谷順子さん(編集工房 球)
★現風研草創期の京都、東京の人びと★
76年に京都に現風研が創立され、東京にも様々な情報がメディアを通じて入ってきた。参加したい人が増えて、77年東京にも現風研が発足した。
それ以来、京都と東京の現風研に参加して、様々な方に出会った。
エポックは、創立から10年目の継続論議と法人化、理事の世代交代、そしてあやかり隊事件が起きる。
その後も様々な知恵を絞って、40年以上存続しているのは慶賀の至り。話は主に前半の20年くらいに光を当てることになると思う。
| 2018年度7月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:7月21日(土)午後2時〜5時
場所:京都教育文化センター205号室
発表者:中山良子さん
太陽族と「純愛コンビ」の間に、なにがあるんやろうか。
吉永小百合はかわいいけど、なんやそれだけとちゃうんちゃうか?
「純愛コンビ」を描く映画作品が生み出され、消費される、ちゅう時代はなんなんやろうか?
1956年から東京オリンピックの始まる直前にかけての、「青少年かくあるべき」という声の高まりを、警察による暴力の管理や非行への言及、青少年問題協議会の動き、そして映画規制に着目ながら、考えたいと思います。
| 2018年度5月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:5月26日(土)午後2時〜5時
場所:京都教育文化センター205号室
発表者:鵜飼正樹さん
「人間ポンプものがたり」
「人間ポンプ」という芸、または芸人が日本にあらわれたのは、今から80年前のことでした。そして、2人の「人間ポンプ」が亡くなった1995年以降、「人間ポンプ」を名乗る芸は、演じられなくなりました。この間、何人もの「人間ポンプ」が、その芸を演じてきました。「人間ポンプ」とはいかなる芸であったのか? どのようにして生まれたのか? だれが演じてきたのか? なぜ姿を消してしまったのか? 忘れられた「人間ポンプ」という芸の謎を解明します。絵看板、ポスター、チラシ、映像などの秘蔵資料も、一挙大公開!
■過去ログ