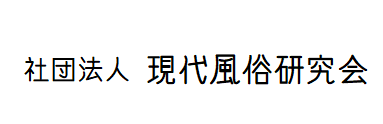| 2016年度3月例会のご案内 | 2007/07/16 |
*1月例会は都合によりお休み(延期)します。
日時:3月5日(土)午後2時~
場所:京都教育文化センター 102号室
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
発表者:工藤保則さん(27年度橋本峰雄賞受賞)
「『乙女の芸能』研究」ことはじめ
――乙女文楽・吉田光華さんをお迎えして――
昨年、私は『カワイイ社会・学』という本を出版しました。その中で、「おとこおとな」の世界観と「おんなこども」の世界観についての考察を行ったのですが、これからも引き続き、そのことを考えてみたいと思っています。
そのようなこととも関係して、今、「「乙女の芸能」研究」を始めたいと思うようになっています。「乙女の芸能」とは何なのか、ということはひとまず置いておくこととして(!?)、「乙女の芸能」(だと思われるもの)に直接アプローチしていこうと考えています。
3月例会では、さまざまなジャンルとのコラボレーションで「乙女文楽」の新境地を開拓している吉田光華(よしだ みつか)さんをお迎えして、乙女文楽の実演とお話をしていただこうと思っています。
【乙女文楽とは】
大正時代の末期、今から約80年前に、女性が一人で一体の人形を遣うことを目的に考案されました。一人遣いの人形芝居は、差し込みの法や片手人形の形式で、現在の三人遣い(文楽)となる以前から行われていましたが、大きさや形など今の文楽遣い人形を、三人で遣うものとして何とかして一人で遣えるようにしたいと、人形捜査に工夫を加え、一人でしかも少女が使うことから、この一人遣いを「乙女文楽」と称しました。
(吉田光華さん公式ホームページ
http://www.otomebunraku.com/ から)
私は2015年5月に吉田光華さんの公演を見て、とてもおもしろく感じました。それがきっかけで「乙女の芸能」について考えてみたいと思うようになりました。
例会では、吉田光華さんによる乙女文楽の実演とお話の後、参加してくださった方々と(もちろん吉田光華さんも含めて)、「乙女の芸能」ということに関して(もちろんそれ以外のことも含めて)、あれやこれやとお話しできればうれしく思います。
お誘いあわせの上(!?)、ご参加いただければ幸いです。(工藤保則)
| 総会開催のお知らせ | 2007/07/16 |
一般社団法人現代風俗研究会の総会を以下の要領で開催します。年末のお忙しい時期だと存じますが、ぜひご出席願います。
日時 12月5日(土)
場所 京都精華大学 黎明館 L-103
​(京都市左京区岩倉木野町137
電話:075-702-5100)
■主な議題(予定)
(1)平成27年度事業報告及び収支決算についての事項
(2)平成28年度事業計画及び収支予算についての事項
(3)「橋本峰雄賞」発表・贈呈式
(4)その他
■プログラム
13:30~ 受付開始
14:00~15:00 総会
15:00~17:00
記念講演 橋本敏子さん「隠居!もしくは暴走老人」
18:30~ 懇親会(会場 ミュンヘン)
正会員の皆様には、出欠確認のためのハガキ(兼委任状)を送らせていただきました。総会の円滑な運営のために、折り返しご郵送下さい。毎年のお願いで恐縮ですが、定足数に満たない場合は流会となり、再召集しなければなりません。ご都合がつかずにご欠席なさる方、総会開催の時間に間に合わない可能性のある方は、ご面倒ですが委任状に必要事項を記入の上、ご投函下さい。
(1)(2)の決算予算は例年通りの議題です。詳しい内容については当日会場で資料を配布いたします。なお、当日受付にて来年度の会費(一般会費:八千円・学生会費:三千円)を申し受けますので、あしからずご了承くださいませ。
* 会場へのアクセス*
・JR「京都」駅→市営地下鉄→「国際会館」駅下車→3番出口を右に30m、京都精華大学スクールバス
・阪急「烏丸」駅→市営地下鉄→「国際会館」駅下車→3番出口を右に30m、京都精華大学スクールバス
・京阪「出町柳」駅→叡山電鉄「鞍馬」または「二軒茶屋」「市原」行き、「京都精華大前」駅下車すぐ
*****************
テーマ 「隠居!もしくは暴走老人」
報告者 橋本敏子さん
(一般社団法人文化農場代表理事&
「ながらの座・座」主宰者)
隠居というたち位置は、なかなかオモシロイです。ヒトに言うと「何が隠居じゃ、ウソだー」と言われますが、こういう生きにくい時代を生き抜くには「インキョ」というのはなかなかええもんです。そもそもゲンプウケンも、そういう側面を持っていたから今まで続いていたのでは?
私が無謀にも会社を始めたのは現風研のスタートと同じ年。そんなわけで自分の分身?的感覚も持っているので、そんなことを含めて話してみようかな。
橋本敏子さんは、ながく現代風俗研究会の理事をつとめてくださいました。橋本さんが主宰される大津の「ながらの座・座」のホームページアドレスはhttp://nagara-zaza.net/ です。
| 2015年度9月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:9月19日(土)午後2時~5時
場所:京都大学楽友会館 二階講義室
京都市左京区吉田二本松町36-1
発表者:加藤秀俊さん
9月例会のスピーカーは、加藤秀俊先生(以下では「さん」づけでお呼びする)である。加藤さんは実は現代風俗研究会の誕生と深い関係がある。1975年にメトロポリタン美術館が所有する衣装のコレクションを初めて日本に持ってきて「現代衣服の源流展 英文名 Inventive Clothes」を京近美で開催するように企画したのは小池一子さん、その企画に乗ってスポンサーになったのが、ワコールの塚本幸一社長だった。当時、ファッションはアートであり、美術館がコレクションすべきものという認識がなかったから、展覧会自体が画期的、独創的なものだった。東京からわざわざ見に来たひとが多かった。その展覧会の協賛行事を何かやりたいということになり、商工会議所でその実行委員長になったのが京都信用金庫の榊田喜四夫理事長であった。榊田さんは親しくしていた加藤さんに相談、加藤さんは、それを機会に20世紀文明というものを基本的に見直すシンポジウムを開いたらどうかと提案され、やって下さい、ということになった。加藤さんは桑原さんに議長就任と、シンポジウムの構成案、メンバーの人選を相談された。技術・都市・芸術・風俗・生活・経済という6つのセッションが設定され、各セッションにはひとりの座長と4人のスピーカーを配し、5人で話し合う、それを他のセッションのメンバーも、円陣になって聞いていて、途中からその5人の議論に参加するという、32人のスター知識人による、前代未聞の、ゴージャスな学際的な会合であった。こうしたなかで風俗というセッションを設定すること自体が非常に新しかったが、それはこのシンポジウムが「現代衣服の源流展」の協賛行事であることを意識してのことであろうが、桑原さんに風俗というものに注目する問題意識があったのだろう。風俗のセッションの座長をつとめたのが多田道太郎さん、4人のスピーカーが佐藤忠男さん、宇野久夫さん、井上ひさしさん、鶴見俊輔さんだった。話は大変盛り上がり、今後風俗研究というものが、人間社会を研究する中心的な課題になるだろう、だから風俗学会を作ってはどうか、ということを都市のセッションの座長の上田篤さんが提案(多田さんが上田さんに予めそういう発言を頼んだのかもしれない)、それを受けて多田座長が、このセッションが風俗学会の最初の成果だと締めくくるというような展開であった。なぜ私がこのことをこんなに詳しく覚えているかというと、この仕事はCDIで受け、私が担当者だったからである。その後、桑現代風俗研究会を作ろうという動きとなるのであるが、このセッションが、現代風俗研究会を作ろうという原点になったことは間違いない。そういうわけで加藤さんは現風研の誕生と深い関係があるのであるが、ご本人にはあまりその自覚もご記憶もない。当時は活動の拠点を東京に移して(学習院大学教授)、永井道雄文相の応援団「文明懇談会」(これも桑原座長)をやっておられて、現風研を作ろうという動きには加わっておられなかったからであろう。今回、現風研にお越しいただいて話しをしてもらおうということになり、鈴付け役を私が依頼され、加藤さんにお願いした。現風研成立以前の、現風研創設者たちとの交遊、共同研究のスタイル、雰囲気のようなことをお話していただいたら面白いのではないでしょうか、と申し上げたが、そんな年寄りの昔話みたいなことをしてもしょうがない、風俗研究というのは、江戸期から非常に盛んで、明治以降も権田保之助、今和次郎、「思想の科学」が、それを引き継いでいるし、生活学会、現風研もその流れのなかにある、そうした流れのなかでの現風研の位置づけ、そのことの意味を改めて考えてみたい、と。うわっ、直球勝負だ。最近、『メディアの転回情報社会学からみた「近代」』という600頁を超える本をお出しになった加藤さんは85歳、ますます意気軒昂で、若造の私は先生の鼻息に吹き飛ばされそうである。(疋田 正博)
*例会内容、その他のお問い合わせは、現風研事務局までお願いいたします。楽友会館へのお問い合わせは、ご遠慮くださいますよう、よろしくお願いいたします。
| 2015年度7月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:7月25日(土)午後2時~
場所:東山いきいき市民活動センター
〒605-0018
京都市東山区三条通大橋東入
2丁目下る巽町442番地の9
TEL:075-541-5151
http://higashiyamacds.main.jp/
発表者:鹿島あゆこさん
(奈良女子大学博士後期課程)
「サラリーマンマンガにみる、サラリーマン像の変容」
通勤中の電車、休日の理容店、昼休みの定食屋、外回り中の喫茶店、自宅のトイレ…。そんな仕事のスキマ時間に、働く人を中心にした読者たちへ向けて「サラリーマン」を語ってきたマンガ群、それがサラリーマンマンガです。
第二次世界大戦終戦以後から高度経済成長期、安定成長期をへて、1990年代以降から現代は、長期経済低迷期といわれて久しくなりました。その間、「サラリーマン」たちの働き方や生活は大きく変化してきました。もちろん「サラリーマン」というカテゴリーに含まれる人々、そのものも変化してきました。
サラリーマンマンガは、そうした実態の変化にさらされた「サラリーマン」たちをどのようにすくい取って、彼らに向けた物語を表現してきたのか。マンガに描かれた「サラリーマン」の姿を歴史的に追うことを通じて、「サラリーマン」として働くことに持たれてきた夢の系譜をたどりたいと思います。
| 2015年度5月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:5月30日(土)午後2時から
場所:徳正寺さん
報告者:長﨑励朗さん
『孤独な鑑賞
―趣味縁的公共圏の盛衰―』
現代の若者にとって音楽鑑賞は最もポピュラーな趣味の1つである。しかし、2007年に行なわれた調査によれば、音楽鑑賞を「最も力を入れている趣味」として挙げた者のうち、半数近くが、「その趣味に一緒に取り組む友人がいない」と回答している。
音楽鑑賞をそもそも孤独な営みとしてとらえるならば、こうした趣味のあり方は当然のことのようにも思える。しかし、歴史的に見れば、音楽鑑賞は決して孤独な営みではなかった。かつての若者達は自身のアイデンティティをかけて、音楽について語り合っていたのだ。このように、音楽鑑賞による社会関係資本は、自身が聴いた音楽について語り合うことによって生まれてくる場合が多い。逆に言えば、音楽について語ることをやめたとき、孤独な鑑賞は始まったのである。
本発表は、音楽雑誌を資料として用い、こうした「音楽語り」の盛衰がどのような要因によって生じるのかを歴史的手法によって明らかにする試みである。
■過去ログ