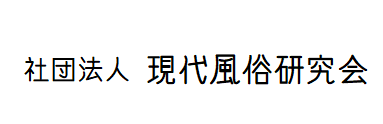| 2014年度5月例会のお知らせ | 2007/07/16 |
日時:5月24日(土)14時から
場所:徳正寺さん(Google Map:http://p.tl/zUMk)
報告者: 加藤政洋さん(立命館大学文学部)
テーマ:
京都花街の周辺文化 -「席貸」と「雇仲居」をめぐって
【内容紹介】
京都花街の周辺には、かつて「席貸」と称される特殊な旅館が集積していました。それらは、花街から見れば外部にありながらも必要不可欠な存在であり、独自の役割を果たしていたのです。また、そのような席貸街には、きまって「雇仲居倶楽部」なる事務所も立地していました。雇仲居(やとな)とは、芸妓と酌婦を兼ねるような職種で、主として席貸や料理屋へ派遣されることから、花街の近傍にありながら、お茶屋に芸妓を呼んで遊興するタイプとは別種の空間をつくりだす存在でもあったのです。今回の報告では、もはや歴史の後景に退いて久しい「席貸」と「雇仲居」をめぐって、前者については立地と建築(現在の用途)について、また後者についてはその成立と展開について幾ばくかの検討をくわえ、京都文化の隠れた側面を掘り起こしてみたいと思います。
| 2014年3月例会案内 | 2007/07/16 |
日時:3月29日(土)14時から
場所:徳正寺さん(Google Map:http://p.tl/zUMk)
発表者:巽美奈子さん(奈良女子大学大学院生)
テーマ:「 糧食-帝国陸海軍の食事― 」
「糧食」-自衛隊では今もその名残で使われる言葉だそうですが、ほとんどの方が初めて目耳にされたのではないでしょうか。糧食とは近代における帝国 陸海軍の兵士の食事全般をさします。
ところで私はあまり大っぴらにこの自分の研究カテ ゴリを話しません。なぜならそう話すと大概、「へ、え・・・」と引き気味の反応が返ってくるからです。さらには右か左かを問うような反応が・・・。ちなみに私は戦艦ヤマトマニアでもなく、軍事オタクでもありません・・・。それにしても不思議なものです。戦争・軍隊に嫌悪 感を抱き、戦争ものの映画やドラマですら見られな かった私が、なぜ兵士の食に強く惹かれるのか――。
その理由を客観的に答えるなら、戦時下にあった“特 殊性”の中にある食への関心であるといえるでしょ う。さらに今の、具体的関心は、イギリス式海軍と フランス式陸軍の糧食における異同を見つけること にあります。したがって今回は、軍事史料を提示しながら、拙いものですが、その興味関心を中心に、お話をさせていただこうと思います。また、提示する史料をもとに、皆さまからの貴重なご意見を賜れればさいわいです。
| 2014年2月例会案内 | 2007/07/16 |
日時:2014年2月8日(土)14時~
場所:徳正寺さん
報告者:亀井好恵さん
タイトル:「女相撲の観客反応からみえること」
概要:女相撲や女子プロレスは、本質的に越境性をもった芸能だと わたしは思っています。そのような芸能に接するわたしたちの受容のありかたを考察することは、安定した秩序をゆるがすものに対するわたしたちの社会の構え、みたいなものを明らかにすることにつながるのではないか、と考えています。
| 2013年度総会のお知らせ | 2007/07/16 |
一般社団法人現代風俗研究会の総会を以下の要領で開催します。年末のお忙しい時期だと存じますが、ぜひご出席願います。
日時 12月7日(土)
場所 京都精華大学 黎明館 L-103
(京都市左京区岩倉木野町137/電話:075-702-5100)
■主な議題(予定)
(1)平成25年度事業報告及び収支決算についての事項
(2)平成26年度事業計画及び収支予算についての事項
(3)「橋本峰雄賞」発表・贈呈式
(4)その他
■プログラム
13:30~ 受付開始
14:00~15:00 総会
15:00~17:00 2014年度のテーマに関する報告
・「現風盛衰記」井上俊
・パネルディスカッション
18:00~ 懇親会(会場は三条・四条界隈を予定)
正会員の皆様には、出欠確認のためのハガキ(兼委任状)を送らせていただきました。総会の円滑な運営のために、折り返しご郵送下さい。毎年のお願いで恐縮ですが、定足数に満たない場合は流会となり、再召集しなければなりません。ご都合がつかずにご欠席なさる方、総会開催の時間に間に合わない可能性のある方は、ご面倒ですが委任状に必要事項を記入の上、ご投函下さい。
(1)(2)の決算予算は例年通りの議題です。詳しい内容については当日会場で資料を配布いたします。なお、当日受付にて来年度の会費(一般会費:八千円・学生会費:三千円)を申し受けますので、あしからずご了承くださいませ。
※会場へのアクセス
http://www.kyoto-seika.ac.jp/access/index.html
| 2013年9月例会案内 | 2007/07/16 |
日時:9月7日(土)
場所:徳正寺さん
報告者:内田忠賢さん(奈良女子大学)
タイトル:「街の衰え-衰退都市の誘惑」
自分が中年になってくると、若い男より中年男のほうが魅力的だと強がってみたくなる。年季が入った物腰の柔らかさや落ち着きをアピールしたくなる。全身から発する加齢臭、いや哀愁もウリにしたいと内心では考えてしまう。愚かな考えとはいえ、反面、いいアイデアだとも思う。
街も同じだ。元気一杯の街、生まれたばかりの街には、深みがない。盛衰を経験し、酸いも甘いも噛み分けた街こそ、魅力的である。古都や城下町の旧市街だけではない。廃鉱となった炭鉱町や鉱山街、元・軍隊の町……特に、栄光の時代もあったであろう廃れきった盛り場など、哀愁むんむん、とても魅力的だ。居酒屋放浪記ならずとも、一人しみじみ歩いてみたくなる。今回は、地理学者の私が、僭越ながら、廃れ街の魅力について、思う存分語ってみたい。乞ご期待。
■過去ログ