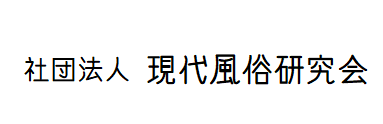| 2018年度4月例会のご案内 | 2007/07/16 |
現代風俗研究会 4月例会のご案内
日時 2018年4月7日(土)午後2時から
場所 徳正寺さん
報告者 森 治子さん
「お手伝いさん、社会学にであう
-現風研的目線でみた介護の世界-」
このところお休みしていますが、会報で「お手伝いさんは見ないふり」を連載している森治子(森ハルコ)です。ふだん私は週の半分を福祉の世界で介護者もしくは介助者として働き、週の半分は非常勤講師として生活文化史や大衆文化論、家庭科的な科目を教えています。
ちょっとした思いつきから福祉の世界に足を踏み入れることになりましたが、生活学や民俗学的な視点や知識をもって福祉の現場に入ることは、かなり大きな強みであると感じています。
最初は訪問介護員(訪問ヘルパー)から仕事を始めました。訪問ヘルパーはご自宅にうかがい、その家の台所用品や電化製品を使って家事援助を行ったり、入浴や排泄の介助をします。入所施設や病院とは異なり、ひとの生活が築かれてきた住まいのなかで支援するということは、その人のプライバシー空間に入り、生(ナマ)の生活に介入することになります。家族でも親戚でもないのに台所に立ったり、家の掃除をする。おむつを交換したり、入浴を手伝うなど、肌に触れることも多い仕事です。家族のプライバシーには立ち入らないけれど、利用者さんとは一対一の親密な関わりを持ちます。
利用者さんから昔の話が聞けること、家財道具やインテリアから、生活のうつりかわりを感じることができるのは訪問介護のおもしろいところです。お風呂の縁にしゃがんで戦前の子供時代の話を聞いたり、洗いもののなかに昔のトリスジュースのコップを見つけてひとり盛り上がったり。
ただヘルパーの仕事は体力もいるし、楽しいことばかりではありません。大雪でも台風でも休めないし、責任も大きい。独居のかたが倒れているのを発見することもあります。観察すること、話を聞くこと、という楽しみがなければ、私はヘルパーの仕事をおもしろいとは思えなかったかもしれません。
訪問ヘルパーとして働くなかで、さまざまな社会問題にぶつかることもありました。いままで自分が知らなかった世界を知り、そこであらためて社会学と出あうことにもなりました。現風研でなじんでいた楽しくおもしろい社会学とは違う社会学でした。
お手伝いさんが遭遇して考えた、現風研的視点からみた現代介護事情をおはなししたいと思います。
| 2018年度1月例会のご案内 | 2007/07/16 |
日時:2月3日(土)午後2時〜
場所:徳正寺さん(富小路通四条下る)
「着せ替え人形はだれのもの」
報告者 川井ゆうさん
着せ替え人形を、たとえば『日本国語大辞典』でひくと、「人形の一つ。紙製、布製などの着物を着せかえることができるようになっているもの。子どもの遊び具」と書かれております。なのでタイトルの「だれのもの」と問われれば、「子どものもの」と答えて、辞典的には正解です。わたくしも女児のころ、着せ替え人形でよく遊んだものでした。だがしかし。着せ替え人形たちをいろいろ見ていると、どうやら「子どものもの」とひとことで済ませてはいけないのではないか。そんなことをつらつらかんがえて二十年が経ちました。そして大げさですが、21世紀の着せ替え人形遊びは、携帯電話を持たない昭和のわたくしにはもう、遊び方さえわからないような一面があります。手に負えないのであります。そこでこの例会で報告をさせていただく機会をもって、いったん棚上げにしようとおもいいたりました。
時間のゆるすかぎり多くの図版をお見せしたいとおもっております。しかし棚上げするとなると、着せ替え人形について報告すると言いながら、わたくし自身の過去を語ることになってしまうかもしれません。たとえば、幼いころ買ってもらえなかった着せ替え人形のコマーシャルソングをいまだに覚えているわたし。とくべつなリカちゃん人形を抽選で当てようと、研究のためとはいえドーナツを大量食いしたあのとき。おもちゃ屋さん(この表現がセピア色)で、おばちゃんのわたしがひとり、子どもたちにまざっていっしょに遊んでしまい、ママたちに警戒された(かもしれない)あのとき。べつのおもちゃ屋では写真を撮っているあやしいわたし。
どうぞ聴いてやってくださいませ。
| 2017年度7月例会のご案内 | 2007/07/16 |
7月22日(土)午後2時
場所:紫明会館 3F講堂
(京都府京都市北区小山南大野町1番地)
京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅より徒歩7分
(紫明通り烏丸通り交差点を西へ歩き北側に面する洋館3階建の建物です。)
発表者:北夙川不可止さん
現風研の皆さん、北夙川不可止です。
7月22日の例会で、久しぶりに発表をさせて頂くことになりました。テーマは『東西名品 昭和モダン建築案内』です。
今年の一月に、同名の書籍を洋泉社から刊行しました。現風研の皆さんと一緒に書かせて頂いた『性の用語集』を始め共著は何冊かあるのですが、背表紙に名前が載る本を出せたのは初めてです。
1988年に神戸・旧居留地の旧神戸商工会議所ビルヂングの保存運動に携わって以来、かれこれ30年近く近代建築と都市の歴史的景観の保存と活用を訴え続けています。2015~6年にかけては心斎橋大丸の保存運動に取り組み、大阪(船場ビルディング)、京都(東華菜館)、神戸(チャータードビルヂング)、近江八幡(アンドリュース記念館)、それに東京の青山学院間島記念館、郵政博物館の計六ヶ所で原図展を開催、シンポジウムも三回催し、相当な反響がありましたが、それでも日本を代表する世界的なアール・デコ建築は今、瓦礫の山になってしまっています。
その悔しさもあり、今までの活動をまとめる意味でも、本を書いておこうと思ったのです。
今年に入ってからは朗報もありました。同じくここ数年、ずっと保存に取り組んできた奈良少年刑務所の重要文化財指定です。負け戦が殆どではありますが、少しずつでも世の中を変えようと足掻き続けて、ほんの少しですが変化を感じることもできるようになっています。
今回は登録有形文化財建築である紫明會舘にて、拙著『東西名品 昭和モダン建築案内』を中心に日本の近代建築と都市景観についてお話させて頂ければ、と思います。
☆懇親会 18時より
東華菜館 (四条大橋西詰南側)
| 2017年度5月例会のご案内 | 2007/07/16 |
「ながらの座・座」見学と懇談
5月27日(土) 午後2時
場所 大津市 ながらの座・座 (下記参照)
あんない人:橋本敏子さん
(元・正蔵坊と古庭園を楽しみ守る会代表)
現風研メンバーの橋本敏子さんは大津の西郊、三井寺の庫裡の一つだった「元・正蔵坊」を保存したうえで、「ながらの座・座」として人びとが出会う場に供し、運営されてこられました。
5月例会では、この場所を訪問し、橋本さんにごあんないをいただいたうえで、これまでの活動についてお話をうかがいます。その後は、歓談。現風研の今後についての意見、これからの企画のアイデアなどを交換……というまじめな交流から、いつものとりとめのない話まで。「座」の雰囲気を楽しみたいと存じます。
なお、終了後に近辺のお店で懇親会というかたちをとらず、「ながらの座・座」でそのまま飲酒歓談とさせていただきます。銘々、ご自身の分の食べ物、飲み物、酒肴などご持参いただきますよう、おねがいいたします。
ながらの座・座 http://nagara-zaza.net/
所在地
〒520-0035 滋賀県大津市小関町3-10 電話 077-522-2926
・JR 東海道本線「大津」駅 北口改札(びわこ口)より徒歩約15分
・京阪電鉄 京津線「上栄町」駅より徒歩約7分
・京阪電鉄 石山坂本線「三井寺」駅より徒歩約7分
| 2017年度3月例会のご案内 | 2007/07/16 |
3月11日(土)午後2時から
徳正寺さん
「鶴見俊輔さんと現風研」
このところ例会・総会の場では、現風研の活動を回顧するために古くからの会員さんや会にゆかりのあった方がたのお話をうかがっております。これまでに、井上俊さん、井上忠司さん、加藤秀俊さん、高橋千鶴子さん、津金澤總廣さん、橋本敏子さん、疋田正博さんら、多くの方々にお話しをうかがってまいりました。
そのいっぽうで、桑原武夫さん、多田道太郎さん、鶴見俊輔さんほか亡くなられた方については、それぞれの回顧のなかで断片的なエピソードは出てくるものの、まとまったかたちでは語り合う機会がありませんでした。
そこで、今回は鶴見俊輔さんがかかわられた現風研内のプロジェクト、ワークショップをとりあげ、ふりかえる機会を設けようと考えております。文章教室、「はがき報告」研究会、「鶴見俊輔集」を読む会からそれぞれメンバーだった方にお越しいただき、お話をうかがいたいと存じます。70年代の文章教室、80年代の「はがき報告」研究会、90年代以降の「鶴見俊輔集」を読む会というふうに、年代ごとの鶴見さんの活動をたどることもできそうです。
報告・討議といった堅苦しいかたちではなく、同窓会のような感覚でお集まりください。むかし話の輪にくわわっていただければさいわいです。
話題提供者は以下のとおりです。
文章教室 日座たえさん(旧姓水嶋さん)
「はがき報告」研究会 疋田正博さん
「鶴見俊輔集」を読む会 野口良平さん
(連絡役・永井良和)
■過去ログ