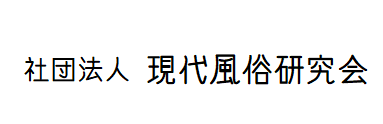| 2022年度総会のご案内 | 2022/12/06 |
日時 12月10日(土)
場所 京都精華大学 黎明館 L-103
(京都市左京区岩倉木野町137 電話:075-702-5100)
■主な議題(予定)
(1)2022年度事業報告及び収支決算についての事項
(2)2023年度事業計画及び収支予算についての事項
(3)一般社団法人現代風俗研究会役員選挙
(4)「橋本峰雄賞」授賞式
(5)庶務報告
■プログラム
13:30~ 受付開始
14:00~15:00 総会・選挙
15:00~17:00 記念講演
報告者 ファッション自分史の会 日座たえ・橋本敏子・山本紫津子
『「昭和のかほり」ファッション自分史の会を通して現風研を紐解く』
| 現代風俗研究会 2022年度 9月例会 | 2022/09/09 |
日時:9月10日(土)14~17時
場所:徳正寺
(対面での開催を予定、京都市下京区 四条富小路下ル徳正寺町)
蔦秀明・内田忠賢
「リメンバー「現代遺跡探検隊」「娯楽の殿堂ツアー」フォーエバー」
現代風俗研究会ではコロナ前から、年間テーマを「昭和のかほり」と設定し、戦後、特に高度経済成長期に花開いた大衆文化の探究を念頭に、例会を設定してきました。
2年半前の橋爪紳也さんによる大阪万博の研究、輪島裕介さんによる昭和ディスコ音楽の研究、コロナ禍による研究会活動の休止2年間を挟んで、(橋本峰雄賞ご受賞)古川岳志さんの競輪研究、そして先頃の色中亭達磨さんのプロ野球(西鉄ライオンズ)研究…。
現代風俗研究会でも、かつて、「昭和のかほり」を探究する幾つかの熱心な活動がゲリラ的に行われていました。たとえば、1980年代末から1990年代にかけての、鵜飼正樹さんや橋爪さんが中心となった「現代遺跡探検隊」、蔦秀明さんや永井良和さんが中心となった「娯楽の殿堂ツアー」。風変わりな地下?活動ですが、思えば、時代を的確に掴んでいたように思われます。
今回は、エキセントリックながら、多くの(当時)若い会員を巻き込んだ、この2つの活動を、記録・記憶から呼び戻し、当時の楽しみ方、味わい方を共有し、令和の楽しみ方、味わい方も展望したいと夢想します。また、できれば文化的な意味、歴史的な意義について妄想してみたいのです。
集え!昭和の若者!平成の若者! 令和の若者(まだ無理か…)!
☆参考図書
現代風俗研究会編『現代遺跡・現代風俗91』(リブロポート、1990年)
現代風俗研究会編『現代風俗 娯楽の殿堂』(新宿書房、2006年)
| 2022年6月例会のご案内 | 2022/06/10 |
日時:2022年6月25日(土) 午後2時〜5時
場所:京都教育文化センター101号室
話題:「西鉄ライオンズがあったころ―神様・仏様・稲尾様―」
話題提供者:色中亭達磨(松田隆典・滋賀大学教授)
〈概要〉
発表者はMLBとNFLのチームの立地条件について論文らしきものを執筆した。一方、日本のプロ野球やJリーグの歴史とチームの立地条件について研究するなか、郷里に近く少年期にファンになった西鉄ライオンズの歴史とその盛衰の背景について調べ、あわせて立地する福岡・博多(合わせて福博)の発展について考察した。メインタイトルは永井・橋爪両氏の著書のオマージュである。未発表のエッセーも同じタイトルで執筆中である。サブタイトルはその中の中心的な登場人物の1人稲尾和久の自伝のタイトルでもある。
コンテンツとしては、西鉄ライオンズがプロ野球チームとして参入した経緯、1950年代まで監督を務めた三原脩の日本シリーズ3連覇と1958年シリーズで稲尾投手がサヨナラホームランを放った時の写真の球場の看板広告の分析、中西太が監督を務めた1960年代半ばにおける福岡市の発展などである。ここまでは発表者がプロ野球をテレビで観戦して仲間とプレーに興じる以前の出来事であり、発表者にとって「神話」である。リアルタイムで「目撃」していない古写真などを使って紙芝居風にお話ししたい。
発表者にとってのリアルタイムのライオンズの野球は、永井・橋爪両氏にとっての南海ホークスと似た、いやより「被虐」的ともいえる状況の中での「経験」であった。南海ホークスと同様にチーム成績は低迷し、ついには「黒い霧事件」で存立の危機を迎える。上記のサブタイトルを掲げたことから、できれば稲尾がライオンズ監督を務める時代、福岡ライオンズとして生き残るところまで何とかお話しできればと思っている。
| 会員各位へのお知らせ | 2020/08/30 |
会員各位へのお知らせ井上章一
このたびは、新型コロナとよばれる感染症のおかげで、社会はたいへんな混乱を余儀なくされています。現風研も、その例外ではありません。通常の例会も、今は開催をひかえています。のみならず、今年は年末の総会もひらかないことを、きめました。理事ら一同の総意で、今年は断念しようということになっています。ここに、会長としてその決断を、各位へおつたえするしだいです。ただし、会費はちょうだいいたしません。何もできないのだから、お金をいただくわけにはいかないと、判断いたしました。会費の徴集が心おきなくできる日常を、はやく回復させたいと、今はねがうのみです。
感染症対応はたいへんです。でも、この状況でもたらされる風俗面の現象を、ひややかに記憶しておくことも大事なのではないでしょうか。
マスク、フェイス・シールド、夜の街…。この時期に、現風研ならではのレポートが作製されるされることも、ねがっています。
・2021年度総会は、書面開催となります。
・2021年度会費は、徴収しません。
・9月以降も、活動休止は続きます。
| 現代風俗研究会の活動に関するおしらせとおねがい | 2020/05/06 |
一般社団法人現代風俗研究会 会長 井上章一
さきに、3月例会(4月4日開催予定)について延期のおしらせをいたしました。その後も新型コロナウイルスの感染状況は好転しているといえず、5月例会、7月例会についても通常の開催は困難だと判断いたしました。理事会でも検討し、8月末まで、現風研例会およびプロレス文化研究会例会・新風俗学教室の開催、会報の発行などの活動を停止することにいたします。
なお、9月例会の開催をもって、会の活動再開といたします。
例会は、以下の要領で9月に再開することを考えています。
日時・会場 いずれも未定
話題 「西鉄ライオンズがあったころ―神様・仏様・稲尾様―」(仮)
話題提供者 色中亭達磨(松田隆典・滋賀大学教授)
ただし、感染状況によっては9月以降の活動もひきつづき停止するばあいがあります。くわしくは、8月末か、9月のはじめごろ、あらためて連絡をさしあげます。
なお、事務局についても8月まで閉鎖いたします。この間の業務についてご不便をかけるかもしれませんが、ご理解をねがいます。
さいごになりますが、会員のみなさまの健康と安全をねがっております。
■過去ログ