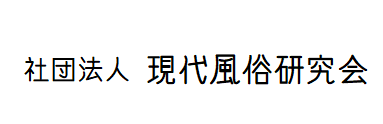| 第14期「街を見る風俗学」第2回 | 2007/07/16 |
報告テーマ
「タウンウォッチングの魅力
-街を見る、店を見る、人を見る」
報告者 大田雅和さん(博報堂 研究開発局)
日時 2006年12月16日(土)午後3時~6時
会場 日本女子大学目白キャンパス百年館高層棟302会議室
| 第14期「街を見る風俗学」第1回 | 2007/07/16 |
報告テーマ
「今和次郎とその後継者
─建築から視る(仮題)」
報告者 黒石いずみ(青山学院女子短期大学)
日時 2006年10月14日(土)午後3~6時
会場 日本女子大学目白キャンパス百年館301会議室
・報告要旨
黒石さんのご著書である『「建築外」の思考-今和次郎論』(ドメス出版、2000)。このご本をもとに今和次郎とその継承者についてお話しいただける予定です。
今和次郎については、川添さんをはじめ多くの方からお話しをうかがってまいりました。今回の黒石さんは、建築の視点からの今和次郎論です。考現学や風俗論・社会学とは異なる視点からの今和次郎論をうかがうことができそうです。
| 第12期「身体の風俗」第7回 | 2007/07/16 |
報告テーマ
『美をめぐる技法
-経験者たちのライフストーリーからみる美容整形-』
報告者 木村絵里子さん(日本女子大学大学院)
日時 2005年3月12日(土)午後3時~6時
会場 日本女子大学目白キャンパス 百年館3階 302会議室
| 第12期「身体の風俗」第6回 | 2007/07/16 |
報告テーマ
『顔にアザやキズのある人の心理』
報告者 石井政之さん
日時 2005年1月29日(土)午後3時~6時
会場 日本女子大学目白キャンパス 百年館3階301会議室
・ご報告要旨
顔面に疾患や外傷のある人たちを支援することを目的に1999年に設立された市民団体「ユニークフェイス」。その活動が、身体論に関心をもつ研究者たちの間で次第に注目されるようなっている。
アザのある青年(ユニークフェイス代表の石井政之がモデル)が、2004年10月から放送されているテレビ番組『3年B組金八先生』に登場して、その知名度は一般の間でも高まりつつある。
しかし、日本では、顔面に疾患や外傷のある当事者に対する社会的、心理的研究は、欧米と比べて立ち遅れているために、正確な理解をしている人はまだ少ない。人間の顔にアザなどの目立つスティグマがあるとはどういうことなのか、を考えます。
事前に読んで頂きたい書籍。
石井政之著『顔面バカ一代』(講談社文庫)
| 第12期「身体の風俗」第1回 | 2007/07/16 |
報告テーマ
『異性装・同性愛研究の射程(仮)』
報告者 杉浦郁子さん(中央大学)
日時 2004年6月12日(土)午後3~6時
会場 日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟3階
大学院第2講義室
・ご報告要旨
「戦後日本<トランスジェンダー>社会史研究会」は1999年の発足以来、異性装や同性愛にかんする口述資料、文献資料を収集してきた。この報告では、当会の活動成果を紹介、検討しながら、日本のクィア研究のこれまでの展開や到達点を概観する。そのうえで今後の研究課題やクィア研究の可能性を考えてみたい。
■過去ログ