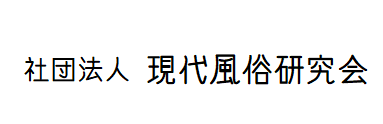| 2012年9月例会のご案内 | 2007/07/16 |
■日時:9月15日(土) 午後2時~
■場所:徳正寺さん(下京区四条富小路下る)
(Google Map:http://goo.gl/w3ZeR)
■報告者:川井ゆうさん(元おままごとの会、祖母兼姑兼母役)
■テーマ:「カレーの食べ方大研究」のその後
■報告要旨
あれはもう十七年前のことじゃったか、当時の二十代の若者たちといっしょに、ちいさな活動をしたことがござった。ひょっこのあつまりという意味をこめて「おままごとの会」と名づけたんじゃ。そのときはのぉ、「カレーの食べ方大研究」、「私鉄沿線みやげもの調査」、「おままごとの真髄」のみっつについて、しらべたんじゃ。かつての若者たちはみなりっぱになったが、ババアのわしは、ずっとババアのまま生きながらえておる。じゃがの、ババはそのみっつの調査を宝物にしてそれ以後もだいじにだいじにして、ババアなりにそだてておったんじゃ。かつての若者たちのように多くの人たちにアンケートをしたりはもうできんのじゃが、ババアがだいじにしてきた宝物のひとつを、今回みなさんにみてもらおうとおもっておる。
十七年まえの報告をごぞんじない方のために言いそえておくと、おままごとの会のカレーの調査は、カレーの歴史がどうのこうのというのではなく、また、カレーのルーの材料云々でもなく、はたまたカレーの味にも関心をむけてはおらぬ。ひたすら、「食べ方」をながめたのじゃ。現風研流には「しぐさ」とでも言おうかのぉ。それから十七年、ババア独自のそだてかたをしたもんじゃから、もとの調査とはかなりちがったものになったがの、それはそれなりに、笑ってもらえるものではないかと、内心期待しておるんじゃよ。
古株の現風研会員諸氏に告ぐ。来られるまえに、十七年前の調査の成果が書かれた年報(脳内グルメ)の54頁から66頁を読んでおかれると、よいかもしれぬ。
| 2012年7月例会のご案内 | 2007/07/16 |
■日時:7月14日(土) 午後2時
■場所:徳正寺さん(下京区四条富小路下る)
(Google Map:http://goo.gl/w3ZeR)
■報告者:小川伸彦さん(奈良女子大学)
■報告要旨
いま、一瞬、まわりを見回してみてください。何かの箱や袋はありませんか。また。モノを見せるちょっとした空間も目に入るのではないでしょうか。
前者は、パッケージ。後者はディスプレイ。ともに私たちの生活や街に不可欠な要素でありながら、その生態は見逃されてきたように思います。
そこで、奈良女子大学文学部文化メディア学コースの学生たちとともに、パッケージ&ディスプレイ研究をおこない、2冊の報告書にまとめました。拙いものですが、今回はその内容を紹介いたします。これをまくらに、パッケージ観察ばなしやディスプレイ体験談などを皆様からご披露いただければさいわいです。
★お願い★
例会に参加される方は、できるだけ何か一点、<気になるパッケージ>をご持参ください。何を「パッケージ」とするかの判断もおまかせします。
| 2012年6月例会案内 | 2007/07/16 |
■日時
6月2日(土)午後2時~5時
■報告者
斎藤光さん(京都精華大学)
■テーマ
「学校制服を考えることに向けて」
■会場
徳正寺さん(下京区四条富小路下る)
| 2012年3月例会案内 | 2007/07/16 |
■日時 3月24日(土)午後2時~5時
■報告者 安田昌弘さん(京都精華大学)
■会場 徳正寺さん(Google Map:http://goo.gl/w3ZeR)
■テーマ「文化のグローバリゼーション
~京都ブルースの事例から」
■趣旨
♪シカゴに来てぇ 二年が経った
だけどいいこと ありゃしねえ
メンフィスから 汽車に乗って やってきたけれど
ほかの 奴らは 上手いこと やってるけど
この俺 だけが 落ちぶれちゃった
街の片隅で 小さくなって ひとり暮らしてる
98年に解散した大阪のブルースバンド・憂歌団の「シカゴバウンド」(1975年)といううたです。このうたを聴くたびに、私はある種の不思議な感覚にとらわれます。それは、どうもこのうたが一人称で語られていることにあるようです。大阪出身の4人組が、大都市シカゴで落ちぶれてしまった「俺」の心情を日本語で歌い上げる。大抵の場合、この歌が好きな人は(少なくとも私は)、「俺」はメンフィスの田舎から夢を抱いて大都市シカゴに来て、数年後に夢破れて落ちぶれた黒人ブルースミュージシャンだと勝手に想像して、「ホンモノらしさ」を感じています。でも、実際には、このうたはかなりちぐはぐな要素で構成されています。歌詞の内容から考えても、「俺」がどんな肌の色で、どんな仕事を求めていて、なぜシカゴにいて、どうしてメンフィスに帰りたがっているのかはわかりません。そもそもどうして「俺」は日本語で歌っているのでしょうか。
文化のグローバリゼーションというと、コンテンツ輸出とかクールジャパンとか、なにかそういう大層なお話が想起されるかもしれませんが、今回は、日本(語)のブルースが持っているこのような多義性、あるいは重層的なアイデンティティのあり方を通して、グローバルなるものとローカルなるものの結びつき方について考えてみたいと思います。ともすると私たちは、グローバルなるものを一方的に振り返ってくる(災厄に近い)なにものかとして捉え、ローカルなるものをそのような災厄に抗おうとする(ロマンティックな)なにものかとして二項対立的に捉えようがちではないでしょうか。しかし、そのような単純な構図だと、どうして1970年代初頭の京都で急にブルースがブームになったのか(ブルース自体はその100年以上前からあります)とか、そもそもどうしてそれが京都から始まったのかなど、答えられない疑問があります。また、京都や大阪から日本のブルースバンドが次々と誕生し、憂歌団のようにだんだん日本語で歌うようになった経緯や、そうした活動を通して逆に「本場」とされるアメリカのブルースミュージシャンにさえ影響を及ぼしてゆく経緯からも、一方通行あるいは相互拮抗という単純な構図では捉えられない、もっと複雑な相関関係が見て取れると思います。
本発表では、このような問題意識を踏まえつつ、京都ブルースを事例に、グローバルとローカルの二項対立という単純な図式の乗り越えを模索してみたいと思います。
| 2012年1月例会案内 | 2007/07/16 |
日時:1月21日(土) 午後2時~5時
報告者:川崎寧生さん(立命館大学先端総合学術研究科)
場所:徳正寺さん(Google Map:http://p.tl/zUMk)
テーマ:「ゲームセンターの系譜学・試論
――戦後日本の若者文化論を目指して」
昨年、11月27日をもって、京都の「スポーツランド北白川」というゲームセンターが閉店しました。以前から京都に住まれている方には懐かしい名前かとも思われますが、1970年に開店し、現在まで生き残ってきた、総合施設型のゲームセンターであります。ゲームセンター産業が日本社会で注目を浴び始めた時期から現在まで生き残ってきた老舗が閉店したことは非常に残念です。
さて、以上のような、日本におけるゲームセンター産業が登場しはじめたのは1960年代からになります。それから半世紀たった現在、ゲームセンターはほかの娯楽に押されがちですが、存在しても違和感がない、日本社会に浸透した娯楽産業となったのは疑いようのない事実といえましょう。この歴史の中で、ゲームセンターには、駄菓子屋や、百貨店内のゲームコーナーのように、全く違う、様々な客層を想定した店舗の形態も多く登場していました。これらの様態は、なくなったものもあれば、現在も残っているものも多々あります。このように、場所や需要に応じて様々な店舗形態が存在することは、ゲームセンターの大きな特徴といえるでしょう。
そこで今回は、ゲームセンターを主題とした研究に関する現状の成果と課題を確認した後に、私自身の研究の現状報告として、日本ゲームセンターの様々な店舗形態について分類していくことにします。特に今回は、ゲームセンター産業の発展史と関連させながらみていくつもりです。最後に、今後の研究の試論として、分類した店舗の風俗、とくに利用方法や、客の年齢層などについて、もう少し突っ込んだ形で比較してみたいと思っております。
ゲームセンターという新たな産業が、戦後の日本社会にどのような形で溶け込み、成長してきたのか。そして、主たる客層である若者文化との関連性について、考えていくきっかけになればと思っております。(川崎寧生)
■過去ログ