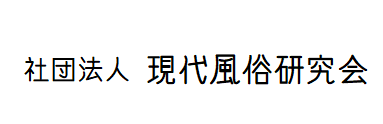| 2009年第4回例会案内 | 2007/07/16 |
「戦後日本における大衆娯楽としてのプロレスの生成と展開
―生成と現代的様相における多様性に注目して― 」
・発表者 塩見俊一さん
(立命館大学大学院社会学研究科応用社会学専攻後期課程
2003年よりフリーランスレスラーとしても活動中)
・日時 7月18日(土)14時~17時
・場所 徳正寺さん(京都市下京区富小路四条下ル)
http://www.genpoo.org/images/map.JPG
今回の発表者、塩見俊一さんは大学院でプロレスについて社会学の立場から研究する一方で、プロレスラーとして日本はもちろんアメリカでもリングに上がっています。つまり、研究者にして実践者という稀有な存在です。
塩見さんの発表のポイントは二つあります。まず、研究テーマである、日本におけるプロレスの生成過程についてです。従来日本のプロレスは力道山とテレビによって敗戦に打ちひしがれる人々の心を奮い立たせたと説明されてきましたが、塩見さんはそれ以外の要素、特に木村政彦を中心とした「プロ柔道」の活動に注目しています。「プロ柔道」の活動自体は短期間で終わりましたが、レスラーの供給源として大相撲と並んで柔道の存在は看過できないと考えています。占領の終結という状況下でのプロ柔道の活動とプロレスの成立の歴史に映画界の動向もからめたお話は戦後風俗史の知られざる一断面を浮かび上がらせることでしょう。
次に、塩見さんが今まで体験してきたアメリカや日本のプロレススクールの様子、プロレス興行の実際、試合の様子を語っていくことを通して、「地域発」のプロレス団体の実情を明らかにしてもらいます。興行の不振やスターレスラーの死亡事故など暗い話題が続くマット界ですが、塩見さんは、地方都市では「地域発」の団体が増え、それにともなってプロレスの担い手はむしろ増えているといいます。われわれは中央にばかり目が向きがちですが、地方における大衆娯楽の可能性として「地域発」プロレス団体に塩見さんは注目しています。ミッキー・ロークが主演している『レスラー』という映画でアメリカのそのような団体の内情を垣間見ることができますが、ここはひとつ現役プロレスラーでもある塩見さんに、体験者でしか語りえない視点からあまり知られていない地方の娯楽事情を語ってもらいましょう。
なお、せっかく塩見さんに語っていただくので、塩見さんの試合を見に行くツアーを計画しています!9月20日、大阪ミナミMove Onアリーナの興行を予定しています。詳細は次回例会で。Don’t Miss It!
(文責・岡村正史/ネットでの公開に伴い相原進により一部改変)
■ホームページ管理者より
会員向けの会報には何もかも書かれてしまっていたのですが、報告者との相談の結果、ネットの告知文ではリングネームは出さない、という方針になりました。
この点に関するご質問については回答できませんので、ご了承願います。
| 2009年第3回例会案内 | 2007/07/16 |
第3回例会テーマ:四角いマットに身体と生き様を描いて~障害者プロレス、かく生まれけり(仮)
・日時:2009年5月16日(土)14時~17時
・報告:建野友保さん(フリーライター、ドッグレッグス・スタッフ)
・場所:キャンパスプラザ京都6階 第8講習室
http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=585&frmCd=14-3-0-0-0
「プロレス」はプロレスラーの独占物ではありません。今日、「プロレス」はひとつの表現手段としてアマチュア、学生によっても実践されています。もっとも、それらの「プロレス」と同一視されることをかのプロレス業界は極度に嫌うわけですが。しかし、なぜ「プロレス」がプロレスラー以外によっても演じられるのかを考察することは現代風俗としてのプロレスを考える上で有益であると思われます。
そこで、障害者によって演じられる「プロレス」を今回は取り上げてみました。言ってみれば、今の時代にこの日本でなぜ障害者のプロレスが成り立ったのか、を通して現代の世相を見ようとする試みです。
北島行徳氏の著書『無敵のハンディキャップ』などで知られる障害者プロレス「ドッグレッグス」。ドッグレッグスはもとはといえば、ボランティア業界から起こってきたものですが、次第に興行化してきた存在です。ドッグレッグスの音響スタッフとして活躍する建野さんには、ドッグレッグスのダイジェスト映像に続いて、「見世物と障害者」にまつわる過去の点描、障害者運動と障害者福祉、ボランティアブーム、ドッグレッグスの歴史、隣接分野(小人プロレス、学生プロレス、障害者スポーツ、など)との共通性と違い、「ほとんど動かない(動けない)」重度障害者レスラーがマットにあがる意味合い、などについて語っていただきます。
ドッグレッグスについて寄せられる最も多い批判は、なぜ表現手段として歌や芝居ではなくプロレスを選んだのか、という点だといいます。いいかえれば、歌や芝居は許されるのに、なぜプロレスだと問題になるのか、ということです。これほどプロレスそのものに焦点が当てられる材料は他にないのではないでしょうか。もちろん、障害者福祉問題、ボランティア、見世物に関心のある方もお越し下さい。皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。(文責 岡村正史)
| 2009年第2回例会案内 | 2007/07/16 |
第2回例会テーマ:スポーツ、コスチューム、エロティシズム
年間テーマ「プロレスが残した風俗―世間にリングを、マットに社会を」
・日時:2009年3月21日(土)14時~17時
・報告:小野原教子さん(詩人。兵庫県立大学准教授)、井上章一さん(アダルト・ピアニスト。国際日本文化研究センター教授)
・場所:キャンパスプラザ京都6階 サテライト講習室
http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=585&frmCd=14-3-0-0-0
詩人の魂とアダルト・ピアニストの夢が交錯するとき、そこには何が生まれるのでしょうか。
今回は、女子プロレスラーのコスチュームの話に始まり、露出度の高い女子スポーツ、フィギュア・スケート、体操、ビーチ・バレーなどに見る「エロ力(ぢから)」の可能性に言及しつつ、スポーツとエロティシズムの関係について考察いたします。
体育会系的禁欲主義にもかかわらず、身体表現に慣れたスポーツ選手はセックスとの親和性が高いのか、男性が女性スポーツ選手を見る眼と、女性が男性スポーツ選手を見る眼はどうちがうのか、などスポーツとエロティシズムをめぐっては疑問が尽きません。そこで、ふたりのアーティストに語ってもらうことにしました。
小野原教子さんはこのたび詩集『刺繍の呼吸』(深夜叢書社)を上梓されました。『力道山と日本人』(青弓社)では力道山の黒いタイツについて考察し、『プロレスファンという装置』(青弓社)ではコスプレ・レスラー広田さくらを論じたほどの衣装論のプロフェッショナルでもあります。意匠論を専門とする井上章一さんは日ごとにアダルト・ピアニスト色を強めているようです。美女に囲まれてのMisty弾きなど新境地を開拓し、エロティシズム追求に余念がありません。スポーツに見るエロティシズムということで、「イパネマの娘」が飛び出すのか、はたまた「レディバード」なのか。
詩人とアダルト・ピアニストのコラボレーションに時の過ぎゆくままに身も心も預け、エロチックな見果てぬ夢に想いを馳せてみませんか。
(文責・岡村正史)
| 2009年1月例会案内 | 2007/07/16 |
第1回例会テーマ:スポーツ選手の入場曲および異名
・日時:2009年1月24日(土)14時~17時
・報告:永岡正直さん(タワーレコード店舗運営本部 SC 店舗統括部スーパーバイザー)
・テーマ「プロレスラーの入場曲・異名に観る世間への爪痕」
・セコンド
井上章一さん(国際日本文化研究センター教授。アダルト・ピアニスト)
・場所:徳正寺さん
http://www.genpoo.org/images/map.JPG
12月の総会は、バルトをめぐるバトルが勃発したり、テーマそのものに違和感を表明する人がいたりと、波乱含みのスタートとなりました。これもテーマが「プロレス関連」だからでしょうか。レスラーに非業の死を遂げる人が少なくないのは、単に肉体的な問題だけではなく、「プロレス」というジャンルを背負っているゆえの宿命と思っていますが、願わくば、現風研の1年が平穏に終わりますように。
さて、例会の第一弾はレコード業界(この言いかたでいいのかな?)のプロによる音楽談義です。メキシコの人気覆面レスラーで70年代に一世を風靡したミル・マスカラスの入場時に「スカイハイ」という曲が流れ、人気を呼びました。これぞまさに「プロレスが残した風俗」。「スカイハイ」を嚆矢として、スポーツ選手の入場時に音楽が流れる現象が一般的になっていきました。記憶に新しいところでは、清原和博が引退した折に長渕剛が「とんぼ」を生演奏していましたよね。
永岡さんには豊富な音源を駆使して、レコード業界から見た音楽に見る時代相の変遷、音楽がスポーツに与えるイメージ、スポーツをやる側と観る側の距離感、などを語ってもらいます。
また、人間発電所、黒い魔神、銀髪鬼、鉄人、荒法師などプロレス界は異名天国でしたが、いつの間にかスポーツ界全般も異名がまかり通る趨勢ですね。この現象も「プロレスが残した風俗」ではないかという仮説についても永岡さんに触れてもらいます。
セコンド役は、5日後に京都の大人の夜をピアノでいろどるであろう井上章一さんです。入場曲をめぐる極上のセッションが体験できることでしょう。乞ご期待。(岡村正史)
| 2008年度総会報告 | 2007/07/16 |
2008年12月6日、京都精華大にて現代風俗研究会総会が開催されました。総会では、2009年度のテーマを「プロレスが残した風俗-世間にリングを、マットに社会を-(仮)」とし、岡村正史さんにより「力道山-プロレスと世間がリンクしていた時代-から始めよう!」と題した基調報告が行われました。
報告では、岡村さんの著作『ミネルヴァ日本評伝選 力道山』での研究成果を元に、プロレスと社会との関係について、力道山を手がかりに明らかにしていきました。岡村さんは、自著について「一般的なプロレスというものを目指して書いた」と述べます。既存の力道山を扱った書籍では、力道山の人間像、内幕、出自などについて書いたものがほとんどで、プロレスをきちんと描いていなかった点を指摘しました。
その上で、力道山の時代において、「世間はプロレスそのものに対し本当に魅力を感じていたのか?」という疑問を呈しました。そこで報告(および著作)では、力道山が、メディアを通してどのように報じられ、人々に受容されたのかについて資料をもとに考察を進め、日本におけるプロレス黎明期を描き出しました。
そこで明らかになったのは、力道山が「敗戦コンプレックス」や「反米」の文脈で人気を博したという一面も否定できないものの、伝える側のマスコミはプロレスをショーとして扱った一方で、社会的には「ショー的要素の強いスポーツ」として受容されていたということでした。
その後、力道山以後のプロレスの変化が紹介されました。力道山以後のプロレスは、高い人気を維持しつつも、街頭テレビの時代ほど熱狂している人はいないという情況になります。その人気も衰退していき、1988年には、プロレス中継がゴールデンタイムから転落し、プロレス団体の多団体化とともに表現の多様化が進みます。今日では、プロレスというジャンルが凋落した一方で、プロレスから派生した「格闘技」が人気を博しています。
しかし、プロレスというジャンルそのものが完全に消えたわけではありません。「タッグ」「デスマッチ」といったプロレス用語や、入場曲やコスチュームなどの演出のように、他のジャンルで、プロレスは今もしぶとく生き残り、影響を及ぼし続けています。そこで2009年の現風研では、プロレスそのものではなく、プロレスが現代においてどのように生き残っているのかをテーマとすることになりました。
報告や質疑応答の中で、「チョップはダメージよりも音が重要」「プロレスは約束事で成り立っている」「プロレスでは、相手が得意とするところは譲ってあげるものだ」といった話が出ました。世間では相撲の「八百長問題」が取りざたされていますが、プロレスはそういう世界であるとお見知り置きください。
また、ある程度プロレスの「仕組み」を理解しているファンたちは、様々なシナリオが存在するという前提でプロレスを見ています。テレビやメディアで報じられたプロレスの試合結果、選手間の遺恨、派閥抗争などを、そのまま鵜呑みにするファンは、極めて少ないと思われます。優れたメディアリテラシーを有するとも言えますが、基本的にひねくれた人種の集まりです。質疑応答では、このような「プロレス的な物の見方を生かせないか」という意見が出されましたが、それに対し「裏読みばかりで物事を解釈するのは面白くない」という批判もされました。
このテーマに何人が付いて来られるか心配だったのですが、基調報告では、プロレスに詳しく無い方々でも楽しめたそうです。プロレスに詳しい方も、よくわからない方も、1年間、ぜひご参加ください。(相原すすむ)
■過去ログ